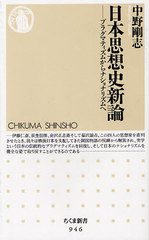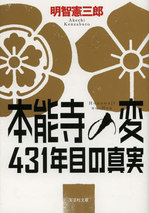大都会郊外のマンションで起きた監禁事件。監禁、傷害、殺害、死体損壊・遺棄事件。猟奇的というのではない、まさにケモノの域だ。どうして逃げない、逃げられないのか。息苦しい。
「社会への逆恨み。でもそれも、愛がゼロだったら起こらない。愛というものがある、それが分かっていながら、自分だけが得られない。そういう思い込みから、彼らは社会を恨むんです」・・・・・・。問題は、無重力の闇に放り出されたような時だ。「その手の犯罪者は、最終的には良心がないとか、反社会的人格だとか、そんなふうに判断されるようですが、反社会というより、人間社会というものを、そもそも認知していない。・・・・・・他の人間を同族とも思っていません。単なる獲物としか見ていない。だから愛しもしないし、哀れむこともない。中身はケモノです」・・・・・・。
残酷、人間の弱さや恐怖と暴力――監禁事件は、今も起きている。
「本書は、戦後日本を支配してきた開国物語を破壊しようという企てである」「本章では、福沢の実学というプラグマティズムもまた、水戸学と同様に、国際問題に応用されることでナショナリズムとして現われたことを示したい。そのためには、福沢諭吉の文明論が尊王攘夷論と対立するものであるという通説を破壊することから始めたい」「伊藤仁斎、荻生徂徠、会沢正志斎そして福沢諭吉。この四人の思想家を直列させたとき、我々は戦後日本を支配してきた開国物語の呪縛から解放され、実学という日本の伝統的なプラグマティズムを回復し、そして日本のナショナリズムを健全な姿で取り戻すことができるのである」――。日本思想の系譜を掘り起こしつつ、剛速球を投げ込んでいる。
明らかに問題意識としてあるのは、戦後日本とは何か。当然のことのように語られる"開国"とは何か。西欧が迫り来る幕末において、「対立軸は『攘夷vs.開国』『鎖国vs.開国』ではなく『避戦vs.攘夷』であった。すなわち事なかれ主義で平和の維持を求めるか、あるいは積極的に国家の独立を維持しようとするかであった(攘夷・開国か避戦・開国か)」など、かなり根源的なものだ。そして「尊王攘夷とは」「攘夷論の源流と古学」「会沢正志斎の『新論』で初めて登場する国体とは」「皇統、政統とは」「水戸学のナショナリズムとは」「福沢の攘夷論と"一身独立して一国独立する"(国の独立は即ち文明なり)」・・・・・・。日本思想、保守思想の水流・水脈を観ずることができる。
島根県の北60キロ、隠岐諸島の中の一つの島であり町である海士(あま)町。人口2331人(2012年8月末)、65歳以上が人口の4割。しかし、この町は注目をされ、先日は官邸でも町長さんから「地域づくり」の報告を受け、私もその場にいた。2004年から11年の8年間でIターン310人、Uターンは173人に及ぶ。挑戦する島だ。
その島に2人の若者が来て、"雇用を生み出す"攻めの姿勢を貫く会社「巡の環」を起ち上げた。阿部裕志代表取締役、信岡良亮取締役だ。山内道雄町長は海士は「よそ者、若者、ばか者」によって地域に新たな力を得たという。そして2人の若者は、「上から目線ではない。彼らの気持ち、目線、人間性が、地域に抵抗なく受け入れられた」と評価する。さらに「海士町は、過疎も、少子高齢化も課題先進地であり、成功事例をつくり、今後の日本にとって何かのきっかけにしたい」と語る。
2人は「この島を愛する。この島が好き。人の努力や想い、同じく実践している人の温かさがわかる」――その喜びが込みあげ、「地域活性」などという言葉には違和感を感ずるようになったという。多くの困難と遭遇しつつも実物に、本物に、生のもの(人)に出会うこと、感動があることが生きる証である。
「僕たちは島で、未来を見ることにした」という表題が、新たな未来を感じさせる。
世界の平均寿命が延びている。1850年に約43歳だったものが、1900年に48歳、現在は約80歳、未来は150歳になる可能性があるという。数学、プロスポーツ、激しい肉体管理など、最高潮の時期は明らかにこの30年、50年を見ても延びている。
本書は、平均寿命がなんと150歳になった時、健康寿命もそれに伴って延びる。その時、個人や社会全体がどれだけ変化するかを追っている。総人口はどうなるか、地球環境は守られるか、家族はどう変貌するか、生活や教育はどう変わるか・・・・・・。当然、細胞操作、遺伝子操作、抗老化薬、生命工学プロジェクトをはじめとする長寿革命への挑戦にもふれている。「長寿は是か非か」の意見対立にも論及している。文献・資料は膨大なものだ。
人口減少、少子・高齢社会、地震など大災害の切迫などが大きな問題となり、この7月に「国土のグランドデザイン2050」を発表したが、150歳といわずとも、平均寿命100歳以上社会を想定して考える意味はある。
「20XX年、仕事・家族・社会はこう変わる」と副題にあるが、2000年代後半、はたして寿命100歳以上の世界が来るだろうか。本書はかなりポジティブ思考だが、必ずしもSFだとは言い切れない。
「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶ」(ビスマルク)――歴史はたしかに勝者が、自分の経験を正当化しがちなものだ。それは真実ではない。明智憲三郎氏は、光秀の子・於寉丸(おづるまる)の子孫。
本書は「本能寺の変」の真実に文献をもって迫るが、その大きな背景として「光秀謀反」「利休切腹」「秀次切腹」は、いずれも信長、秀吉の「唐入り」があるとする。皆が反対するなかでの絶対者の強行姿勢に対して、その阻止のために謀反が企てられた、という。
本能寺の謀反は、光秀の個人的な野望と、残忍な信長への怨みによるものであり、光秀の単独犯行である――こうしたのは秀吉が「惟任退治記」を公式発表してつくり上げたものだ。それを示すとした「時は今あめが下しる五月かな」は、「下なる」が真実で、改竄されていた。光秀は、信長の天下統一と、長期織田政権構想の下では、大名は領地没収と遠国への移封(唐へも)は避けられない。土岐氏としての存続には、迫りくる長宗我部征伐の阻止を何としてもしなくてはならない(信長の長宗我部征伐の発令は5月7日)――こう考えた。突然でも何でもない。同じ5月、信長は家康討ちを計画した。そして光秀は家康と談合して謀反同盟を締結した(5月14日~17日)。その謀略は生きていたが、秀吉軍が予想外の早さで京都に迫り、家康の西陣は遅れた。秀吉は信長の長期政権構想を潰すために、光秀の決起をいわば待っており、事前に本能寺の変を予期していた形跡がある(細川藤孝父子)。勝者のつくった史観は、「太閤記」をはじめとして、どんどん流布していった。明智さんは、文献にあたって裏付けていく。
「利休切腹」も「秀次切腹」も短文だが、「唐入り」問題から解読する。興味深い。