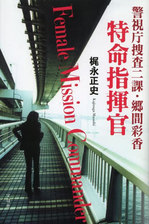副題に「時代の十歩先が見えた男」とある。「百歩先の見えるものは狂人扱いされ 五十歩先の見えるものは多くは犠牲者となる 十歩先の見えるものが成功者で 現在を見得ぬものは、落伍者である」(小林一三「歌劇十曲」)――。
明治6年、山梨県に生まれ、慶応大卒業後、三井銀行を経て、箕面有馬電気軌道の専務に。沿線開発を通じて利用者を拡大し、阪神急行電鉄とし、社長に就任。宝塚歌劇団をつくり上げ(今年、創立100周年)、阪急百貨店、東京宝塚劇場、東宝映画、阪神ブレーブス・・・・・・。次から次へと無から有を生み出していく夢と信念の稀代の事業家・小林一三は、商工大臣にも就く。
「人一倍豊かな想像力」「無理をするな――焦らず堅実に着々と」「人に頼るな。最後に頼むものは自分以外には決してない」「あれほど頭のいい人は見たことがない(白洲次郎)」「えらい人ってのは、世の中に対して貸勘定の多い人ってことだね(小林一三は、事業の面でも、大衆に楽しさ、便利さの貸勘定を残していった人だ)」「飽くなき探究心」「国民全体が働くことだ。努力することだ。努力を惜しまなければ日本は実に立派な国になる(昭和31年、梅田コマ竣工式で)」「働くことだ。人の二倍も三倍も働け。働きもしないで人が認めてくれるはずがない」「金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である」「無から有を生み出すのは家の芸だ。枯れ木に花を咲かせましょう」・・・・・・。
さらに思うことは、豊富な人間関係、いざという時に、必ず助けてくれる人が現われていることだ。岩下清周、平賀敏、岸本兼太郎、矢野恒太、松永安左ヱ門、高碕達之助、白洲次郎・・・・・・。人間の縁と運は、偶然などではけっしてない。
「敗北を抱きしめて」のジョン・ダワーは「今日の諸問題に取り組むとき、私たちはいつも、第二次大戦における日本の降伏、次いで米国による対日占領、そして1951年から52年にかけてのサンフランシスコ講和および日米安保両条約に行き当たる」という。憲法、朝鮮戦争、そして領土・・・・・・。そして、両氏は「現在を理解するには、もっと長い目で物事を見る必要がある」「問題は、米中、日米、日中、日韓、日朝における緊張がどのように制御され、解決されるか、ということだ」という問題意識を共有する。ジョン・ダワーは、戦後日本を規定したサンフランシスコ体制の"負の遺産"として、「沖縄と"二つの日本"」「未解決の領土問題」「米軍基地」「再軍備」「歴史問題」など8項目を挙げ、"従属的独立"と手厳しくいう。歴史は、そうした"遺産"とそこに生ずる感情、力、経済、誇り、恥辱を含めて形成されて今をつくる。いずれにしても、大事な時にさしかかっている。
「明治以後の日本人は、なに食わぬ顔をして儒学を捨てた」「(しかし)江戸時代に学問は儒学しかなかった。人文科学も社会科学も自然科学もない。だから我こそはと意気込む天下の俊秀、大天狗、小天狗は、草莽の臣であっても、こぞって儒学に向かった。・・・・・・知と知を競い合うことに鎬を削った」「その知の競い合いの頂点に立った男こそ"知の巨人、荻生徂徠"その人であった」――その江戸の250年、日本人は脳に磨きをかけたからこそ、明治以来の人文科学等をただちに"我が物"にできたのだという。
この荻生徂徠伝は、伝記的な面と徂徠学、思想の面が融合して描かれる。
「財政難」「富士山噴火や大火」「生類をいたわり、憐むこと」「学問重視」の綱吉の時代は延宝8年(1680年)から28年に及ぶ。綱吉に重用された柳沢美濃守吉保の庇護のもと猛勉強した荻生徂徠。新井白石、伊藤仁斎・東涯父子との対立感情、荻生徂徠の下に集う平野金華、太宰春台、服部南郭、安藤東野、三浦竹渓らの俊秀。学者間の鍔迫り合いは時代の空気を浮き彫りにする。
「先王の道は天下を安んずるの道なり」「礼楽刑政こそが"道"である」――。道は天下国家を平定するために、聖人が建立した道である。朱子学一辺倒の時代に、それを乗り越え、徂徠学の根本テーゼを打ち立て、実践的な「道」の概念を重視した。「名君・徳川吉宗に天下国家を治める道を説いた思想家"荻生徂徠"」だが、本書で描く両者のやり取りも"いかにも"面白い。
「終わりなき危機 君はグローバリゼーションの真実を見たか」「世界経済の大潮流」の両著の延長線上にある。
「地理的・物的空間(実物投資空間)」に見切りをつけた先進国の資本家たちは「電子・金融空間」という新たな空間をつくり、利潤極大化という資本の自己増殖を継続している。リーマン・ショックは、その無理な膨張が破裂したものだ。グローバリゼーションは「中心」と「周辺」の組み替え作業であり、「先進国(中心)と途上国(周辺)」「ウォール街(中心)と自国民(周辺)」という構造をもつ。食料価格や資源価格の高騰は、貧富の二極化、中間層の没落を引き起こす。グローバル化と格差の拡大だ。「ゼロ金利は資本主義卒業の証」「矛盾が、資本主義終焉の一歩手前まで蓄積している」「資本主義の本質は"中心・周辺"という分割にもとづいて、富やマネーを"周辺"から"蒐集"し、"中心"に集中させることだ」――。
そこでどうするか。本書の意図はそこにある。まず資本主義の暴走を食い止めて、どう"定常状態"をつくるかだ。ゼロ金利、ゼロ成長、ゼロインフレに突入している日本は、それをアドバンテージだととらえて、人口減少に歯止めをかけ、国内での安価なエネルギー創出なども含め、"定常状態"をつくるべきだ。成長市場主義から脱却しよう、という。