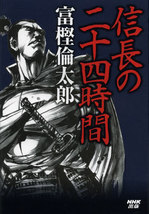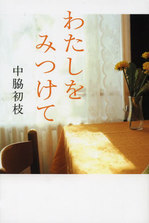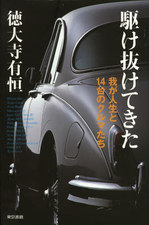傑作「軍配者シリーズ」の富樫倫太郎さんが、「本能寺の変」に挑む。NHKのTVドラマ「黒田官兵衛」も、ちょうど今、本能寺の変にさしかかっている。
天下統一をめざした信長の暗殺計画。伊賀を焦土作戦で皆殺しにされた百地党の里村紹巴(じょうは)や文吾(石川五右衛門)の復讐。統一後は「諸国の大名から領地を取り上げ、朝廷に返上する」と信長は目論むが、朝廷の太政大臣・近衛前久らは"朝廷乗っ取り"計画と見て、暗殺計画に加わる。統一後に漢の高祖が功臣たちを次々に粛清したことを踏襲することを恐れる徳川家康、そして誰よりも羽柴秀吉。あの有岡城に幽閉された時、嫡男を処刑されようとしたことで、信長への恨みと憎しみをもつ黒田官兵衛。"朝廷乗っ取り"に反対する織田信忠、そして逡巡する明智光秀・・・・・・。
信長への恐怖で、戦々恐々となるなかで、「信長に死んでほしい」と思わぬ者はなかった。しかし、誰がやるか。どう実行するか。主殺しの汚名を他に押しつけたい。息の詰まる"陰謀"のなかで、百地党の里村紹巴が朝廷を巻き込み、さらに秀吉と官兵衛は光秀を犯人に仕立てあげる謀略をめぐらす。
全ては天正十年(1582年)六月二日になだれ込んでいく。
平成の世から老中・田沼意次が失脚寸前の天明の世にタイムスリップした武村竹男(タケ)が見たものは・・・・・・。地本問屋「耕書堂」の蔦屋重三郎(蔦重)、歌麿、りよ、蔦屋の面々、狂歌連のメンバーや吉原や料亭で働く人々、勝川春朗(北斎)、花魁の菊乃や蜻蛉など、江戸の生きいきとした民衆が描き出される。
「"あがり"を定めて、人生を逆算しろってことだ」「かけてもらった恩は下に送らなきゃなんねえし、人にかけた情けは、いずれてめぇに返ってくる(恩送り)」「てめぇの道をてめぇで塞いでどうする?"でも"とか"しかし"なんて言ってる奴は、金言を逃すし、人様に可愛がってもらえねぇぞ(人の言葉を否定しない)」「てめぇの好きな仕事をやって人様に喜ばれることほど目出てぇことはねぇ」「やっぱり、怒りや恨みってぇ感情は、人を突き動かす力になるもんだ」・・・・・・。まさに人生の知恵、人生の勘どころが、次々と蔦重から発せられる。
「いい子じゃなければ、また捨てられる」「今度こそ、いい子でいよう。ずっといい子でいよう」「こんなことをしても、わたしを捨てないでくれる? それを確かめたくてわるい子になる」――捨て子として施設で育てられ、ナースになる主人公・山本弥生。どうしようもない病院、そこに新しく来た藤堂師長や、患者にもなる近隣のおじさん・菊地さん等に導かれて成長する話。そういってしまえば実もふたもない。本書ではそれが淡々と、心の深層に迫りつつきわめて内省的に語られる。かつ生まれた時から命に染みついた諦観を、人と接するなかで一枚ずつはがし取っていく過程が描かれる。人が生まれ、生きていくということ、そして生き方というものを考えさせる感動的な小説。人間、人生、生老病死を考えさせ、煩悩・生死の海を乗り越えることを描いている本だ。医療現場の抱える問題にも切り込んでいる。
「終わらない読書」と副題にあり、読書家で知られる中江有里さんの"読書録"を交えたエッセイ。何よりも伝わってくるのは、爽やかさ、人生への真面目さ、ひたむきさ、丁寧さだ。読書家というとどうしても理屈をこね回したりしがちだが、生命の自然態に感心する。高野和明著「ジェノサイド」について、「人間の心の襞、良心が丁寧に描かれる」と書いているが、本書自体がそうだ。
「読書神経(運動が体を動かすように、読書は想像力を働かせる。読書も運動も『正しく苦しがる』もの)」「作家たちの心を開き、名言を引き出したのは、児玉清さんの本への愛情と人柄によるところだろう」「ひとりでしかできない読書は面白いことに"自分はひとりじゃない"と確認することでもある」「本はわたしの心の友達」などと語る。私も児玉さんと話がしたかったなと思った。
「我が人生と14台のクルマたち」と副題にある。
「私は自動車評論家・徳大寺有恒である以前に、自動車ファン・杉江博愛である。自動車が好きで好きでたまらない。さまざまなメーカーのクルマを、本当はすべて買って試したいと思う」――所有したクルマの数は約100台、試乗したクルマは約4000台。恐ろしいほどの数だ。
「ベントリィは調度である。クルマではあるが、クルマではない」「青春とともに駆け抜けた忘れえぬ2台の車、トヨペット・コロナとニッサン・ブルーバード」「自動車には乗る者に対して干渉して(語りかけて)くるクルマと干渉してこない二種がある。ジャグァーは、その語りかけがうるさいどころか、癒されるのだ。ジャグァーが発するメッセージは"上品であれ、紳士たれ"なのだ。ダンディに生きよう」「フェラーリ。このクルマは、たしかに私の人生を彩ったのである。フェラーリの官能性、いやクルマが本来持っている官能性というものに、初めて開眼したのだった。フェラーリは"死を予感しながら生きよ"と訴えてくる類いまれなクルマである・・・・・・。世の自動車が"自動運転"に切り替わっていくとき・・・・・・人間がドライブしない運転。快楽のない運転。フェラーリはそれを許さない、と私は思う」「物語を持つクルマ――これが名車の条件だと思う。それは背後にひかえる"世界"があるということだ。イギリス車の貴族性・悦楽性、ドイツ車のメカニズムへの偏愛とスピードへの憧憬、フランス車のアート性と合理性・・・」・・・。そして日本社会を全的に肯定した「終のクルマ」としてクラウンをあげて締めくくっている。
クルマとともに暮らし、ともに泣き、ともに笑って一緒に駆け抜けてきた徳大寺さん。ダンディだし、人生・生き方を考えさせるインパクトがある。