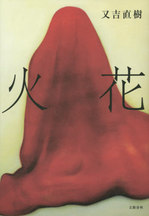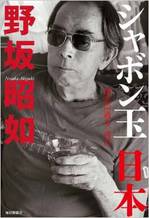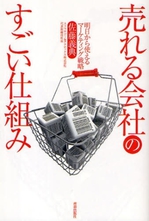
「明日から使えるマーケティング戦略」として、ハイレベルのマーケティング戦略を平易に体系的に解説してくれる。
売れる仕組みは「せ・す・じ・評価(戦略→数字→実行→評価)」の全社的プロセスで、それを作ることが経営者としての最優先事項だ。戦略がない者は社長失格であり、このプロセスを全社員が共有する。強い「想い」をリーダーがもち、それを共有することが重要となる。
本書では「戦略的BASiCS(「戦略・競合」「独自資源」「強み・差別化」「顧客ターゲット」そして「メッセージ」)」「売上5原則(新規顧客の獲得、既存顧客の維持、購買頻度の向上、購買点数の増加、商品単価の向上)」「マインドフロー(客のココロの流れ)」「プロダクトフロー」を売れる仕組みを作るツールとして示す。
徹底した分析のもとに戦略が立てられ、成功への道が開かれることを感ずる。
日本を愛したスパイ、ドクター・ハックことフリードリッヒ・ハック。副題には「日本の運命を二度にぎった男」とあるが、ひとつは日本を悲惨な戦争に導いた日独伊三国同盟(1940年4月27日)に至る契機となった1936年(昭和11年)11月25日締結の日独防共協定にかかわったこと。ヒトラーのファシズム国家ドイツと軍国主義の日本が協力してソビエトの共産主義の進出に対抗しようとした条約だ。そしてもうひとつは、「日本を戦争から救い出す」ための和平工作(藤村・ダレス工作とヤコブソン工作)だ。
ヒトラー側近のリッベントロップ、日本陸軍駐独武官・大島浩、リヒャルト・ゾルゲ、酒井直衛、藤村義郎、アレン・ダレス、ゲーロー・フォン・ゲヴェールニッツ、そしてアーノルド・ファンク監督と原節子・・・・・・。緊迫した世界のなかで、日本とナチスを結び付けた十字架を背負いつつ、反ナチに立ち上がり「日米開戦不可を警告」日本に早期の和平を説いたドクター・ハックの人間像と時代の舞台裏が浮き彫りにされる。より鮮明にされるのは戦争末期の軍人・官僚の世界からの孤立と、情報遮断、そして思考停止だ。本書が今、出版されたということはそれは過去の話ではないという指摘だ。
人気お笑いコンビ「ピース」の又吉さんの話題の純文学作品。主人公の「僕」・徳永は熱海の花火大会で、天才肌の先輩芸人・神谷に会い、師弟関係を結ぶ。同世代の芸人が売れていっても、なかなか芽が出ない。
「漫才師である以上・・・・・・あらゆる日常の行動は全て漫才のためにあんねん。だからお前の行動の全ては既に漫才の一部やねん。・・・・・・漫才は、偽りのない純正の人間の姿を晒すもんやねん」・・・・・・。神谷の日常は、それゆえ真っすぐで、ハチャメチャ、破滅的でもある。都会とメディアの喧騒のなかで、笑い、面白さを追い求める二人の日常は、常軌を逸する脱輪状況のまま無常世界を往復し、泣き、笑い、もの悲しさを伴なう時間を刻む。
笑いと逸脱、敗れもする人生、青春の直球・・・・・・。今もこうした世界と若者が残っていることを感じながら読んだ。
久し振りに野坂さんの肉声を聞いた思いだ。戦後70年、あの戦争、20年6月5日に焼け出された野坂さんと妹。「神戸が焼かれ、家族が死んだ6月5日が近づくと憂鬱になる」。飢えと深い闇、「他のことは忘れても、あの深い闇は昨日のことのように、ぼくにのしかかる。戦争をしょうがなかったではどうしても済まされない」・・・・・・。原点、原像はあまりにもくっきりとしている。豊かさとともに、自然は荒廃し、社会は浅薄になっている。いったん突き進み出すと止まらない風潮の日本。惰性で、思考停止の日本。そして、「大人の幼児化が目立つ。若者の老人化も同様」「ぼくらは戦後の歪みを背負っている。67年かけて出来た歪み、またこの数年のうちに生じた歪み、歪みは放置していても治らない」「あのテロ(9・11)は世界を変えたと言われる。・・・・・・国家対国家の場合は、会話が成立する」「(豊かさへの邁進)(使い捨て社会)成長だけを考え、便利さを望み、やっつけ仕事の積み重ねが負の財産として現在を押しひしいでいる」「昔、たまに目にする老人には威厳、風格、貫録のようなものが備わっていたように思う。・・・・・・威厳のあるおじいさんもいなくなった」「戦前、また戦後しばらくは、主に町内のガキ大将がうまく取り成した。さらに弱い者をいじめる行為は男として恥。・・・・・・ガキ大将の育つ環境は、もはや無い(豊かさが生んだ殺風景)」・・・・・・。
若者に、日本に、自ら全力で生きてきた人生観から、痛烈で切れ味鋭い二枚蹴りを決めている。
「ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則」と副題にある。矢野さんは、日立製作所中央研究所の主管研究長。24時間、人に装着するリストバンド型のウエアラブルセンサで人間の行動を記録する。そこで得られた100万人日以上の膨大なデータ、人間行動の研究が、人間や社会に普遍的に見られる「法則」や「方程式」を明らかにする。
アダム・スミスの「見えざる手」は、いまやビッグデータを活用して「データの見えざる手」により、社会に豊かさを生み出す。ビッグデータとコンピュータが、さまざまな要因間の複雑な依存関係の全体を見渡しているからこそ可能となることであり、人の「共感」や「ハピネス」の向上をより鮮明にできる。そして対立すると考えられがちな「経済性の追求」と「人間らしい充実感の追求」の両者を結びつける――このように矢野さんは新たな地平を開示する。ビッグデータによってサービス、科学、技術が未来社会に向けて協創する社会が始まるということだ。
日々の効率的な時間の使い方から「ハピネス(幸福)」や「運」ということまで、新たな視座が生まれてくる。たとえば、「運は人の出会いによってもたらされる」「運と出会いを理論化・モデル化する」などを示し、「運も実力のうち」から「運こそ実力そのもの」へ、という。「運」を宗教・哲学・人生論とは別の世界から解明している。