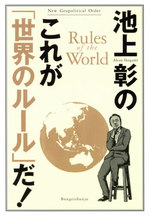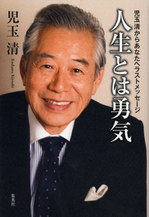佐治敬三(1919~1999)――稀代の経営者であるサントリー二代目社長、生産量世界一のウイスキーをつくり、"大阪最後の大旦那"といわれた存在感と人間味あふれる経営者。一方の開高健(1930~1989)――貧困のどん底から佐治敬三に活躍の場を与えられ、コピーライターとして才能を開花、芥川賞受賞、破天荒の世界基準の無類派作家。
戦後の荒廃から高度成長期の日本。その先頭をかきわけ、ぶつかりながら走った佐治敬三と開高健、そしてその仲間たちのエネルギーはすごい。「身体が大きくて声がでかい。底抜けに明るく豪快で無神経な言動も多いが、実はシャイで傷つきやすく繊細な神経の持ち主。そして心の奥に、触れたくない心の傷を抱えている。それが二人の共通点だった」「彼らは互いの中に似たものを感じ、惹かれあい、刺激しあって人生をより豊饒なものとしていった」と北さんはいう。佐治の父親・鳥井信治郎、そして「マッサン」の竹鶴政孝・・・・・・谷沢永一など。その友情と絆は、不運と幸運を超えた激情、豪流の人生を形づくる。北さんが時折りはさむ珠玉の言葉がとてもいい。
昨年9月の御嶽山噴火から浅間山、桜島、口永良部島、そして大涌谷(箱根山)や蔵王山・・・・・・。日本には活火山だけで110、陸上の火山の7分の1が日本にあり、常時観測しているのは50火山に及ぶ。
「日本誕生から破局噴火まで」と副題にあるように、「プレートの動きが地震も火山も生み出してきたこと」「地震と火山噴火の関係とメカニズムの違い」「火山災害の歴史」「噴火の5つのタイプ」「どんな大噴火がこれから日本を襲うのか」「危ない火山は意外に近くにある」など、解説する。そして「予知は一筋縄ではいかない。それは噴火予知にとって肝心な、地下でなにが起きているかということが、わかっていないからだ」「マグマがどう動いて、どう噴火に至るかというそれぞれの段階での学問的な解明がまだできていない」「有珠山の2000年噴火で直前予知に成功したのは、350年前から正確な記録が残る7回の噴火を繰り返してきた、世界の火山では例外的な好条件に恵まれたためだ」という。
そのうえで、私たちは被害最小化のための観測体制、人材確保に努めることだ。最後に「火山国日本に住む覚悟を日本人は持っているべきだろう」と結んでいる。
「物事をわかりやすくする論理は、因数分解なんですね。括弧の中の話をすると凄くわかりやすくなる」「伝える情報を減らすことで、わかりやすく説明できる。複雑なニュースでも、いろんな要素の中からそぎ落として、これだけは知っておいてほしい、というものを選別して、情報量を減らして伝えている」「ニュースの内容を逐一追うのではなく、基礎基本から解説する」「世界は目まぐるしく変化している。変化に対応するには、変化の底流を知らなければなりません。そのための情報収集と整理」・・・・・・。
「組織拡大術――イスラム国が急成長したわけ」に始まり、「トラブル解決法」「ホンネを見抜く」「歴史の勉強法」「究極のリーダー術」「お金、マネー、資本を知ろう」「交渉術、プレゼンテーションを磨け」「ビジネスのカギは科学にあり」「インタビュー術」・・・・・・。本当にわかり易く解説してくれている。
「クイズは人生と同じ。そのときボタンを押せるか押せないか。人生とは勇気、と、毎回思う」――。人生とは勇気だという児玉さんの生き方、決断の背後には、「人生は祈りの旅路」「人間が生きるということは"祈り"なくしてはあり得ない」「亡き母が僕をどこからかいつも見守ってくれている」「娘の死は天から鉄槌を受けたような衝撃であった。僕は心の底からの笑いを失った」「雨降らば降れ、風吹かば吹け。花に嵐の譬えもあるぞ、さよならだけが人生だ。心の中でにわかに輝きを増した言葉だ」――こうした誠実に、武士のように一人歩んできた人生哲学がある。
亡くなってもう3年以上たつとのこと。子供の頃のこと、俳優の時のこと、テレビに出るようになってからのこと、そして読書。素晴らしい生きざま、人生哲学が、静かににじみ出ている。中江有里さんが解説を添えて(捧げて)いる。