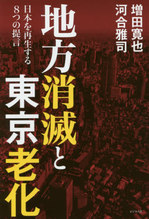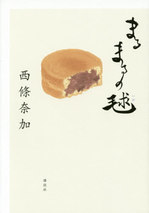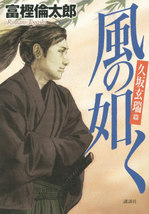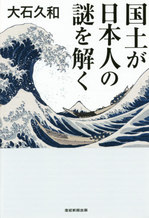人口減少、地方消滅、一極集中による東京崩壊(老化)――これは最重要の問題であり、因果関係が複雑に絡み合っている。あらゆる分野にわたって、少子高齢化や人口減少に対応し、見直していかない限り、日本には歪みが噴出し、衰退への道をたどることになる。ラストチャンスだが、今なら間に合う。「東京一極集中で成り立ってきた20世紀型成功モデルをひとまず否定し、東京一極集中ではない社会がどういうものかを考える」「人口減少を前提とした大胆な国家のつくり替えをする」「東京一極集中の危険性と限界を理解・再認識し、東京をどうするかを考える」ことだ。
そこで「地方と東京を元気にする8つの提言」がされる。「東京との"距離"が武器」「世界的ローカル・ブランドの創出」「世界オンリーワンの街づくり」「都会にはない暮らしやすさの発信」「県内二地域居住で"にぎわい"維持」「発想の大転換"スーパー広域合併"」「アクティブシニアが活躍"CCRC"構想」「第三子以降に多額の現金給付」――。
対談によって展開される発言の1つ1つを、考え考え読んだ。考えることを促す書だ。
NHK大河ドラマ「花燃ゆ」において「蛤御門の変」で久坂玄瑞が死亡した(7月5日放映)。本書は久坂玄瑞を中心として、風倉平九郎、高杉晋作、そして桂小五郎、吉田栄太郎、伊藤俊輔らを「桜田門外の変」「航海遠略策(長井雅楽起草)」「寺田屋事件」「奇兵隊」「蛤御門の変」の5部で描く。
幕末を吉田松陰門下の若者がいかに、師の魂を抱きしめ、尊王攘夷を掲げて走ったか。幕府、朝廷、各藩がいかなる思惑で動いたか。頭に血がのぼったかのような激情と思想。そのなかで久坂玄瑞は確かに「風の如く」去り、「激情のなかにも風の如く冷静に」「風の如くもの悲しく」「風の如く同志にやさしく、さわやかに」散った若者だったのだろう。英傑とは対極にある俊英・久坂玄瑞を感じた。
「国土学」の第一人者の大石さんが、国家論を論述している。日本国家を考えれば日本人論、その日本人論は当然、国土に人間が働きかける「国土学」という広大な背景から把えなければならない。そうした国土学から日本人論、国家論へと迫っている。
その射程は日本の今と未来にある。「戦後は戦前の否定では終わらなかった。日本そのもの、歴史も精神を含むすべてのものを否定された。これを放置したままでは、われわれ日本人は根無し草として世界に漂う存在であり続けるしかない」「わが国土の自然条件、位置条件によって世界中の他の国民や民族と相当に異なる経験をし、考え方・感じ方を育んできたのが日本人」であり、「"仲間と共同して働く""集団力の発揮"を取り戻そう」と指摘する。たとえば新自由主義経済の「小さな政府」「緊縮財政」「規制緩和」「自由化」「民営化」などの主流化は、この日本人の強みである特性を破壊してきた。日本人が厳しい自然に翻弄されながら培ってきた互いに助け合う「共」の原理と、欧米人が築いてきた「公」の原理とは根本的に違う。思考停止を戒め、日本人の強みを生かして未来に挑め。智慧は蓄積されているではないか――そんな声が聞こえる。
衣笠幸夫(人気作家の津村啓)は、冷めた関係になっていた妻・夏子を突然のバス事故で失う。同じ事故で亡くなった友人には、夫(大宮陽一)と真平、灯の3人の家族がいる。悲しみを露わにする陽一家族と、涙を流すことができなかった幸夫の交流が始まる。悲しみ、喪失、狼狽、悔恨、自責、葛藤、愛別離苦、憎愛、屈折、孤独・・・・・・。
「人は後悔する生き物だということを、頭の芯から理解しているはずなのに、最も身近な人間に誠意を欠いてしまうのは、どういうわけなのだろう」「愛するべき日々に愛することを怠ったことの、代償は小さくはない。・・・・・・喪失の克服はしかし、多忙さや、笑いのうちには決して完遂されない。これからも俺の人生は、ずっと君への悔恨と背徳の念に支配され続けるだろう」「あのひとが居るから、くじけるわけにはいかんのだ、と思える"あの人"が誰にとっても必要だ。想うことの出来る存在が。・・・・・・人生は、他者だ。・・・・・・遅いか、あー」
本文の「長い言い訳」が、「永い言い訳」の題に変わっているがゆえに、永遠の人生的、哲学的な問いになっている。"言い訳"というより"問いかけ"、どこまでも続く「永い問いかけ」となって深みを増している。それが息の長い、丁寧な文章で書かれて、心に浸み込んでくる。