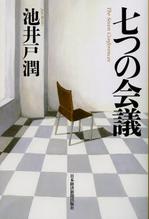欲望、人間中心主義、自然との対立概念、科学技術優先――。そうした近代西洋文明批判、近代合理主義批判がなされて久しい。むしろ最近では、骨太の文明論は少なくなっている感すらある。しかし、梅原猛さんは、それに代わり人類文化を持続的に発展せしめる原理が、日本文化のなかに存在する。それは「草木国土悉皆成仏」だという。
欲望、人間中心主義、自然との対立概念、科学技術優先――。そうした近代西洋文明批判、近代合理主義批判がなされて久しい。むしろ最近では、骨太の文明論は少なくなっている感すらある。しかし、梅原猛さんは、それに代わり人類文化を持続的に発展せしめる原理が、日本文化のなかに存在する。それは「草木国土悉皆成仏」だという。
文明と文化を全的に把握したうえで、真正面からナタを振り降ろすがごとき大きな肺活量の文明論だ。天台本覚思想、縄文文化、アイヌ文化。そして西洋のデカルト、ニーチェ、ハイデッガーの哲学。更にヘブライズムとヘレニズムという西洋近代文明の源を示しつつ、西洋哲学から人類哲学への転換を説く。「草木国土悉皆成仏」「森の思想」だ。
生命の尊厳、色心不二、草木成仏、一念三千論、五陰・衆生・国土の三世間・・・・・・。私はそうしたことを想いつつ読んだ。壮大な人類哲学は、想いがあふれなければ、とうてい書けるものではないと思った。
 国際政治学の白熱授業を受けているようだ。「見方、考え方」を確立するには、分析する根拠、道具立てがいる。巻末に「ブックガイド」が載せられているが、それら全てを土台としたうえで、藤原さんは思考の道標を示してくれる。「"戦争の条件"には、戦争を避けるための条件と、それでも戦争に訴えなければいけないときに満たすべき条件という二つの意味を、込めている。暴力が国際政治の現実であることは否定できない。暴力に頼ることなく戦争を回避することもきわめて難しい。だが、その現実のなかには常に複数の選択が潜んでいることも見逃してはならない」「暴力への依存を最小限に留めながら平和を実現する方法を具体的な状況のなかで探ることであり、そこでは戦争の条件と平和の条件が裏表のように重なり合うのである」――。「戦争違法化と好戦国家の排除が平和の条件」「歴史問題は時が解決するという議論がある。だが事実は違う」......。「広島の語り、南京の語り、靖国の語り」などはきわめて印象的であったが、藤原さんは現実の問題の根源を剔抉してくれている。
国際政治学の白熱授業を受けているようだ。「見方、考え方」を確立するには、分析する根拠、道具立てがいる。巻末に「ブックガイド」が載せられているが、それら全てを土台としたうえで、藤原さんは思考の道標を示してくれる。「"戦争の条件"には、戦争を避けるための条件と、それでも戦争に訴えなければいけないときに満たすべき条件という二つの意味を、込めている。暴力が国際政治の現実であることは否定できない。暴力に頼ることなく戦争を回避することもきわめて難しい。だが、その現実のなかには常に複数の選択が潜んでいることも見逃してはならない」「暴力への依存を最小限に留めながら平和を実現する方法を具体的な状況のなかで探ることであり、そこでは戦争の条件と平和の条件が裏表のように重なり合うのである」――。「戦争違法化と好戦国家の排除が平和の条件」「歴史問題は時が解決するという議論がある。だが事実は違う」......。「広島の語り、南京の語り、靖国の語り」などはきわめて印象的であったが、藤原さんは現実の問題の根源を剔抉してくれている。
 何のために働くか――。とくに"自分探し"の中途半端に沈み込む若者が多いとか、社会的にあらぬ罵倒を受けている人が、生命力を失うことが多々あるなかで、根源的に問いかけである。
何のために働くか――。とくに"自分探し"の中途半端に沈み込む若者が多いとか、社会的にあらぬ罵倒を受けている人が、生命力を失うことが多々あるなかで、根源的に問いかけである。
本書は多岐にわたり、「自分の人生」「使命」「人生観」「圧倒されるような人との出会い」「中東や米でのギリギリの経験」「新しい産業社会と時代認識」「企業と人」など広範だ。寺島さんが自らを語っているから迫る力がある。
働くことを通して、世の中や時代に働きかけ、歴史の進歩に加わること。それが働くこと、生きることの意味ではなかろうか」
内村鑑三の『後世への最後の遺物』に心に沁みる最後の四行がある。われわれに後世に遺すものは何もなくとも、われわれに後世の人にこれぞというて覚えられるべきものはなにもなくとも、アノ人はこの世の中に活きているあいだは真面目なる生涯を送った人であるといわれるだけのことを、後世の人に遺したいと思います」――誰もが後世に遺せるものは、高尚なる生涯である。
社会にぶら下がって生き延びるのではない。壁にぶつかり自問自答するのは当然だが、時代と真剣に向き合い、その変動を感じつつ、そこで自らが立つ、価値創造への意思を貫くことだ。大切なのは「素心」だと、寺島さんはいう。
 「公共事業が日本を救う」「救国のレジリエンス」などの著書でも知られる、現在、内閣官房参与(防災・減災ニューディール政策担当)を務める気鋭の藤井さん。本書は国土強靭化、公共事業を当然書いているが、そうした現状分析や技術的データを駆使する本では全くない。表題にあるように「思想」であり哲学。文明論であり政治哲学の本であり、心理学にも論は及ぶ。副題に「強い国日本を目指して」とあり、国土強靭化のなかに貫かれているのは、日本強靭化であり、日本人強靭化だ。
「公共事業が日本を救う」「救国のレジリエンス」などの著書でも知られる、現在、内閣官房参与(防災・減災ニューディール政策担当)を務める気鋭の藤井さん。本書は国土強靭化、公共事業を当然書いているが、そうした現状分析や技術的データを駆使する本では全くない。表題にあるように「思想」であり哲学。文明論であり政治哲学の本であり、心理学にも論は及ぶ。副題に「強い国日本を目指して」とあり、国土強靭化のなかに貫かれているのは、日本強靭化であり、日本人強靭化だ。
時々挿話される「映画ガイド」がとてもいい。終章の「世界一タフたろうとする決意」にある村上春樹論もいい。「一身独立して一国独立す」も、まちづくりが「民俗の力」にまで及んでいい。
「諦め物語」を「希望の物語」へ。デフレは日本人の精神をも蝕み、「諦め」と「しょうがない」症候群を生んでいると思う。本来の「諦め」は東洋思想の「明らかに観る」という如実知見、諸法実相の哲学に立つべきものだ。卑俗な「ニヒリズム」と「ポピュリズム」を越える時、はじめて21世紀の日本が動くはずだし、動かしたい。気鋭の良い本。