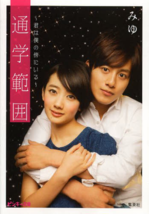「3・11の教訓に学ぶ地震対策」と副題がついている。首都直下地震と南海トラフ巨大地震が起これば、人的および社会経済被害は計り知れない。被害の最小化、迅速な回復を図る「減災」と「レジリエント(強靭化)」を早くから訴え続けた河田さんが、災害多発・激化時代に対して国・自治体、企業、個人・家族がどう迎え撃つかを示した著作だ。
「3・11の教訓に学ぶ地震対策」と副題がついている。首都直下地震と南海トラフ巨大地震が起これば、人的および社会経済被害は計り知れない。被害の最小化、迅速な回復を図る「減災」と「レジリエント(強靭化)」を早くから訴え続けた河田さんが、災害多発・激化時代に対して国・自治体、企業、個人・家族がどう迎え撃つかを示した著作だ。
東日本大震災やタイ・チャオプラヤ川氾濫被害、米のハリケーン災害などで何がおきたのか。そこから導き出される教訓は、災害は各般、広域、時間的変化と多岐にわたる甚大な影響をしっかり想定した対応の必要性だ。さらに地震と水害などが重なってくる複合災害となることを想定した体制、組織、対策をつくることの緊要性だ。企業におけるBCPは、そうした大災害に対応するものでなくてはならないし、道路や通信などのネットワーク(網)というものにとくに配慮したものでなければならない。
脆弱国土・日本。それが高度に発達し脆弱性をより内包した社会となっていることを直視し、国土と社会の安全保障に踏み出さなければならないことを痛感させる。具体的、包括的、実践的な防災・減災の必読書だ。
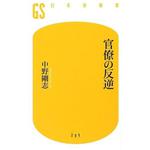 オルテガの大衆社会論と、ウェーバーの官僚論がまず提起される。「官僚の反逆」とは、オルテガの「大衆の反逆」をもじっている。オルテガの大衆批判は辛らつを極めるが、今なお鋭い。オルテガのいう大衆とは「個人としての特定の意見をもたず、附和雷同、大勢に流される人間」という。一方で「エリート、貴族とは決して現状に満足することなく、より高みを目指して鍛錬を続け、常に緊張感をもって生きている存在」であり、オルテガ大衆社会論に依れば、当然ながらエリートは大衆に嫌悪されることになる。この困難な道を引き受けて進もうとすれば、官僚バッシングを蒙ることになるが、その道を逃げれば(エリートからの逃走)凡愚に屈する大衆的人間となり果てる。
オルテガの大衆社会論と、ウェーバーの官僚論がまず提起される。「官僚の反逆」とは、オルテガの「大衆の反逆」をもじっている。オルテガの大衆批判は辛らつを極めるが、今なお鋭い。オルテガのいう大衆とは「個人としての特定の意見をもたず、附和雷同、大勢に流される人間」という。一方で「エリート、貴族とは決して現状に満足することなく、より高みを目指して鍛錬を続け、常に緊張感をもって生きている存在」であり、オルテガ大衆社会論に依れば、当然ながらエリートは大衆に嫌悪されることになる。この困難な道を引き受けて進もうとすれば、官僚バッシングを蒙ることになるが、その道を逃げれば(エリートからの逃走)凡愚に屈する大衆的人間となり果てる。
ウェーバーは、官にも民にも及ぶ近代社会の「官僚化現象」――「官僚は規則の拘束の下で職務を執行し、"非人格的"な没主観的目的に奉仕する義務を負う」「そのためには批判基準の定量化・数値化や、主観的価値判断・感情の排除が随伴する」ことを示す。人格的、主観的な「政治」とは対極に位置する。
私自身が長く意識してきた「大衆社会論」「ファシズム論」には、1930年代のオルテガ、ウェーバー、ホイジンガ、アドルノやベンヤミンらのフランクフルト学派、その後のE・フロム等が常に基底にあった。
本書では、70年代頃から日本の大衆社会化が顕著になり、80年代には決定的になったと見る。「政治の上に立つような"国土型官僚"は60年代までは多数存在したが、70年代には"政治的官僚""調整型官僚"が優勢となり、80年代にはそれとは全く異なる"吏員型官僚(非政治的な官僚)"が現われるようになった。それはウェーバーが抽出した官僚像だ。90年代にはグローバル化の進展とともにその官僚制的支配の拡大が顕著になる」。そして「非政治化・官僚制化による自由民主政治の破壊」となると指摘。
現代社会は、オルテガの大衆社会化状況、ウェーバーの官僚制化現象、ホイジンガの小児病化が顕著になっている。そして中野さんは、リーマン・ショック、ユーロ危機、日本の失われた20年等で、官僚制的支配の破綻が明らかになった今、「自由民主政治」を復活させなければならない。「政治とは何か」を考え、「政治主導」なる意味を真に蘇らせなければならないという。