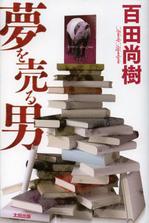「私もまだ85歳」「日本人が守ってきた4000年来の鎮守の森のノウハウを見直し、現地植生調査に基づく、エコロジカルな脚本に則った防災・環境保全林として、いのちを守り、地域経済とも共生する本物のふるさとの森をつくろう」「被災地に南北300kmの"森の防波堤"を築き、それを母胎として日本列島の海岸沿いに、3000kmに及ぶ"森の長城"を築いてはどうか」「今見ている緑は、劣化したものや植えられたものばかりで、その土地本来の森が変えられたものだ。潜在自然植生の樹種を植えて、21世紀の鎮守の森、いのちの森をつくろう」「タブノキこそ、日本の土地本来の照葉樹林文化の原点だ」「"森の防波堤"は、タブノキ、シイ、カシ類を主木とした本物の森とすべきで、これが最適な防潮林、防災・環境保全林として機能する」――。
「私もまだ85歳」「日本人が守ってきた4000年来の鎮守の森のノウハウを見直し、現地植生調査に基づく、エコロジカルな脚本に則った防災・環境保全林として、いのちを守り、地域経済とも共生する本物のふるさとの森をつくろう」「被災地に南北300kmの"森の防波堤"を築き、それを母胎として日本列島の海岸沿いに、3000kmに及ぶ"森の長城"を築いてはどうか」「今見ている緑は、劣化したものや植えられたものばかりで、その土地本来の森が変えられたものだ。潜在自然植生の樹種を植えて、21世紀の鎮守の森、いのちの森をつくろう」「タブノキこそ、日本の土地本来の照葉樹林文化の原点だ」「"森の防波堤"は、タブノキ、シイ、カシ類を主木とした本物の森とすべきで、これが最適な防潮林、防災・環境保全林として機能する」――。
宮脇先生の主張は一貫していて明確。熱気を帯び、未来を見つめ、そして今こそ何をすべきか波が押し寄せるように迫ってくる。
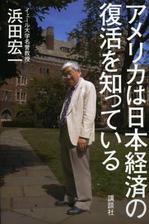 「デフレは、円という通貨の財に対する相対価格、円高は外国通貨に対する相対価格――つまり貨幣的な問題なのである」「実質生産に、人口あるいは生産人口が影響するのは当たり前だが、貨幣的現象である物価、あるいはデフレに人口が効くというのは、まったく的外れな議論だ」「円資産が相対的に品薄なため超円高になっているのだから、円資産の供給を増やしてやればいい」「ゼロ金利下の貨幣の増加は、"流動性の罠"に陥っているため、効かないというが、短期ではない長期国債や民間株式や債券の購入などの広義の買いオペをすることだ」「日本経済が国際的競争力を保つには、もちろん生産性を上げるよう努力しなければならない。しかし、プラザ合意のあとや、リーマン・ショックのあとなど、為替市場に急変が起こって、円高が2桁にまで達したときには、生産性の向上努力では追いつかなくなることがある」「為替は金融政策によって変わる」――。「金融政策がデフレに効くとは限らない」というのは世界孤高の日銀理論だと言い切る。「人々に通貨にしがみつかせないため"期待"に働きかけよ」とその実行を求めている。
「デフレは、円という通貨の財に対する相対価格、円高は外国通貨に対する相対価格――つまり貨幣的な問題なのである」「実質生産に、人口あるいは生産人口が影響するのは当たり前だが、貨幣的現象である物価、あるいはデフレに人口が効くというのは、まったく的外れな議論だ」「円資産が相対的に品薄なため超円高になっているのだから、円資産の供給を増やしてやればいい」「ゼロ金利下の貨幣の増加は、"流動性の罠"に陥っているため、効かないというが、短期ではない長期国債や民間株式や債券の購入などの広義の買いオペをすることだ」「日本経済が国際的競争力を保つには、もちろん生産性を上げるよう努力しなければならない。しかし、プラザ合意のあとや、リーマン・ショックのあとなど、為替市場に急変が起こって、円高が2桁にまで達したときには、生産性の向上努力では追いつかなくなることがある」「為替は金融政策によって変わる」――。「金融政策がデフレに効くとは限らない」というのは世界孤高の日銀理論だと言い切る。「人々に通貨にしがみつかせないため"期待"に働きかけよ」とその実行を求めている。
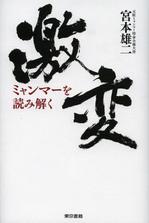 ミャンマーの激変は顕著だ。熱い。そして注目されている。2010年11月、新憲法に基づいての総選挙が実施され、2011年2月には国会でテイン・セイン大統領が選出された。軍も民主勢力も国民が求める経済発展を成し遂げなければならず、ともに自己改革を迫られることになる。政治も社会も明らかに激変の兆しがみられる。志向する経済改革、中国とインドにはさまれるASEANからのゲートウェイ。日本に好意をもってくれている大切な国である。
ミャンマーの激変は顕著だ。熱い。そして注目されている。2010年11月、新憲法に基づいての総選挙が実施され、2011年2月には国会でテイン・セイン大統領が選出された。軍も民主勢力も国民が求める経済発展を成し遂げなければならず、ともに自己改革を迫られることになる。政治も社会も明らかに激変の兆しがみられる。志向する経済改革、中国とインドにはさまれるASEANからのゲートウェイ。日本に好意をもってくれている大切な国である。
ミャンマーの歴史そのものともいえるアウン・サン、ネ・ウィン、タン・シュエ、キン・ニュン、テイン・セイン、そしてアウン・サン・スー・チー。歴史を紐解きつつ、いよいよミャンマーが新しい段階に入った。今度こそ入ったと元ミャンマー大使の宮本さん(私にとっては中国大使としてお世話になった)が期待を込めてミャンマーを語ってくれている。今年は政府間交流も盛んとなっている。