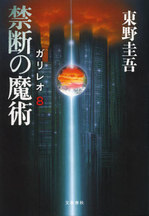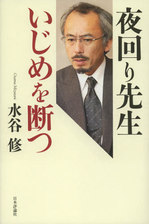 こうすればいじめを解決できる――"夜回り先生"水谷さんは、明確に示す。
こうすればいじめを解決できる――"夜回り先生"水谷さんは、明確に示す。
今の子どもたちがいかに追い詰められているか。大人と違ってストレス発散ができない。子どもたちには閉鎖された学校と家庭しかないうえに、その二つが追い詰められる場所となった時に、もう逃げ場はない。
"いじめ"の原因は家庭や学校、地域などの社会にある。だから閉鎖された学校空間の中の問題ではない。いじめる子もいじめられる子も交替もするし、生涯の傷を負う。水谷さんは、今の子どもに暴れ回るエネルギーや気力がなくなり、「目力」がなく、自己肯定感の希薄さ、自分への自信のないことを心配している。認められたり、ほめられたりすることなく、否定、否定で育てられればたしかにそうなる。
"夜回り先生"水谷さんはずっと、「死にたい、助けて」という子どもに体当たりで相談し続けてきた。本書にもその一端、実例が紹介されている。愛情のない、実情に迫らない、本質を探ろうとしない全てに対して憤りがあふれている。
いじめ現象は「不健全な人間関係(無視や悪口)」「人権侵害(死ね、学校へ来るな)」「犯罪」の三つに分かれるのに、文科省は曖昧な定義で、学校の内に抱え込ませている。人権侵害には人権擁護局などを、犯罪には警察との連携を、学校と教員は「不健全な人間関係」を直し、できなければ"いじめ"の責任を取ること――水谷さんの主張は明確だ。
いじめにどう対処するか――。「今いじめられている君へ」「いじめに気づいている君へ」「今だれかをいじめている君へ」「すべての親へ」「学校関係者へ」「関係機関の人たちへ」「すべての人たちへ」。皆、逃げているではないか。いじめ対策は、総がかりで、踏み込んでこそできるものだ。戦ってこそ解決の道がある――そうした叫びが伝わってくる。必読の本だ。
 内田樹さんの「街場シリーズ」だが、本書は神戸女学院大学での最終講義「クリエイティブ・ライティング」で文学と言語について語ったことを基にしたもの。
内田樹さんの「街場シリーズ」だが、本書は神戸女学院大学での最終講義「クリエイティブ・ライティング」で文学と言語について語ったことを基にしたもの。
「生成的な言葉とは何か?」というテーマが、あたかも宇宙のかなたに一気に行ったかと思うと、緻小の素粒子の世界に入り込むかのように自由自在。「僕らの身体の中心にあって、言葉や思想を紡いでいく基本にあるものは、かたちあるものではない。それは言葉にならない響きや波動や震えとか、そういうような非言語的な形態で、死者たちから生者へと手渡される。言葉というのは、『言葉にならないもの』をいわば母胎として、そこから生成してくる。それを『ソウル』と言ってもいいし、『生身』と言ってもいいと僕は思います。そこから発してくる言葉だけがほんとうに深いところで人を揺さぶる」といい、「響く言葉」「届く言葉」「身体に触れる言葉」とはどういうものか、を語ってくれる。とくに「届く言葉」だ。
それにしても、「人間の言語能力は、われわれが想像しているよりはるかに深く、複雑な仕事を信じられないほどの高速度でこなしている」し、人間の底知れなさは、言語と世界の底知れなさに行き着く。ソシュールのアナグラム研究、ロラン・バルトの「エクリチュール」理論、村上春樹の世界性と司馬遼太郎の日本人のための美学、「大日本帝国の瓦解を怜悧に切り捌く丸山眞男」と「トラウマを抱えた人、大日本帝国に半身を残した少年、吉本隆明や江藤淳」、階層と言語、階層再生産に強い力を発揮する教養・文化資本、階層がない日本と言語、PISAと「広めの射程で自分をとらえる」能力......。
言語、人間、世界、宗教、宇宙、日本、世間、地域、階層、演説、そしてiPS細胞と生命など、さまざま考えさせてくれた。
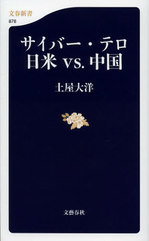 アメリカのワシントンDCに国際スパイ博物館があり、オバマ大統領の演説が引用されている。「テロ行為は、自殺ベストを着たほんの少しの過激派からだけではなく、コンピュータのボードをほんの数回叩くことからもやってくる。これは大量破壊兵器だ」――。
アメリカのワシントンDCに国際スパイ博物館があり、オバマ大統領の演説が引用されている。「テロ行為は、自殺ベストを着たほんの少しの過激派からだけではなく、コンピュータのボードをほんの数回叩くことからもやってくる。これは大量破壊兵器だ」――。
アメリカの「四年毎の国防計画の見直し(QDR)」は、陸、海、空、宇宙に続いて、サイバースペースは第五の戦闘空間になっているとし、宇宙とサイバースペースは「グローバル・コモンズ」であり、それを守らなくてはならないと提言されているという。
しかし、土屋さんは陸などの4つは「自然空間」だが、サイバースペースは「人工空間」であり、情報通信端末、情報通信ネットワーク、記憶装置が相互に接続されているに過ぎず、それぞれには所有者がおり、実はきわめて脆弱な基盤に立脚していると指摘している。
2007年のエストニアへのサイバー攻撃、同年、イスラエルがシリアの防空網を電子的に不能にした後に砂漠の中の秘密設備を爆撃したと思われる事件、2007年7月の米韓への攻撃、2011年にイランが米最新鋭ステルス無人機を撃墜(不時着)させたといわれる事件、そして日本の昨年の衆議院のサーバーに不正侵入が行われてパスワードが盗まれた事件。今年の7月、財務省のコンピュータ約120台が長期にウイルスに感染したことや、昨今の「犯行予告メール」事件・・・・・・。不安を煽ることは良いことではないが、さまざまな規模で"サイバー戦争"が行われる潜在的な脅威を看過することができない。
サイバーセキュリティ(情報セキュリティ)は国際的重要課題となっているし、重要インフラの情報セキュリティ対策の加速、司令塔NISCとインテリジェンス機関の役割拡大は急務だ。
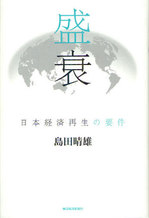 世界から賞賛と羨望を集めた「ジャパンシステム」が、その後進化せず、逆にいまや日本の桎梏となっている。世界がこの半世紀、情報化、グローバル化、環境制約の激化、人口爆発などのメガトレンド、さらには世界経済の大変動、不安定化にさらされるなか、日本では少子高齢化、人口収縮、デフレ、財政難が加速している。島田さんは「これだけの巨大潮流変化のなかで、自らのシステムを進化させなければ、衰退するのは当たり前だ」という。そして「覚悟を決めて、新たな仕組みに変革していけば、日本にはまだまだ大きな可能性と潜在力はある」と具体的提言をしている。
世界から賞賛と羨望を集めた「ジャパンシステム」が、その後進化せず、逆にいまや日本の桎梏となっている。世界がこの半世紀、情報化、グローバル化、環境制約の激化、人口爆発などのメガトレンド、さらには世界経済の大変動、不安定化にさらされるなか、日本では少子高齢化、人口収縮、デフレ、財政難が加速している。島田さんは「これだけの巨大潮流変化のなかで、自らのシステムを進化させなければ、衰退するのは当たり前だ」という。そして「覚悟を決めて、新たな仕組みに変革していけば、日本にはまだまだ大きな可能性と潜在力はある」と具体的提言をしている。
「安心の基本は年金」「雇用慣行と労働政策の大転換を」「新しいエネルギーミックスの考え方」「新時代の国際立国と対日投資を促進させよ」「戦略農業への大転換」「医療を強力な成長産業に」「求められる新たな住宅思想と住宅政策」「日本観光の問題点と可能性」――。時の政府の真ん中で日本の閉塞を打ち破り未来を切り拓く推進役となってきた島田さんだけに、未来性ある具体策が提示されている。進める政治の力こそ本当に大切。