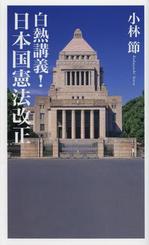「奇跡のリンゴ」「比類なき美味しいリンゴ」「腐らないリンゴ」を農薬も肥料も使わないでつくり上げたリンゴ農家・木村秋則さんの物語。
「奇跡のリンゴ」「比類なき美味しいリンゴ」「腐らないリンゴ」を農薬も肥料も使わないでつくり上げたリンゴ農家・木村秋則さんの物語。
「悲観主義は感情のものであり、楽観主義は意志のものである」――。仏の哲学者アランの「幸福について」の言葉だ。本書を読んで感ずるのは、陽気、執念、夢、生命力、愛情、苦闘、狂気、自然、生態系......。不可能を可能にした木村さんは、「私じゃない、リンゴの木が頑張ったんだよ」「自然の中には、害虫も益虫もない。土、水、空気、太陽の光に風。岩木山で学んだのは、自然というものの驚くべき複雑さだった」と言う。奇跡のリンゴは、文明の対極、人為を意志をもって捨て去った生命哲学の果実、人生哲学の果実だ。
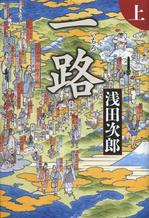 小野寺一路、父が謀略によって不慮の死を遂げたあとを受け、突然、参勤交代を取り仕切る御供頭(おともがしら)の大役を継ぐことを命じられる。主君は知行7500石の旗本、西美濃田名部郡を領分とする蒔坂左京大夫だ。道は中仙道。季節は冬の12月、寒い難所続きだ。
小野寺一路、父が謀略によって不慮の死を遂げたあとを受け、突然、参勤交代を取り仕切る御供頭(おともがしら)の大役を継ぐことを命じられる。主君は知行7500石の旗本、西美濃田名部郡を領分とする蒔坂左京大夫だ。道は中仙道。季節は冬の12月、寒い難所続きだ。
参勤交代という珍しいテーマが扱われ、難所と各宿場での当時の現場の状況が活写されてきわめて新鮮。貫かれているのは、「参勤交代の行列は行軍也」ということだ。物語は「一路とは人生一路、命を懸ける道を歩むこと」「一所懸命」、そして「馬鹿とかうつけ、呆けたふりをしている賢者・名君」の振る舞いや、「今の世の中、うつけでのうては命をなくすゆえ」「人間には隙がなくてはならぬ」「人間の幸福とは、ある程度のいいかげんさによってもたらされるものだ」など、人間学の世界へといざなう。
表紙絵に全てが描かれており、これを見ながら読んだ。
 フランツ・リストの「巡礼の年」「ル・マル・デュ・ペイ」が静かに、メランコリックに流れている。本書に低く奏でられているのは、この心に抱え込んでいる深い哀しみだ。
フランツ・リストの「巡礼の年」「ル・マル・デュ・ペイ」が静かに、メランコリックに流れている。本書に低く奏でられているのは、この心に抱え込んでいる深い哀しみだ。
「自分だけに何故」――突然、あれほど親しかった4人の友に交流を拒絶され、多崎つくるは死を常に意識するほど追い込まれる。それが10年以上も続く。そして現実に肉体を殺害される以上に人生の色彩を奪い、"人生の亡命者"とまでに自らを変貌させた奪命的な傷が、じつは友人にも、年月を超えても振り払うことができないものであったことを知る巡礼の旅――。漱石の小説「こころ」をまず想起した。
人間は自分の色を持って生きる。多崎つくるが自覚するのは、「個性がない」「特段とりえもない」「色彩をもたない」ということだ。しかし高校時代の赤松、青海、白根、黒埜の4人の友人にとっての多崎つくるは、カラフルであったり、安心感のある良き器であった。そのことを拒絶された16年の苦悩を経て知る。
仏法でいう五大――地水火風空のなかで、調和という最も大切な働きである空の存在だ。この巡礼の旅は人間の心の深層に静かに迫るとともに、心地よく一気に読ませる。深く落ち着いて、いい。
 デフレの克服は日本にとって最大の課題だ。「デフレと金融政策をめぐる論争は、混迷する現代マクロ経済学の反映だ」と、吉川さんはいう。そして、日本の「デフレ20年の記録」をたどるとともに、マーシャル、ケインズ、リカードからクルーグマンまでの経済理論を概説する。
デフレの克服は日本にとって最大の課題だ。「デフレと金融政策をめぐる論争は、混迷する現代マクロ経済学の反映だ」と、吉川さんはいう。そして、日本の「デフレ20年の記録」をたどるとともに、マーシャル、ケインズ、リカードからクルーグマンまでの経済理論を概説する。
デフレは「貨幣的な現象」であり、最も重要な変数はマネーサプライであるとする経済学の背後にある「貨幣数量説」――。それらに対して「ゼロ金利のなかでは話は変わってくる」「マネーサプライのなかに解はない」と指摘する。そして「デフレの正体」として「生産年齢人口の減少」の影響は小さく、経済成長にとって主役とは全くいえないとする。さらに日本経済の長期停滞は、デフレが要因であり金融政策が不十分であったという論に対して「デフレは長期停滞の原因ではなく"結果"だ」「デフレに陥るほどの長期停滞を招来した究極の原因はイノベーションの欠乏にほかならない」「経済成長にとって最も重要なのは、新しいモノやサービスを生み出す需要創出型のイノベーションだ(低価格志向、安いモノへの需要のシフトであってはならない)」「日本のデフレは、90年代後半、大企業を中心に高度成長期に確立された旧来の雇用システムが崩壊し、変貌し、名目賃金が下落したことが大きい」などと指摘する。
「流動性のわな」から脱出し、このデフレの下でいかに「将来」の期待インフレ率に働きかける政策が重要なのか、その基本的考え方を提起している。経済論争そのものだ。