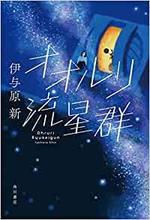 「コーン」「コーン」という流星群の音が読後に余韻として残る。18歳、高校3年生の夏――。6人を中心にした仲間が、文化祭に出展する空き缶を集めた巨大なタペストリーを制作する。校舎の屋上から吊り下げた驚くべき大きさのものだ。近くに進出してきたチェーンのドラッグストアに苦戦する薬局を営む種村久志、東京の番組制作会社を辞め弁護士を目指して勉強中の勢田修、中学教師をしている伊東千佳、天文学の研究者となったスイ子こと山際彗子、会社を辞め引きこもり状態の梅野和也、そして空き缶タペストリーを言い出した張本人・槙恵介。恵介はなぜかタペストリーが完成する前に突然に仲間を抜け、その1年後の夏に死んだ。
「コーン」「コーン」という流星群の音が読後に余韻として残る。18歳、高校3年生の夏――。6人を中心にした仲間が、文化祭に出展する空き缶を集めた巨大なタペストリーを制作する。校舎の屋上から吊り下げた驚くべき大きさのものだ。近くに進出してきたチェーンのドラッグストアに苦戦する薬局を営む種村久志、東京の番組制作会社を辞め弁護士を目指して勉強中の勢田修、中学教師をしている伊東千佳、天文学の研究者となったスイ子こと山際彗子、会社を辞め引きこもり状態の梅野和也、そして空き缶タペストリーを言い出した張本人・槙恵介。恵介はなぜかタペストリーが完成する前に突然に仲間を抜け、その1年後の夏に死んだ。
それから28年、「こんなはずではなかった」と、ため息をつきながら45歳を懸命に生きている皆のもとに、スイ子が秦野市に帰ってきた。手作りで太陽系の果てを観測する天文台を建てるというのだ。久志、修、千佳らは、スイ子の計画に力を貸すことになるが、次第にあの高校3年の輝ける夏に思いを馳せていく。そして、恵介やスイ子が、思いもかけない悩みを抱えながらあの夏を過ごしていたことを知るのだった。「完璧」と思われていた恵介が他に見せなかった心の闇と決断を。
「人間は誰しも、一つの星を見つめて歩いている。・・・・・・それを頼りに歩いていけばいいと思っていた星が突然光を失い・・・・・・。けれど『星食』はいずれ終わる。その時は、見失った星をまた探してもいいし、別の星を見つけて生きていってもいい」「そう、星を見つけるためには、天文台が必要だ。だから今はあれこれ悩むのをやめて、この天文台を作り上げよう。彗子のためではなく、自分のために」「彗子は洟をすすり、千佳の顔を見た。秦野に戻ってくるのは怖かった。だけど、戻ってくるしかなかった。ここで一から始めて、恵介と18歳の自分に向き合わない限り、わたしはもう二度と星にも向き合えない」・・・・・・。
そしてオオルリが導いてくれた天文台だからと、「オオルリ天文台」を、28年の歳月を経た仲間が再結集して作り上げていく。流星電波観測の音が響くのを聴く。なんとも澄みきった星空の心象空間が広がっていく。
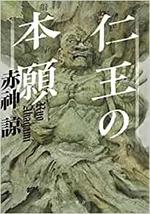 歴史は勝者の歴史となることが多い。織田信長が朝倉・浅井を滅ぼし、本願寺・一向宗を倒したというが、加賀一向宗の中で、孤高の戦いを続けた「仁王」と呼ばれた男がいた。その最強の武僧・杉浦玄任の側から、壮絶な戦いを描き、激しき加賀一向一揆の実像に迫る。
歴史は勝者の歴史となることが多い。織田信長が朝倉・浅井を滅ぼし、本願寺・一向宗を倒したというが、加賀一向宗の中で、孤高の戦いを続けた「仁王」と呼ばれた男がいた。その最強の武僧・杉浦玄任の側から、壮絶な戦いを描き、激しき加賀一向一揆の実像に迫る。
「民の国をつくる」「誰の支配も受けず、民衆が自らのことを自ら治める政」を、加賀一向一揆の坊官・杉浦玄任は不動の信念として貫く。立ちふさがるのは、まずは越前の仏敵・朝倉義景、そして仏敵・上杉謙信、止めは仏敵・織田信長。加賀が生き残るために「仁王」は、あるときは朝倉とも結び、また謙信とも結ぶという智謀を巡らす。本願寺が軍事をも指揮をとる坊官を派遣し、衆議で決める体制をつくったところに信長を悩ました一向宗門徒の独特の形がある。しかし、加賀はこれら強大な外敵に囲まれるなか、間断なき戦闘を余儀なくされる。しかも一向宗内の政は、自己保身と腐敗・堕落が充満する有様であった。普段は穏やかで私心がなく、戦いにあっては鬼神のごとき「仁王」への民の信頼が高まるが、それがまた嫉妬の感情を呼び起こす始末。そのなかで「仁王」は戦い続けるが、歴史の濁流に飲み込まれていく。
「乱世と加賀一向一揆」「民の国への本願と宗教的情念」「民主主義の理想と政治権力」などの難題を、武僧の感動的・崇高な生き様で描く。現実にあった悲劇的エンタテイメント。
 「消費者金融と日本社会」が副題。個人への少額の融資を行ってきたサラ金や消費者金融。戦前の素人高利貸から質屋、団地金融を経て、経済変動や不況、法的規制を受けながらも金融技術の革新によって乗り越えてきたサラ金・消費者金融。サラ金が貧困者のセーフティーネットであった事実とともに、多重債務者や苛烈な取り立てによって自己破産や自殺者を生み、多くの人々を破滅へと追いやったことも現実である。「サラ金の非人道性を強調するだけで、問題が本当の意味で解決するとは思えない」「サラ金は、貯蓄超過や金融自由化というマクロな経済環境の変化と深く結びつきながら成長し、現在も日銀・メガバンクを頂点とする重層的な金融構造の中にしっかり根を下ろしている。個人間金融から生まれたサラ金を肥大させたのは、日本の経済発展を支えてきた金融システムと、それを利用する私たち自身だった」「21世紀初頭、主要なサラ金企業の多くはメガバンクを中心とする銀行の傘下に入った。小口信用貸付の主流は、サラ金を含む貸金業から、銀行カードローンへと移りつつある」・・・・・・。戦後76年、激変する日本経済・社会の中で、現場の庶民の生活・家計と小口信用貸付・サラ金という生々しい現実から描く日本の経済史。極めて優れた意欲作。
「消費者金融と日本社会」が副題。個人への少額の融資を行ってきたサラ金や消費者金融。戦前の素人高利貸から質屋、団地金融を経て、経済変動や不況、法的規制を受けながらも金融技術の革新によって乗り越えてきたサラ金・消費者金融。サラ金が貧困者のセーフティーネットであった事実とともに、多重債務者や苛烈な取り立てによって自己破産や自殺者を生み、多くの人々を破滅へと追いやったことも現実である。「サラ金の非人道性を強調するだけで、問題が本当の意味で解決するとは思えない」「サラ金は、貯蓄超過や金融自由化というマクロな経済環境の変化と深く結びつきながら成長し、現在も日銀・メガバンクを頂点とする重層的な金融構造の中にしっかり根を下ろしている。個人間金融から生まれたサラ金を肥大させたのは、日本の経済発展を支えてきた金融システムと、それを利用する私たち自身だった」「21世紀初頭、主要なサラ金企業の多くはメガバンクを中心とする銀行の傘下に入った。小口信用貸付の主流は、サラ金を含む貸金業から、銀行カードローンへと移りつつある」・・・・・・。戦後76年、激変する日本経済・社会の中で、現場の庶民の生活・家計と小口信用貸付・サラ金という生々しい現実から描く日本の経済史。極めて優れた意欲作。
「家計とジェンダーから見た金融史」「『素人高利貸し』の時代――戦前期」「質屋・月賦から団地金融へ――1950~60年代」「サラリーマン金融と『前向き』の資金需要――高度成長期」「低成長期と『後ろ向き』の資金需要――1970〜80年代」「サラ金で借りる人・働く人(債務者の自殺・家出、債務回収の金融技術) ――サラ金パニックから冬の時代へ」「長期不況下での成長と挫折(改正貸金業法の影響と帰結) ――バブル期〜2010年代」「『日本』が生んだサラ金」・・・・・・。
戦後日本の経済・社会が、生々しく描かれる鮮やかな労作。私自身、様々なことが思い起こされる。
外濠、日本橋川を浄化、玉川上水の清流を復活させ、「水の都」東京を蘇らせる――。28日、公明党東京都本部の「水と緑の回廊PT」(顧問=太田昭宏、座長=竹谷とし子参院議員)が東京都庁で行われ、出席しました。
これには、「玉川上水・分水網を生かした水循環都市東京連絡会」(代表=山田正・中央大教授)の有識者、国交省、東京都の三者が集合。公明党から竹谷としこ座長をはじめ、国会・都議会・関係する区市議会議員らが参加し、意見交換をしました。
「外濠浄化を具体的に始め、人々が憩う外濠の水辺再生をめざす(東京都)」「世界では大都市内の水浄化プロジェクトが話題になっている。現在の外濠のようにアオコが発生している状況を早く打開すべきだ」「玉川上水は大都市江戸の用水供給の重要な施設であり、貴重な土木資産でもある。『史跡及び名勝区間』として誇るべきものであり、再評価すべきだ」「外濠・日本橋川が浄化され、舟運・観光のできるものにしたい」「東京はかつて水の都であった。その歴史を学び、復活・再生させる最後のチャンスだ。公明党のこのPTに大いに期待する」など多くの意見がされました。
私は、このPTの呼び掛け人でもあり、水循環・防災・観光・まちづくりのためにも歴史性をしっかりと踏まえた構想実現を決意しています。先般、成立した東京都の来年度予算においても、外濠浄化の推進を始め、様々な取り組みが決まっており、前進しています。
 村上春樹の短編小説6編。いずれも「女のいない男」「いろんな事情で女性に去られてしまった(去られようとしている)男たち」を描く。「ドライブ・マイ・カー」は映画化されて、カンヌ国際映画祭、アカデミー賞など数々の受賞をした原作でもあり、どう映像となるかも興味深い。
村上春樹の短編小説6編。いずれも「女のいない男」「いろんな事情で女性に去られてしまった(去られようとしている)男たち」を描く。「ドライブ・マイ・カー」は映画化されて、カンヌ国際映画祭、アカデミー賞など数々の受賞をした原作でもあり、どう映像となるかも興味深い。
「ドライブ・マイ・カー」――。舞台俳優・家福は突然、美しい妻を子宮癌で失い喪失感に苛まれ続ける。愛し合っていた二人だが、妻はなぜか他の男と関係を結んでいた。専属ドライバーになった寡黙な若い女性・渡利みさきと少しずつ内面の話をするようになる。「僕らはみんな同じような盲点を抱えて生きているんです」「家福さん。考えてどうなるものでもありません。私の父が私たちを捨てていったのも、母親が私をとことん痛めつけたのも、みんな病がやったことです。頭で考えても仕方ありません」・・・・・・。
「イエスタデイ」――。田園調布出身なのにコテコテの関西弁をしゃべる浪人中の木樽と、芦屋出身で一切関西弁をしゃべらない大学生の谷村。木樽はなんと自分の彼女の栗谷えりかを「おまえ、こいつと個人的につきおうてくれへんかな?」と驚くべきことを言う。「独立器官」――。52歳になるまで約30年、常に複数の「ガールフレンド」を持っていた独身の医師・渡会。思いもよらず深い恋に落ちてしまった。「逢ひ見ての のちの心に くらぶれば 昔はものを 思はざりけり」(権中納言敦忠)のような、さよならの後に感ずる喪失感や息苦しさを感じるのだった。そして「私とはいったいなにものだろう」と・・・・・・。食べ物が喉を通らなくなり命を落とすのだが、渡会は「すべての女性には、嘘をつくための特別な独立器官のようなものが生まれつき具わっている」と意味深長なことを言っていたことを想い起こす。
「シェエラザード」――。北関東の地方小都市の「ハウス」に送られた羽原のところに、週2回のペースで「連絡係」の女性が訪れる。交わった後彼女は「千夜一夜物語」の王妃シェエラザードと同じように興味深い話をしてくれる。「シェエラザード」と名付けられた彼女は、17歳の高校2年の時、同じクラスの男の子に恋をして、「私は定期的に彼の家に空き巣に入らないではいられないようになった」ことを打ち明けるのだった。「木野」――。妻に男ができて離婚、小さな喫茶店「木野」を開いた男・木野。そこを訪れるカミタという男、体に火傷を負う女、猫、そして蛇。「彼をほのめかしの深い迷宮に誘い込もうとするかのように、どこまでも規則正しく。こんこん、こんこん、そしてまたこんこん。目を背けず、私をまっすぐ見なさい、誰かが耳元でそう囁いた。これがおまえの心の姿なんだから」・・・・・・。成熟した男女の心のひだと深層、色彩のない景色と長雨、それを絶妙のセンスとメロディーとリズムで描く。
「女のいない男たち」――。夜中の1時過ぎに低い声の男から「妻が先週自殺した」と電話がある。なぜ、長い間彼女に会ってもいない自分に知らせてきたのだろう。結婚したことも、どこに住んでいるかも知らない自分に。「女のいない男たちになるのはとても簡単なことだ。一人の女性を深く愛し、それから彼女がどこかに去ってしまえばいいのだ」「女のいない男たちになるのがどれくらい切ないことなのか、痛むことなのか、それは女のいない男たちにしか理解できない。素敵な西風を失うこと」・・・・・・。一人の女性を失うことは、すべての女性を失うことでもあり、仕切りのない広々とした音楽、色彩や奥行きのある世界を失うことでもある。




