 訳者の岸本佐知子さんはいう。「ルシア・ベルリンの名を知ったのは今から十数年前・・・・・・。一読して打ちのめされた。なんなんだこれは、と思った。聞いたことのない声、心を直に揺さぶってくる強い声だった。行ったことのないチリやメキシコやアリゾナの空気が、色が、においが、ありありと感じられた。見知らぬ人々の苛烈な人生がくっきりと立ち上がってきた。彼らがすぐ目の前にいて、こちらに直接語りかけてくるようだった」と。とてもこんなにうまく表現できないので引用させていただいた。全くその通り。人生の起伏が、大いなる振幅が、感情豊かに、しかもラップのようなリズムで迫ってくる衝撃作だ。彼女の作品の多くは彼女の実人生に基づいているが、小説なのか実際なのかがよくわからない。それ以上に圧倒的な迫力でどっちでも良いと思ってしまう。
訳者の岸本佐知子さんはいう。「ルシア・ベルリンの名を知ったのは今から十数年前・・・・・・。一読して打ちのめされた。なんなんだこれは、と思った。聞いたことのない声、心を直に揺さぶってくる強い声だった。行ったことのないチリやメキシコやアリゾナの空気が、色が、においが、ありありと感じられた。見知らぬ人々の苛烈な人生がくっきりと立ち上がってきた。彼らがすぐ目の前にいて、こちらに直接語りかけてくるようだった」と。とてもこんなにうまく表現できないので引用させていただいた。全くその通り。人生の起伏が、大いなる振幅が、感情豊かに、しかもラップのようなリズムで迫ってくる衝撃作だ。彼女の作品の多くは彼女の実人生に基づいているが、小説なのか実際なのかがよくわからない。それ以上に圧倒的な迫力でどっちでも良いと思ってしまう。
ルシア・ベルリンは1936年アラスカ生まれ。鉱山技師だった父親の仕事の関係で幼少期より北米の鉱山町を転々とし、成長期の大半をチリで過ごす。3回の結婚と離婚を経て4人の息子を育てる。その間、学校教師、掃除婦、電話交換手、看護助手などをして働くが、アルコール依存症にも苦しむ。数少ない短編小説の中で、本書はその中の24の小説を選んでいる。いずれもこれほどの躍動感、洞察力、迫力、詩情、したたかな生命力、むき出しの言葉とユーモアはないと思わせる作品ばかりだ。とにかく庶民の泣き笑い、ズルさや怠惰、たくましさや怒り、死に直面する恐怖と寂寥が激しく迫ってくる。それらは、今の時代に最も欠け、隠蔽されているように思える。同時代を生きた者の一人として、感じることも多く、また日本と違って、荒々しい米国、チリ、メキシコの生々しい生活の実態に抱え込まれる。リズムある訳の素晴らしさにも感動する。拍手。
 外国人と共生する日本、外国人労働者が働きに来て良かったという日本――。今後の日本にとって重要なこの課題が、コロナ禍のなかでどうなっているかを心配している私にとって、貴重なルポだ。
外国人と共生する日本、外国人労働者が働きに来て良かったという日本――。今後の日本にとって重要なこの課題が、コロナ禍のなかでどうなっているかを心配している私にとって、貴重なルポだ。
劣悪で悲惨な技能実習生や留学生。そういった時代はこの10年、変革への途上にある。私自身も「建設」を中心にして課題克服に力を注ぎ、3年前からは「特定技能」の制度が始まっている。外国人を「都合のよい雇用調整弁」として使い捨てた歴史があるが、コロナ禍でも「クビを切られるのは、まず外国人から」という現実は今回でも起きていた。ゆえに「10万円給付が外国人も対象となったという喜びがあった」「東海地方に多い外国人労働者(1990年の入管法改正で日系2世・ 3世と配偶者に定住者の資格が与えられ急増)」「技能実習生が2年間を終え技能実習3号となると転職できる。しかし、コロナ禍で中小企業の仕事は激減して放り出され、パワハラにも遭い、名古屋イエス・キリスト教会に転がり込んだ」「2020年4月に襲った首切りの大波」「コロナ失職とともに外国人労働者の高齢化問題がある」「とくに留学生が母国で足止めを食らって新大久保の街からも消えた」「オンラインの授業は果たして留学なのか(現地で暮らし、人と交流し、友達ができてこそ留学)」「まだまだある技能実習生への不当な天引き、残業代不払い、暴力、セクハラ」「逃亡実習生が助けを求める埼玉県本庄市のベトナム尼僧の大恩寺」「ルールを優先する日本人、動く範囲が広く、ルール・法律よりも家族の縁や仏の教えが規範となる東南アジアの人々」「名古屋にもあるベトナム人の駆け込み寺」「留学生は都市出身で実家も裕福が多いが、実習生は地方出身で野生のような生き抜くたくましさがある。従順な労働力と思ったら大間違い」「何でも対象外の難民たち(10万円も)」・・・・・・。
しかし、悲惨とか「かわいそうな弱者」ではない。たくましく、したたかに「コロナをチャンス」としようとしている姿、「出店ラッシュ」「店舗に空きが出るとすぐ埋まってしまう」姿を描き出している。「この街はコロナに負けなかった」・・・・・・。「彼らはもうこの国にしっかり根づき、この社会の成員として生活を紡いでいる」という。
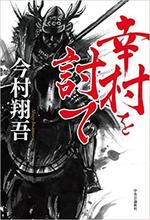 「そもそも人は何故、名を残そうとするのだろう」「鳥の如く、獣の如く、ただ飯を食らい、糞をして、眠りにつく。その繰り返しでよいはずなのに、人は何故か生に意味を見出そうとする。・・・・・・そしてそれを後世に何らかの形で残したいという願望を心の何処かで持っている」「真田の家を守りつつ、後世まで真田の名を轟かせる。父(昌幸)の死後、この壮大な計画を持ちかけてきたのは源次郎(真田幸村=信繁)であった」「兄・信幸は真田を守るために徳川につき信之と名を変えた。九度山を出て大坂城へ向かう砌、信繁は真田家累代が受け継いできた字『幸』を名乗リ幸村となった」「『信』の字は、御屋形様の俗世の名、武田晴信からきているのである」・・・・・・。
「そもそも人は何故、名を残そうとするのだろう」「鳥の如く、獣の如く、ただ飯を食らい、糞をして、眠りにつく。その繰り返しでよいはずなのに、人は何故か生に意味を見出そうとする。・・・・・・そしてそれを後世に何らかの形で残したいという願望を心の何処かで持っている」「真田の家を守りつつ、後世まで真田の名を轟かせる。父(昌幸)の死後、この壮大な計画を持ちかけてきたのは源次郎(真田幸村=信繁)であった」「兄・信幸は真田を守るために徳川につき信之と名を変えた。九度山を出て大坂城へ向かう砌、信繁は真田家累代が受け継いできた字『幸』を名乗リ幸村となった」「『信』の字は、御屋形様の俗世の名、武田晴信からきているのである」・・・・・・。
慶長19年、20年(1615年)の大坂冬の陣と夏の陣。大坂城には、魑魅魍魎、曲者たちが、それぞれの思惑と野望と人生をかけて集っていた。元大名や武将や浪人・・・・・・。長曽我部盛親、後藤又兵衛、織田有楽斎、南条元忠、毛利勝永・・・・・・。その中心の一人が真田幸村であった。これら武将や浪人も、それに対する徳川家康、伊達政宗ら周りのものも皆、何年にもわたって積み重ねられた真田父子の想像を絶する智謀に翻弄される。そして本書は、幸村と緻密に連携する兄・信幸の凄まじき用意周到なる深慮遠謀を浮き彫りにする。いつも新しい人物像を鮮やかに描く今村翔吾だが、今回は真田幸村の陰に隠れがちであった兄・真田信之の凄まじさを描いている。
「なぜ幸村と名乗ったのか」「兄は徳川、弟は豊臣、家康を翻弄した父・昌幸の父子三人は何を考え志したか」――。その智謀と尋常ならざる父子の情が描かれる。心の奥底からの重い情念だ。「これまで家康は、昌幸を、真田という家を問答無用に憎悪してきた。だが今回、真田家について、親兄弟の間に存在する尋常ならざる情の深さを知った。その根にある絆を」。そして戦国時代最後の戦いである大坂の陣、大坂落城、幸村の死後、家康と真田信之の壮絶な言葉による智謀の戦いを描く。攻める家康、凌ぐ真田信之。その生死をかけた尋問は息が詰まるほどの緊迫感に満ちたものだ。そして真田信之は語るのだ。「背後には乱世が。眼前には泰平が。・・・・・・悠久の歴史に己の名を刻むために生きるのか、それとも歴史に刻み込まれて生きるのか。どちらが正しいというわけではなく、どちらもまた人という生き物のあり方なのではないか。ただ弟は、少なくとも前者を求め、荒れ狂う時代を風のごとく最後まで駆け抜けた」と。本書もまた素晴らしき力みなぎる作品。
6日、愛知県豊橋市で行われた「東三河政経セミナー」で講演を行うとともに、豊橋市駅前の再開発地にできた「emCAMPUS(エムキャンパス)」を視察。また田原市の港湾開発が予定されている公共岸壁などを視察しました。これには自民党根本幸典衆院議員、公明党の伊藤渉衆院議員、安江伸夫参院議員等が出席しました。
政経セミナーでは神野吾郎豊橋商工会議所会頭、浅井由崇豊橋市長、山下政良田原市長など、東三河の有力者多数が参加。私は「世界は今、コロナウィルス、ロシアによるウクライナ侵攻、気候変動問題など、歴史の大きな転換点にある。日本は自身の立ち位置が大きく問われており、未来に向けて根源的かつ総合的な戦略を構築しなければならない」「国際社会は、中国・ロシアと対峙する欧米先進国のなかにあって、情報・軍事・経済が複雑に絡み合っている。大国が他国を侵略するなどという事態は戦後なかったことだ。経済も安全保障もどう進めていくか。国内での長期の緩やかなデフレや少子高齢社会、頻発する災害や環境・エネルギー問題など難問に立ち向かっていかなければならない。深い論議があってこそのリーダーシップである」などと講演しました。地域の発展に向けてさまざま懇談を行いました。公明党への期待が寄せられました。
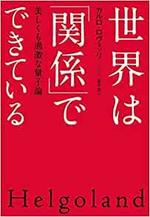 「美しくも過激な量子論」が副題。著者は「時間は存在しない」の著書でも名高い理論物理学者で「ループ量子重力理論」の提唱者の一人。竹内薫氏の解説がついている。単なる量子物理学の解説書、難解な数式を駆使しての書ではない。「科学とは世界を概念化する新しい方法を探ること」であり、物理学もそのルーツをたどれば「自然哲学」であり、この世界をひもとく思想である。コペルニクスの地動説、ニュートン力学、ダーウィンの進化論、アインシュタインの相対性理論を経て、古典力学では捉え切れない一見奇異な量子現象をとらえる「量子論」が、いかに人類の世界観にインパクトを与えたか、量子物理学の真髄を解き明かそうとしたのが本書だ。したがってロヴェッリの思索の旅は物理学にとどまらず、あらゆる思想・哲学に及ぶ。ハイゼンベルクのみならずボグダーノフ、レーニンの政治まで及ぶが、特に「量子理論」がナーガールジュナ(龍樹)の「空」の哲学にまで結びついていく。「びっくり仰天した」とロヴェッリはその衝撃を語るが、圧巻であり、興奮を私自身、共にする思いだ。
「美しくも過激な量子論」が副題。著者は「時間は存在しない」の著書でも名高い理論物理学者で「ループ量子重力理論」の提唱者の一人。竹内薫氏の解説がついている。単なる量子物理学の解説書、難解な数式を駆使しての書ではない。「科学とは世界を概念化する新しい方法を探ること」であり、物理学もそのルーツをたどれば「自然哲学」であり、この世界をひもとく思想である。コペルニクスの地動説、ニュートン力学、ダーウィンの進化論、アインシュタインの相対性理論を経て、古典力学では捉え切れない一見奇異な量子現象をとらえる「量子論」が、いかに人類の世界観にインパクトを与えたか、量子物理学の真髄を解き明かそうとしたのが本書だ。したがってロヴェッリの思索の旅は物理学にとどまらず、あらゆる思想・哲学に及ぶ。ハイゼンベルクのみならずボグダーノフ、レーニンの政治まで及ぶが、特に「量子理論」がナーガールジュナ(龍樹)の「空」の哲学にまで結びついていく。「びっくり仰天した」とロヴェッリはその衝撃を語るが、圧巻であり、興奮を私自身、共にする思いだ。
科学界最大の発見である量子論の核心とは何か。時は1925年夏、物質粒子を追い求めてきた世界に、量子論を着想したドイツの青年、ハイゼンベルクが登場する。そして本書は、ハイゼンベルクやシュレーディンガーらの戦いをドラマチックに表現する。ミクロの世界の深淵に迫れば、「物理学は長い時間をかけて、物質から分子、原子、場、素粒子・・・・・・というふうに『究極の実体』追い求めてきた。そのあげく、量子場の理論と一般相対論のややこしい関係に乗り上げて、にっちもさっちもいかなくなった」、そして「この世界は実体ではなく、関係に基づいて構成されている」「あくまでも相互依存と偶発的な出来事の世界であって、『絶対的な存在』を引き出そうとするべきではない。根源的な確かさの不在こそ、知の探求を育む」「私たちが観察しているこの世界は、絶えず相互に作用しあっている。それは濃密な相互作用の網なのだ」「『シュレーディンガーの猫』の思考実験が示すように、量子は確率的で重ね合わせされた状態にある」・・・・・・。
量子力学は「粒子と波の二重性(本質は波)」「観測するまで実在しないという非実在性」「位置と速度は同時に決まらないという不確定性(古典力学では確定)」「エネルギーの壁をすり抜けるトンネル効果」などの特徴をもつが、本書はその歴史的な数々の論争をドラマチックに再現する。そして宇宙とは何か、世界とは何かの命題に、物理・科学者だけでなく哲学者・宗教者等がいかに迫ったか、そして今も挑戦しているかを生きいきと描く。




