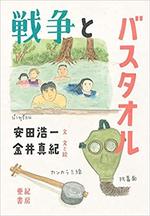 銭湯は癒しの空間だ。一仕事終えた後、「ふう」と湯船につかった心地良い思い出を誰しももっているだろう。内風呂をもってなかった我々の世代は特にそうだ。安田さんと金井さんのコンビが国内外の様々な銭湯や温泉を訪ねるが、そこには凄まじい歴史があった。
銭湯は癒しの空間だ。一仕事終えた後、「ふう」と湯船につかった心地良い思い出を誰しももっているだろう。内風呂をもってなかった我々の世代は特にそうだ。安田さんと金井さんのコンビが国内外の様々な銭湯や温泉を訪ねるが、そこには凄まじい歴史があった。
「ジャングル風呂と旧泰緬鉄道」「秘境・ヒンダット温泉」――。タイ中部の街カンチャナブリーからバスで3時間、そこには映画「戦場にかける橋」の舞台となった場所、クウェー鉄橋があり、日本兵がジャングルで露天風呂として整備したヒンダット温泉があった。クワイ河マーチが響き出すが、強制労働と虐待と日本兵の心情を想い起こす。
「日本最南端の沖縄ユーフルヤー」――。沖縄市にある今や沖縄唯一の銭湯「中乃湯」に行く。湯上がりに出会ったおじさんが語る米軍上陸、特攻隊、収容所の日々。そして今に続く基地問題・・・・・・。
「温泉、沐浴場、チムジルバン・・・・・・、釜山やソウルのお風呂」――。日韓の入浴観の違いやアカスリ、そして日韓の歴史・・・・・・。「神奈川県の寒川町(引揚者住宅には風呂がなく銭湯開業の嘆願書でできた風呂)」――そこには相模海軍工廠があり、その秘密の工場で毒ガスが製造されていた。
「広島県の大久野島(「うさぎの島」の毒ガス兵器)」――。温泉が湧き、各所でうさぎが跳ね回る大久野島には、陸軍の日本最大規模の毒ガス工場があった。作業に従事した人の被害、中国大陸に送られた毒ガス兵器と戦後の被害・・・・・・。
二人は裸になる銭湯や温泉で、庶民からあの戦争の加害・被害の生々しい証言を聞いていく。「温泉と戦争」という対比が鮮やか。それがより深く浮き彫りにされる。
 あの「スマホ脳」のアンデシュ・ハンセン氏の特別授業。前著では、スマホの便利さに溺れているうちに、うつ、睡眠障害、記憶力・集中力・注意力の減退、学力低下、依存等々、脳が蝕まれていく恐るべき実態を暴き出した。脳は周囲の環境を理解し、新しい情報を探そうとするが、その脳内物質がドーパミン。ドーパミンの最重要課題は、人間に行動する動機を与えることだが、SNSはその報酬中枢を煽る。ではどうすればいいのかを本書で語る。
あの「スマホ脳」のアンデシュ・ハンセン氏の特別授業。前著では、スマホの便利さに溺れているうちに、うつ、睡眠障害、記憶力・集中力・注意力の減退、学力低下、依存等々、脳が蝕まれていく恐るべき実態を暴き出した。脳は周囲の環境を理解し、新しい情報を探そうとするが、その脳内物質がドーパミン。ドーパミンの最重要課題は、人間に行動する動機を与えることだが、SNSはその報酬中枢を煽る。ではどうすればいいのかを本書で語る。
一言で言えば「運動しよう。そうすれば脳は確実に強くなる」ということだ。「運動の後にもらえるドーパミンの方が、スマホからもらえるよりずっと量が多い」「ストレスを受けると扁桃体が警報を鳴らす。この扁桃体の大騒ぎにブレーキをかけてくれるのが海馬(記憶をつかさどる)と前頭葉。海馬と前頭葉を強くするのが運動だ」「運動によって1番強化される脳の部分は前頭葉と前頭葉皮質」「昔に比べるとスマホ、パソコン、テレビなどスクリーンの前で過ごす時間が増えている。今の子供は、すぐご褒美(ドーパミン)をもらうことに慣れてしまい、スポーツ、勉強、読書、楽器を弾くなど我慢強く練習できない。ドーパミンの罠にハマらないようにすることが大切」「短期記憶が保存される場所が海馬。短期記憶から長期記憶の移動(固定化)を選ぶのも海馬」などという。
自分最強の脳を手に入れ、ストレスに強くなるため、運動がいかに大事かを解説している。
新しい年を迎えました。これまで多くの方々に本当にお世話になり、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。新たな気持ちで、「報恩」「共戦」で頑張ります。
今年は日本にとって大事な年となります。コロナの克服は全てにわたる最重要課題。「ワクチン」「治療薬」の2つの武器を手に入れましたが、日常の油断なき対応に心して努めなければなりません。
今年のテーマは、2030年へのダッシュ。SDGsの目標も2030年、地球環境・エネルギー問題も2030年までにどこまでやり抜けるか。「少子高齢社会」「AI ・IoT・ロボット・デジタル化の急進展」「レベルの変わった大災害への防災・減災」という構造変化にどう挑むか。コロナ克服後の世界の激変・競争にどう闘うか。
本年も何卒よろしくお願いいたします。
本年が皆様にとって良き1年でありますように。
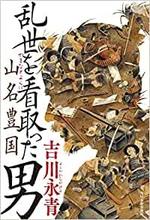 「何ゆえ山名家は没落の途を余儀なくされたのか。幕府の累代管領、栄達と権勢を渇望した者たちの私欲に巻き込まれ、振り回されてきたからだ」「信長には天下布武の大志があった。天下に静謐をもたらし、武王の徳政を布く。・・・・・・翻って羽柴はどうだ。立身出世も結構だろう。では何を志すがゆえの栄達なのか。それに対する答えを、恐らく羽柴は持たない」――。
「何ゆえ山名家は没落の途を余儀なくされたのか。幕府の累代管領、栄達と権勢を渇望した者たちの私欲に巻き込まれ、振り回されてきたからだ」「信長には天下布武の大志があった。天下に静謐をもたらし、武王の徳政を布く。・・・・・・翻って羽柴はどうだ。立身出世も結構だろう。では何を志すがゆえの栄達なのか。それに対する答えを、恐らく羽柴は持たない」――。
足利幕府の名門と崇められた山名家。12代目・山名宗全が応仁の乱を起こし凋落を始める。その90年後、時は戦国時代間近。かつて治めていた分国も次々失われ、今となっては但馬と西隣の因幡を家領に残すのみとなっていた。この苦境を撥ね退け、中興との願いを当主・伯父の裕豊の下で育った山名豊国は託せられる。
しかし、織田と毛利の二大勢力に挟まれ、どちらにつくかで、裏切りを繰り返す。但馬衆や因幡衆の手前勝手な不平・不満・反発を戒められず、国はますます混乱していく。尼子の残党(山名鹿之助ら)の生き残り戦略、秀吉の策謀等々、ついに山名家は潰れる。まさに東西の攻防激しき地、因幡、但馬、播磨、摂津の武将はいずれも苦難の歴史をたどることになる。
そして秀吉に"名門"であることで身を寄せることになった山名豊国だったが、家康から声をかけられ、将棋相手となるなど心を打ち明けるほど昵懇となる。秀吉の死、関ヶ原、二度の大坂城攻めによる豊臣滅亡、家康の死・・・・・・。禅高入道・山名豊国は乱世の終わりを見届ける"役目"(我が生、定数あり)を終え、寛永3年(1626年)齢79の生涯に別れを告げた。





