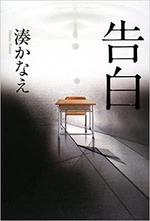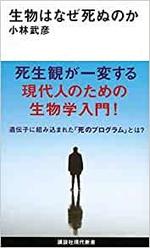 そもそも「生物はなぜ誕生したのか」「生物はなぜ絶滅するのか」「生物はどのように死ぬのか」「ヒトはどのように死ぬのか」「生物はなぜ死ぬのか」――。東大定量生命科学研究所教授、前日本遺伝学会会長、生科学学会連合代表の小林武彦教授が、医学というより「生物」「生命科学」での研究から論及し、思索へと導く。「死は生命の連続性を維持する原動力」「死とは、進化、つまり『変化』と『選択』を実現するためにある。『死ぬ』ことで生物は誕生し、進化し、生き残ってくることができた」「生まれるのは偶然、死ぬのは必然、だから"なぜ自分は死ぬのか"を考えることに意味がある」・・・・・・。
そもそも「生物はなぜ誕生したのか」「生物はなぜ絶滅するのか」「生物はどのように死ぬのか」「ヒトはどのように死ぬのか」「生物はなぜ死ぬのか」――。東大定量生命科学研究所教授、前日本遺伝学会会長、生科学学会連合代表の小林武彦教授が、医学というより「生物」「生命科学」での研究から論及し、思索へと導く。「死は生命の連続性を維持する原動力」「死とは、進化、つまり『変化』と『選択』を実現するためにある。『死ぬ』ことで生物は誕生し、進化し、生き残ってくることができた」「生まれるのは偶然、死ぬのは必然、だから"なぜ自分は死ぬのか"を考えることに意味がある」・・・・・・。
「138億年前にビッグバンから宇宙が始まり、やがて生き物の"タネ"が誕生する」「有機物が生成され、その中にはタンパク質の材料となるアミノ酸や核酸(DNA、RNA)の元"タネ"となった糖や塩基が含まれる」「自己複製型RNAが変化と選択を繰り返し、"生物のタネ"ができ上がる」「生き物の中で最も作りがシンプルなのは細菌(バクテリア)、それより小さいのがウイルス(遺伝物質DNAやRNAとそれを取り囲むタンパク質のカプシド(殻)からなる)。ウイルスは自分だけでは生きられない、体やエネルギーに必要なタンパク質を作れないので"無生物"」「ウイルスは直径1万分の1ミリ、スパイク(トゲの生えた膜)に遺伝物質であるRNAが入っている。体内に入るとスパイクが細胞表面のタンパク質と結合し、細胞にウイルスが入ると1本鎖のRNAが、宿主細胞のリボソーム(遺伝情報の翻訳装置、細胞内でRNAの配列情報からアミノ酸を繋げてタンパク質を作る装置)を使って自身を増やすためのタンパク質を合成、数百倍にも増える」「DNAとRNAは似ているが、DNAは安定していて分解されにくい。RNAは反応性に富んでおり、自己複製やタンパク質と結合しやすい」。
「現在の地球は、過去最大の大量絶滅時代」「ヒトの先祖は果物好きなネズミ?」「赤と緑の色覚の相同組換えという配列交換が起こりやすい」「アフリカに残った霊長類は、気候変動で木から下りたサルとなった(ヒトへの進化)」「死も進化がつくった生物の仕組みの一部(ほとんどが絶滅、"進化"して、たまたま生き残った)」「生物種で死に方が異なる。小さい動物は"食べられないこと"、大きい動物は"食べること"が生きること。人間のような長い老化期間はなく、生殖というゴールを通過すると寿命となる。死に方は生き残るために進化する過程の"選択"」。
「日本人の平均寿命は、旧石器縄文時代は13~15歳、弥生時代20歳、平安時代31歳、鎌倉・室町時代は20歳台に逆戻り、江戸時代は38歳、明治・大正は43歳~44歳、今は女性87.45歳、男性81.41歳」「幹細胞と生殖細胞は生涯生き続けるがゆっくり老化する。組織や器官を構成する体細胞は約50回分裂するとやがて死んでいく(幹細胞が新しく供給する)(体細胞でも心筋と神経細胞・脳は入れ替わらない)」「老化した体細胞は"毒"をばらまく」「老化細胞で多量に発現するFOXO4がP53を邪魔する。邪魔できないようにP53の結合部位にくっつく小さいタンパク質(ペプチド)を合成してマウスに投与すると機能回復した」「なぜ細胞の老化が必要か――活性酸素(細胞を酸化・錆びさせる)で多細胞生物の細胞が機能低下し、がん細胞が生き残って増殖する。がん化のリスクを避けるには1つは免疫機構、1つは細胞老化機構だ。細胞が異常になる前に新細胞と入れ替えるのが細胞老化機構だ。老化もまたヒトが生きるために獲得してきたものだ」「ヒトの体内でわざわざ細胞を死なせるプログラムが遺伝子レベルで組み込まれている」と解説する。
生き物が死ななければならないのは2つの理由――。1つは食料や生活空間などの不足。「食われない」「食えなくなる」に加えて、精神面でも「子供を作りたくなくなる」。そうすると「人類は100年ももたないと思う」と指摘する。もう1つは「多様性」のため。生き残りの仕組みは「変化と選択」、多様な"試作品"を作る戦略。そのおかげで「生命の連続性」が途絶えることなく繋がってきたという。生物は、ミラクルが重なってこの地球に誕生し、多様化し、絶滅を繰り返して選択され、進化を遂げてきた。「私たちはその奇跡的な命を次の世代へと繋ぐために死ぬのです。命のたすきを次に委ねて『利他的に死ぬ』というわけです」と語るのだ。
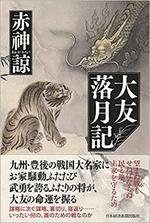 豊後の戦国大名・大友氏の「二階崩れの変」(1550年、天文19年)から6年、再び内紛・分裂の危機となる。当主・大友義鎮(後の宗麟)は、政より美と女に執着、とくに美貌となれば他の妻まで自らの正室や側室とした。家中の最高実力者の田原宗亀など一部の重臣たちが内政をほしいままにし、肥後方分の小原鑑元、"鬼"とあだなされる武将・戸次鑑連(後の立花道雪)などは、肥後や筑後・肥前の一部を平定して大友に服せさせていた。
豊後の戦国大名・大友氏の「二階崩れの変」(1550年、天文19年)から6年、再び内紛・分裂の危機となる。当主・大友義鎮(後の宗麟)は、政より美と女に執着、とくに美貌となれば他の妻まで自らの正室や側室とした。家中の最高実力者の田原宗亀など一部の重臣たちが内政をほしいままにし、肥後方分の小原鑑元、"鬼"とあだなされる武将・戸次鑑連(後の立花道雪)などは、肥後や筑後・肥前の一部を平定して大友に服せさせていた。
義鎮の近習頭・田原民部は謀略をめぐらし、本書の主人公である同じく近習の吉弘賀兵衛(二階崩れの変で失脚した吉弘鑑理の長子)は振り回される。後世に「氏姓の争い」とも「小原鑑元の乱」とも呼ばれるこの大乱は、なぜ起きたのか。肥後を善政によって蘇らせた小原鑑元はなぜ挙兵に追い込まれたのか。相次ぐ謀略、裏切り、寝返りのなかでの武将の苦哀と覚悟を描く。胸に迫る力作。
乱を鎮定した戸次鑑連が「この戦はいったい何のための戦だったのか」との吉弘賀兵衛のつぶやきに語る。「戦はしょせん人と人との醜い殺し合いにすぎぬ。正義じゃ何じゃと理由をつけてみたところで、双方に言い分はある。正しい戦なんぞありはせぬ。あるのは、いかなる戦でも勝たねばならぬという真理だけじゃ。このたび神五郎(小原鑑元)は生きるために兵を挙げた。わしは大友を守るために戦うた。正邪はない。あるのは勝敗だけじゃ」「神五郎は大友への忠義を貫いて死んだ忠臣じゃ。己が生と死をもって富める肥後の地と民と二万の精兵をそっくり大友に遺したではないか。月は落ちても、天を離れず。神五郎は大友に叛する己が運命に打ち克ったのじゃ。むろん、世の者は知るまい。されど天と、わしと賀兵衛が真実を知っておる」・・・・・・。「戸次鑑連は鬼だ。たしかに苛烈な鬼だが、情にあふれた鬼だと賀兵衛は思った」・・・・・・。
全国の公立小中学校の耐震化率99.6%――文科省は6日、今年4月の調査結果を発表しました。耐震性がない建物は、学校の統廃合で廃校となる学校が多いということです。
私は京大土木工学科で耐震工学を専攻。2000年当時は学校耐震化のデータすらない状態で、耐震化に全力をあげることを強く要請してきました。そして、初めて2002年4月1日現在で耐震化が44.5%であることが発表され、2003年度予算で学校耐震化予算が増額。以来、毎年の本予算・補正予算で増額されてきました。次に大きな節目となったのが2008年。中国・四川大地震で多くの校舎が倒壊し、多数の児童が犠牲となったことから、福田首相(当時)に直接要請。わずか3週間余りで、改正地震防災対策特別措置法が成立。これにより学校耐震化の実質的な自治体負担額は、従来の31.25%から13.3%へと半分以下に引き下げられ、小中学校を担う各自治体が学校耐震化に取り組みやすくなり、加速しました。この時、衆院文部科学委員長だったのが、佐藤茂樹衆院議員、公明党の幹事長が北側一雄衆院議員。二人をはじめ、多くの公明党の国会議員、地方議員の熱意によって学校の耐震化が進んできました。2009年、民主党政権となって予算が大幅に縮小されましたが、翌年は取り戻しました。
学校耐震化は「子どもの命を守る」とともに、大災害時は緊急避難場所ともなる大事な大事な拠点。防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化に更に頑張ります。
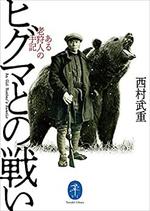 「私の叔父(北海道石狩郡当別村)が狩猟家であったので、私の家(札幌郡篠路村)へ訪れると、大きなガンやカモ、ウサギなどをおみやげに時々持ってきた。私はおとなになったら狩人になろうと思った」「徴兵検査がすみ、満21歳で狩猟免状を受けた」「私はついに、ヨローウシの出湯に魅せられて腰を据え、思う存分未開の林野内に鳥獣を追った」「私は、明治44年より今日に至るまでほとんど一生を、未開の森谷渓谷を探して、狩猟と釣りに費したようなもので、最早人生の終着駅にあり、気息奄奄たる老爺になってしまった。この本にあるものは、大正から昭和にかけての若き時代の思い出の昔話である」――。100年前の北海道の原野を縦横に駆け巡り、狩猟に釣り、温泉開発、鉱山発掘などフロンティアマンとして生き抜いてきた西村武重(1892年明治25年生まれ、1983年死去)が、1971年に上梓した代表作「ヒグマとの戦い――ある老狩人の手記」。養老牛温泉がある現在の中標津町が1916(大正5)年には2戸8名だったという。孫にあたる現町長・西村穣氏が「100年前の根室原野を駆け巡った祖父の冒険談の楽しさが伝わると幸いです」と語る。2021年7月5日文庫化。
「私の叔父(北海道石狩郡当別村)が狩猟家であったので、私の家(札幌郡篠路村)へ訪れると、大きなガンやカモ、ウサギなどをおみやげに時々持ってきた。私はおとなになったら狩人になろうと思った」「徴兵検査がすみ、満21歳で狩猟免状を受けた」「私はついに、ヨローウシの出湯に魅せられて腰を据え、思う存分未開の林野内に鳥獣を追った」「私は、明治44年より今日に至るまでほとんど一生を、未開の森谷渓谷を探して、狩猟と釣りに費したようなもので、最早人生の終着駅にあり、気息奄奄たる老爺になってしまった。この本にあるものは、大正から昭和にかけての若き時代の思い出の昔話である」――。100年前の北海道の原野を縦横に駆け巡り、狩猟に釣り、温泉開発、鉱山発掘などフロンティアマンとして生き抜いてきた西村武重(1892年明治25年生まれ、1983年死去)が、1971年に上梓した代表作「ヒグマとの戦い――ある老狩人の手記」。養老牛温泉がある現在の中標津町が1916(大正5)年には2戸8名だったという。孫にあたる現町長・西村穣氏が「100年前の根室原野を駆け巡った祖父の冒険談の楽しさが伝わると幸いです」と語る。2021年7月5日文庫化。
とにかく凄まじい。開拓時代に最も恐ろしかったヒグマ。打ち続くヒグマとの死闘。戦って命を落とした若者。組みついてヒグマが若者を弾防けにして撃てない。急所をはずした時のヒグマの暴れる姿。そして極寒、豪雪、猛吹雪との命がけの戦い。一転して晴れるや自然の美しさと清浄なる空気、アイヌの酋長である榛幸太郎、滝を登る何百尾ものサケやマス、大ヤマベ釣り、ガンやキネズミ・キツネ狩り・・・・・・。
異次元の壮絶な開拓時代に体当たりされた思いだ。