 「歴史初心者からアカデミアまで」が副題。歴史を愛する人と、歴史学の間には、コミュニケーション・ギャップが生じていると懸念する。「アカデミズム史学の側の人間が求める『面白さ』とアマチュア歴史家が考える『面白さ』が往々にしてずれ、コミユニケーション・ギャップを生んでしまうことは、このような2つの要素を併せ持つ『歴史学』の宿命なのである。そもそも、話している本人が『科学』として話しているのか、『文学』として話しているかを明確にしないことがほとんどなので噛み合わなくなる」と言う。疑うことで発展してきた科学と、物語として叙述する文学の二面性が歴史学にあり、「歴史学」に面白さを感じる人と、文学としての「歴史」に面白さを感じる人は、多くの場合重ならない。そこで著者は、歴史を愛する人たちには、学会や論文のルール、「学会とはどのようなところか」などを丁寧に示す。一方で歴史学者には、歴史を愛する人の様々なアプローチ、「タイプ別・アマチュア歴史家のススメ(自費作家型、『発見』重視型、SNS・イベント活用)」を丁寧に示す。双方ともに真剣に取り組んでいる様子がわかるが、それゆえにギャップが必然的に生じるのだ。
「歴史初心者からアカデミアまで」が副題。歴史を愛する人と、歴史学の間には、コミュニケーション・ギャップが生じていると懸念する。「アカデミズム史学の側の人間が求める『面白さ』とアマチュア歴史家が考える『面白さ』が往々にしてずれ、コミユニケーション・ギャップを生んでしまうことは、このような2つの要素を併せ持つ『歴史学』の宿命なのである。そもそも、話している本人が『科学』として話しているのか、『文学』として話しているかを明確にしないことがほとんどなので噛み合わなくなる」と言う。疑うことで発展してきた科学と、物語として叙述する文学の二面性が歴史学にあり、「歴史学」に面白さを感じる人と、文学としての「歴史」に面白さを感じる人は、多くの場合重ならない。そこで著者は、歴史を愛する人たちには、学会や論文のルール、「学会とはどのようなところか」などを丁寧に示す。一方で歴史学者には、歴史を愛する人の様々なアプローチ、「タイプ別・アマチュア歴史家のススメ(自費作家型、『発見』重視型、SNS・イベント活用)」を丁寧に示す。双方ともに真剣に取り組んでいる様子がわかるが、それゆえにギャップが必然的に生じるのだ。
著者は、それを架橋しようとする。「これまで歴史学は比較的学術コミュニケーションがなされできたと思われてきた。しかし受け手である歴史好き、そしてアマチュア歴史家の人たちの実態や思いを正しく理解する努力を怠ったまま、『簡単に理解できそうな知見』だけを伝えるならば、どう受け手に伝わるかという効果面に無理解であったように思われる」「歴史学という分野が親しみやすいと感じられることは良いが、ハードルが低く、誰でも参入できる学問であると軽視されたことが、アカデミズム史学とアマチュア歴史家の分断を招いた大きな原因であったように思われる」と指摘する。
著者は「いお倉」を起ち上げている。「一瞬笑えて後からジワジワ考えさせられる」――そんな歴史学の論文だけを掲載する新しい学術雑誌で、名前はラテン語で「冗談のような歴史」を意味する「Historia(ヒストリア)Iocularis (イオクラリス)」からと言う。
「架橋」するのは、この「笑い」。ベルクソンは「笑いは『無感動』からくる」「無感動は機械的なこわばりに発する。生きている人間が機械を思わせるようになればなるほどにおかしみが生ずるのだ」と言う。真剣であるが故に、他者から見ると「笑ってしまう」ことがある。歴史の面白いエピソードをことさら探して提示するのではない。
著者は明治の政治家・品川弥二郎を研究し、日本の政党政治の発展にとって「ヒール」的存在である彼に独特の感情を抱き、愛おしく感じたと言う。面白いのだ。そんな「笑い」で歴史学の新たな世界を開いていこうとする意欲が伝わってくる。
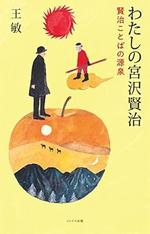 「賢治ことばの源泉」が副題。宮沢賢治研究の王敏法政大学名誉教授。「宮沢賢治を研究して40年ーー出会いの衝撃は、今も生きるエネルギー!」と帯にあるように、宮沢賢治研究、日中比較文化研究への熱量はすごい。これまで何回もお会いしたが、その熱量と誠実さに感動を覚えてきた。「きょうも、そしてこれからも、私は澎湃として涌く問題意識に向かうでしょう。なぜなら、宮沢賢治作品に触れることによって、日中からアジア文化圏、漢字文化圏という大世界へ邁進することができたからです。・・・・・・謝々!賢治、いつまでも、です」と言う。
「賢治ことばの源泉」が副題。宮沢賢治研究の王敏法政大学名誉教授。「宮沢賢治を研究して40年ーー出会いの衝撃は、今も生きるエネルギー!」と帯にあるように、宮沢賢治研究、日中比較文化研究への熱量はすごい。これまで何回もお会いしたが、その熱量と誠実さに感動を覚えてきた。「きょうも、そしてこれからも、私は澎湃として涌く問題意識に向かうでしょう。なぜなら、宮沢賢治作品に触れることによって、日中からアジア文化圏、漢字文化圏という大世界へ邁進することができたからです。・・・・・・謝々!賢治、いつまでも、です」と言う。
宮沢賢治は、「雨ニモマケズ」「銀河鉄道の夜」など、100点あまりの寓話や童話と1000余りの詩や文章を書いた。「雨ニモマケズ」「デクノボー」など心を激しく叩く宮沢賢治独特の言葉の底には、自然への畏敬、民への共感、究極の誠実さという深き哲学性、精神性がある。
さらにその奥を掘り下げると、繰り返し襲う三陸大地震・津波、冷害等を引き起こす厳しい自然の脅威、さりながら美しい動植物との共生、広がる宇宙、もたらされる漢字文化、西域(シルクロード)に翔ける夢が賢治にはあったと言う。本書で「東日本大震災と『雨ニモマケズ』」「言葉の魔術師・賢治と漢字」「賢治と『西域(シルクロード)』と禹王」を語っている。王敏さんでなければできない卓越した日中文化関係論が宮沢賢治を語るなかで展開される。さらに「禹王への尊敬と信仰は、漢字文化圏の日本においても、中国と同様に存在したことに気づいた」「人々が禹王を『治水神』として祀り、信仰し続けてきたことがわかった」と言い、神奈川県開成町の石碑を始め、全国各地での共同調査が行われ、「禹王サミット」まで作り上げたと言う。すごいことだと感嘆する。
「孔子のモデルは『君子』、賢治のそれは『デクノボー』。孔子は『修身斉家治国平天下』をエリートに教えたが、宮沢賢治は政治的な志向を抱かず、『ホメラレモセズ』の脱俗の姿勢をよしとし、対象は地位や肩書のない農民などの不特定多数」「荘子や老子の言葉が、賢治の『デクノボー』に共通する生き方を示しているように思われる」と言う。
「世界がぜんたい幸福にならないうちは、個人の幸福はありえない」と宮沢賢治は言い、人生そのものを幸福のための「求道」と見立てた。王敏さんは「生きることの原点を求めて問いかけ、その解答に全身全霊を導入した賢治の姿勢に啓示を受けた」「賢治を文学者より哲学者と言ったのは、賢治に学び、文学という枠を超えて、社会科学の範囲における人間学を探求したかった」と言っている。
宮沢賢治の詩に頻繁に登場する「微笑み」や「笑い」――。災害をはじめ苦難にあっても、微笑みを絶やすことなく、「イツモシズカニワラッテイル」日本人。「微笑みの文化」について、エドワード・S・モース、ラフカディオ・ハーン、エドウィン・O・ライシャワーの3人を挙げ、「悲しい時ですら、日本人は微笑みを湛えている。日本人に生活の作法として、生活のしきたりとなって根付いている」「感情を表面に出すまいとする日本人の自制だろう」を紹介し、「『笑い』は、諦観もしくはさとりの境地ともいうべきもの」「自然を人間の『敵』とする西洋の自然観に対して、賢治は自然の中の存在としての人間、自然と共に生きていく自然観、人間像を打ち出し、それを『笑い』『微笑み』で表現した」「『笑い』を媒介して、多様な生物とのある種のコミュニケーション空間を形成している(人間と自然との共生モデル)」と王敏さんは言う。また「デクノボー」にも注目し、「誰が賢くて誰が賢くないかわかりません」「いちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが、いちばんえらい」「心の苦痛を取り除く『癒し』、日本人の感性に根ざす『清らかさ』『清浄感』がある」と分析している。
宮沢賢治の生命観、人間観、自然観、哲学が、「賢治ことばの源泉」から浮き上がってくる。

