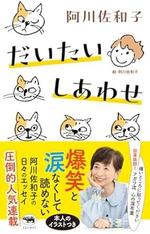 地方紙に連載されたエッセイ56 話。「効果抜群! 痛いところに貼ってください アガワ流 心の湿布薬」と帯にあるが、本当にその通り。日常のふとしたことを実に柔らかく、温かく、ユーモラスに描いている。各話ごとにイラストがあるが、阿川さん自身の絵。これが何とも言えなくいい。
地方紙に連載されたエッセイ56 話。「効果抜群! 痛いところに貼ってください アガワ流 心の湿布薬」と帯にあるが、本当にその通り。日常のふとしたことを実に柔らかく、温かく、ユーモラスに描いている。各話ごとにイラストがあるが、阿川さん自身の絵。これが何とも言えなくいい。
「そこで私は決めた。『今日はまあ、だいたいこんなもんかな』----もはや、このモットーにも年季が入ってきた。考えてみれば、私の人生は『だいたいしあわせ』だったと、ありがたく思うのである」「誰もが多面的な性格を、出したり引っ込めたりして歳を重ねていく。だからおもしろい。自分の見知ったほんの一部だけで『こういう人だ』と思い込むと、あるいは『自分はこういう性格なんです』と決めつけると、人生はつまらなくなる。だから私も『だいたい』と『きちんと』を行ったり来たりしている」・・・・・・。
猫の話、犬の話、メダカを飼った話・・・・・・。動物は、本当に家族だ。能登半島地震で避難所の方々と餃子を作ったり、金沢で自らのトーク&ライヴ----。力まずできるところが素晴らしい。
「毎夏どんどん暑くなっていく」――確かに昔学校にはエアコンなどなかったし、「数年前まで、もっぱら節電を呼びかけていた」「近ごろは、夜中はずっとエアコンをつけっぱなしで寝てください」とテレビでも言ってる。「電子化不安」――レストランでも、タブレットの画面を出されるし、便利だが、「難儀な場面が増えていくことに恐怖を覚える」と言う。阿川さんまでそう言うんだと、何故かちょっと安心したりする。
「父と耳かき」――。高校時代から耳かきが欠かせず、大学受験の時も試験場に耳かきを持って行った私としては、してやったりと思ったほどの話だった。耳かき話なら、山ほどある。「しゃっくりのいろは」――。「『いろはにほへと』をゆっくり唱えてごらんなさい。まず大きく息を吸って『いーーーーーー』」。初めて聞いた。
あのインテリの阿川さんが、ぶつかったり、転んだり、慌てたり、不安になったり・・・・・・。面白い。人間って誰でもそういうものかも。
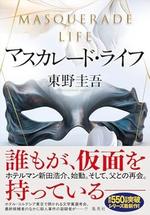 ホテル・コルテシア東京を舞台にして、捜査一課の刑事・新田浩介とフロントクラークの山岸尚美のコンビが事件を解決する「マスカレード」シリーズ第5作。新田は刑事を退職し、ホテルの保安課長として勤務している。
ホテル・コルテシア東京を舞台にして、捜査一課の刑事・新田浩介とフロントクラークの山岸尚美のコンビが事件を解決する「マスカレード」シリーズ第5作。新田は刑事を退職し、ホテルの保安課長として勤務している。
今回、ホテル・コルテシア東京で急遽、日本推理小説新人賞の選考会が行われることになる。最終候補者のなかに、殺人事件の容疑者・青木晴真がおり、選ばれれば記者会見をすることになるいう。
発端は2か月ほど前、奥多摩の山中で遺体が発見され、看護師の宮原亜子と判明。交際相手であり、同じ総合病院に勤務していた青木が容疑者と見られ行方がわからなくなっていた。その青木が、なんと日本推理小説新人賞に応募、最終候補作品に残ったというのだ。警視庁捜査一課の女性警部・梓真尋らが潜入、新田と尚美が全面協力することになる。選考委員、青木と思われる男、宮原の妹等関係者がホテルに集結するが・・・・・・。
一方、約30年前、新田の父・克久が弁護人となった大泉学園家族殺傷事件(母親と孫を殺害、娘に重症を負わせた会社員梶谷徳雄による殺人事件)の関係者もこのホテルに集まることになっていた。その結末は・・・・・・。
この全く違う2つの殺人事件の真相と解決に向けての知恵の攻防戦は、さすが東野圭吾の世界。「姉が苦しんだ分、青木さんにも苦しんでもらわなきゃ、と思いました。制裁を加えたい、とも」「殺したいほど憎むのも、殺されて当然と思われるほど憎まれるのも、悲しい運命ですものね」「死ぬより辛い道を選ぶこと。生き続けて、償うこと。それが自分の宿命だと気づいたんでしょう」「心に仮面を持っていない人なんていません。時に被り、時には外す。そうして生きているんです。だからこそ、人生が豊かで楽しいものになる。私はそう信じています」・・・・・・。人の宿命、人の出会い。ホテルはその衝突する交差点。
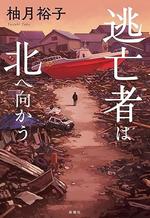 東日本大震災の混乱のなか、2つの殺人を犯し、逃亡しようとする青年・真柴亮。それを追う刑事・陣内康介たち。
東日本大震災の混乱のなか、2つの殺人を犯し、逃亡しようとする青年・真柴亮。それを追う刑事・陣内康介たち。
生まれてすぐに、家族を捨てた父から突然届いた1通の手紙。それを手に、父のいる北へ向かう途中、津波の中で家族とはぐれた子供・直人と出会い、2人しての奇妙な逃亡となる。一方、陣内は事件に忙殺され、娘を必死に探す妻と決定的な辛い亀裂を生んでしまう。事件は、福島から岩手へ。避難所となっている体育館へ立てこもる真柴亮は・・・・・・。
「この世には、どこまでもついていない奴がいる」「父親が(ひき逃げ)事故を起こしていなかったら――母親と別れてなかったら、亮がニ人の人間を殺してしまうことはなかったはずだ。いま、自分が警察に追われて、体育館に追い詰められているのは、すべて父親のせいなのだ」「どうしてこんなことになってしまったのか、考えた。いったい誰を恨めばいい。娘を失った悲しみのあまり、自分に間違った父親像を植え付けた祖父か。車にひかれた高齢者か。酒を飲んでいながら、車を運転した父親か。甲野が店で半グレと揉めなければ、眉なしに恨まれることはなかった。眉なしが死ななければ、警察官を殺さずに済んだ。そして、震災が起きなければ、自分は殺人犯にならなかった」・・・・・・。凶悪犯とは程遠い若者が、次から次と転落の罠にはまっていくのだが・・・・・・。
あの東日本大震災の津波・・・・・・。必死に家族を探し、そして家族を失う。「命」「家族愛」のギリギリを追い求める、しかし「救いがある」「勇気づける」柚月裕子の力作。
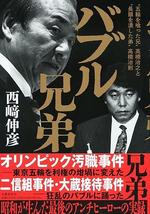 「"五輪を喰った兄"高橋治之と"長銀を潰した男"高橋治則」が副題。
「"五輪を喰った兄"高橋治之と"長銀を潰した男"高橋治則」が副題。
あのバブルのなかホテル・リゾート開発事業などで、資産1兆円を築いた「イ、アイ、イ」の高橋治則。バブル崩壊とともに、長銀による支援が打ち切られ、彼の影響下にある東京協和信組なども破綻、95年6月、背任容疑で逮捕される。2005年7月、最高裁の判決を待っている最中に亡くなる。私と同じ1945年生まれ。その兄が、電通時代からスポーツマーケティングで敏腕を振るい、東京五輪組織委員会の理事となり、現在汚職で裁判中の高橋治之。
「バブルの申し子と呼ばれながら志半ばで逝った弟と、スポーツビジネスの"フィクサー"として、電通で出世の階段を駆け上った兄。二人にとって『イ、アイ、イ』グループが作り上げてきた帝国は、誰にも侵されたくない聖域だった」「『俺たち兄弟は二人で一大コンツェルンを確立しようと話し合っているんだ』 治則は事業を始めた早創期に、こんな言葉を口にしていたことがあるという。----そして兄自身は飽くなき上昇志向で、次々と成功を手にしながら、自らが作り出した強烈な磁場に翻弄されていった。もう二度と日本にこんな兄弟が現れることはないだろう」と描いている。
何もかも失った戦後、必死の復興、高度成長からバブル、そしてバブル崩壊、90年代後半の銀行・証券等の破綻、さらに長期にわたるデフレ・・・・・・。戦後80年の今、私たちも80歳になる。人の人生は、時代とともにあり、時代の空気を吸いながら生きてきた。右肩上がりと言うよりも、チャレンジ精神は時代の空気を身にまとったものだろう。失敗も多くなる。ケータイもネットもない。熱量が大きかった時代なのだ。
本書には、多くの政治家や官僚が登場する。皆、知っている人ばかりで、亡くなった方もいる。なぜか笑顔のとても良い人が多いような気がした。
 「帝国日本最後の戦い」が副題。玉音放送後も続けられた帝国日本の最後の全面戦争。日本とソ連との間で1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第二次世界大戦最後の全面戦争。玉音放送後に戦闘が始まる地域もあり、「ロシアはこの戦争で領土を得たが、対して日本では、ロシアは条約を平然と破って領土を奪取したという不信感が根強く残る。日ソ戦争は、このような不信感を基調とする現代の日露関係の起点である」「スターリンが奪取させた南樺太と千島列島の帰属と北方領土問題は、日露関係の最大の懸案のままだ。いまだに日露両国は『スターリンの呪縛』に苦しんでいるともいえる」「日ソ戦争の敗因は軍事と政治を束ねる政戦略家や組織が不在だったとはかねてから指摘されているが、最大の敗因は、政戦略家の不在ではない。既に対米戦で、日本の軍事力と経済は破綻しており、加えて、対ソ戦では勝機はなかった。国家戦略の失敗を作戦や戦闘のレベルで逆転するのは、いかなる軍隊であれ困難である」・・・・・・。
「帝国日本最後の戦い」が副題。玉音放送後も続けられた帝国日本の最後の全面戦争。日本とソ連との間で1945年8月8日から9月上旬まで満洲・朝鮮半島・南樺太・千島列島で行われた第二次世界大戦最後の全面戦争。玉音放送後に戦闘が始まる地域もあり、「ロシアはこの戦争で領土を得たが、対して日本では、ロシアは条約を平然と破って領土を奪取したという不信感が根強く残る。日ソ戦争は、このような不信感を基調とする現代の日露関係の起点である」「スターリンが奪取させた南樺太と千島列島の帰属と北方領土問題は、日露関係の最大の懸案のままだ。いまだに日露両国は『スターリンの呪縛』に苦しんでいるともいえる」「日ソ戦争の敗因は軍事と政治を束ねる政戦略家や組織が不在だったとはかねてから指摘されているが、最大の敗因は、政戦略家の不在ではない。既に対米戦で、日本の軍事力と経済は破綻しており、加えて、対ソ戦では勝機はなかった。国家戦略の失敗を作戦や戦闘のレベルで逆転するのは、いかなる軍隊であれ困難である」・・・・・・。
これまで、ソ連の中立条約破棄、非人道的な戦闘の実態、さらにシベリア抑留や南樺太・千島列島の玉音放送後の真相を描く小説などをずいぶん見てきたが、本書は新資料を駆使し、米国のソ連への参戦要請から、各地での戦闘の実態、終戦までの全貌を描いている。読売・吉野作造賞、司馬遼太郎賞受賞など、評価の高さは納得するものがある。
「米国は対日戦で『原爆』とともに、ソ連の参戦を必要とした。1945年2月4日からの米英ソ首脳によるヤルタ秘密協定でドイツ降伏後2、3ヶ月以内の参戦を求めた(ドイツの降伏は5月9日)」「ソ連は対独戦でニ正面作戦を避ける戦略」「7月26日のポツダム宣言はソ連抜きの『米・ 英・中・三国宣言』」「日本は最後まで戦争終結の仲介をソ連に頼んでいた」「スターリンは、核攻撃で日本の内閣が交代し、降伏が早まると予想、開戦を早めた」「日本は『一撃講和論』戦略に立ち、『国体』の変更を恐れ無条件降伏を拒絶した」・・・・・・。そして8月8日、ソ連の宣戦布告。2度の「聖断」、そして8月15日。米英との戦闘は終わった。しかし、「なぜ日ソ戦争は8月15日に終結しなかったのか」・・・・・・。
「満洲の蹂躙、関東軍の壊滅(開戦までの道程、ソ連軍の侵攻、在満日本人の苦難、北緯38度線までの占領へ)」「南樺太と千島列島への侵攻(国内最後の地上戦・南樺太、日本の最北端での激戦・占守島、岐路にあった北海道と北方領土、日ソ戦争の犠牲者たち)」「日本の復讐を恐れたスターリン(対日包囲網の形成、シベリア抑留と物資搬出)」・・・・・・。掘り出した新たな史料も含めて精緻に分析する。
トルーマン、スターリンを始めとする各国の思惑、「『日本軍の本質』を描く決定版(加藤陽子)」――大変よくわかる。「沖縄・広島・長崎と違って、日ソ戦争には公的な個別の慰霊行事もない。今は夢物語だが、すべての参戦国が参加して、犠牲者を追悼する場が設けられ、古戦場で日本政府や天皇・皇族による慰霊が実現する日が来ることを願いたい」と結んでいる。

