 関白・豊臣秀次の遺児である三好孫七郎。秀吉の甥に当たる秀次は、あらぬ罪状を被せられて高野山へ追放、自刃。その妻妾子女は残らず三条河原で惨殺された。ところが、孫七郎だけは秀次自刃の翌年に生まれたため生き残り、旅芸人の母は秀次の家老だった木村常陸介・重成の親子のもとに孫七郎を預けていた。そこには、秀次に仕えて自刃した者の子である武藤源蔵も隠れ住んでいた。
関白・豊臣秀次の遺児である三好孫七郎。秀吉の甥に当たる秀次は、あらぬ罪状を被せられて高野山へ追放、自刃。その妻妾子女は残らず三条河原で惨殺された。ところが、孫七郎だけは秀次自刃の翌年に生まれたため生き残り、旅芸人の母は秀次の家老だった木村常陸介・重成の親子のもとに孫七郎を預けていた。そこには、秀次に仕えて自刃した者の子である武藤源蔵も隠れ住んでいた。
「大坂の陣」前夜、孫七郎は、大阪方の密使として、全国に散らばる牢人たちを仲間に引き入れる役目を受ける。武藤源蔵、大阪方からの目付である水木左門とともに豊家の味方を募る旅に出る。
まず向かったのは、紀州・九度山の真田幸村(信繁)。「もはや徳川の世は覆らぬ」と、まずは断られるが、謎の武士の急襲にも才蔵を遣わす配慮をみせる。次に京にいる長曽我部盛親、次に長曽我部の故地・土佐にいる牢人・毛利勝永、そして後藤又兵衛らを味方につける。又兵衛は真田幸村を「あれは、いつなりとも死ぬる漢の貌でござる」「現し世に執着を持たぬ、じつはそういう御仁がいちばん怖い」と言うのだった。
孫七郎が、次に会おうとするのは、福島正則。秀次の死の直前、最後の使者として対面したのが福島。味方につけるという以上に、父のことを聞きたいという渇仰からだ。福島正則は言う。「手腕は危ぶまれ、人望は薄かった」「石田三成ではなく、謀叛の濡れ衣は太閤殿下が」「関白殿下(秀次)は、生き残るため謀叛を決意されたのでござる」・・・・・・。秀頼が生まれたことで軋轢が生じ、秀吉は秀次の謀叛を待ち構え、あらかじめ通報の手筈まで整えていたというのだ。
秀吉の策、家康の策、淀の策・・・・・・。翻弄される家臣、牢人、女人、子供。「父とはなんだろう? なれるのか、おれは父に・・・・・・」。「大坂の陣」を前にして、驚くべき結末へ・・・・・・。
 昭和20年生まれの私は、関川さんより4つ上。まさにどっぷり、昭和を生きてきた。短いエッセイの数々は、自分の記憶をくっきりと再生させてくれた。「昭和人間」の心を懐かしく膨らませてくれた。まさに味わい深い、人生を時空で引っ張り、今へ投射してくれる良書。人物にしても、事象についても的確で本質的で見事、それに注ぐまなざしが暖かい。南伸坊さんの絵がまた素晴らしい。写真では全く及ばない、奥行きのある昭和の世界に誘ってくれる。
昭和20年生まれの私は、関川さんより4つ上。まさにどっぷり、昭和を生きてきた。短いエッセイの数々は、自分の記憶をくっきりと再生させてくれた。「昭和人間」の心を懐かしく膨らませてくれた。まさに味わい深い、人生を時空で引っ張り、今へ投射してくれる良書。人物にしても、事象についても的確で本質的で見事、それに注ぐまなざしが暖かい。南伸坊さんの絵がまた素晴らしい。写真では全く及ばない、奥行きのある昭和の世界に誘ってくれる。
「山田風太郎の長寿祝い(昭和45年の65歳以上は7%、今は30%超)」「黒澤明の『姿三四郎』は速度感に満ちて明るかった。『影武者』のとき黒澤は70歳、全く速度がない。老いたのである」「三島由紀夫は、鶴田浩二の『我慢』の芝居に共感する(我慢の美しさと辛抱)」――時代劇やヤクザ映画をよく観たものだ。
「昭和的汽車旅・電車旅(松本清張原作、野村芳太郎の「張込み」)」「『天国と地獄』の大胆な列車内撮影」「元美人革命家(重信房子)の半世紀(テルアビブ・リッダ空港乱射事件の奥平剛士は、私の大学同級生だった)」「最近愛読している昭和8年発行の教科書地図帳(ヒトラー首相、日本の国際連盟脱退、大英帝国は世界総人口の5分の1強、日本も現在の1.8倍の面積)」「クレージーキャッツの『ぜにのないやつ・・・・・・』『スーダラ節』」・・・・・・。まさに昭和。「70年代はがさつではあったが勢いがあって『意地悪』な年配者の存在を許さないほど多忙であった」と言う。
「『倍速』で見てもいいですか? 何を生意気な。小津安二郎にスピード感を求めてどうする(セリフとセリフの『間』こそ大切)」「黒澤明の第二作『一番美しく』と女子挺身隊」「無着成恭と『やまびこ学校』(戦後初期の貧しさと明るさ)」――確かに貧しかったが明るさがあった。「3丁目の夕日」でも「何もなかった」時代だったが、「何か」があった。忙しかったが、タイパ・コスパではない「ゆったりした時間」「間」があった。
「プロ野球」――。1950年誕生の大洋ホエールズ、三原マジックと秋山や桑田、金田、長嶋、王、村山、バッキー、引退後の村田や門田・・・・・・。「男は外で働いて家族を養う。その代わり家の中のことは一切しない」という昭和を引きずる男の人生には「引退後の悲しさ・悲劇」がある。
「本田靖春の山谷潜入」「昭和39年の東京オリンピックの閉会式」「第4次中東戦争とオイル・ショック。その昭和48年8月30日が三菱重工本社ビル爆破事件、その2日後に多摩川の堤防決壊で家が流されるテレビ中継」「渥美風天(清)の俳句」・・・・・・。
昭和100年の今年。戦争までの20年とその後80年・・・・・・。役人や企業でも、「昭和入省はもうほとんど、全くというほどいない」のが今だ。「昭和は遠くなりにけり」だが、この心身ともに「昭和」でつくられている。良いも悪いもない。「今」だ。あっ、これも「昭和」か?
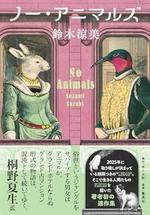 取り壊しが決まっている老朽化したマンション。少しずつ空き部屋も増えるなかで暮らす住民の悲哀や憂鬱、仕事などの日常を、それぞれの部屋ごとに描く7小編連作。特別なドラマでもない、成長物語でもない。脱力系のなぜか新しい感性がにじみ出る作品。
取り壊しが決まっている老朽化したマンション。少しずつ空き部屋も増えるなかで暮らす住民の悲哀や憂鬱、仕事などの日常を、それぞれの部屋ごとに描く7小編連作。特別なドラマでもない、成長物語でもない。脱力系のなぜか新しい感性がにじみ出る作品。
「204号室 28歳は人のお金で暮らしたい」――。コンカフェに勤めながら、恋人と同棲生活を送っている28歳の芹。結婚もしたくないが、独身の40歳にもなりたくない。自分のしたい生き方を手に入れるために男の高収入を利用するのは動物的に思えるが、高収入男と結婚すれば、お金は確保できても何か我慢と不自由が付随する気がして仕方がない・・・・・・。
「403号室 43歳はどうしても犬が飼いたい」――。「ペット禁止」のこのマンション。43歳バツイチの女ライター鮎美は犬を飼いたい気持ちを抑え切れない。
「402号室 8歳は権力を放棄したい」――8歳の李一は3人兄弟の長男。縁日に行っても、家族で食事をしても、「何があっても最初に起こされるのは自分」というように、長男として扱われる李一。与えられた「長男の権力」を放棄したいと思うことも・・・・・・。確かにあることだ。
「501号室 17歳はこたつで美白に明け暮れたい」――。両親が離婚し、母と2人で暮らしている高校生の17歳の羽衣。奔放な母の自己中はもう慣れたが、ブサイクで金もない恋人と付き合っている母が気に食わない。2人を別れさせたい羽衣。
「309号室 33歳はコインロッカーを使わない」――。10年以上ホストとして生きてきた33歳の春樹。同棲中の女を実家に連れて行こうと思っていたら、あっけなく女は出て行ってしまう。いろいろな女性と付き合い、そして去っていく。
「403号室 39歳は冷たい手が欲しい」――。40歳を目前にして、子供が欲しいかどうかもよくわからないまま、卵子凍結を決めた元女優の有希子。人生の選択を先送りする最良の方法だと思って・・・・・・。
「1階 26歳にコンビニは広すぎる」――。マンション1階のコンビニで働くジュン。マンションの住民と顔見知りになるし、その生活や人間関係、最近の様子が気になってしまう。「今あるものでは、何もかもが満たされない。かといって自分の欲しいものがよくわからない。一度は文句を言うが、ではどういう変化が望ましいのかと問われれば黙り込むしかない」――。そんな人々。
貧しいのか豊かなのか。安定とか成長をさほど求めることもなく、悩みや不安、憂鬱を抱えながらも平板で普通に生きる人々。マンション解体で出て行かなくてはならないのだが、切羽詰まっているわけでもない。現代社会の断面をサクッと切り裂く作品は、最も現代的なのかもしれない。「空き部屋の多い建物は、昼間に見てもどこか鬱蒼とした森のようで物悲しい。ところどころの部屋に残った住民は、まるで暗い森に隠れる不気味な動物で、来る森林伐採を恐れて、ひっそりと暮らしている」・・・・・・。
 「陰謀論が、現実社会に及ぼす影響がどんどん無視できないものになってきた」「陰謀論の虜になる人が少しずつ増えている」「政治家が『みんな悪党』で『私腹を肥やす』連中だという発想も陰謀論的思考」と言い、「人々の中に昔からあった素朴な陰謀論的思考はネットの中で純化され、濃度を高め、より過激なものへと変異を遂げてきた」「陰謀論は私たちのすぐ『となり』にある」と言う。「悪者探し」と「悪者に仕立て上げる」は昔からあったものだが、このネット社会は「陰謀に満ちた荒れた言論空間」を増強させている。
「陰謀論が、現実社会に及ぼす影響がどんどん無視できないものになってきた」「陰謀論の虜になる人が少しずつ増えている」「政治家が『みんな悪党』で『私腹を肥やす』連中だという発想も陰謀論的思考」と言い、「人々の中に昔からあった素朴な陰謀論的思考はネットの中で純化され、濃度を高め、より過激なものへと変異を遂げてきた」「陰謀論は私たちのすぐ『となり』にある」と言う。「悪者探し」と「悪者に仕立て上げる」は昔からあったものだが、このネット社会は「陰謀に満ちた荒れた言論空間」を増強させている。
「陰謀と陰謀論の違い」――。「陰謀」とは、現実に計画、実行された悪巧みのこと。「陰謀論」とは、世の中の出来事が全て誰かによって仕組まれた陰謀であるかのように、不確かな根拠をもとに、決めつける考え方のこと。「愚かな人間が陰謀論を信じるというよりも、むしろ賢い人間ほど出来事の裏側に隠れているものを暴き出そうとして、陰謀論を信じてしまうカラクリがある」と言う。そして二つの原因を指摘する。一つは「この世界をシンプルに解釈したい」という欲望。もう一つは「何か大事なものを『奪われる』」という感覚。これが絡み合って陰謀論を誘発すると言うのだ。
さらに、インターネットが陰謀論の世界を変えた。噂のラーメン店の行列、ネットの炎上などが起きる「集合行動の地殻変動」だ。アメリカのQアノン、日本の〇〇チャンネルなど、噂やフェイクは日常化しすぐ集まり集合的沸騰する。トランプの1.6連邦議会議事堂襲撃事件、MAGAもその類いだ。
タイパ・コスパにシンプル化が加わる時代は誠に厄介な時代と言える。陰謀論の温床となるもの――。「強い剥奪感と被害者意識」「剥奪感にとらわれたヒルベリーたちの中に育ったニヒリズムという化け物は、陰謀論を貪りながら肥大化していった」「格差が拡大し、アメリカン・ドリームは多くの人にとって絵空事のようになった」ーーそして「『あたかも』自分が地球を滅ぼす悪の組織と戦う戦隊ヒーローになったような気分」になったり「山田昌弘氏が言う『生きる希望をアニメやゲームや推し活などのバーチャルな活動から得ようとする」ことになる。さらにポピュリズムは「民の声」を錦の御旗に掲げ暴走するようになる。「本書が強く関心を寄せる陰謀論政治も純度の高いポピュリズムの産物だ」と指摘する。
本書は、トランプの不正選挙陰謀論、ナチスのユダヤ陰謀論、フリーメイソンなど多くの実例を分析する。日本の「諸悪の根源は〇〇だ」と攻撃する強い怒りと剥奪感を持った人々の強い怒りを例示する。
そして「陰謀論は非常識な『彼ら/彼女ら』の問題ではなく、現代を生きる『われわれ』自身の問題であることに気づくことが『陰謀論が支配する社会』という最悪のシナリオを回避するための肝心な一歩だと思う」と言う。「奪われている」という剥奪感をどう受け止めるか。難しいデジタル・ポピュリズム時代に遭遇している。
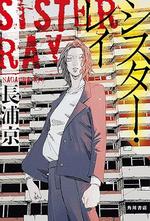 在留外国人数が増加して4000万人を越えようとしている日本。光と影の影の部分、様々な犯罪組織が動き始めていることを描き出した生々しい社会派エンタメ。かつては新宿などの繁華街が舞台であったが、現在は東京23区やその周辺の団地などに広がっているという。本書の舞台は、墨田区とその周辺。
在留外国人数が増加して4000万人を越えようとしている日本。光と影の影の部分、様々な犯罪組織が動き始めていることを描き出した生々しい社会派エンタメ。かつては新宿などの繁華街が舞台であったが、現在は東京23区やその周辺の団地などに広がっているという。本書の舞台は、墨田区とその周辺。
東京・墨田区で、外国人たちの世話を焼き、「シスター」と慕われる能條玲が主人公。彼女は予備校講師をしているが、かつてフランスの特殊部隊のエースという隠された経歴があった。玲の母の在宅介護を任せているフィリピン出身の女性マイラ・サントスから息子・乃亜を探すよう頼まれた玲は、思いがけず、暴力団と外国人半グレ集団との抗争に巻き込まれてしまう。そこでは、激しい抗争が行われており、玲は冷静な判断と磨き抜かれた戦闘技術で暴力団と半グレ集団を制圧する。
周囲の外国人たちのトラブルを次々と解決する玲だが、平穏に見える日本の在留外国人の裏では、敵の敵は味方とばかりの国際的な陰謀が巡らされており、玲はその陰謀・ 事件に巻き込まれ、命の危険にもさらされる。
「私が浦沢組の徳山に会うことになったため、あなたは仕方なく徳山も一緒に拉致しろと命令を変更した。しかし、失敗した上、徳山を悪い形で刺激し、結果、私は徳山から、河東郁美がJ& Sの違法送金に加担していたことを教えられた。さらには、あなた方が違法臓器移植に絡む金を偽装オンラインカジノを通じてやりとりしている事実まで知らされることになった」「リェンの母と兄はJ& Sコーポレーションのトップであり、彼女たちが戻らなければ、今後、J&Sのみならず、他の複数の外国人組織と、中国の秘密警察との間の大規模な抗争に発展する可能性が高い」「日本国内に存在するベトナム人、台湾人、ネパール人、パキスタン人などの外国人犯罪組織が中国秘密警察の子会社化することを、日本、アメリカ、韓国などの政府は絶対に許さないということです」「中国政府が秘密警察を介して発注した、日本に対する攪乱の行為や破壊行為を、直接関係のない外国人犯罪組織が請負い、実行する。両者の間に思想的、政治的な共通点などは一切ない。互いをつないでいるのは金のみ」・・・・・・。
様々な国際的な犯罪集団の陰謀、それに絡む日本のヤクザ、半グレ、そして日本の警察。それに巻き込まれてしまう生活不安の中にある在留外国人の人々と、その仲間たち。帯には「極限アクション×非合法組織の抗争×多国籍社会の現実」の「予測不能の衝撃エンタメ‼︎」とあるが、全くその通り。あまりに複雑すぎる事件と人物、激しいアクションに、ついていくのに苦労するほどだ。

