 「夫が死んだ。死んでいる。私が殺したのだ。ここは? 仙台市内の自宅マンションだ」――。結婚して妊娠、そして夫の転勤。その頃から、夫は別人のように冷たくなり、罵られた。そしてついに暴力。佐藤量子は、金槌を掴み・・・・・・。もうそろそろ息子の翔が幼稚園から帰ってくるのに・・・・・・。そこに何故か、2週間前に近所でばったり会った大学時代のサークルの後輩・桂凍朗が訪ねてきて、「量子さん、旦那さんはどうしていますか。怒られているんじゃないですか。問題が起きていますよね?中に入れてください」と、事件がわかっているようなことを言う。そして死体を革袋に入れ、車で山奥に運んでいく。そこで量子は意識を失う。
「夫が死んだ。死んでいる。私が殺したのだ。ここは? 仙台市内の自宅マンションだ」――。結婚して妊娠、そして夫の転勤。その頃から、夫は別人のように冷たくなり、罵られた。そしてついに暴力。佐藤量子は、金槌を掴み・・・・・・。もうそろそろ息子の翔が幼稚園から帰ってくるのに・・・・・・。そこに何故か、2週間前に近所でばったり会った大学時代のサークルの後輩・桂凍朗が訪ねてきて、「量子さん、旦那さんはどうしていますか。怒られているんじゃないですか。問題が起きていますよね?中に入れてください」と、事件がわかっているようなことを言う。そして死体を革袋に入れ、車で山奥に運んでいく。そこで量子は意識を失う。
山中で眠っていた量子を起こしたのは破魔矢と絵馬の若い夫婦。「俺たち、探しているんですよ。桂さんを。ジャバウォックで何かを企んでいるから」。「鏡の国のアリス」に出てくる怪物・ジャバウォック。トキソプラズマという寄生虫が脳に入り、恐怖心や不安感を鈍らせる神経伝達物質を作らせるように、ジャバウォックは、人間の脳の前頭前野(理性や衝動の抑制を司る)に張り付いて収拾のつかない暴れ方をさせると言う。アルコールが脳に働きかけ、冷静な思考を妨げ、失言や暴言、暴力を誘発するが、それ以上のケタ外れに・・・・・・。
「人の脳からこのジャバウォックをいかに剥がすか」――。桂も破魔矢も絵馬もSFのような物語が展開される。音楽家・伊藤北斎とそれを助ける斗真、ジャバウォックに侵されるた北斎の娘・歌子。「歌子さんの場合は、あの交通事故で亡くなった人から移ったんだろうと言われました」「音楽を使い、ジャバウォックを剥がす。そして亀に移動させる」・・・・・・。
そもそも「人間の本質は『暴力』なのか、『親切』なのか」「動物の中で、これほど温厚な種はいないし、これほど残忍な種もない」「人を助けると気分が良くなるという性質がプログラムされている時点で、ヒトは、特別に温厚で親切。そして、優しい」「他人と過去は変えられない。だけど、自分と未来は変えられる。・・・・・・桂さんは、他人どころか、ヒト全部を変えたかったんですよ」「ヒトのニ面性----ずいぶん前から『琴線に触れる』と『逆鱗に触れる』を混同する人が増えているのを知っていますか? ・・・・・・意外に紙一重だと思いませんか。感動と怒りは、実は近いんです」・・・・・・。
物語は、SF的、あるいは翻弄される主人公的存在・ 量子の名に象徴される量子力学、量子もつれ、さらに人間の善悪の哲学、科学の進歩と人体実験などを往還しながら、最後のクライマックスヘと合流していく。1日と思えたのが20年だったという驚きの結末でもある。
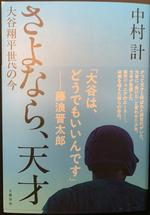 「大谷翔平世代の今」が副題。異次元のスーパースター大谷翔平の世代は2024年度に30歳になった。同世代の野球少年には、大谷に"負けた"と言わせた「怪物」や「天才」がいた。藤浪晋太郎はその先頭を走っていた。その「天才」たちは、大谷を横目で見ながら、どう生きてきたのか。そして今は・・・・・・。
「大谷翔平世代の今」が副題。異次元のスーパースター大谷翔平の世代は2024年度に30歳になった。同世代の野球少年には、大谷に"負けた"と言わせた「怪物」や「天才」がいた。藤浪晋太郎はその先頭を走っていた。その「天才」たちは、大谷を横目で見ながら、どう生きてきたのか。そして今は・・・・・・。
「藤浪晋太郎、30歳の告白」――阪神時代、「眠れなくなった」。「大坂智哉、怪物中学生は今」――「大谷に"負けた"と言わせた少年」だ。「渡辺郁也、消えた東北の天才」――「大谷が落選した楽天ジュニアのエース」だ。
「岡野祐一郎、超無名中学生の逆転人生」――「母親のウソ(特待で聖光学園の嘘)で、ドラフト3位に」を描く。一歩一歩積み上げて中日ドラゴンズ投手に。「北條史也、高卒エリート組の後悔」――「大谷にも藤波にも聞けなかった」。伝説の光星学院の3番田村、4番北條。阪神に2位指名。藤浪は「別格」、大谷は「別」と語る。また「誠也がいちばんかわいそう。大谷が居るから、これだけの成績を残しながら、こっちが麻痺しちゃっている」と言う。「田村龍弘、大谷世代"最後の1人"」――「アイツのことは話せない」。ロッテで今も現役だ。
「天才たちの孤独」――中学校と高校、大学、プロはレベルがあまりに違う。「挫折があったときに頑張れるかどうか。頑張れなかった。うちのめされちゃったんで」と渡辺は言う。「早熟なものにとってのウィークポイントは『やらなくてもできてしまったところ』」と著者は言う。渡辺は、「私もどっちかっていうと、できちゃったタイプ。特に練習を頑張ったという記憶もなくて。気づいたら、周りがすごい、すごいって言っていた。挫折は早い方が良いと思いますよ」と語る。早熟という悲運に泣かされて消えていく。年相応に成長していく選手がいちばん大成するというわけだ。渡辺は「プロになったやつを見てると、身の程知らずなところがある」と言う。天下の身の程知らずは大谷、大谷ほど非常識な思考の持ち主もいないわけだ。
2016年7月の藤波、「161 球事件」。懲罰の意味合いのあるこの事件は、藤波に「劣等生」のレッテルを貼ることになった。苦しい時代を乗り越えて勝った武豊との交流は藤浪を支えた。武豊は「大変だと思ったことはない。『俺は武豊だと思ってるから』。自分はスペシャルなんだ」と言ったという。
「誰も歩いたことのない道を行ってみたかった」と大谷は若い頃よく言っていたという。藤浪は「アメリカに来た時点で、人生としては成功」と語ったという。「藤浪にとっての成功の反対。それは失敗ではない。踏み出さないことなのだ」と著者は言う。そして大谷と同世代の「怪物」「天才」は今、「彼らはすでに自分の道へ一歩踏み出していた」と結んでいる。
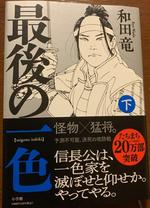 丹後の一色五郎と長岡忠興との激しい戦いの物語だが、この下巻は天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変から、一色五郎が謀殺される9月28日まで。実に短い期間だが、時代の動きは激しく、まさに驚くべき決死の攻防戦、武将の覚悟が描かれる。凄まじい力作。
丹後の一色五郎と長岡忠興との激しい戦いの物語だが、この下巻は天正10年(1582年)6月2日の本能寺の変から、一色五郎が謀殺される9月28日まで。実に短い期間だが、時代の動きは激しく、まさに驚くべき決死の攻防戦、武将の覚悟が描かれる。凄まじい力作。
一色五郎に潜む「一色の業報」――それは、「一色宗家に仇する者は必ず非業に死ぬ。これが一色家の業報だ」「長岡家と和睦し、国人が斬られたとて沈黙を守り、馬揃えや検地を受け入れた挙句、武田征伐への出兵に応じたのも、いずれ信長が非業に死に、あらゆることが振り出しに戻ると予見していたからだ」「光秀はほどなく討たれる」・・・・・・。五郎は雌伏し時を待ったのだ。「時は我らに味方した。これより宮津城へと攻め入り、長岡家の者どもを討ち滅ぼし、長岡藤孝、忠興が首級を挙げる」・・・・・・。
光秀に対し、長岡藤孝、忠興と玉、一色五郎と伊也、そして秀吉、柴田勝家、さらに丹後堂奥城の矢野藤一郎・・・・・・。それぞれの逡巡と決断が描かれる。
一色五郎もまた大返し。怒涛のごとく加悦城へ迫り、忠興を助けるが、銃弾を浴び倒れる。「今こそ一色家の息の根を止めるべし。翌朝をもってて弓木城を攻撃」の声を忠興一人が止める。
秀吉の意向に対し、「彼の者は光秀には与しておりません」と忠興は抗い、「信長が認めた一色家の所領を奪うは、このわし自身である」と固く心に決める。そして、命を取り留めた一色五郎は、直ちに宮津城に出兵。しかし軍勢を引き揚げる。「突然、五郎ははらはらと涙を流し始めたのだと言う」と描写する。
「どうか、我が家臣となってくれ」「ただ一色五郎という武将が欲しかった。――この男と共に乱世を生きてみたい」・・・・・・。一色五郎は受け入れるが・・・・・・。その結果は忠興の心とは全く違う謀殺計画と変ずる。
本能寺の変を挟んで、丹後において、一色家と長岡(細川)家の因縁の激烈な攻防戦があった。そこに一色五郎という怪物のような武将がいたことを衝撃的に描き出した力作、感動の物語だ。
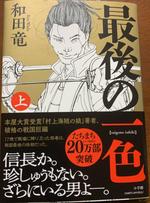 「信長か。珍しゅうもない。ざらにいる男よ――」。天下布武を掲げる織田信長が勢いを増す戦国時代。怪物のような武将が丹後にいた。桁はずれの勇猛、意表をつく判断、本心を明かさぬ深淵は常に周りを翻弄する。
「信長か。珍しゅうもない。ざらにいる男よ――」。天下布武を掲げる織田信長が勢いを増す戦国時代。怪物のような武将が丹後にいた。桁はずれの勇猛、意表をつく判断、本心を明かさぬ深淵は常に周りを翻弄する。
天正6年9月、信長は丹後の守護大名、一色義員の討伐に着手する。討手に選ばれたのは長岡藤孝。足利家の家臣から、信長の家臣へと、鞍替えするのに伴い、苗字を細川から長岡に改めていた。天正7年1月、攻められた一色義員は切腹。後を継いだのは17歳の嫡男・五郎。丹後を舞台に、長岡藤孝、忠興親子と一色五郎との激しい知略の攻防戦が繰り広げられる。特に同年の激しい気性の忠興の悔しい歯ぎしりが聞こえてくる。
大雲川の戦闘。「丹後国をほしくばこの俺が相手じゃ」「五郎は討取りたる四十九人の首を槍の穂にさし貫き、討れし敵の雑兵百人の骸を川ヘ沈め、浅みを計りて馬にて渡し」・・・・・・。
「一色五郎弓木城に楯籠り」――味方にも、本心をあかさない。「一色五郎は何ゆえ、いともあっさりと丹後ニ郡を譲ったのだ」「あ奴は負けたゆえニ郡を譲ったのではない。勝たんが故にそうしたのだ」・・・・・・。一色家と長岡家の死闘は続く。「一色家の業報を、戦に使わんとしているのか」――五郎は黙している。
天正9年2月23日、信長は京でお馬揃えを催し、一色五郎にも声をかける。五郎は、ただ一人武装、陣羽織の背中にはなんと隆々たる陰形。信長に会う。目に浮かぶような活写だ。そして信長は、長岡家の伊也姫を一色五郎に嫁がせるという驚くべき手を打つ。五郎を使おうとする信長、対する長岡藤孝、特に忠興の怒りと焦り・・・・・・。
そして天正10年6月2日、本能寺の変勃発。下巻ヘ。丹後一色氏最後の傑物の物語。面白い力作。
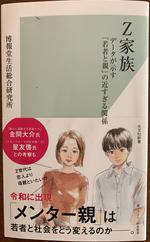 「データが示す『若者と親』の近すぎる関係」が副題。博報堂の生活総研が、30年前と同じ設計で実施した「若者調査」をもとに、首都圏に住む19~22歳のコアZ世代と、その親世代(現在4~52歳、団塊ジュニア世代)を比較分析。「ここ30年で若者の幸福度や生活満足度が非常に高まっていること。その幸福感を構成する『人間関係』において、家族関係が大きく変化して両親、特に母親との距離が近づいていること。さらに同性の友人との結びつきが非常に強くなっていること」を明らかにしている。極めて貴重で面白いデータ分析。
「データが示す『若者と親』の近すぎる関係」が副題。博報堂の生活総研が、30年前と同じ設計で実施した「若者調査」をもとに、首都圏に住む19~22歳のコアZ世代と、その親世代(現在4~52歳、団塊ジュニア世代)を比較分析。「ここ30年で若者の幸福度や生活満足度が非常に高まっていること。その幸福感を構成する『人間関係』において、家族関係が大きく変化して両親、特に母親との距離が近づいていること。さらに同性の友人との結びつきが非常に強くなっていること」を明らかにしている。極めて貴重で面白いデータ分析。
「『今の若者は空気を読みすぎる、他人ばかり気にする』と言うが、空気を読みすぎるのは、若きも老いも差がない。時代と共に皆そうなっている」「『最近の若者はベンチャー志向だ』と言うが、大企業を選ぶ若者が増えている。親が安定した職業を願っている(親の影響)」「『最近の若者は、人間関係が希薄で、一人の時間を大切にする傾向が強い』と言うが、大きくは変化していない。むしろ人間関係を敬遠しているのは中高年」・・・・・・。「今の若者は『成長を知らないかわいそうな世代』」と言われるが、「生活に十分満足している」と答えた人は、30年前の9.4%から、なんと30.0%と3倍以上に増加している。
幸福度の3大要素は、「経済社会状況」「心身の健康」「人との関係性」――。最も変化が際立っていたのが「家族」との関係で、幸福感の裏にはこれまでと全く異なる「親密な家族関係」がある。「近く、親しく、密すぎるZ家族の姿」がある。「恋人より、親友より・・・・・・心の拠り所は圧倒的に母親」と言う。また「恋愛観」――1990年代の若者は「恋愛至上主義」であったが、恋愛的な行動を無理にとろうとする若者は減少し、特に「女性の男性離れ」が起きている。
大きな特徴は、「令和の親は絶対的味方――メンター・ペアレンツ」であり、社会進出を果たした母親が家庭でメンター化している。勉強や人生のアドバイザーだ。そして「親子の距離を劇的に縮めたチャットアプリ」だと言う。いつも連携を取り合っている。一方、父親は「課題解決型」のやりとりが頻出していると言う。
Z世代のビジネス現場――「奉仕する部下と上司」の関係は崩れている。「協調性が高く素直で真面目」「目立つことを避ける」「自己主張を避ける」という特徴を持ち、傾向として「指示待ち」。上司は「システム」に徹すべきだと言う。「褒めると叱るはどちらが効果的」と言うが、全く見当違いで、「わかりやすく」伝えることが信頼を得る最短ルートだと指摘している。
「Z世代の緊密な関係の先にある課題――若者が『外』に向かう社会へ」――。内にこもるZ世代。日本に典型的な「安心社会」だが、それを基盤として、他者と信頼関係を結び、協働する力が育っているかどうか。開かれた社会で、新しい人をどんどん巻き込んで、新しい関係を作っていくことが大切で、それが世界で求められていると言っている。子供には「体験させてあげること(星友啓)」「困っている人を助けろ(宮台真司)」が大事だと言う。
しっかりしたデータと分析。貴重な提言になっている。

