 短編の名手と言われる著者の長編サスペンス。現在の自分の存在が、無数の人たちが紡ぐ糸の絡み合いの中で形づくられることを、じっくりと描く。喪失感の時空が離島の寂寥とともに迫ってくる。
短編の名手と言われる著者の長編サスペンス。現在の自分の存在が、無数の人たちが紡ぐ糸の絡み合いの中で形づくられることを、じっくりと描く。喪失感の時空が離島の寂寥とともに迫ってくる。
タクシー運転手の川西青吾は恋人・ 中園多実と一緒に暮らしていたが、ある日、家に帰ると帰宅しているはずの多実がいない。音信不通が続き、焦りを募らせていたところ、五島列島の遠鹿島で海難事故に遭って行方不明と知らされる。多実は青吾の知らない男・出口波留彦と一緒だったという。多実の持ち物からは、音信不通になっている青吾の母が写っている昔のテレフォンカードが見つかる。
そこへ突然、出口波留彦の妻と名乗る沙都子が訪ねてくる。謎の多い事故の真実、多実と波留彦の関係を求めて、青吾と沙都子は遠鹿島へ向かう。沙都子はしっかり者で積極的な女性。人の良い青吾。不思議な事件の真相を探る旅は、次第に多実の人生、青吾自身の母親とのつながり、波留彦と島を支配していた父親や島自体のきわどい歴史などの思いもよらぬ場所へとニ人を誘い込んでいく。
遠鹿島に住んでいた多実、そして青吾の母。波留彦の父の悪どい支配と好き放題の放蕩。波留彦の父と反目しあっていた町役場に勤めていた浦誠治の溺死事件。東京で起きた青吾の母・久美子の放火殺人事件・・・・・・。
五島列島の離島を舞台にした絡み合う人間関係。一緒に住みながらも、秘密を抱えて暮らす男女に訪れた突然の別れと、それを探りながら深まっていく喪失感と愛を描いた心惹かれる力作。
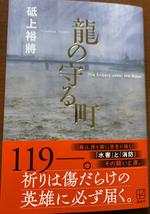 火災、水害、様々な事故・・・・・・地域を守る消防士の戦いと葛藤を描く生々しい物語。東日本大震災でも消防士・消防団が身を挺して戦い、何人もの消防関係者が犠牲となった。
火災、水害、様々な事故・・・・・・地域を守る消防士の戦いと葛藤を描く生々しい物語。東日本大震災でも消防士・消防団が身を挺して戦い、何人もの消防関係者が犠牲となった。
北の海に流れる瑞乃川の左右に広がる瑞乃町を守る瑞乃消防署に勤務する秋月龍朗。「俺にとって仕事といえば、体を鍛え、装備を点検し、車両を運転し、現場で救助や消火活動を行う」というまさに現場の最高の消防士だった。5年前の大洪水で、町は濁流にのまれ、妻・薫の両親まで失った。「来るな! 私たちは後でいい。君は私たち以外を助けるんだ! 皆を助けろ!」――その叫び声は、悔恨となり、心に癒えない傷跡となっている。
幼少期の火遊びをヘて消防士を目指した男は現場で常に救助の先頭に立ってきた。しかし急遽、指令室の司令補を命じられ、慣れない事務作業。「はい、こちら119番、火事ですか救急ですか」の電話対応とパソコンの操作だ。チームを組む4人。立石順平、三田夢菜、樋口祐樹。仕事をすると1秒もおろそかにできない要であることを実感していく。声だけで状況を察知し、的確に指導しながら救急車等を出動させる。事務作業に戸惑いながらも、現場を知ってるが故に、より的確な指示ができることを実感していく。
「あなたたちに会えてよかった。ずっと頭からあの子たちのことが離れなかったけれど、今日は痛みが和らぐような気持ちよ・・・・・・。幸せな気持ちになれる日もあるのね。あなたたちが命をかけて向かってくれたことが、答えだったのかもしれない。言葉よりも大事な行いがある」「どうしようもない状況でした。入ったときには、誰も助けられませんでした」「家族の誰も、あなたを責めてない。私も、子供たちも、お父さんやお母さんだって、そんなこと思ってないはずよ」「あなたは、私たちの町の英雄よ。涙を拭いて。竜神様に笑われちゃうよ・・・・・・。(また、5年前までのように、明るく元気に過ごしてくれますように 薫)」「人がなぜ手を合わせ、目を閉じるのか。生きることが、その瞬間の中にあるからだ」・・・・・・。
「馬鹿みたいに優しくあれ」・・・・・・。炎と衝撃波が向かって飛んでくるフラッシュオーバーの現場突入。子犬を助ける水害の現場。肉親を失う大洪水の現場。消防士を深く理解し支えようと努める家族。現場の安全と安心は、生死の境界に立ち、昼夜を分かたず献身する現場の人によって守られている。
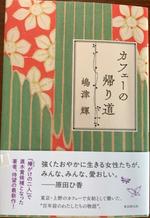 関東大震災の後、大正から昭和にかけて――。東京上野の繁華街を過ぎてちょっとの所にある「カフェー西行」。あまり流行ってはいないが、食堂や喫茶を兼ねて近隣住民の憩いの場となっていた。穏やかな店主が淹れるコーヒーの香りがただようこの店には、個性豊かな女給たちが朗らかに働いていた。震災、不況、戦争へと向かう激動のなか、様々な事情を抱える女性たちはどう生きたのか。戦争に向かう男たちの陰で、悲しみを抑えつつしっかり生きる女性たちを、実に静かに丁寧に心のひだを擦るように描いた絶妙の5つの連作短編集。よく練り上げられた素晴らしい秀作。
関東大震災の後、大正から昭和にかけて――。東京上野の繁華街を過ぎてちょっとの所にある「カフェー西行」。あまり流行ってはいないが、食堂や喫茶を兼ねて近隣住民の憩いの場となっていた。穏やかな店主が淹れるコーヒーの香りがただようこの店には、個性豊かな女給たちが朗らかに働いていた。震災、不況、戦争へと向かう激動のなか、様々な事情を抱える女性たちはどう生きたのか。戦争に向かう男たちの陰で、悲しみを抑えつつしっかり生きる女性たちを、実に静かに丁寧に心のひだを擦るように描いた絶妙の5つの連作短編集。よく練り上げられた素晴らしい秀作。
「カフェー西行」には3人の女給がいる。竹久夢二の絵のような色っぽい柳腰のとびきりの美人・タイ子、親切で清々しい小柄な美登里、皮膚が浅黒く眉もまつ毛も黒々とした野性的な容姿で高女出の文学好きのセイ。
「稲子のカフェー」――。国語の教師の夫がタイ子の家によく通うようになり、その仲を疑った稲子はタイ子に会う。タイ子は夫を亡くし、一人っ子の豪一を育てていたが、字が読めなかった・・・・・・。
「嘘つき美登里」――。昭和4年4月、松坂屋上野店の新館が開店、日本で初めての「昇降機ガール」が生まれた。美登里はその制服に憧れる。「女給募集 19歳」の求人の紙を見て、「妹小路園子」というよく肥えた中年婦人が「19歳」「華族」と言って入ってくる。嘘と思っていたが、探ってみると・・・・・・。面白く絶妙。
「出戻りセイ」――。10年前、カフェー西行をやめたセイが戻ってきた。35歳の年増になって。髭面の男が店に来ては、髪型をああしろ、こうしろとうるさく言う。悔しいが助言は正しい。向井正一という理髪師だった。そして向井に召集令状が来て・・・・・・。
「タイ子の昔」――。20歳になったタイ子の息子の豪一が出征する。35歳で女給を辞めたタイ子はいろいろあってタバコ屋になっていた。豪一と手紙のやりとり。心配でならない。「無事に帰ってきて」・・・・・・。
「幾子のお土産」――。昭和25年、店主兼マスターの菊田は喜寿を迎えており、美登里と結婚、カフェーは「純喫茶西行」になっていた。昭和8年生まれの幾子はここで働いていた。5年前に兄が戦死。母は延々と嘆き続け泣いていた。アメ横で働いているセイが賑やかに現れ、お菓子をいっぱい持ってくる。幾子が持っていくアメリカ製のお菓子を母は受け付けない。息子の戦死から立ち直れない母・・・・・・。そこで父娘は・・・・・・。
100年前の日本、戦前、戦後の日常。言葉は少ないながら、より深く通い合う心・・・・・・。一人ひとりが抱える事情と生が交錯する。
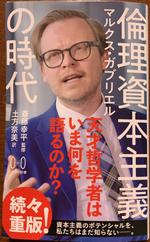 戦争、異常気象、AIの加速による社会変化、経済格差の増大と貧困・・・・・・。この現代の問題に対処するため、新たな社会契約、まさに「新しい啓蒙」が必要だ。この新しい啓蒙は、「道徳的な人間の進歩を、モノやサービスの社会経済的生産手段と、さらには豊かさや繁栄と早急にリカップリング(再統合)しなければならない」「我々が目指すべきは、道徳的価値と経済的価値のリカップリング、すなわち倫理資本主義だ」と言う。新自由主義や、停滞と貧困をもたらす「脱成長」に活路はない。資本主義の行き詰まりを打開するのは倫理である。倫理と資本主義をリカップリングした倫理資本主義だと言う。善、倫理、資本主義の本質をアダム・スミス、カントらの哲学・思想の根源から掘り起こし、倫理資本主義を提起する。
戦争、異常気象、AIの加速による社会変化、経済格差の増大と貧困・・・・・・。この現代の問題に対処するため、新たな社会契約、まさに「新しい啓蒙」が必要だ。この新しい啓蒙は、「道徳的な人間の進歩を、モノやサービスの社会経済的生産手段と、さらには豊かさや繁栄と早急にリカップリング(再統合)しなければならない」「我々が目指すべきは、道徳的価値と経済的価値のリカップリング、すなわち倫理資本主義だ」と言う。新自由主義や、停滞と貧困をもたらす「脱成長」に活路はない。資本主義の行き詰まりを打開するのは倫理である。倫理と資本主義をリカップリングした倫理資本主義だと言う。善、倫理、資本主義の本質をアダム・スミス、カントらの哲学・思想の根源から掘り起こし、倫理資本主義を提起する。
哲学的だが現実的でもある。「資本主義のインフラを使って、道徳的に正しい行動から経済的利益を生み出し、社会を改善することができる。道徳的に正しい行為によって利益を得ることは、富を求めて、恣意的で強欲に行動するより、経済的サスティナビリティが高く、最終的にはより大きな利益につながる」「入れ子構造の危機に直面する時代の不確実性や複雑性への正しい対応は、体制変革や革命ではなく、様々な改革を高度に組み合わせていくことだ」「倫理資本主義とは、資本主義の社会経済インフラが道徳的進歩への寄与度という観点から評価される(ジェンダー、人種、経済的不平等、健康、クリーンエネルギーへの移行、政治的自由・・・・・・)ように、剰余価値生産という社会経済活動を倫理的にアップデートする必要があるという考えだ」「資本主義を克服する考えではなく、必要なのは剰余価値生産を道徳的進歩とリカップリングさせるという改革だ」・・・・・・。
そして、「経済的剰余価値生産と道徳的善には『真の利益』という概念のなかで相関性がある。両者の均衡点をカントの概念にちなんで『最高善』と呼べば、『最高善』とは、経済的価値と道徳的価値の均衡点である。それは真摯に道徳的配慮を持って財を生産・分配することで、経済活動が前向きな社会変化に積極的に寄与する状況だ」「消費主義社会の克服と倫理資本主義の実装として、SDGsのあらゆる側面に投資する。人間の社会経済的発達の次なるステージヘ積極的に未来を作っていこうとする」と言う。
「応用編」として、「次世代の企業に倫理部門の設置を義務付ける」を挙げる。それを率いるのは、最高哲学責任者(CP O)。社内の組織と対話・協力し、真の利益のためのアイディアを生み出す研究開発部門となる。2つ目は、「子どもへの選挙権付与」のアイディア。子どもの想像力が未来を変える、彼らの想像力の可能性を解き放つべきだと主張する。3つ目は、「A Iを社会的技術として再定義すること」だ。AIの開発と使用については倫理的問いが喫緊の課題。AIを持続可能な未来創造のエンジンにするためのイノベーションと、その倫理的な研究が急務だ。
帯には「天才哲学者はいま何を語るのか」とある。斉藤幸平監修、土方奈美訳、昨年出版された著作。
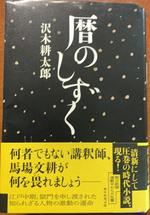 宝暦8年(1759年、9代将軍徳川家重)、講釈師・馬場文耕は獄門に処せられる。時の権力により芸能が弾圧されることはあるが、その芸を理由に死刑を宣せられたのは文耕ただ一人。なぜ馬場文耕は獄門を申し渡されたのか。そもそも馬場文耕とは何者であったのか。その激動の生き様を描く圧倒的な感動巨編。
宝暦8年(1759年、9代将軍徳川家重)、講釈師・馬場文耕は獄門に処せられる。時の権力により芸能が弾圧されることはあるが、その芸を理由に死刑を宣せられたのは文耕ただ一人。なぜ馬場文耕は獄門を申し渡されたのか。そもそも馬場文耕とは何者であったのか。その激動の生き様を描く圧倒的な感動巨編。
文耕は元武士らしく実に端正、屹立した人格と情愛を併せ持つ、魅力的な人物だったらしい。御家人として生まれたが、家禄を返上し西国ヘ向かい剣術修行もする。園木覚郎の無尽流に出会い、抜きん出た腕前と境地に達するが、士分を捨てて江戸に出る。そして貧乏長屋に住み講釈師となる。「太平記」など軍記物を語るという市井の日々。深川の芸者・お六、隣に住むお清、長屋の隣人、仕事で付き合う町衆、吉原の旦那など、文耕に心を寄せ、信頼する者に囲まれていた。
転機が訪れる。ある芸者を助け、売り出すために話を拵えて講釈の場で披露していただけないかという頼みだ。「軍書を読むのではなく、一芸者について講釈するなどという途方もないこと」――。世の噂話を書き集めて、自分で話を作り語る。昔の軍記物を型通りに読むよりも、今の生の物語に惹かれるのが庶民なのだと気づいていく。これが評判となり、文耕人気は高まっていく。しかし噂は面白いが真実ではない。ノンフィクションとフィクション、噂と真実とフェイク――。この現在の情報社会で、最重要のテーマに文耕はぶち当たっていく。
今の生々しい問題を扱う限り、噂を集めながらも、虚偽ではなく、真実に向かおうとする文耕。そして起きたばかりの秋田佐竹藩の「秋田騒動」を語ることになる。「今回の話は少し度が過ぎているかもしれねぇな」「佐竹の騒動は、既に決着していることとはいえまだ生ものだ。触れれば、血が出るかもしれねぇ。佐竹の家の内情に入り込みすぎている。お咎めあっても不思議じゃねぇ」・・・・・・。
そして、ついにあの郡上一揆。美濃の金森家の騒動と、農民一揆の詳細を独自に取材・調査に踏み込んでいく。そして自らが果たせるのは、それを講釈の場で世に知らせ、幕府にも理解させることだと動く。当然、「将軍家はもとより大名旗本の家内のことを、みだりに広めたりするなという町触に違反しているのは明らか」なのだ。老中、評定所等の怒りを買うことは当然。しかし文耕はのめり込む。「公儀を畏れず」「その疑い、悦んで引き受けましょう。何者でもない講釈師馬場文耕が何を畏れましょう。畏れるものは天のみ。天の道に外れたものは畏れるに足りません」・・・・・・。
しかも、この時の幕府は、あの徳川家重、大岡忠光の時代。さらにその下で台頭していく田沼意次が、馬場文耕と10代の頃に共に過ごした仲間であり、意次は文耕を敬愛していたという背景まである。話が面白すぎる展開。
文耕はなぜ獄門に処せられたか。真実を語ることが、自他ともにどれだけの被害リスクをもたらすか。名君家重と大岡忠光はどうさばいたか。そして田沼意次はどう動いたか。文耕をこよなく愛した江戸の町の人々は凛として生きる人格者・文耕にいかなる真心で接し行動したか。丹念に立体的に展開されるドラマは圧倒的な、しかも人間の生き様の重厚さをもって迫ってくる。素晴らしい作品に出会った。

