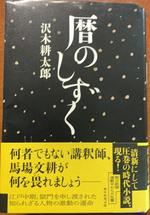 宝暦8年(1759年、9代将軍徳川家重)、講釈師・馬場文耕は獄門に処せられる。時の権力により芸能が弾圧されることはあるが、その芸を理由に死刑を宣せられたのは文耕ただ一人。なぜ馬場文耕は獄門を申し渡されたのか。そもそも馬場文耕とは何者であったのか。その激動の生き様を描く圧倒的な感動巨編。
宝暦8年(1759年、9代将軍徳川家重)、講釈師・馬場文耕は獄門に処せられる。時の権力により芸能が弾圧されることはあるが、その芸を理由に死刑を宣せられたのは文耕ただ一人。なぜ馬場文耕は獄門を申し渡されたのか。そもそも馬場文耕とは何者であったのか。その激動の生き様を描く圧倒的な感動巨編。
文耕は元武士らしく実に端正、屹立した人格と情愛を併せ持つ、魅力的な人物だったらしい。御家人として生まれたが、家禄を返上し西国ヘ向かい剣術修行もする。園木覚郎の無尽流に出会い、抜きん出た腕前と境地に達するが、士分を捨てて江戸に出る。そして貧乏長屋に住み講釈師となる。「太平記」など軍記物を語るという市井の日々。深川の芸者・お六、隣に住むお清、長屋の隣人、仕事で付き合う町衆、吉原の旦那など、文耕に心を寄せ、信頼する者に囲まれていた。
転機が訪れる。ある芸者を助け、売り出すために話を拵えて講釈の場で披露していただけないかという頼みだ。「軍書を読むのではなく、一芸者について講釈するなどという途方もないこと」――。世の噂話を書き集めて、自分で話を作り語る。昔の軍記物を型通りに読むよりも、今の生の物語に惹かれるのが庶民なのだと気づいていく。これが評判となり、文耕人気は高まっていく。しかし噂は面白いが真実ではない。ノンフィクションとフィクション、噂と真実とフェイク――。この現在の情報社会で、最重要のテーマに文耕はぶち当たっていく。
今の生々しい問題を扱う限り、噂を集めながらも、虚偽ではなく、真実に向かおうとする文耕。そして起きたばかりの秋田佐竹藩の「秋田騒動」を語ることになる。「今回の話は少し度が過ぎているかもしれねぇな」「佐竹の騒動は、既に決着していることとはいえまだ生ものだ。触れれば、血が出るかもしれねぇ。佐竹の家の内情に入り込みすぎている。お咎めあっても不思議じゃねぇ」・・・・・・。
そして、ついにあの郡上一揆。美濃の金森家の騒動と、農民一揆の詳細を独自に取材・調査に踏み込んでいく。そして自らが果たせるのは、それを講釈の場で世に知らせ、幕府にも理解させることだと動く。当然、「将軍家はもとより大名旗本の家内のことを、みだりに広めたりするなという町触に違反しているのは明らか」なのだ。老中、評定所等の怒りを買うことは当然。しかし文耕はのめり込む。「公儀を畏れず」「その疑い、悦んで引き受けましょう。何者でもない講釈師馬場文耕が何を畏れましょう。畏れるものは天のみ。天の道に外れたものは畏れるに足りません」・・・・・・。
しかも、この時の幕府は、あの徳川家重、大岡忠光の時代。さらにその下で台頭していく田沼意次が、馬場文耕と10代の頃に共に過ごした仲間であり、意次は文耕を敬愛していたという背景まである。話が面白すぎる展開。
文耕はなぜ獄門に処せられたか。真実を語ることが、自他ともにどれだけの被害リスクをもたらすか。名君家重と大岡忠光はどうさばいたか。そして田沼意次はどう動いたか。文耕をこよなく愛した江戸の町の人々は凛として生きる人格者・文耕にいかなる真心で接し行動したか。丹念に立体的に展開されるドラマは圧倒的な、しかも人間の生き様の重厚さをもって迫ってくる。素晴らしい作品に出会った。
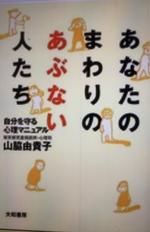 「あなたの善意、熱意、努力が問題を悪化させている!」と指摘し、自分自身をこうした人からどう守るか、巻き込まれてはいけないと山脇さんはいう。そのためには、精神科の治療対象の人、またそれに近い人を見分ける。繰り返し、繰り返し、同じように迷惑をかける人に対して、巻き込まれない、毅然とした態度をとること。苦しんでいる人を突き放す、冷たい態度のようだが、その人の為でもあるといっている。
「あなたの善意、熱意、努力が問題を悪化させている!」と指摘し、自分自身をこうした人からどう守るか、巻き込まれてはいけないと山脇さんはいう。そのためには、精神科の治療対象の人、またそれに近い人を見分ける。繰り返し、繰り返し、同じように迷惑をかける人に対して、巻き込まれない、毅然とした態度をとること。苦しんでいる人を突き放す、冷たい態度のようだが、その人の為でもあるといっている。
買い物病が止まらない、逆上して死んでやると騒ぐ、そして実際に手首を切る、脅しなのか、本気なのか――境界性人格障害の女性だ。嫉妬深い、24 時間行動をチェックする、暴力をふるう、別人のように甘えたりやさしくなる、別れるなら死んでやる殺してやると脅す、アルコールやギャンブル好き、仕事が続かない――境界性人格障害の男性だ。それには許すのは 1 回だけ、暴力が出たら即逃げる、警察にいうことが大切だと山脇さんはいう。
人の心が鍛えられないと生き抜けない時代に入っている。
 これまで「家族の愛と絆」「家族のトラウマ」「喪失による心の痛み」などを描いてきた著者のさらに進化(深化)した最新作。
これまで「家族の愛と絆」「家族のトラウマ」「喪失による心の痛み」などを描いてきた著者のさらに進化(深化)した最新作。
ニ年前に父・原田啓和が他界し、先月には母・晶枝が急逝。不動産仲介管理会社で働く原田燈子は天涯孤独となる。母が亡くなり実家の整理に訪れた燈子は、母が書いていた日記を見つける。4つ下の弟・輝之が3歳の時、車にはねられ死亡、家族には心の中に「大きな穴」が開いていた。「私が目を離したから」との罪の意識は晶枝の心から離れず、夫の啓和は、それをかばい守ろうと意識した。「母親も、父親も、輝之もいなくなった。・・・・・・この家には、本当は誰もいなかった。もうずっと前から」・・・・・・。弟の事故死をきっかけにして、家族はそれぞれの心にこもってしまったのだ。
やがて日記には亡くなった母の筆跡で色のない文字が刻まれるようになった。亡き後も綴られる書かれるはずのない母の日記。
物語は燈子のいる「この世」と両親がいる「あの世」が日記を通じて往還する形で進む。不思議な「あの世」では、様々な後悔や執着、傷を抱えた人々がそれを消化できないまま、死者の「夜行」に加わったりしていた。晶枝と啓和も出会い、「なぜ目を離したか」と悔恨する晶枝、「輝之はどうして死んだんだろう。どうして目を離したのかじゃない。どうして輝之は車道に出たのか」と言う啓和。
「どうして車道に出たと思う? 公園に寄ってくれて嬉しかったんだよ。今世界で一番幸せ! みたいな気分になった。はしゃぎすぎて、ただ、失敗したんだと思う」という境地にたどり着く。
「今、輝之はどこにいるのだろう」――。生と死。この世とあの世。それは切れてるのかつながっているのか。宇宙生命に溶け込んでいるのか。有と無、そして空。ダークマターとダークエネルギー。「量子もつれ」・・・・・・。本書は、生と 死を日記でつなげているが・・・・・・。
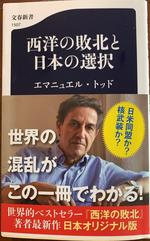 「西洋の敗北」の著者エマニュエル・トッドが、日本オリジナル版として出したもの。ウクライナ戦争、イスラエル・イラン紛争、トランプ関税、米欧の分裂が意味する「西洋の敗北」。「西洋の民主主義」を作り出した英米仏の三極は安全保障においても、産業の空洞化・経済的にも崩壊し、なかでもプロテスタンティズム「労働倫理」が崩壊、「進歩」という理想が崩壊していると言う。「西洋は世界から尊敬されていて、西洋が世界を指導している」と言うのは現実には違っており、「西洋の虚偽意識」なのだ。それは今、「2008年、ジョージアとウクライナを将来的にNATOに組み込むことは絶対に許さない」とするプーチンの宣言は、「信頼できるロシア、信頼できない米国」「ロシアが軍事的に優勢に立ち、経済も安定しているのに対して、産業が空洞化した米国は十分な武器を供給できず、欧州は経済制裁の最大の被害者となっている」に帰結していると言う。
「西洋の敗北」の著者エマニュエル・トッドが、日本オリジナル版として出したもの。ウクライナ戦争、イスラエル・イラン紛争、トランプ関税、米欧の分裂が意味する「西洋の敗北」。「西洋の民主主義」を作り出した英米仏の三極は安全保障においても、産業の空洞化・経済的にも崩壊し、なかでもプロテスタンティズム「労働倫理」が崩壊、「進歩」という理想が崩壊していると言う。「西洋は世界から尊敬されていて、西洋が世界を指導している」と言うのは現実には違っており、「西洋の虚偽意識」なのだ。それは今、「2008年、ジョージアとウクライナを将来的にNATOに組み込むことは絶対に許さない」とするプーチンの宣言は、「信頼できるロシア、信頼できない米国」「ロシアが軍事的に優勢に立ち、経済も安定しているのに対して、産業が空洞化した米国は十分な武器を供給できず、欧州は経済制裁の最大の被害者となっている」に帰結していると言う。
そこで、日本の根本問題は「安全保障」と「少子化」という先進国共通の文明史的問題だ。安全保障においては「日本は核武装せよ」と言う。「核の傘概念は無意味で、使用すれば自国も核攻撃を受けるリスクのある核兵器は原理的に他国のためには使えない。米国が自国の核を使って日本を守るとは絶対にありえない。核は『持たないか』『自前で持つか』以外の選択はない」と言うのだ。また「『異国』を戦争に巻き込む米国」であり、日本に勧めたいのは「できるだけ何もしないこと」と言う。
エマニュエル・トッドは人口学者。「私が懸念しているのは、日本だけでなく西洋諸国、北欧ですら低下している出生率の低さ」。経済との関係のなかで言う。「今日、核家族社会では『教育水準の低下』が顕著です。核家族社会はドイツと日本など直系家族社会(育児を可能にする持続的な夫婦関係)ほど、子供を教育で『囲い込む』ことがない。教育水準が低下した結果、今日の米国には『良質で勤勉な労働者』が不足している」と言う。
「イスラエルは神を信じていない」「戦争自体が自己の存在理由に」――。「ガザは、イスラエルの政治的主権が及ぶ地域でイスラエルの一部」「ハマスはイスラエル国家の支配空間に生まれたもので、ハマスは明らかにテロリストの集団ですが、『イスラエルの現象』」と言う。「イスラエルは、宗教的に『超正統派』の存在にもかかわらず、『宗教的空虚』(宗教のゼロ状態)が社会を覆っている」と言い、「今や西洋は米国や欧州のニヒリズムの原因となる『宗教のゼロ状態』に達している」「イスラエル国家の振る舞いは、社会的・宗教的価値観を失い(ユダヤ教・ ゼロ)、国家存続のための戦略に失敗し、周囲のアラブ人やイラン人に対する暴力の行使に自己の存在理由を見出している国家だ」と言い切る。戦争自体が自己の存在理由になっていると言うのだ。
「危険なのは、イランより米国とイスラエルだ」「日本と同じくイランの核武装は何の問題もない。平和に寄与する」・・・・・・。「世界は米国を必要とするのではなく、米国は世界を必要とする」と強調する。だからと言うべきか、世界的なベストセラー「西洋の敗北」はまだ英語版では翻訳がされていない。
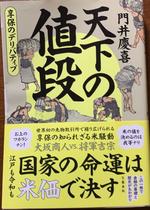 「享保のデリバティブ」と副題が付いている。第8代将軍吉宗の享保時代。天下の台所、大阪堂島には全国から米が集まり、日々値がつけられ、膨大な取引が行われていた。しかもこの時代、貨幣経済が始まり、すべての中心の米の市場が形成されるという歴史の分水嶺。
「享保のデリバティブ」と副題が付いている。第8代将軍吉宗の享保時代。天下の台所、大阪堂島には全国から米が集まり、日々値がつけられ、膨大な取引が行われていた。しかもこの時代、貨幣経済が始まり、すべての中心の米の市場が形成されるという歴史の分水嶺。
江戸の幕府は、米の年貢収入が権力の根源であっただけに、その米価が大坂の商人たちの意のままに決められていることに苛立っていた。商人たちは、紙と筆と頭脳を用い、利鞘を稼ぐ今でいう先物取引に魂を注ぐ状況。「米価は武士にとって死活問題。その米価を大坂商人がほしいままに操るとは不届き千万」と米価の決定権を握ろうとする幕府と、市場の自治を守ろうとする大坂商人との真っ向勝負、「銭金の世の関ヶ原」が描かれる。史実に基づく躍動のフィクション。
主人公は垓太とおけいの双子の姉弟。おけいは大橋屋安兵衛という小さな米仲買の妻であったが、夫が大坂を襲った「享保の大火」で圧死、垓太に跡を継がせる。一方、江戸の吉宗は大岡越前守忠相に指示し、江戸の商人を大坂に送り込み、コントロールしようとする。
激しい頭脳戦。焦点は帳合米の扱い。「なんでこの世に帳合米があるのか。・・・・・・まさしくそれです。下がったら上がる。上がったら下がる。手を加えるなんて誰もできひん。大岡様も上様も。それを決めるのは、商人たちの欲の流れなんです」「資本の親子関係というべきか。大阪の米の値段とは、こういう巨大な蜘蛛の巣のようなものによって、日本の隅々にまで伝わっているのだ」「せやから大坂の値段は、大坂の値段やないんです。天下の、値段」・・・・・・。吉宗も、支配、被支配とは全く違う利益と損失の論理が世に行き渡り、大名も百姓も商人も巻き込んで、全国60 余州の国と民をひとつのものにしてしまっていると思い知るのだった。
市場経済、貨幣経済が、江戸と大坂、武士と商人、享保の米騒動の激しい戦いの中で始まっていく。面白い。

