 かつて「暴走老人!待てない、我慢できない、止まらない」(藤原智美著)や「祖母力」(樋口恵子著)なども興味深く読んだが、曽野綾子さんは、年を重ねても自立した老人になっていない、年のとり方を知らない(......してくれないというくれない族)が
増えていることを問題とする。「自立と自律の力」「孤独と付き合い、人生を面白がる力」などが大切。老いの才覚=老いる力を持つことが重要だという。「い
くつになっても話の合う人たちと食事をしたい」「あるか、ないか、わからないものは、あるほうに賭ける」「孤独と絶望こそ、人生の最後に充分味わうべき境
地なのだと思う時がある」、そして最後のブラジルの詩人の「浜辺の足跡」は印象的だ。
かつて「暴走老人!待てない、我慢できない、止まらない」(藤原智美著)や「祖母力」(樋口恵子著)なども興味深く読んだが、曽野綾子さんは、年を重ねても自立した老人になっていない、年のとり方を知らない(......してくれないというくれない族)が
増えていることを問題とする。「自立と自律の力」「孤独と付き合い、人生を面白がる力」などが大切。老いの才覚=老いる力を持つことが重要だという。「い
くつになっても話の合う人たちと食事をしたい」「あるか、ないか、わからないものは、あるほうに賭ける」「孤独と絶望こそ、人生の最後に充分味わうべき境
地なのだと思う時がある」、そして最後のブラジルの詩人の「浜辺の足跡」は印象的だ。
12年前の「中年以後」とあわせ読むと感銘深い。「『老いの才覚』が大変なベストセラーになってしまって......」とか、時代そのものを曽野さんは感じているのかもしれない。両書の微妙な変化もまた「老いの才覚」なのか。
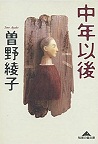 99年
の本だが、「中年以後の人の心をずっと前から書きたいと考えていた。つまり青くない、幼稚ではない人の心を、である」――「ただ人間だけがいる――この世
には神も悪魔もいないことを知る頃」と題する冒頭のエッセイはこの文章から始まる。「若い頃の人間の思考は単反射である」「物の判断については大人にな
れ」「他人のことはわかっていない、という自覚のある人は極めて少ない。......事情がわかると、簡単に、いい人だとか悪い人だとか言えなくなる」
「曖昧さに耐える」「いい年をして正義感だけでものごとを判断していたら、人間になり損ねる」とも。
99年
の本だが、「中年以後の人の心をずっと前から書きたいと考えていた。つまり青くない、幼稚ではない人の心を、である」――「ただ人間だけがいる――この世
には神も悪魔もいないことを知る頃」と題する冒頭のエッセイはこの文章から始まる。「若い頃の人間の思考は単反射である」「物の判断については大人にな
れ」「他人のことはわかっていない、という自覚のある人は極めて少ない。......事情がわかると、簡単に、いい人だとか悪い人だとか言えなくなる」
「曖昧さに耐える」「いい年をして正義感だけでものごとを判断していたら、人間になり損ねる」とも。
こんなエッセイが24も 詰まっている。「かつて自分を傷つける凶器だと感じた運命を、自分を育てる肥料だったとさえ認識できる強さを持つのが、中年以後である」「中年以後にしか 人生は熟さない」「正義など、素朴な人間の幸福の前では何ほどのことか、そう思えるのが中年というものだ」「醜いこと、惨めなこと、にも手応えのある人生 を見出せるのが中年だ」「権力追求病は、主に中年以後にかかる病気らしい。それも女性より男性の罹患率が高い」「中年を過ぎたら、私たちはいつもいつも失 うことに対して準備し続けていなければならないのだ」......。
如 実知見、経験も深さもあり、哲学の背骨も感ずる。何か横にすわって日常の対話をしてくれているようだ。「若い時は自分の思い通りになることに快感がある。 しかし中年以後は自分程度の見方、予測、希望、などが裏切られることもある、と納得し、その成り行きに一種の快感を持つこともできるようになるのであ る」......。
北島康介、福原愛、魁皇、乙武洋匡、さかなクン、山崎直子、ベッキー、広瀬章人、大日方邦子、吉田沙保里......。子どもゆめ基金10周年を記念して、各分野で活躍している30名とのインタビュー。
子どもの頃、個性あるゆえか仲間はずれにされたり、悩んだり......。しかし、「好きなものを見つける努力」「夢をさがす」「もうやめたいと思ってもやり続ける」「厳しい練習を乗り越えてきたことが、自分の自信となった」などと語る。今の若者は伸びる。自由度も大。
 東
野圭吾の加賀恭一郎シリーズ。なじみの地域なので想像力がかきたてられる。日本橋の欄干にもたれかかった男に突き刺さったナイフ。ていねいに、ささいなこ
とから感情をもたどって事件の真相に迫る加賀。東野さんの小説はだんだんシンプルに人がやさしくなっていくように思う。「麒麟の翼」は親父のかなしさか。
東
野圭吾の加賀恭一郎シリーズ。なじみの地域なので想像力がかきたてられる。日本橋の欄干にもたれかかった男に突き刺さったナイフ。ていねいに、ささいなこ
とから感情をもたどって事件の真相に迫る加賀。東野さんの小説はだんだんシンプルに人がやさしくなっていくように思う。「麒麟の翼」は親父のかなしさか。
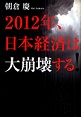 「日
本経済と世界経済がいかに危機的状況か」「金融市場で高速取引をするコンピューターがいかに資本市場を支配しているか」「上昇を続ける商品価格とインフ
レ」「リーマン・ショック後の世界中でバラ撒かれたマネーは、各国の国債市場の大暴落をもたらす」「米国・EU・中国の思惑と弱点」などを示しつつ、2012年、世界経済の大崩壊の危機を指摘している。
「日
本経済と世界経済がいかに危機的状況か」「金融市場で高速取引をするコンピューターがいかに資本市場を支配しているか」「上昇を続ける商品価格とインフ
レ」「リーマン・ショック後の世界中でバラ撒かれたマネーは、各国の国債市場の大暴落をもたらす」「米国・EU・中国の思惑と弱点」などを示しつつ、2012年、世界経済の大崩壊の危機を指摘している。
各国の思惑、ヘッジファンド、格付け会社など、市場における裏面にふれつつ、警告する。

