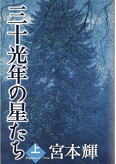
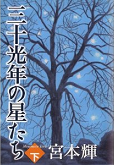 尊
き人生とは師弟に生きること。師の心と弟子の誓い。宇宙のなかで、自然のなかで、市井に生きる尊さと創造すべき価値。世界中に三千万本の木を植えた作中に
出てくるモデル・横浜国大宮脇昭先生に対する師の言葉「見よ、この大地を!
39億年の地球の生命の歴史と巨大な太陽のエネルギーの下での生命のドラマが目の前にある。まず現場に出て、目で見て、匂いを嗅いで、舐めて触って調べ
ろ!
現代人には二つのタイプがある。見えるものしか見ないタイプと、見えないものを見ようと努力するタイプだ。きみは後者だ。現場が発しているかすかな情報か
ら見えない全体を読み取りなさい」――。主人公の青年・坪木仁志は、佐伯平蔵からこの言葉を送られる。
尊
き人生とは師弟に生きること。師の心と弟子の誓い。宇宙のなかで、自然のなかで、市井に生きる尊さと創造すべき価値。世界中に三千万本の木を植えた作中に
出てくるモデル・横浜国大宮脇昭先生に対する師の言葉「見よ、この大地を!
39億年の地球の生命の歴史と巨大な太陽のエネルギーの下での生命のドラマが目の前にある。まず現場に出て、目で見て、匂いを嗅いで、舐めて触って調べ
ろ!
現代人には二つのタイプがある。見えるものしか見ないタイプと、見えないものを見ようと努力するタイプだ。きみは後者だ。現場が発しているかすかな情報か
ら見えない全体を読み取りなさい」――。主人公の青年・坪木仁志は、佐伯平蔵からこの言葉を送られる。
最後に、小説では珍しく「あとがき」がある。宮本さんの思いだと思うが、本書は人生、哲学そのものの小説だ。
 一部と二部で構成されている。東日本大震災の被災後、竹森さんが約1か月、感じたこと、考えたことを日記風に書いた一部。そして第二部では、1995年の
阪神大震災のあと、過剰設備が修正され、生産設備に対する需要拡大によって日本経済が好転した。今回も同じ現象が起こる可能性があり、そのためには供給の
ボトルネックが解消されること、つまり電力不足が解消されなくてはならない。それが2年で完了すれば、輸出力を増大させること(電力不足、世界的な脱原発
の流れもあって輸入の石油依存が高まり、石油価格高騰もある)が大切となる。計画停電もしっかりとポリシーをもって産業活動に配慮せよ。日本のエネルギー
(安価なクリーン・エネルギーはすぐには生まれない)を経済・産業の視点から考え、需要と供給を考え、そしてバブル崩壊後に最大の経済成長率を達成した
95年阪神大震災型の経済復興を考えよ。不況・デフレ下という同様の状況下で、過剰設備が解消され、好循環をもたらした「95年モデル」だ――竹森さんは
率直に言う。
一部と二部で構成されている。東日本大震災の被災後、竹森さんが約1か月、感じたこと、考えたことを日記風に書いた一部。そして第二部では、1995年の
阪神大震災のあと、過剰設備が修正され、生産設備に対する需要拡大によって日本経済が好転した。今回も同じ現象が起こる可能性があり、そのためには供給の
ボトルネックが解消されること、つまり電力不足が解消されなくてはならない。それが2年で完了すれば、輸出力を増大させること(電力不足、世界的な脱原発
の流れもあって輸入の石油依存が高まり、石油価格高騰もある)が大切となる。計画停電もしっかりとポリシーをもって産業活動に配慮せよ。日本のエネルギー
(安価なクリーン・エネルギーはすぐには生まれない)を経済・産業の視点から考え、需要と供給を考え、そしてバブル崩壊後に最大の経済成長率を達成した
95年阪神大震災型の経済復興を考えよ。不況・デフレ下という同様の状況下で、過剰設備が解消され、好循環をもたらした「95年モデル」だ――竹森さんは
率直に言う。
 体制とやり方を継続し、部分の対応をしている限り、日本は沈む。復興が「戦後日本」の再現であってはならない。豊かな省エネ社会、地域主権型の多極的特色
をもつ国の形(文化都市、道州制へのスタート)、70歳まで働ける好老文化、「嫌々開国」ではない「好き好き開国」――この4つを指標とせよ。電力供給、
産業構造、農・工・知価産業の連携、官僚主導からの脱却などを、岩田一政さん、圓尾雅則さん、柳川範之さん、大滝精一さん、宋文洲さん等、専門家との緊急
対談のなかで、堺屋さんは意欲的に言う。
体制とやり方を継続し、部分の対応をしている限り、日本は沈む。復興が「戦後日本」の再現であってはならない。豊かな省エネ社会、地域主権型の多極的特色
をもつ国の形(文化都市、道州制へのスタート)、70歳まで働ける好老文化、「嫌々開国」ではない「好き好き開国」――この4つを指標とせよ。電力供給、
産業構造、農・工・知価産業の連携、官僚主導からの脱却などを、岩田一政さん、圓尾雅則さん、柳川範之さん、大滝精一さん、宋文洲さん等、専門家との緊急
対談のなかで、堺屋さんは意欲的に言う。
 「新しい日本」を創ろう。変わらぬ産業構造、長引くデフレ、人口減少もあって、ただでさえ衰退が懸念される日本が、東日本大震災によって致命的打撃を受
け、トドメを刺されてはならない。これまでの延長線上の復旧では衰退は必至。岐路だ。新しい日本を創る契機にしよう。東北を「太陽経済」都市圏にしよう、
再生エネルギーにシフトしよう。自然と共生する太陽経済国家・世界に開かれた活力ある経済にしよう。高齢化が進もうと、人口減少となろうが、日本に魅力が
あれば資金・人材・技術・経営力は集まってくる。島田晴雄さんは、そういいつつ、日本経済はデフレ、人口減少、農業・医療・教育・行政・原発事故と「かな
りの重病」。それゆえに、たんなる理想論やスローガンではなく、実行過程を明示することが大切だという。今の震災の分析、経済の分析、エネルギーの分析を
しつつ、現場を歩いた現場感覚・皮膚感覚から「今やるべきこと」を具体的に提示する。しかも、大前研一氏、平井憲夫氏、飯田哲也氏、山崎養世氏らの主張も
イデオロギーにとらわれず引用している。今の証言と緊急提言の書。
「新しい日本」を創ろう。変わらぬ産業構造、長引くデフレ、人口減少もあって、ただでさえ衰退が懸念される日本が、東日本大震災によって致命的打撃を受
け、トドメを刺されてはならない。これまでの延長線上の復旧では衰退は必至。岐路だ。新しい日本を創る契機にしよう。東北を「太陽経済」都市圏にしよう、
再生エネルギーにシフトしよう。自然と共生する太陽経済国家・世界に開かれた活力ある経済にしよう。高齢化が進もうと、人口減少となろうが、日本に魅力が
あれば資金・人材・技術・経営力は集まってくる。島田晴雄さんは、そういいつつ、日本経済はデフレ、人口減少、農業・医療・教育・行政・原発事故と「かな
りの重病」。それゆえに、たんなる理想論やスローガンではなく、実行過程を明示することが大切だという。今の震災の分析、経済の分析、エネルギーの分析を
しつつ、現場を歩いた現場感覚・皮膚感覚から「今やるべきこと」を具体的に提示する。しかも、大前研一氏、平井憲夫氏、飯田哲也氏、山崎養世氏らの主張も
イデオロギーにとらわれず引用している。今の証言と緊急提言の書。
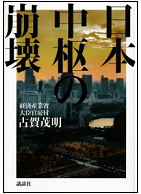 公務員は"身分保障"で守られている。省益を求める。内向きの論理で国民の為に働くシステムでない。公務員制度改革をやらないと、この国難・日本は新しい
スタートができない。改革を進めると思われた民主党政権では逆走している。政治家も公務員も、国家・国民の為に死にもの狂いで働かないと未来はない。経産
省の現役・古賀茂明さんはそう言い、とくにこの10数年、自らかかわってきた問題についてその考えと行動を明らかにしている。改革断行には強い意志ととも
に揺るがぬ行動理念が必要だが、あわせて痛みは常に弱者に来るゆえに弱者への配慮が大切。善悪の二元論を越えた如実知見が大事だと私は思っている
公務員は"身分保障"で守られている。省益を求める。内向きの論理で国民の為に働くシステムでない。公務員制度改革をやらないと、この国難・日本は新しい
スタートができない。改革を進めると思われた民主党政権では逆走している。政治家も公務員も、国家・国民の為に死にもの狂いで働かないと未来はない。経産
省の現役・古賀茂明さんはそう言い、とくにこの10数年、自らかかわってきた問題についてその考えと行動を明らかにしている。改革断行には強い意志ととも
に揺るがぬ行動理念が必要だが、あわせて痛みは常に弱者に来るゆえに弱者への配慮が大切。善悪の二元論を越えた如実知見が大事だと私は思っている

