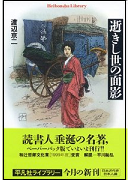 本の表題自体がこの書の深さと丹念さを表わしている。「過ぎし時代の思い出」ではない。「過ぎ」ではなくて「逝きし」であり、「時代」ではなくて「生活や習慣や思考を含む世の中」であり、「思い出」ではなく、「滅びた、とはいえ残っている面影」だ。
本の表題自体がこの書の深さと丹念さを表わしている。「過ぎし時代の思い出」ではない。「過ぎ」ではなくて「逝きし」であり、「時代」ではなくて「生活や習慣や思考を含む世の中」であり、「思い出」ではなく、「滅びた、とはいえ残っている面影」だ。
「幕 末に異邦人たちが目撃した徳川後期文明は、ひとつの完成の域に達した文明だった。それは成員の親和と幸福感、あたえられた生を無欲に楽しむ気楽さと諦念、 自然環境と日月の運行を年中行事として生活化する仕組みにおいて、異邦人を讃嘆へと誘わずにはいない文明であった。しかしそれは滅びなければならぬ文明で あった」
すでに現世の物質的目的、実利主義的産業社会に突入していた欧米人が、近代以前の、しかも完成された文明をもつ日本をどう見たか。「陽気 な人びと」「簡素とゆたかさ」「親和と礼節」「雑多と充溢」「勤勉と忍耐と安易な生活」「専制主義と身分と自由」「混浴・行水、裸体と性」「子どもの楽 園」「女と家」「風景とコスモス(私の地元、王子の風景が出てくる)」「生類とコスモス」「心の垣根(休息と安寧と平和)」など、すさまじいほどの文献か ら、日本と日本人を根底から問いかけている。ただし、イデオロギーでもないし、復古でもない。渡辺さん自ら、関心は自分の「祖国」を誇ることにはないと 言っているが、だからこそ日本と日本人が照らし出されている。
 災害時の人間心理に焦点をあて、避難行動の重要性・仕組み・影響を与えるヒューマン・ファクターなどを示す。そして、災害の衝撃から回復までを実例をあげ
て分析し、生きのびるための条件を提示してくれる。今回の東日本大震災においても災害心理学・広瀬教授のテレビ等を通しての解説はきわめて明解。現場の実
情を踏まえてすごく納得した。
災害時の人間心理に焦点をあて、避難行動の重要性・仕組み・影響を与えるヒューマン・ファクターなどを示す。そして、災害の衝撃から回復までを実例をあげ
て分析し、生きのびるための条件を提示してくれる。今回の東日本大震災においても災害心理学・広瀬教授のテレビ等を通しての解説はきわめて明解。現場の実
情を踏まえてすごく納得した。
「どんな人が生きのびるか」――洞 爺丸海難事故の押沢・渕上両先生や、被爆者の北山上葉さんの母としての生きる執念は、感動的だ。また大災害は行政だけでないマンパワー、ボランティアや NPOなしには乗り越えられないこと、災害復興といっても、災害は被災社会の効率化をもたらし、元には戻らないこと・・・・・・。示唆に富む書。
 「私はよく、理屈は大嫌いだと言って、笑われることがある。......あるいは、この件についての御意見を、と訊かれて、たいていは言葉につまる。意
見というものを、もったことがないのである」――。理屈を言い、意見をもっていると思われた池田さんは、たしかにそうだったろう。哲学とは全てをそぎ落と
した境地から始まると思う。
「私はよく、理屈は大嫌いだと言って、笑われることがある。......あるいは、この件についての御意見を、と訊かれて、たいていは言葉につまる。意
見というものを、もったことがないのである」――。理屈を言い、意見をもっていると思われた池田さんは、たしかにそうだったろう。哲学とは全てをそぎ落と
した境地から始まると思う。
小林秀雄と池田さんが一体となって如実知見、諸法実相の世界に迫っている。亡くなる3年前、2004年の著作。
 岩見さんが、2009年から2011年2月まで、「毎日新聞(近聞遠見)」「サンデー毎日(サンデー時評)」「選択」などに書いたものをまとめている。
3・11以降は、まさに非常事態だが、それ以前もじつは深刻な非常事態の日本――。「国民も政治家も漠然と不安を覚えながら確たる非常時意識がない。じわ
じわと忍び寄る、始末の悪い非常時である」、そしてそこには、「政治の鈍感と怠慢がある」。さらに政治家の「言葉の貧しさ、軽さや大安売り」が、政治の軽
さと政治不信を増幅させる。
岩見さんが、2009年から2011年2月まで、「毎日新聞(近聞遠見)」「サンデー毎日(サンデー時評)」「選択」などに書いたものをまとめている。
3・11以降は、まさに非常事態だが、それ以前もじつは深刻な非常事態の日本――。「国民も政治家も漠然と不安を覚えながら確たる非常時意識がない。じわ
じわと忍び寄る、始末の悪い非常時である」、そしてそこには、「政治の鈍感と怠慢がある」。さらに政治家の「言葉の貧しさ、軽さや大安売り」が、政治の軽
さと政治不信を増幅させる。
3・11東日本大震災以前の文章だが、「いま政治に求められているのは、非常事態の本質を過不足なく厳密に国民に伝え、貧弱な危機意識と過剰な危機意識の両方を防ぐことだ」――。全くそう思う。
 「石油に代わる新エネルギー資源」と副題にあるが、石油文明に変わるのは自然エネルギー・水素社会か、という問いを発している。突破する解は「マグネシウ
ム循環社会」――。太陽光発電などの自然エネルギーだけでは石油の代替にならない。水素は運搬や貯蔵が難しい。「太陽熱を利用した淡水化装置を使って、海
水中の塩化マグネシウムを取り出す」「太陽光からレーザーをつくる」「太陽光励起レーザーで酸化マグネシウム(熱を加えて塩化マグネシウムを酸化マグネシ
ウムにしておく)を、金属マグネシウムに製錬する」「それを交通機関や発電所などの燃料として利用する」「利用したあとに残った酸化マグネシウムを再び金
属マグネシウムに製錬する」――この循環の研究が進められている。極力やさしく書かれている。挑戦しないと何も生まれない。緊急事態だ。
「石油に代わる新エネルギー資源」と副題にあるが、石油文明に変わるのは自然エネルギー・水素社会か、という問いを発している。突破する解は「マグネシウ
ム循環社会」――。太陽光発電などの自然エネルギーだけでは石油の代替にならない。水素は運搬や貯蔵が難しい。「太陽熱を利用した淡水化装置を使って、海
水中の塩化マグネシウムを取り出す」「太陽光からレーザーをつくる」「太陽光励起レーザーで酸化マグネシウム(熱を加えて塩化マグネシウムを酸化マグネシ
ウムにしておく)を、金属マグネシウムに製錬する」「それを交通機関や発電所などの燃料として利用する」「利用したあとに残った酸化マグネシウムを再び金
属マグネシウムに製錬する」――この循環の研究が進められている。極力やさしく書かれている。挑戦しないと何も生まれない。緊急事態だ。

