 朝日新聞の記者・奥山俊宏さんが、東電本店において3.11から50日間の克明な取材・記録。断片的にしか報道されなかった会見での一部始終。混乱、危
機とあせり、試行錯誤、情報の不足、そのなかでの決断。――貴重な記録だが、そのなかに「なぜ備えを怠ったか」「電源喪失のような危機の兆しはこれまでも
あったではないか」――小事を大事としなかった背景にあるもの。それが原発・エネルギー問題として浮き彫りにされる。
朝日新聞の記者・奥山俊宏さんが、東電本店において3.11から50日間の克明な取材・記録。断片的にしか報道されなかった会見での一部始終。混乱、危
機とあせり、試行錯誤、情報の不足、そのなかでの決断。――貴重な記録だが、そのなかに「なぜ備えを怠ったか」「電源喪失のような危機の兆しはこれまでも
あったではないか」――小事を大事としなかった背景にあるもの。それが原発・エネルギー問題として浮き彫りにされる。
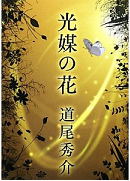 六つの短編(六章)それぞれ別だが、人物や心象はつながっている。子ども、兄妹、姉弟、親子、昆虫、草花、夕暮れ、光、悲哀、沈潜する思い
出......。第一章から徐々に旋律が高まり、「冬の蝶」「春の蝶」でヤマを迎えるような感がする。息苦しいほどに心に迫ってくる小説だが、最終第六章
「遠い光」で、解き放たれて安堵する。運命に翻弄されながら「風が吹くのを待つ"風媒花"」のような心に影をもつ人々が、ちょっとしたことで前へ進む小さ
な光を見出す。「この全六章を書けただけでも、僕は作家になってよかったと思います」と道尾さんは語っているが、そうだろうなと思う。優しさが広がる作品
だ。
六つの短編(六章)それぞれ別だが、人物や心象はつながっている。子ども、兄妹、姉弟、親子、昆虫、草花、夕暮れ、光、悲哀、沈潜する思い
出......。第一章から徐々に旋律が高まり、「冬の蝶」「春の蝶」でヤマを迎えるような感がする。息苦しいほどに心に迫ってくる小説だが、最終第六章
「遠い光」で、解き放たれて安堵する。運命に翻弄されながら「風が吹くのを待つ"風媒花"」のような心に影をもつ人々が、ちょっとしたことで前へ進む小さ
な光を見出す。「この全六章を書けただけでも、僕は作家になってよかったと思います」と道尾さんは語っているが、そうだろうなと思う。優しさが広がる作品
だ。
当然、北方領土、尖閣諸島、竹島。これらは長き歴史とともに、あの戦争、ポツダム宣言が出発点にある。そして51年のサンフランシスコ平和条約、56年の日ソ共同宣言、65年日韓基本条約、72年の日中共同声明。孫崎さんはその交渉の背景にあったもの、両国の思惑、そして米国の戦略などを、端的に、具体的文書や当事者の発言録などで浮き彫りにしている。北方領土・日ソ共同宣言の背景をみても、孫崎さん自ら踏み込んで言うように新鮮だ。
ドイツと日本は同じ敗戦国といっても違う。今日からみても欧州と北東アジアは地勢、国勢からも違う。しかしそのうえで、アデナウアーが「私が取り組んだのはドイツをも加えた欧州合衆国という問題であった」とし、独仏協力やがてはEU構想へと発展する思考のパースペクティブ、それを具体化しようとした勇気がある。苦難の蓄積とそれをためこみ放つ哲学を感ずる。変化する時代をリアルに凝視した構想力をもつこと、自らの思考のバリアを越えること、戦争を回避する智慧(本書では平和への9つの方策が提示される)――それが大事であることを示唆してい
 米共和党・民主党を代表する知日派二大巨頭が日米同盟について、驚くほどはっきりと語り合う。とにかく率直だ。「米国の安全保障政策にとって、日本との同
盟関係は死活的に重要である」という認識。民主・共和両党の理論的軸の2人はほとんど一致する。幾度か日米同盟は漂流し、岐路に立っている。とくに鳩山民
主党政権以降はその点、最悪の状況を自らつくり出し、今日に至っている。「抑止力」の何たるかもわからぬと自ら語るほどひどいものだ。そんななかでのナ
イ・アーミテージ対談。春原さんの聞き方も率直で多彩、きわめていい。本書が「アーミテージ・ナイ緊急提言」と副題が付されているように意味は大きい。
米共和党・民主党を代表する知日派二大巨頭が日米同盟について、驚くほどはっきりと語り合う。とにかく率直だ。「米国の安全保障政策にとって、日本との同
盟関係は死活的に重要である」という認識。民主・共和両党の理論的軸の2人はほとんど一致する。幾度か日米同盟は漂流し、岐路に立っている。とくに鳩山民
主党政権以降はその点、最悪の状況を自らつくり出し、今日に至っている。「抑止力」の何たるかもわからぬと自ら語るほどひどいものだ。そんななかでのナ
イ・アーミテージ対談。春原さんの聞き方も率直で多彩、きわめていい。本書が「アーミテージ・ナイ緊急提言」と副題が付されているように意味は大きい。
90 年代半ば以降、「座標軸を失い、漂流した」といわれた日米同盟体制を21世紀にかけて再活性化(世界を視野)することで超党派でつくり上げた2000年 11月の「アーミテージ・ナイ報告書」。そして2007年2月の第2作。両氏から見れば激流のなかで"たたずむ日本"だろうが、2人はそんないらだつ感情 を平気で見せつつ、米国の考えを縦横に語っている。
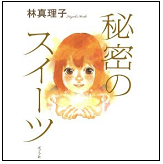 現在に生きる不登校の小学生・村田理沙と昭和19年の戦時下に生きる中森雪子が、時代を超えてケイタイでつながる。不思議な2人の心温かな友情。わくわくするような奇想天外の夢と現実の世界を、林真理子が描いた児童文学。
現在に生きる不登校の小学生・村田理沙と昭和19年の戦時下に生きる中森雪子が、時代を超えてケイタイでつながる。不思議な2人の心温かな友情。わくわくするような奇想天外の夢と現実の世界を、林真理子が描いた児童文学。

