昭和3年、1年半ほど断筆した江戸川乱歩が、「陰獣」で戻ってきた。「猟奇耽異を過剰に描き、大衆の低俗な好奇心を刺激するばかりの似非乱歩風作品が増殖し、読者の知的興味に訴える文芸の高級なジャンルとしての探偵小説不在を嘆く批評も目につくようになった。不健全派の旗頭と言われ、文芸を頽廃させる悪の根源のように思われては、くさるのも無理はない(風間賢二)」というなかでの江戸川乱歩の再登場だ。「意表をついた犯人像を描いた変格探偵小説して、昭和初期エログロ・ナンセンス隆盛への誘い水となった(風間賢二)」という時代を背景にし、時代を画する作品になった。
探偵小説作家・寒川が主人公で、美貌の人妻・小山田静子と知り合い文通を始める。ところがその静子に恐ろしい脅迫の手紙が次々と届けられる。まずは夫である小山田六郎を殺すという。脅迫してくるのは変格小説作家・大江春泥。じつはこの男は、ずっと若き頃から静子に恨みを持っていた平田一郎。そして、寒川と静子はドロドロした恋仲となり、寒川は大江を探すが全く手がかりがない。そんななか、小山田六郎変死事件が起きる。心の中を覗くようなじっくり読ませる小説だ。
 18世紀英国ゴシック小説が、時代とともに変化・展開し、日本で本格・変格推理小説に変容し、今日に至る怪異猟奇ミステリー全史を語る。まさに古今東西、驚くべき博覧強記に圧倒される。人間が怪異猟奇、怖いものに惹かれ、性欲・本能の社会的逸脱にのめり込むことは致し方ない生命の本質的乱射ではある。秩序と抑制をベクトルとする人間の歴史にあって、ミステリー小説は、異端であり、流行りものであった事は否めない。それが時代を経て、数々の文学賞を獲得するに至るほどの地位を得る。その変遷が本書からよくわかる。大変な力技を感じた。
18世紀英国ゴシック小説が、時代とともに変化・展開し、日本で本格・変格推理小説に変容し、今日に至る怪異猟奇ミステリー全史を語る。まさに古今東西、驚くべき博覧強記に圧倒される。人間が怪異猟奇、怖いものに惹かれ、性欲・本能の社会的逸脱にのめり込むことは致し方ない生命の本質的乱射ではある。秩序と抑制をベクトルとする人間の歴史にあって、ミステリー小説は、異端であり、流行りものであった事は否めない。それが時代を経て、数々の文学賞を獲得するに至るほどの地位を得る。その変遷が本書からよくわかる。大変な力技を感じた。
「ゴシックの元来の意味は、ゴート人のようなということだった。それが転じて、無教養の、野蛮な、無粋な、という意味に変化した」という。この「ゴシックこそがミステリーの源流」であることを示す。アン・ラドクリフの「ユドルフォ城の怪奇」は、恐怖と驚異を語った傑作。18世紀末だ。そして1830年代に登場するエドガー・アラン・ポー。今日の推理小説・探偵小説の始祖、「モルグ街の殺人」「黒猫・アッシャー家の崩壊」など自我の分裂と異常心理が描かれる。そしてコナン・ドイル。シャーロック・ホームズが人気を博す。ドイルは当初、ホームズものを生活費稼ぎのために執筆していたといい、専業作家としては他のタイプの小説を書きたかったようだ。面白い。
「進化論と退化論は表裏一体」で、「ジキルとハイド」「吸血鬼ドラキュラ」などが生まれている。19世紀後半は日本でいえば明治。ダニエル・デフォーの「ロビンソン・クルーソー」は植民地政策が背景にあり、日本ではそれが翻訳されて人気を博す。その明治時代の翻訳王が黒岩涙香だ。彼は俗悪なすっぱ抜き記事で小新聞を率いるが、翻案は講談にまでなる。当時の日本は、夏目漱石が言うように「探偵は高利貸しほどの下等な職業」で「文学界という花園を荒らした」と弾劾されたという。大正時代はモーリス・ルブランの怪盗紳士アルセーヌ・ルパンが話題を呼ぶ。ルパンやジゴマ、ファントマを受けて、江戸川乱歩の怪人二十面相が描かれる。「(江戸川乱歩は)創作は初期はドイル、中期は谷崎潤一郎、後期は黒岩涙香といった具合に、読書遍歴の始原へとさかのぼっていった」と解説する。名探偵・明智小五郎の活躍だが、当時はまだ若者であった横溝正史など、時代の背景には猟奇的殺人事件などがその時代に起きていたこともある。阿部定事件や2.26事件は1936年だ。夢野久作から、綾辻行人、京極夏彦・・・・・・。探偵小説から推理小説、そしてミステリーヘ。連綿と受け継がれたその流れを圧倒的熱量で描き解説する。
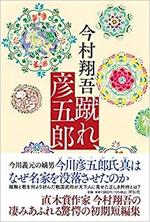 今村翔吾の初期短編など八編。いずれも歴史の表舞台には立っていない人物、愚将・ 暗君とされる人物が、実は魅力的な名君であったことをあぶり出している。歴史の表面を1枚めくってみると、より歴史が鮮やかによみがえる。気鋭の作品。
今村翔吾の初期短編など八編。いずれも歴史の表舞台には立っていない人物、愚将・ 暗君とされる人物が、実は魅力的な名君であったことをあぶり出している。歴史の表面を1枚めくってみると、より歴史が鮮やかによみがえる。気鋭の作品。
「蹴れ、彦五郎」――。駿河今川氏の家督を継いだ今川彦五郎氏真。歌を詠み、蹴鞠にかけては達人の域、戦や政はからきし駄目と言われた彦五郎氏真だが、妻となった北条氏康の娘・由稀は「優しさ」「人の才を見抜く観察眼・洞察力」「目にも止まらぬ早技の武術」に驚く。その氏真が織田信長に見せた最後の意地・・・・・・。「黄金」――織田信長の嫡孫・織田秀信(あの清洲会議での三法師)が、関ヶ原決戦を前にしてとった西軍参加への決断と感状。さすが信長の嫡孫。
「三人目の人形師」――幕末の人形師、松本喜三郎、安本亀八、その師匠・秋山平十郎の数奇な人生を描く。
「瞬きの城」――江戸城を築いた太田道灌の圧倒的な力と西に築いた星ヶ丘城(現在の永田町のキャピタル東急ホテルの所)。古河公方と堀越公方の対立、公方を補佐する関東管領のニ家である山内上杉家と扇谷上杉家。太田道灌の力と名君・扇谷政真。関東の争乱は治まっていく。目まぐるしい戦乱を太田道灌を中心に端的に描く。
「青鬼の涙」――「彦根の赤鬼」と呼ばれた井伊直弼に対して「鯖江の青鬼」と言われた辣腕の為政者・間部詮勝。明治となって、元大名の老人が昔の恋人の面影を求めて故郷に行く。「山茶花の人」――直江兼続は名高いが、それに抗した上杉家きっての猛将であった新発田重家。そこに惹かれていく由良勝三郎景隆。新発田重家の乱から見えてくるものは・・・・・・。
「晴れのち月」――武田信玄の嫡男・太郎義信。甲斐の武田家、駿河の今川家、相模の北条家は三国同盟を結び、武田義信は今川家の姫・月音を妻とする。武田信玄は上杉謙信と川中島で戦い、あるときは海を得ようとして今川を攻めようとする。義信は父を守る戦をするが、諫言もする。父・武田信玄からは徹底的に疎まれる。最後は幽閉され、家督は四男の勝頼に。「御屋形様が必ず口に出すであろう言葉があります」「太郎が生きておれば」と月音は言うのだった。
「狐の城」――北方謙三との出会いを生んだ今村翔吾のニ作目の作品。天正17年、小田原の元当主・北条氏政の弟であり現当主・氏直にとって叔父となる氏規は大阪から帰還する。外交にたけた氏規であったが、豊臣家との友好関係は破綻し、開戦は不可避であった。世にいう小田原評定の毎日。豊臣家との決戦となれば韮山城こそ最重要拠点と考えた氏規はそこで知略を尽くした戦を展開する。「氏規が助五郎と呼ばれた幼い頃、今川家に人質に出された。家康もまた同時期に、人質として同じ駿府にいたのである」「(秀吉は言う)あれはとんだ狐よ。牙を隠しておるわ。確か、そなた(家康)と氏規は縁があったの」「あれは恐ろしく、またつかみどころのない男でござる」「狸がそう言うなれば正しく狐」・・・・・・。氏規は氏直とともに高野山へ追放。しかし宗家を残そうとした「氏規の戦」は氏直の赦免をもたらし大名に復帰させたのだ。
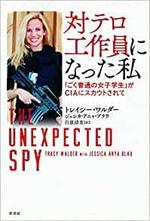 「ごく普通の女子学生がCIAにスカウトされて」が副題。南カリフォルニア大学在学中にCIAにスカウトされ、対テロ工作員になってテロリストを追い活躍する実話。その後、FBIに入ってアメリカにいる国外のスパイをとらえる仕事をする。そして、それらの経験も生かし、女子高校の教師として世界を変えようとしているのが今だ。
「ごく普通の女子学生がCIAにスカウトされて」が副題。南カリフォルニア大学在学中にCIAにスカウトされ、対テロ工作員になってテロリストを追い活躍する実話。その後、FBIに入ってアメリカにいる国外のスパイをとらえる仕事をする。そして、それらの経験も生かし、女子高校の教師として世界を変えようとしているのが今だ。
CIAの時代は、まさに9.11の時。昼夜を分かたず必死に働き、そこにはチェイニー副大統領、ライス大統領補佐官、パウエル国務長官らが、ごく普通に訪れる。ブッシュ大統領にも接し、その人柄にも好感を寄せる。中東を中心にしてテロ組織の中心に迫ろうとするが、大量破壊兵器が存在しないということでCIAが苦境に陥ることを、若く新人同然の彼女としても体験する。ブッシュ大統領への評価も反転する。「ホワイトハウスがCIAを裏切った」と弾劾する。イスラム過激派との戦いで、中東などの地域に派遣され、その激しく厳しい日々が描かれる。アフリカでも組織的な自爆テロが起きる。そして、毎日のように、交戦地帯ではよくあるPTSDに苦しめられる。「私は自分を救う必要もあった。落ち着き、安心し、こもることのできる家がほしかった」「ヨーロッパや中東、アフリカでテロが起きるたびに感じる責任を手放したかった」と、FBIに転身する。いかに切り刻まれるような日々であったかがわかる。FBIもまた大変厳しい仕事であることも描かれる。2001年から2005年に至るまで。20代の若き意欲と責任感溢れるアメリカ女性の姿が浮き彫りにされる。なかなか得難い実話。白須清美さんの訳。
 考えてみれば人生は失敗の連続だ。参院選にしても、悔しい安倍元総理銃撃事件も。またKDDIの通信障害もごく最近のことだ。「失敗をしゃぶり尽くせる人だけが、正解にたどり着ける」「自らの正解を導く思考法を」「失敗しないようにではなく、よりよく改造し未来を創造する。過去の失敗に真摯に学ぶことが大切になる」と、失敗学・創造学を打ち立てた畑村先生は言う。
考えてみれば人生は失敗の連続だ。参院選にしても、悔しい安倍元総理銃撃事件も。またKDDIの通信障害もごく最近のことだ。「失敗をしゃぶり尽くせる人だけが、正解にたどり着ける」「自らの正解を導く思考法を」「失敗しないようにではなく、よりよく改造し未来を創造する。過去の失敗に真摯に学ぶことが大切になる」と、失敗学・創造学を打ち立てた畑村先生は言う。
日本の産業の長い低迷の根本原因は、これまで当たり前としてきた考え方から抜け出していないことにある。教科書通り、マニュアル通りの正解主義だ。福島の原発事故は、非常用発電機が「アメリカでの脅威は竜巻であるが故に大事なものは地下に置く」を取り入れてしまったことにある。また2004年の回転ドアの事故はオランダからの技術を中途半端に使い「ドアは軽くなければ危ない」という知識が完全に消えてしまったことにある。
同じ優秀さでも、パターン認識の優等生タイプではなく、応用ができ「物事の本質」を突き詰めて考えるタイプの人が真の優秀だ。現代は、今までの思考法では通用しなくなってきている。「正解がない時代」というより「正解がいくつもある時代」となっており、誰かに言われてではなく、「自分で考えて実行する」が大事だといい、「失敗から学べる人だけが成長する」「動かないことが失敗になる、先送りの時代は終わった」という。また「挑戦することを奨励しているトップがいる組織は活気が出る」「ろくに知識がないのに、自分の権限を振りかざして若い人の動きを妨害したり止めたりする老人の行為は老害である」と指摘する。そして必要に迫られたら適切にアドバイスしコーチングする指導員(メンター)の存在が重要であることを述べる。大事なことだと思う。
畑村先生は「現地」「現物」「現人」の三現が重要であることを繰り返し述べている。三現は、五感をフルに使って観察対象と向き合うので、メディアやネットよりもはるかに立体的で情報量も圧倒的に多く、知識の定着もより強固になる。加速するネット社会、オンライン社会であればこそ、三現をより強固にしなくてはならない。だからこそ圧倒的な情報量が得られ、知識を超えた知恵が出る。未来への創造と挑戦ができるわけだ。
また現代社会で、仮説を立てるときに忘れてはいけない3つの重要な視点、①価値について考える②想定外を考える③時間軸を入れて考える――を提起する。求めるべき価値が見えずに多くの人が困惑し迷走しているのが今の日本だと危惧をする。絶対に起こらないと思われても、いざというときのために考えておくことが必要という。
三現の重要性、メンターの役割、情報は言葉によるものだけではないこと、「仮説―実行」を自分の頭を使って繰り返し、失敗経験を糧とするところに.私たちの進むべき道があると語る。

