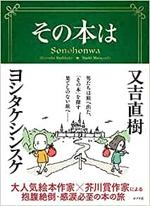 又吉直樹と絵本作家のヨシタケシンスケによる、世にも不思議な本の物語。童話のようでもあり、中身は辛辣な比喩の物語でもあり、泣き笑いも、それぞれにオチがついて、こんな発想があるのかと「本を探す旅」に連れていかれる。本の大好きな王様がいて、もう年寄りで目が見えなくなってきている。「目が悪くなり、もう本を読むことができない。でもわしは本が好きだ。お前たち、世界中をまわって『めずらしい本』について知っている者を探し出し、その本についての話を聞いてきて、わしに教えてほしいのだ」・・・・・・。旅に出たニ人の男はたくさんの本を持ち帰る。
又吉直樹と絵本作家のヨシタケシンスケによる、世にも不思議な本の物語。童話のようでもあり、中身は辛辣な比喩の物語でもあり、泣き笑いも、それぞれにオチがついて、こんな発想があるのかと「本を探す旅」に連れていかれる。本の大好きな王様がいて、もう年寄りで目が見えなくなってきている。「目が悪くなり、もう本を読むことができない。でもわしは本が好きだ。お前たち、世界中をまわって『めずらしい本』について知っている者を探し出し、その本についての話を聞いてきて、わしに教えてほしいのだ」・・・・・・。旅に出たニ人の男はたくさんの本を持ち帰る。
そして王様に毎夜にわたって世にも不思議な物語を語るのだ。よくもこんなに不思議な話が作れるものだと感心する。「第7夜」は、他に比べて長いが、絵本作家になりたいと願う少年・少女のやりとりが、なんとも切なく、また爽やかに心に迫ってくる。全体を通じて「本っていいな」と思わせる。
 「カシの胸が高鳴る。これこそわたしが探していた物語だ。強く優しい母親と率直で健気な男の子。頑迷な夫の父親の気持ちをも変えていく――。ここには、日本の封建的な身分制度に近い環境があり、そんな中、逆境に置かれても子を育てる母の強い愛がある。そしてその母の愛を受け、育てられた子が古い価値観をものともせず、健やかに成長する。求めていた物語が見つかった! その興奮をカシは抑えきれず......。その日から、カシは翻訳に取り組んだ」――。若松賤子が「小公子」と出会った瞬間だ。「この一冊が、子どもたちへ、子を持つ多くの母親たちへ、そして児童文学という新たな道を開く嚆矢となると信じていたに違いない」と語る。
「カシの胸が高鳴る。これこそわたしが探していた物語だ。強く優しい母親と率直で健気な男の子。頑迷な夫の父親の気持ちをも変えていく――。ここには、日本の封建的な身分制度に近い環境があり、そんな中、逆境に置かれても子を育てる母の強い愛がある。そしてその母の愛を受け、育てられた子が古い価値観をものともせず、健やかに成長する。求めていた物語が見つかった! その興奮をカシは抑えきれず......。その日から、カシは翻訳に取り組んだ」――。若松賤子が「小公子」と出会った瞬間だ。「この一冊が、子どもたちへ、子を持つ多くの母親たちへ、そして児童文学という新たな道を開く嚆矢となると信じていたに違いない」と語る。
幕末の1864年、会津で生まれ、戊辰戦争を生き延びた孤独な少女・松川カシ。かぞえ8歳、横浜の大川の養女となる。寄宿学校のフェリス・セミナリーに移り、学び、受洗する。「女性が、自らの意志を持って、羽ばたいていることだ。堂々と大きな翼を広げ、時に雛鳥の私たちを包み込み――それは誰かの強制ではなく、慣習でもない。志を持った、凛としたその姿だ」・・・・・・。カシはキダー先生の姿に、女性の自立と子供の幸せを希求し、女学校フェリス・セミナリーの先生となっていくのだ。そして明治の文学者、翻訳者として歩み出す。肺結核に侵されながらも、翻訳者として、教師として、母として懸命に生きる姿は、美しさを通り越して壮絶だ。療養のために住み、ひと時も休まず仕事をしたのが王子村下十条。なんと私の地元。「命を燃やし尽くした31年の生涯」とあるが、全くその通り。「未だに女性の地位は低く、権利も得ていません。でも、わたしが語りかけたこと、してきたことが、未来につながればと思っています」とあるが、その一筋の道は間違いなく時代を切り開いている。
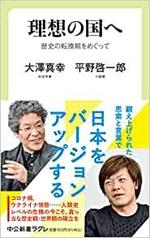 「歴史の転換期をめぐって」が副題。コロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、日本社会の極端な凋落・・・・・・。破局への予感を秘めた転換の渦中にある今、「考えに考え抜くことが、今ほど必要な時はない」としてニ人が対談する。「人類史レヴェルの移行期」という時代認識のなか、「平成を経て日本はどう変化したのか」と問いかけ、「自分探し」を続けた平成という時代であり、「虚勢を張った自慢(日本はスゴイ)」「幸福への意識が変化(若い人と高齢者の満足度が高く、30代、40代が不幸を感じている傾向が強い)」「中国への嫌悪が高まる」と、希望が枯渇し希望に飢えている時代となっていると指摘する。そしてアメリカのベースボールに、イチローのやり方で切り込んだように、日本的で特殊な考え方と国際的に通用する普遍性とが直結したことをヒントとすべきだ、という。
「歴史の転換期をめぐって」が副題。コロナ禍、ロシアのウクライナ侵略、日本社会の極端な凋落・・・・・・。破局への予感を秘めた転換の渦中にある今、「考えに考え抜くことが、今ほど必要な時はない」としてニ人が対談する。「人類史レヴェルの移行期」という時代認識のなか、「平成を経て日本はどう変化したのか」と問いかけ、「自分探し」を続けた平成という時代であり、「虚勢を張った自慢(日本はスゴイ)」「幸福への意識が変化(若い人と高齢者の満足度が高く、30代、40代が不幸を感じている傾向が強い)」「中国への嫌悪が高まる」と、希望が枯渇し希望に飢えている時代となっていると指摘する。そしてアメリカのベースボールに、イチローのやり方で切り込んだように、日本的で特殊な考え方と国際的に通用する普遍性とが直結したことをヒントとすべきだ、という。
「世界から取り残される日本」では、三島由紀夫を取り上げ、「あの三島がその三島になった理由」を語り、時代を掘り下げる。さらに「破局を免れるために――環境・コモン・格差」では、斎藤幸平「人新世の資本論」を論じつつ、「分人主義」と「コモン」の関係性と可能性に触れる。また、ロシアのウクライナ侵略をめぐって「国を愛する」を論じる。「手段の正義」と「目的の正義」。普通は愛国主義者と普遍主義者は対立すると考えられるが、「本当に信頼できるのは、愛国主義者であるがゆえに普遍主義者であるような人だと思う」と言う。環境問題、コロナ、ロシアのウクライナ侵略などの世界的課題にさらされている今、国民国家を超えた連帯をどうするか、世界の中で日本がよりよく生きるために、外交努力や相互理解をどうつくるか、「経済的に豊かで、平和を国是としている日本」にどう進むか語り合っている。
10月1日、いよいよ「新しい働く仕組み」である労働者協同組合法が施行――。その前日となる9月30日、都内で施行記念の前日祭が行われました。
この労働者協同組合法は、「働く者たちが自ら出資して仕事を起こし、経営にも携わる」「地域や暮らしに必要な仕事は自分たちで立ち上げよう」との挑戦から始まり、2020年に成立したもの。「働くということは、雇われて、その下で仕事をする。しかし、協同・連帯して働く『協同労働(協働)』という働き方はできないものか」という挑戦です。
この日のイベントに出席した私は「源遠ければ流れ長し――。この法律は、私にとって20年も前に、笹森清連合会長や坂口力厚生労働大臣から話を受け、公明党の同僚・桝屋敬悟衆院議員らが受け継いで、多くの方々の熱意と挑戦を受けて成立した。いよいよ施行となり、万感胸に迫るものがある。高齢となった友人たちも、まだまだ自分で働きたいという人が多い。仲間で共に仕事を立ち上げ、共に働く仕組みができたことは大きい。多様な働き方を実現しつつ地域の課題に取り組む具体的展開が進むことを期待する。今後もよろしくお願いいたします」と述べました。公明党から桝屋敬悟さん、中川康洋衆院議員が出席しました。



