23日、愛知県豊橋市で行われた「東三河活性化セミナー」に出席、基調講演を行いました。これには浅井由崇豊橋市長など東三河の各市町村長、企業・団体・地域の有力者が参加。公明党の伊藤渉衆院議員、里見隆治、安江伸夫両参院議員も出席しました。
今回のテーマは「地域における公共交通の再構築」――。私は国交大臣時代に策定した「国土のグランドデザイン2050」の「対流促進型国土形成」に触れつつ、「豊橋・浜松・飯田を結ぶ三遠南信の連携は、まさにそのモデル」と強調。「人口減少はますます激しく地域を襲う。まちづくりと公共交通の再生の課題は重い」「コンパクトシティーを進め、個性ある都市と都市とを連結させるネットワーク、これが対流促進型国土形成だ」「鉄道、路線バス、タクシー等の個々の存続を考えるだけでなく、全てを連携させて地域公共交通の活性化と再生を図ることが重要。自治体と地域交通事業者と利用者が地域全体の公共交通を協議することが大切。そのマスタープランに基づいて国は支援をする」などと話しました。各首長から、現場の厳しさと再生を目指す発言が活発に出され、きわめて有意義な意見交換会となりました。
 政府の新型コロナウィルス感染症対策分科会等、政府の機関でも尽力いただいた小林慶一郎、佐藤主光の両氏。コロナ対策の中で見えてきた「本来はこうすべきであった」「仕組みを変えなければ、日本は長期衰退に陥る」との観点から、極めて具体的に問題を提起し、ポストコロナの政策構想を提示する。
政府の新型コロナウィルス感染症対策分科会等、政府の機関でも尽力いただいた小林慶一郎、佐藤主光の両氏。コロナ対策の中で見えてきた「本来はこうすべきであった」「仕組みを変えなければ、日本は長期衰退に陥る」との観点から、極めて具体的に問題を提起し、ポストコロナの政策構想を提示する。
コロナ禍での対策を中で行ってきたわけだが、その指摘は遠慮なく鋭い。「医療以外の社会的なコストに淡白な医療エリート」「後回しになった医療体制強化の議論」「経済政策としてのPCR検査の有益性を認めなかった医療側」「ワクチン供給が間に合わなくて7月にブレーキを踏んだ政府。自治体の予約制限が相次ぐ」「乖離する医療現場と医療政策」「病床数は多いが、コロナ病床確保が進まない要因」「かかりつけ医の活用、オンライン診療を平時の常識に」「必要な診療報酬の見直し」・・・・・・。
「ポストコロナ時代に課題となる財政再建問題。中小企業等の過剰債務問題」「コロナ特別会計の必要性(別勘定で)」「社会保障のコストを賄うために必要な消費税(17%、18%にも)」「成長期待による財政再建不要論に妥当性はあるか?」「M M Tは朝三暮四の理論」「ポストコロナに向けた税財政の国際協調の必要性」・・・・・・。
「個人への給付で目立ったデジタル化の遅れ」「事後調整型にして迅速・公平な給付を行う。大学授業料の所得連動型ローンを始めとする所得連動型給付」「ベーシック・インカムや給付付き税額控除の検討」「給付のインフラとしてのマイナンバー制度」「目立った国と地方の乖離。食い違う政策と現場」「医療・介護の基幹産業化を」「デットからエクイティへ」「企業の事業構造の転換――ビジネスモデルの転換、債務処理、雇用対策」「生産性の低い企業の退出促進を」・・・・・・。
そして「ポストコロナへの八つのビジョン」として①デジタル化を促進する②医療提供体制を再構築する③リスクを分かち合う社会保障の仕組みを構築する④非常時のガバナンスを改善する⑤万機公論に決すべし⑥誰でも再チャレンジできる自由を広げる⑦将来世代の立場に立つ⑧新たなグローバル秩序を構想する――を提起する。この2年の諸問題を踏まえ、分析をし、具体的に提起している。
8月21日、公明党中国方面本部(本部長・谷合正明参院議員)の夏季議員研修会が開かれ、出席しました。
今年は、「大衆とともに語り 大衆とともに戦い 大衆のなかに死んでいく」との立党精神が示されて60年――。当時は、大企業や労働組合など大きな組織を背景にした自社ニ大政党対立の時代。世界的にも核をめぐる一触即発のキューバ危機。激変・緊迫のなか、庶民大衆は置き去りにされていました。「庶民大衆を代弁する政治家(政党)はいないのか」との叫びのなかで生まれたのが公明党です。
「政治はリアリズムであり、現実を直視し解決する臨機応変の自在の知恵である」「政治は空中戦ではない。現場こそ戦いの場だ」「現場には臭いがあり、空気があり、(課題の)優先順位がわかる」「立党精神の魂を心中に呼び起こして頑張ろう」と語りました。
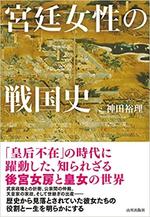 天皇の権威が低下したと捉えられがちな戦国時代――。後宮女房・皇女達は何をしていたのか、どういう役割を果たしていたのか。戦国時代のみならず、日本の歴史は男性の歴史であったと思われるが、本書は天皇・朝廷を取り巻く、これら女性の実像に学問的に迫っている。すばらしい研究だ。
天皇の権威が低下したと捉えられがちな戦国時代――。後宮女房・皇女達は何をしていたのか、どういう役割を果たしていたのか。戦国時代のみならず、日本の歴史は男性の歴史であったと思われるが、本書は天皇・朝廷を取り巻く、これら女性の実像に学問的に迫っている。すばらしい研究だ。
後宮女房は、天皇の日常生活を支える「侍女」の役割を担うとともに、後宮と外部を結ぶ「伝達者」「使者」の役割も果たしていた。さらに戦国時代は、天皇の正妻(嫡妻)たる皇后や中宮が立てられなかったようで、天皇との間に、世嗣ぎの皇子をはじめ、多くの皇子・皇女をもうけていた。そうなると生母となって重きをなすことになる。
「後宮女房が記した執務日記」「武家政権との間を取り次ぐ女房たち(足利将軍・三好氏、織田信長時代の多彩な活躍、活躍の機会が減った豊臣政権時代)」「朝廷内を揺るがす大スキャンダル事件(猪熊事件など)」「戦国期の後宮女房のはたらきと収入」「将軍側近に勝るとも劣らぬ役割を果たしていた女房たち」「後宮女房の一生と様々な人生」「娘の出仕をはたらきかける実父」「周防の大内義隆に嫁いだ二人の娘、京の文化を取り入れることに熱心であった大内義隆」「その多くが出家した、皇女たちの行方」らが詳述される。大変興味深い著作。
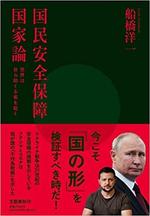 「世界は自ら助くる者を助く」が副題。フクシマでもコロナでも、ウクライナ危機を考えても、日本は危機と有事に対する備えがあまりにも乏しいことが明白になっている。気候変動に伴うエネルギー危機もきわどい。安全保障の枠組みが根底から揺さぶられている今、「国の形」と「戦後の形」を検証し、国民が参画する危機管理という観点から新たな国家安全保障、経済安全保障、国民が危機管理に参画する国民安全保障国家を築かねばならない。ウクライナの状況を見ても、「自分の国は自分で守らねばならない」という意思が大事だ。「日本は、平時において、その法制度と規制とインテリジェンスと人的資源、つまりは国家統治を安全保障の観点から見直し、有事の体制を構築するべきである。安全保障とは、国民の生命と財産の安全及び国家としての価値の保全を保障することである」という。
「世界は自ら助くる者を助く」が副題。フクシマでもコロナでも、ウクライナ危機を考えても、日本は危機と有事に対する備えがあまりにも乏しいことが明白になっている。気候変動に伴うエネルギー危機もきわどい。安全保障の枠組みが根底から揺さぶられている今、「国の形」と「戦後の形」を検証し、国民が参画する危機管理という観点から新たな国家安全保障、経済安全保障、国民が危機管理に参画する国民安全保障国家を築かねばならない。ウクライナの状況を見ても、「自分の国は自分で守らねばならない」という意思が大事だ。「日本は、平時において、その法制度と規制とインテリジェンスと人的資源、つまりは国家統治を安全保障の観点から見直し、有事の体制を構築するべきである。安全保障とは、国民の生命と財産の安全及び国家としての価値の保全を保障することである」という。
本書は2020年春のコロナ危機から2022年のウクライナ危機までの2年間の論考をまとめている。各誌に発表したものだが、ウクライナ危機後の論考は書き下ろしで新しい。その「国家安全保障、レアルポリティーク時代の幕開け――ウクライナの悲劇、米中新冷戦と日本の選択」「経済安全保障、経済相互依存とネットワークの武器化――グリーン大動乱とエネルギー危機」は、ウクライナ危機以降の論考で、深く広く安全保障 の 重要性をえぐり出している。「ウクライナ 戦争 が 日本 に 問い かけて いる 最大 の 教訓 にして 最大 の クエスチョンは、自らを守ることができる国を世界を助ける、というその点にある」「これからの時代、最も恐ろしい『日米中の罠』は、米中対決の中で日本が選択肢を失う罠である。中国に日本の自国防衛の意思と能力、日米同盟の抑止力の有効性、科学技術力とイノベーションの力を常に理解させるべきである。同時に、日米が中国を全面的な敵性国と決めつけ、それが中国の排他的民族主義を煽り、双方とも後戻りができなくなる状況を避けるべきである。互いに相手の意図を正確に把握、不断の対話をすることが必要である」「そのためには、日本がより自立し、自らの安全保障に責任を持ち、日米同盟を相互依存的な責任共有の体制に進化させるべきであり、有事に国民を保護できる国の体制を作らなければならない。日本の抑止力を高めなければならない・・・・・・」といい、戦略的思考、外交力、統治力を求めている。またウクライナ問題が、エネルギー危機の始まりになることを指摘し、エネルギーの経済安全保障上の脆弱性に論及。かつサイバー攻撃力、監視力、情報統率力、諜報力の全てが脆弱であることを指摘する。さらに「国家的危機には、大きな政府と大きなビジネスが必要だ」という。
コロナでは「デジタル敗戦」「ワクチン暗黒国家」を指摘するが、「不確実性のシナリオの前に、政治家も官僚も『作為のリスク』を恐れ、結果として『不作為のリスク』を生じさせることになった」という。コロナで「泥沼だったが結果オーライ」との言葉を再三にわたって述べている。その場しのぎの"泥縄貧乏"が、構造的に日本を危機に弱い国にしているという指摘を噛み締めなくてはならない。



