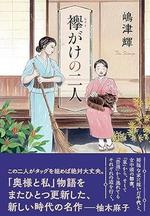 大正から昭和の戦前戦後――。不思議な絆で結ばれた二人の女性の生きる姿を、静かに、心のひだを情感を持って描く感動作。
大正から昭和の戦前戦後――。不思議な絆で結ばれた二人の女性の生きる姿を、静かに、心のひだを情感を持って描く感動作。
昭和24年(1949年)、視力を失った三味線の師匠・ 初衣の家で、住み込み女中として働き始める千代。実は、千代は大正15年(1926年)、19歳で裕福な家に嫁ぎ、その女中頭が「お初」と名乗っていた初衣。昭和20年3月の東京大空襲で離れ離れとなっていたのだ。これといった特徴がなく、おっとりして根がのんびりなところのある人の良い千代、元芸者でさんざん苦労もし、酸も甘いも噛み分け何でもできるし優しい初衣。千代が雇い主で初衣が女中というより、むしろ初衣が師匠で千代が弟子というような結びつきであった。
戦時色が次第に濃くなっていく激動の昭和の初め。千代は夫とのぎこちない夫婦関係に悩みを抱える。夫の会社は傾いていき、夫と若い事務職員との間に子供が生まれる。気丈に振る舞うしっかり者の初衣も、芸者時代の自分の密かな行いに悔恨を抱えていた。戦火は日常の生活そのものを奪い取っていく。日本はどうするといった戦争の攻防ではなく、食べ物を確保することに懸命となり、「隣組」で活動する女性の具体的な日常が重みを持って描かれる。そして東京大空襲で街は焼かれ、初衣は火の粉で視力を失う。
そうした2人の女性を中心にしながら、時代に翻弄されながらも助け合って生きていく女性の日常の生活、感情の起伏が描かれる。たんたんと伸びやかに、悲壮感がなく、ぐいぐいと引き込まれる。信頼し合う女性でしか話せないであろう"性"のこともごく自然に語られる。現実から遊離しない賢い女性の語らいがユーモラスでもあり心地よい。重苦しい時代と男性優位の時代の中で、生き抜いていく女性の姿は靭く尊い。素晴らしい長編小説。
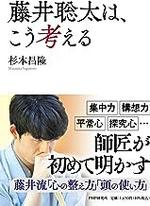 10月11日、王座戦に勝って藤井聡太竜王が21歳2ヶ月で史上初の8冠独占を成し遂げた。優勢であった永瀬拓矢王座が、痛恨の一手で形勢逆転。それをもたらしたのは、AIも予想せぬ一手で永瀬を惑わしミスを誘い出したという。驚くべき印象的な対局だった。その藤井聡太の「心の整え方」「頭の使い方」を師匠である杉本昌隆8段が語る。
10月11日、王座戦に勝って藤井聡太竜王が21歳2ヶ月で史上初の8冠独占を成し遂げた。優勢であった永瀬拓矢王座が、痛恨の一手で形勢逆転。それをもたらしたのは、AIも予想せぬ一手で永瀬を惑わしミスを誘い出したという。驚くべき印象的な対局だった。その藤井聡太の「心の整え方」「頭の使い方」を師匠である杉本昌隆8段が語る。
将棋の世界でプロになるためには、奨励会に属さなければならない。小学生でアマチュア4段クラスを力を持つ子供たちが試験を受けて入会、研鑽を進めて、3段まで上がると最も厳しい「3段リーグ」が待ち構えており、これを勝ち抜いて4段となり、初めて棋士になれる。しかも年齢制限があり、21歳までに初段、26歳までに4段に上がらないと戦いの場からはじかれてしまうという。厳しい世界だ。AIの申し子とも言われる藤井8冠だが、「彼の指し手は、極めて人間的なもので、AIのパターン認識を超えた創造力といえる」と言う。
「対局前に作戦を立てることを構想というが、ガチガチの構想を築いてしまわず、ひたすら目の前の状況だけに焦点を合わせ柔軟に対応するのが藤井の構想力」「最善手を最速で見抜くスピード。計算のスピードが全く違う」「角と桂馬の使い方が抜群にうまい。対角線、斜めのラインを強く意識させる。駒に角度がある」「リスクを恐れない。相手の駒を呼び込めるだけ呼び込んで、見た目には形勢不利と見せながら、その実、相手方に、もう打つ手のない状況を作り出す(自分の玉を「打ち歩詰め」にしたこともある)」「藤井曲線――相手からリードを奪ったときに、その有利を藤井は絶対に手放さない」「集中力の持続と脳のスタミナがある(集中力の持続力)」「プレッシャー、緊張を前向きに捉え、成功へのエネルギーに変える向上心が平常心を生んでいる」「本物(強い棋士)に触れることで、成長が早まった」「藤井の探究心は『楽しい』の感覚」「棋士は勝負師、研究者、芸術家の3つの顔を持つべきだ(谷川浩司17世名人)」・・・・・・。
「才能とは、努力を続けられること」とあるが、全くその通りであろう。「藤井聡太は今、100メートル走で言えば、1人だけ9秒台で走った男。1人が10秒の壁を破ると続々と出てくる。将棋界のレベルがさらに上がっていくことを楽しみにしている」と杉本さんは言う。
 Z世代の区切りはいろいろあるが、本書では「1997年から2012年の間に生まれた若者世代」を言う。ネット環境の中で育った「デジタルネイティブ」であり、「テロとの戦い」や金融危機など、綻ぶアメリカを見ながら育った世代である。2001年の同時多発テロは記憶にない。日本で言えば、「デジタルネイティブ」であり、「ずっと給料の上がらないデフレ時代」「ほとんどが自公連立政権の時代」「人口減少・少子高齢社会への始まり」の中にいた世代だ。若者は時代の写し絵だから、日米ともに夢・ロマンを追うより、冷静で現実主義になっている。アメリカでは、人口の約2割を占め、今後いよいよアメリカ社会の中心となっていくのがZ世代だ。彼らの眼にアメリカの今の政治や社会はどう見えており、どう考えているのかを多角的に紹介しているのが本書だ。
Z世代の区切りはいろいろあるが、本書では「1997年から2012年の間に生まれた若者世代」を言う。ネット環境の中で育った「デジタルネイティブ」であり、「テロとの戦い」や金融危機など、綻ぶアメリカを見ながら育った世代である。2001年の同時多発テロは記憶にない。日本で言えば、「デジタルネイティブ」であり、「ずっと給料の上がらないデフレ時代」「ほとんどが自公連立政権の時代」「人口減少・少子高齢社会への始まり」の中にいた世代だ。若者は時代の写し絵だから、日米ともに夢・ロマンを追うより、冷静で現実主義になっている。アメリカでは、人口の約2割を占め、今後いよいよアメリカ社会の中心となっていくのがZ世代だ。彼らの眼にアメリカの今の政治や社会はどう見えており、どう考えているのかを多角的に紹介しているのが本書だ。
彼らの眼には、「弱いアメリカ」の現実が見えている。「例外主義の終わり――『弱いアメリカ』を直視するZ世代」だ。「例外主義」とは「アメリカは、物質的・道義的に比類なき存在で、世界の安全や世界の人々の福利に対して、特別な使命を負うという考え方」だ。しかし今、その使命感を持ちながらも「軍事介入、国防費の増大より、社会保障と国民福利の充実こそが重要である」と言うサンダースの考え方が広がっている。Z世代は、「ポスト例外主義世代であり、今のアメリカには悲観的で絶望すらしているが、未来への希望を失ってはいない人種・民族的に、アメリカの歴史上最も多様化した世代」と言う。民主主義の退潮、権威主義の台頭は今、アメリカにおける所得格差の拡大、反リベラリズムの広がり、保守とリベラルの分断、対中感情の悪化等のなか、アメリカのZ世代は、「選挙や社会の欺瞞」を嫌い、「強国の中国」と共に生きていかねばならない世代としての「現実主義」が刻まれている。また9.11を知らないZ世代は、「テロとの戦い」への懐疑と批判をもっている。西洋人の殺害に対し反省の弁を述べながら、アフガニスタンやイラク以外の国・地域でドローン攻撃をするオバマ大統領に見られるダブル・スタンダードに批判的で、黒人の命と尊厳を訴えるブラック・ ライブズ・マター運動の中心的な担い手となっている。国益や国境にとらわれず、環境や正義や人権をますます重視するゆえに、Z世代は「社会正義(ソーシャル・ジャスティス)」世代とも呼ばれている。人道や正義のダブル・スタンダードにとりわけ敏感で批判的だ。
「ジェンダー平等」「中絶の権利」の考え方は、アメリカ社会での重要なテーマだ。Z世代のフェミニズム、Z世代の人権闘争は、どうなっているか。「ジェンダー平等」では、女性として初の副大統領となったカマラ・ハリスへの期待と落胆・不人気の要因に迫っている。黒人、アジア系の女性としてハリスが積み上げてきたキャリアは革命的なものであったが、いまや黒人コミュニティーからの不信感が募り、警察権力の肥大化や大量投獄に加担してきた存在とみられている。中南米移民の問題も「来ないで」発言で、明確に進歩主義的な態度を取らなかったことは、人々に大きな幻滅を与えた。中道路線は本当に難しい。Z世代にはハリスの姿勢への疑問が広がっているという。
人工中絶論争も難しい。1973年に連邦最高裁が人工妊娠中絶を行う憲法上の権利を認めた「ロー判決」がトランプ政権によって覆る。プロライフ(中絶反対)とプロチョイス(中絶賛成)が、共和党と民主党の対立に重なったが、現実は、二元論に還元できるほど簡単ではない。選挙でも、若年層は中絶の権利を最大の関心事に挙げているという。
Z世代は、他の世代とは異なる思考形態をとっており、アメリカ社会の底流が読み取れるというわけだ。
 日本の安全保障とか、経済成長戦略、少子化対策などという問題ではない。社会が変化し、問題として浮上している論点、16のテーマについてそれぞれの専門家が掘り下げる。「『死んでまで一緒はイヤ』日本で死後離婚と夫婦別墓が増えた理由(井上治代)――妻による家意識からの離脱」「女性に大人気『フクロウカフェ』のあぶない実態(岡田千尋)」「いまの若者にとって『個性的』とは否定の言葉である(土井隆義)」などは知らなかった話。差別について、「『差別』とは何か?アフリカ人と結婚した日本人の私が今考えること(鈴木裕之)」や「私が『美しい』と思われる時代は来るのか?"褐色肌、金髪、青い眼"のモデルが問う(シャララジマ)」などは角度が新鮮。「日本の死角」として日本が今どうなっているか、定説に鋭角的に切り込む。
日本の安全保障とか、経済成長戦略、少子化対策などという問題ではない。社会が変化し、問題として浮上している論点、16のテーマについてそれぞれの専門家が掘り下げる。「『死んでまで一緒はイヤ』日本で死後離婚と夫婦別墓が増えた理由(井上治代)――妻による家意識からの離脱」「女性に大人気『フクロウカフェ』のあぶない実態(岡田千尋)」「いまの若者にとって『個性的』とは否定の言葉である(土井隆義)」などは知らなかった話。差別について、「『差別』とは何か?アフリカ人と結婚した日本人の私が今考えること(鈴木裕之)」や「私が『美しい』と思われる時代は来るのか?"褐色肌、金髪、青い眼"のモデルが問う(シャララジマ)」などは角度が新鮮。「日本の死角」として日本が今どうなっているか、定説に鋭角的に切り込む。
「『日本人は集団主義』という幻想(高野陽太郎)」――科学的な研究から来たものではなく、明治時代訪日した米国人による著書や、日本人の戦時中の集団主義的な行動がイメージを作ったと指摘する。「日本人が『移動』しなくなっているのはなぜ?地方で不気味な『格差』が拡大中(貞包英之)」「日本人が大好きな『ハーバード式・シリコンバレー式教育』の歪みと闇(畠山勝太)」――ハーバードやシリコンバレーで見る米国の基礎教育は、米国のごく限られた上澄みに過ぎず、日本の教育の平等さと比較しても意味を持たない。「日本が中国に完敗した今、26歳の私がすべてのオッサンに言いたいこと(藤田祥平)」――中国の荒々しいエネルギーに対し、エネルギーを失った日本とその若者のように感じる。阿古智子東大教授は、「日本のエリート学生が『中国の論理』に染まっていたことへの危機感」として、民主主義の価値を認識していない日本の若者の恐るべき実情を指摘している。正直驚いた。
「日本の学校から『いじめ』が絶対なくならないシンプルな理由(内藤朝雄)」――社会でいえば本来犯罪なのに、学校という小さな社会の全体主義のなかで隠蔽される。「家族はコスパが悪すぎる?結婚しない若者たち、結婚数の信者たち(赤川学)」――少子化の要因は、結婚しない人の割合が増加したことにある。特に女性が、自分よりも学歴や収入など社会的地位の低い男性と結婚するいわゆる「下降婚」が日本では少ないままになっていることを指摘する。下降婚率が増えると、出生率が高まる。「未婚の女性に対して格差婚を勧めてみてはどうだろうか」と言っている。その他、「ご飯はこうして『悪魔』になった〜大ブーム『糖質制限』を考える(磯野真穂)」「なぜ『ていねいな暮らし』はブーム化した一方、批判も噴出するのか(阿古真理)」「自然災害大国の避難が『体育館生活』であることへの大きな違和感(大前治)」「性暴力加害者と被害者が直接顔を合わせた瞬間・・・・・・一体どうなるのか(藤岡淳子)」など、切り込み方は鋭い。





