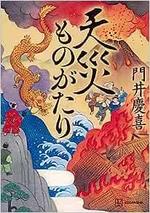 日本に襲いかかった大災害。その時、人はどう動き、歴史はどう変わったか。それぞれの人間ドラマを描く。
日本に襲いかかった大災害。その時、人はどう動き、歴史はどう変わったか。それぞれの人間ドラマを描く。
天文11年(1542)の甲府洪水。甲斐国は谷の峡(かい)。甲斐国の国主となった21歳の武田晴信は、板垣信方らが隣国の攻略こそ大事とするなか、「甲斐千年の宿痾を癒やす大普請」として、築堤に乗り出す。霞堤の原型となる信玄堤。この築堤とともに河道改修や遊水地保全を行う。
明治29年(1896)の三陸沖地震。田老村の漁師・四郎は、「海の男なら、大波が来たら向かっていけ」との言葉どおり正面から津波に向かって進み助かる。津波が来ない高台に仲間とともに移り住むが、時間が経つとともに、仲間は海に近いところに移っていく----。決して山に上がりたがらなかった老人と、決して浜に下りたがらなかった大工の親方と、山から浜へ節を曲げた船頭の号泣する声・・・・・・。
寛喜2年(1230)の大飢饉。執権北条泰時の頃の京都。下流から、米の荷を上げて京の街へ送り出す問丸の仕事をしている滝郎は米を買いまくって高く売ろうとする。大飢饉のなか京の人口は種籾まで食べてしまう地方の農民が流入して増加。滝郎は、ついに田舎から百姓を連れてくる違法の人身売買にまで手をつける。全国各地で農民の逃亡が続き、難民が流入する京都・・・・・・。飢饉は、断続的に数年続いた。
宝永4年(1704)富士山噴火。この年は49日前に宝永の大地震(南海トラフ)があり、死者は3万人に及んだ。富士山噴火は新井白石の「折りたく柴の記」に「昼にもかかわらず空が暗く、蝋燭をともして講義をした」とある。左右対象の富士山に「宝永火口」が生じた。噴火の火口に最も近い須走村に生まれ育った与助は、「百貫与助」と呼ばれ、重い荷駄も運べる「馬追い」「馬方」。必死に逃げた先は浜松。須走村のひとつ東側の大御神村から浜松に逃げてきたおときに頼まれ、大御神村を訪ねることになる。驚くことに火口に最も近い須走村だけは、復興への力強さがあった。その理由とは・・・・・・。
明暦3年(1657) 1月の江戸大火、振袖火事。キリスト教を信じて牢に入れられた権右衛門らは解放され、「鎮火したら、浅草の善慶寺へ出頭せよ」と言われる。千住大橋を渡ろうとするが、浅草門は開かない。「あ、江戸がない」――権右衛門は、江戸が巨大だったからこそ大火なのであり、人のいるところに天災があるのだと感じるのであった。そして島原の乱と老中・松平伊豆守信綱と南蛮絵師が絡む。
昭和38年(1963)の裏日本豪雪。練馬の小学校教諭の鳥井ミツは正月休みで新潟県に帰る。そこで豪雪。始業式となっても帰れず、やっと乗った急行「越路」の中に閉じ込められる。死者228名、行方不明者3名、住宅全壊753棟という大被害。当時は裏日本という言葉が普通に使われた。「現代は、天災でないものを天災にした。天災と人災の区別をなくした」と言う。
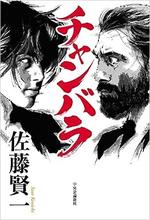 吉川英治の「宮本武蔵」を始めとして数多ある武蔵像のなかでは極めて異質。60余戦して全て勝利したその戦いの部分を徹底的、迫力満点で描きあげた。壮絶な生死をかけた戦いによって技を磨き、自らを心身ともに鍛え上げ、地水火風空の「五輪書」を書くに至った高尚な剣聖・宮本武蔵ではなく、何が何でも勝ち抜なければならないと、ただただ戦い勝つ荒々しい執念そのものが剣豪・宮本武蔵であったことが噴き上げるように描かれている。荒ぶる武蔵の魂だ。
吉川英治の「宮本武蔵」を始めとして数多ある武蔵像のなかでは極めて異質。60余戦して全て勝利したその戦いの部分を徹底的、迫力満点で描きあげた。壮絶な生死をかけた戦いによって技を磨き、自らを心身ともに鍛え上げ、地水火風空の「五輪書」を書くに至った高尚な剣聖・宮本武蔵ではなく、何が何でも勝ち抜なければならないと、ただただ戦い勝つ荒々しい執念そのものが剣豪・宮本武蔵であったことが噴き上げるように描かれている。荒ぶる武蔵の魂だ。
「今日まで剣に生きてきて・・・・・・兵法というほどのものではないな。ただのチャンバラにすぎん」・・・・・・。最後に、父親・新免無ニとの戦いに勝った武蔵はそう吐き捨てる。新免無ニの当理流は、左手に十手を構え、さらに槍、手裏剣、捕手の技まで含む。宮本武蔵の円明流は、左に脇差を持つ。武蔵は気を飛ばす。父子のアンビバレント的関係がジワリと描かれ面白い。
幼き頃、当理流・新免無二と京八流・吉岡憲法との壮絶な戦いを見る。描かれる武蔵の戦いは、生きるか死ぬかの壮絶な戦いの連続。有馬喜兵衛、秋山新左エ門、吉岡清十郎、その弟吉岡伝七郎、百余名にも及ぶ一乗寺下り松の吉岡一門の撫で切り。1人、2人・・・・・・99人、100人・・・・・・104人、105人と1人ずつ描かれるド迫力ときめ細かな描写。そして宍戸又兵衛。三河谷刈谷の徳川譜代・水野勝成の下にいた宮本武蔵は父に呼び出され、佐々木小次郎との決戦に至る。場所は船島。本書では、この佐々木小次郎との決戦が、「当理流と岩流の争いではなく、細川家の小倉城と岩石城の戦い」「相思相愛であった雪がなんと佐々木小次郎の妻となっており、その息子小太郎は武蔵の子であった」などの背景が語られる。佐々木小次郎に止どめを刺さなかった武蔵。長刀のつばめ返しに勝つため、それより長い木刀を削り持つ。なぜだったのか。それらの解釈にもつながる話だ。
宮本武蔵を、「戦闘」に集中することによって描いた本書は、これまでにない宮本武蔵の迫力と生き様、そして戦国時代の武人の哀愁をも見事に書き出している。
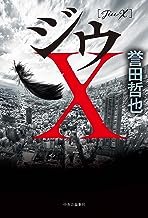 誉田哲也「ジウ」シリーズ。広尾中央公園で子宮を抉りとられた死体が発見された。東弘樹警部補らが懸命に捜査するが、2ヶ月たっても身元さえ判明しない。一方、「歌舞伎町セブン」の陣内陽一は、彼の店「エポ」を訪ねてきたルポライター土屋昭子から「ちょっと、裏仕事を手伝ってほしいの。ジンさんか、ジロウさんのどっちかに」と頼まれる。土屋は、「歌舞伎町封鎖事件」を起こした巨大犯罪組織「新世界秩序 N W O」にに長く関わり、今は脱退希望。正体不明でセブンから嫌われていた。しかしジロウが動くことになる。
誉田哲也「ジウ」シリーズ。広尾中央公園で子宮を抉りとられた死体が発見された。東弘樹警部補らが懸命に捜査するが、2ヶ月たっても身元さえ判明しない。一方、「歌舞伎町セブン」の陣内陽一は、彼の店「エポ」を訪ねてきたルポライター土屋昭子から「ちょっと、裏仕事を手伝ってほしいの。ジンさんか、ジロウさんのどっちかに」と頼まれる。土屋は、「歌舞伎町封鎖事件」を起こした巨大犯罪組織「新世界秩序 N W O」にに長く関わり、今は脱退希望。正体不明でセブンから嫌われていた。しかしジロウが動くことになる。
やがて死体の身元が判明。中国人女性、しかも驚くことに経団連の事務総長で、パナテック会長の初島邦之の愛人であった。その後、中国大使館近くで帝都大学院生・尾身崇彦と恋人・原田里香の惨殺死体が発見される。さらに陣内の店「エポ」に威圧感おびただしい奇妙な客が集団で訪れ、歌舞伎町封鎖事件を起こした「新世界秩序」について、中心の女性が「いろいろな誤解があったと思うんです」と話し始める。
そうしたなか、世間を驚愕すべき出来事が次々と起きる。初島邦之が発表した経団連の「脱中国」方針。留学で日本に来ていた中国共産党幹部の子息の行方不明。惨殺された尾身崇彦の恩師・高垣昌良教授による日本学術会議の軍事科学・安全保障研究の容認への方針転換・・・・・・。いったい何が起きているのか。事件との関係は・・・・・・。
そしてNWO・CATとセブンの壮絶な戦いが始まっていく。
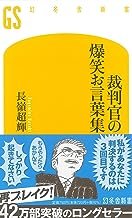 最近、本屋で目立っているが、実は2007年3月に発刊されたもの。「爆笑」と言えば、「エンタの神様」にも出ていた阿曽山大噴火を思い出すが、本書はむしろシリアス。「裁判官は建前としては『法の声のみを語るべき』とされていますが、法廷ではしばしば裁判官の肉声が聞かれます。私情を抑えきれず思わず、本音がこぼれてしまうこともあれば、人の心に直接響く『詩』や『名言』を借りることもある」――。苦渋に満ちた心こもった発言は、抑制的である故に、感動的でもある。
最近、本屋で目立っているが、実は2007年3月に発刊されたもの。「爆笑」と言えば、「エンタの神様」にも出ていた阿曽山大噴火を思い出すが、本書はむしろシリアス。「裁判官は建前としては『法の声のみを語るべき』とされていますが、法廷ではしばしば裁判官の肉声が聞かれます。私情を抑えきれず思わず、本音がこぼれてしまうこともあれば、人の心に直接響く『詩』や『名言』を借りることもある」――。苦渋に満ちた心こもった発言は、抑制的である故に、感動的でもある。
「唐突だが、君たちは、さだまさしの『償い』という唄を聞いたことがあるだろうか。この唄の、せめて、歌詞だけでも読めば、君たちの反省の弁が、なぜ人の心を打たないかわかるだろう(実話に基づいた『償い』は、交通事故の加害者が、自分の幸せや楽しみを犠牲にして、必死にお金を作り、毎月欠かさず被害者の奥さんに郵送し続けるという唄)」「死刑はやむを得ないが、私としては、君にはできるだけ長く生きてもらいたい(死刑判決言い渡しの後で)、」「刑務所に入りたいのなら、放火のような重大な犯罪でなくて、窃盗とか他にも・・・・・・(刑務所に入りたくて、国の重要文化財の神社に放火した男に対して)」「いい加減、これっきりにしてください(「だってバッグが素敵だったから」と窃盗の罪に問われた母と娘に対して、執行猶予付きの有罪判決を言い渡して)」「この前から聞いてると、あなた、切迫感ないんですよ(姉歯事件の被告人質問の中で)」「家族らの信頼を裏切ったが、多くの人たちが更生を期待していることは、じゅうぶんわかっていると思う(シンガー・ソングライターの槇原敬之に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡して)」「被害を受けたと申告した女子高生を、恨まないようにしてください(痴漢容疑で無罪判決を言い渡して)」「しっかり起きてなさい。また机のところで頭打つぞ(公判中に大あくびをする松本智津夫に)」「今、この場で子供を抱きなさい。我が子の顔を見て、二度と覚せい剤を使わないと誓えますか」「恋愛は相手があって成立する。本当に人を愛するなら、自分の気持ちに忠実なだけではダメだ。相手の気持ちも考えなくてはいけない」「電車の中では、女性と離れて立つのがマナーです(痴漢の罪に問われた被告人に対し、逆転の無罪判決を言い渡して)」「君の今後の生き方は、亡くなった3人の6つの目が、厳しく見守っている(殺人・死体遺棄の罪に問われた被告人に、無期懲役の判決を言い渡して」「私があなたに判決するのは3回目です」「吸いたくなった時、家族を取るか大麻を取るか、よく考えなさい」・・・・・・。
知っている事件も多いが、そんな発言がされていたとは・・・・・・。
8月最後の1週間、各地に赴き会合に出席しました。26日は栃木県で宇都宮のLRT開業式典と公明党OB議員の大光会の集い、27日は金沢に行き公明党石川・福井・富山北陸3県合同夏季議員研修会と石川県大光会総会に出席、31日は大分県全県から集っての公明党国政報告会と大光会に出席しました。いずれも勢いのある会合となり、多くの方と有意義な懇談をすることができました。
「地域をどう活性化するか」「人口減少、人手不足にどう対応するか」「公明党議員のフットワークとネットワークで結果を出す日々の活動」などを語り、またそれぞれの要望も多くいただきました。互いに意見交換するなかで、思考が回転して決意し合ったと思います。それにしても今年の夏は暑かった。



