 今年3月亡くなった坂本龍一さんと「動的平衡」の福岡伸一さんとの対談。「生命とは何か」「音楽とは何か」をめぐる対談だが、大変噛み合ったいい対談になっている。軸となっているのは「ロゴスv sピュシス」の相剋であり、「世界をどのように記述すれば良いのか」との問いだ。科学は、生命を要素還元主義的に解析し、ロゴス化される。時間は止まり、動的な生命は、失われる。音楽も音符はアルゴリズムとなり、音は電子音楽などデジタル化されロゴス化していく。秩序は美しさと安定をもたらすが、豊かな自然(ピュシス)はロゴス化によって侵食され削られていく。二人は、ロゴスに偏りすぎた世界の歪みに目を向け、自然の豊かさを回復するための新たな思想を求め共鳴板を鳴らす。
今年3月亡くなった坂本龍一さんと「動的平衡」の福岡伸一さんとの対談。「生命とは何か」「音楽とは何か」をめぐる対談だが、大変噛み合ったいい対談になっている。軸となっているのは「ロゴスv sピュシス」の相剋であり、「世界をどのように記述すれば良いのか」との問いだ。科学は、生命を要素還元主義的に解析し、ロゴス化される。時間は止まり、動的な生命は、失われる。音楽も音符はアルゴリズムとなり、音は電子音楽などデジタル化されロゴス化していく。秩序は美しさと安定をもたらすが、豊かな自然(ピュシス)はロゴス化によって侵食され削られていく。二人は、ロゴスに偏りすぎた世界の歪みに目を向け、自然の豊かさを回復するための新たな思想を求め共鳴板を鳴らす。
坂本龍一さんは、「若い頃は、無機質な音楽がすごく好きで、無機質でない音楽を作るのはすごく難しかった。メロディーというものは、あくまで12音階の順列組み合わせで、作曲するということはその組み合わせをどう作っていくかということだと考えていた」と言い、「YMOをやるようになってから、だんだんと考え方が変わり、音を操るということをしない音楽があるんじゃないかということを感じだした。それで今は、ピュシスとしての脳を持ち、非線形的で、時間軸がなく、順序が管理されていない音楽というものを作れないかと考え続けている」「科学は何度繰り返しても、同じ結果が得られる、つまり再現性に価値を置く。音楽はそれとは反対。1回しか起こらないというところにベンヤミンがいう『アウラ(オーラ)』があり、そこに価値がある」「今でもそういうノイズのないシンプルな美しさが皆、好きだ。つるつるででこぼこしていないほど賛嘆されるし、建築もまっすぐなものが美しいと言われる。ノイズが排除されるが、ジョン・ケージという素晴らしい作曲家が、図ばかりを取り出すのではなくて地、ノイズを聞いてみようという挑戦を始めた」「僕たち人間は、進化の過程で、自然現象を丸ごと受け取ることがしにくい鈍感な動物になってしまっている。一番身近な自然は海や山ではなくて、自分自身の身体なんです」「言葉で言い表わせない世界があるから音楽をやっているわけだ」「地球という惑星には、空気の振動つまり音という現象が常に起こっている。誰かが聞いて、その振動を共有する空間や時間があるということを音楽と言っているんだと思う」と語る。音と曲について、あくなき求道、挑戦の姿を感ずる。
福岡伸一さんは、「操作的に生命を扱い、生物学ではなく、死物学を極めようとしていた。ゲノムはマッピングされ、遺伝子は名づけられ、全てが情報としてデータベース化された。生命は完全にロゴス化された。その時点で時間は止まり、動的な生命は失われた。ピュシスの本体はスルリとどこかへぬけだしていた。私は生命を動的平衡として捉え直すために再出発した」と語る。「ファーブルは、『あなた方は研究室で虫を拷問にかけ、細切れにしておられるが、私は青空の下で、蝉の歌を聴きながら観察している・・・・・・』と言っている。動的平衡、つまり、生命が全体としてのバランスを保つ機能というものを、もう少し精密に考えようと思うようになった」「生命の動的平衡とは、絶え間のない合成と分解を行うことですが、そこでは合成、つまり作ることよりも分解、壊すことの方を絶えず優先しています」と語り、ベルクソンの「創造的進化」、シュレーディンガーの「負エントロピー」に触れ、生命が常に合成と分解をすることによって成り立っているというモデルを考え、この動的円弧を「ベルクソンの弧」と名付けたことを紹介する。
「円環する音楽、循環する生命」――。「音楽の円環というものは、楽譜を書く人、演奏する人、聞く人がいて、初めて成り立つわけで、ずいぶん時間がかかりましたが、そんな当たり前のことにやっと気がつくことができたんですね」と言う。そして「ピュシスの実態は、ロゴスの極限にまでたどりつかないと見えにくいものです」「有限であるからこそいのちは輝く」と福岡さんは語っている。
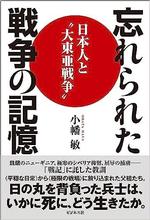 小幡さんは東大から自衛隊、そして今は文筆活動している。「私は自分の生きる時代が信じられなかった。・・・・・・この時、なぜか私の脳裏にはいつも日本軍将兵が居た。どうやら私には彼らが最後の日本人に見えた」「願わくは、愛すべき我ら日本民族の欠陥と向き合い、誠実なる打開を試みんことを」・・・・・・。ロシアのウクライナ侵略に対し、「自らの国は自らが守る気概」の重要性を改めて感じるが、世界価値観評価で「仮に、戦争が起こる事態になったら、自分の国のために戦いますか」との質問に、「はい」と答えた人は、2019年の調査時点で、日本は13%と際立って低く、77カ国中最下位だったという。しかも「わからない」と言う回答が38%もあり、国際比較で極めて多いことが明らかになっている。さらに、「自衛隊に入りたい」という若者が、減少しているという現況にある。「戦争」は「死」を覚悟する。日常の生活や職業とは、決定的に断絶する。本書は、「飢餓のニューギニア」「極寒のシベリア抑留」「屈辱の捕虜」を中心に、「戦記」を読み解き、「平穏な日常」から「極限の戦場」に放り込まれた兵士たちは、いかに考え、いかに死んでいったか、さらに死を免れた者の苦悩を、考察する。
小幡さんは東大から自衛隊、そして今は文筆活動している。「私は自分の生きる時代が信じられなかった。・・・・・・この時、なぜか私の脳裏にはいつも日本軍将兵が居た。どうやら私には彼らが最後の日本人に見えた」「願わくは、愛すべき我ら日本民族の欠陥と向き合い、誠実なる打開を試みんことを」・・・・・・。ロシアのウクライナ侵略に対し、「自らの国は自らが守る気概」の重要性を改めて感じるが、世界価値観評価で「仮に、戦争が起こる事態になったら、自分の国のために戦いますか」との質問に、「はい」と答えた人は、2019年の調査時点で、日本は13%と際立って低く、77カ国中最下位だったという。しかも「わからない」と言う回答が38%もあり、国際比較で極めて多いことが明らかになっている。さらに、「自衛隊に入りたい」という若者が、減少しているという現況にある。「戦争」は「死」を覚悟する。日常の生活や職業とは、決定的に断絶する。本書は、「飢餓のニューギニア」「極寒のシベリア抑留」「屈辱の捕虜」を中心に、「戦記」を読み解き、「平穏な日常」から「極限の戦場」に放り込まれた兵士たちは、いかに考え、いかに死んでいったか、さらに死を免れた者の苦悩を、考察する。
「地獄の島ニューギニア」――。飢餓と悪疫、「人間、やめとうなる」、地獄に戦友も日本人もなかった。地獄は人を壊し、人が人を食い始めた。そのなかでの善意と良心、人間を勇気づけたものは、やはり人間であった。
「凍てつく大地シベリア」――。飢えと過酷な労働と骨まで凍る寒さ。転向を迫る赤化による同胞相食む分断と反動探し。思想や宗教をめぐる弾圧の熾烈さは島原の乱・ キリシタン弾圧を想起させる。日本人に内在する民族的性格の弱さ、宗教・哲学の弱さが極限状況で露呈する。
それは反面、「捕虜」となったときに歪む。戦陣訓の「生キテ虜囚ノ辱ヲ受ケズ」は強く浸透し、日本人は自決や自殺的攻撃を選んだ。「欧米では、捕虜となる事は、一般に名誉を失うこととはみなされず、敵前逃亡や命令違背とみなされるような場合を除き、最後まで敢闘したとしてむしろ厚遇されることが常であるのに対し、日本では石をもって追われたのである」と言う。日本人の大半は、捕虜となったことに後ろめたさを覚え、強い自己嫌悪に襲われた。日本人の弱点が、「従順な日本人」として露呈する。
著者は「武の精神(道義を愛し、国を愛し、己を愛することは、不可分一体の一事であり、武の精神はこれらを通貫するものであるが故に、他者に対しても開かれた精神と呼べるのである。武は己を陶冶していくことを目的にするばかりでなく、自分よりも大きい、より高次の存在としての共同体に奉仕することをも目指す。それゆえに武は、個人の倫理、道徳の範疇を越え、個の輪郭を共同体に拡大発展させていく・・・・・・)」を強調している。それはむしろ「生命哲学」であろう。このような人間が人間でなくなることを断じてなくすために「だから戦争はいけないのだ」「戦争ほど残酷なものはない。戦争ほど悲惨なものはない」ことを、「生命哲学」として骨髄に刻むことだ。
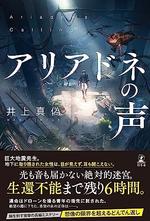 ITを駆使し、商業施設やオフィスや工場、インフラ設備など、主な施設を地下に置いた実験的スマートシティ「WANOKUN I」を巨大地震が襲う。崩落や火災などで、地上からの救助が困難をきわめるなか、最深部の地下5階の暗闇に1人の女性が取り残されてしまう。しかもその女性は「見えない、聞こえない、話せない」という3つの障がいを抱え、街のアイドル(象徴)的存在となっていた中川博美だった。崩落がひどく、救助隊の侵入は不可能。しかも6時間後には浸水してしまうという絶体絶命の状況だった。災害救助用ドローンを扱うベンチャー企業に勤める高木ハルオは、最新機を操作し、彼女を2階上のB3にあるシェルターに誘導するという前代未聞のミッションに挑むことになる。この地下都市では、地上の物流網の代わりに、地下に「チューブ」と呼ばれるドローン専用の配送路が網目のように張り巡らされており、救命のためには、ドローンを使うのが唯一の道だったからだ。次々と襲いかかる予期せぬ困難。誘導するにも障害を抱えているために反応が全くわからない。時間との戦いのなか、緊迫の救出作戦が行われる。
ITを駆使し、商業施設やオフィスや工場、インフラ設備など、主な施設を地下に置いた実験的スマートシティ「WANOKUN I」を巨大地震が襲う。崩落や火災などで、地上からの救助が困難をきわめるなか、最深部の地下5階の暗闇に1人の女性が取り残されてしまう。しかもその女性は「見えない、聞こえない、話せない」という3つの障がいを抱え、街のアイドル(象徴)的存在となっていた中川博美だった。崩落がひどく、救助隊の侵入は不可能。しかも6時間後には浸水してしまうという絶体絶命の状況だった。災害救助用ドローンを扱うベンチャー企業に勤める高木ハルオは、最新機を操作し、彼女を2階上のB3にあるシェルターに誘導するという前代未聞のミッションに挑むことになる。この地下都市では、地上の物流網の代わりに、地下に「チューブ」と呼ばれるドローン専用の配送路が網目のように張り巡らされており、救命のためには、ドローンを使うのが唯一の道だったからだ。次々と襲いかかる予期せぬ困難。誘導するにも障害を抱えているために反応が全くわからない。時間との戦いのなか、緊迫の救出作戦が行われる。
「無理と思ったら、そこが限界だ」――。繰り返し響いてくる水の事故で亡くなった兄の言葉。「無理」と思えばお終い。しかし果たしてそれだけか。「無理っていうのは信号なんだ。これ以上やったら危険だっていう脳や体の信号。その信号が正しいかどうかはわからない。慎重になりすぎて失敗することもあれば、甘く見すぎて無謀なことをやっちまうこともある。けど大事なのは、その『無理かどうか』のラインを自分で引くことだ」と夢の中の兄は呼びかけてきた。
未来のスマートシティーを襲った大地震に、IT技術を駆使した緊迫した救命の究極の戦い。未知の大救出作戦に巻き込まれる。
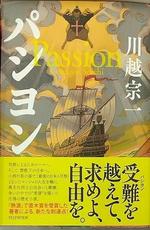 キリスト教が禁じられ、島原の乱に至った江戸時代――。最後の日本人司祭となった小西マンショの生涯を通じて、キリシタンへの迫害の凄惨な歴史が語られる。パシヨンとは受難。"受難の時代"を生き抜こうとする者の懊悩と魂の叫び、加えて弾圧をする幕府の総目付・キリシタン奉行の井上政重の心象が対比的に描かれ、緊迫の度が増す。ニ人はついに運命的な直接対峙の時を迎えるのだった。
キリスト教が禁じられ、島原の乱に至った江戸時代――。最後の日本人司祭となった小西マンショの生涯を通じて、キリシタンへの迫害の凄惨な歴史が語られる。パシヨンとは受難。"受難の時代"を生き抜こうとする者の懊悩と魂の叫び、加えて弾圧をする幕府の総目付・キリシタン奉行の井上政重の心象が対比的に描かれ、緊迫の度が増す。ニ人はついに運命的な直接対峙の時を迎えるのだった。
小西彦七(後のマンショ)はキリシタン大名・小西行長の孫で、対馬藩主・ 宗義智の子として生まれるが、関ヶ原の戦いで小西行長が西軍について斬首、母・マリヤは離縁される。長崎へ移り、小西家の遺臣・益田源介らの世話になりながら成長していく。江戸幕府が禁教令を強化し、キリシタンへの弾圧は強化され、それへの抵抗と小西家再興が画策されていく。逡巡する彦七は、司祭となるため、日本を出る決断をする。
そうしたなか、時代はますますキリシタン弾圧へと進み、40万にもなっていたキリシタンは、棄教か殉教かに追い込まれていく。そして島原の乱へと進んでいく。
一方、弾圧政策を強化していく幕府。少禄の幕臣から大目付に出世した井上政重は、幕府統治による太平の世を目指し、世を乱す不穏な動きをひたすら制止しようとする。政重は、なし崩しで禁制を指揮するようになり、厳しい拷問や火刑や斬首が相次ぎ、たちまち畏怖と嫌悪の対象となっていく。あたかも、ハンナ・アーレントの「エルサレムのアイヒマン」を想起させるが、彼の場合、心の中に潜む世への憤怒と空虚・孤独は深まっていく。
島原の乱に帰国が間に合った小西マンショ。餓死寸前の原城のキリシタン戦士に司祭となったマンショは叫ぶ。「逃げよ」「教えを棄てよ」「放免されて落ち着いたら棄てた教えを取り戻せばいい」・・・・・・。そして数年後、江戸時代最後の日本人司祭・小西マンショは捕われ、拷問のなか井上と対峙するのだが・・・・・・。
「生きる」ことと「自由」。「魂の自由」と「宗教」。弾圧する幕府の側の井上政重を出すことによって、本書は「受難の時代」を生きる魂の叫びを剔抉してみせた力作となっている。





