日本の現場の底力である技能労働者の賃金アップにつながる公共工事設計労務単価が、3月1日以降の工事につき、全国・全職種平均で5.2%引き上げられることになりました。14日の斉藤鉄夫国土交通相発表です。引き上げは私が国交大臣の2013年から連続11年、2012年比で、実に1.655倍となりました。21世紀になって毎年連続して下がってきており、悲鳴が上がっていました。建設業では「担い手」が重要。特に若者が入ってくる職場にしなければ、日本の現場の底力がどんどん下落していきます。
建設業は、「きつい、汚い、危険」の3Kの職場とも言われてきましたが、経済活性化を促すストック効果のインフラ整備です。そこで新しい3Kとして、「給料がいい、休暇がある、希望がある」を発表。関係者上げての協力体制をとってきました。今回の設計労務単価5.2%アップは、9年ぶりに5%以上となったもので、「賃上げ」が最重要課題となっている今の日本の先駆けともなるものです。これが現場の職人さんの給料アップにつながるようさらに努力したいと思っています。
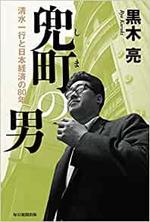 「清水一行と日本経済の80年」が副題。まさに激流とも言うべき経済成長の昭和30年代からの日本。その経済の生々しい現場、欲望の激突、そこから生ずる事件の数々。それら経済小説を書き続けた清水一行の波乱の人生と日本経済の興亡を描く。なんと生涯の作品数は214にもなった。あの城山三郎ですら118の作品であったことを思うと凄まじい。「全盛時代の昭和46年~60年頃は年間8~10作という猛烈な勢いで刊行していた」「400字詰め原稿用紙で月に800枚から1300枚という猛烈な勢いで執筆を続けた」という。
「清水一行と日本経済の80年」が副題。まさに激流とも言うべき経済成長の昭和30年代からの日本。その経済の生々しい現場、欲望の激突、そこから生ずる事件の数々。それら経済小説を書き続けた清水一行の波乱の人生と日本経済の興亡を描く。なんと生涯の作品数は214にもなった。あの城山三郎ですら118の作品であったことを思うと凄まじい。「全盛時代の昭和46年~60年頃は年間8~10作という猛烈な勢いで刊行していた」「400字詰め原稿用紙で月に800枚から1300枚という猛烈な勢いで執筆を続けた」という。
感じるのは、日本経済成長の凄まじい勢いだ。描かれる一つ一つの事件が自分の人生をたどるように思い起こされる。松本清張、あの梶山季之、黒岩重吾、森村誠一、横溝正史。梶山の「黒の試走車」と清水の「動脈列島」・・・・・・。走り回る取材スタッフ。映画化され、文庫は売れる。出版界も勢いを増す。追いまくられるように出版されるこれら経済小説、事件小説を読みまくったものだ。生々しい事件現場を描くゆえに、訴訟が起きる。ペンとは何であるか、最高裁にまでいく争いの激しさも描かれる。時代も経済も人も荒々しく激しかった。
忘れていたあの時代のエネルギーが蘇り、長期にわたり緩やかなデフレの中に沈む現在の日本を対比する。共産主義者として戦後の焼け跡を奔走し、結核にもなる。兜町を這い回り、週刊誌に株情報を書き続ける。書きためた原稿が、ついに昭和41年、「小説兜町」として、見出してくれた三一書房から出され、せきを切ったように次々と爆発的な売れ行きを示す。時代に作り出され、時代と人生を共にした男の姿を描く。清水一行、1931年生まれ、2010年没。
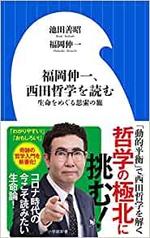 「動的平衡」の福岡伸一氏が、西田幾多郎研究の第一人者・池田善昭氏と「生命とは何か」について対談。「ロゴス」の西洋科学・哲学思想に、「ピュシス」の実在把握によって対峙し、乗り越えることを示す。実在の全的把握で根底から包み込むといえようか。「生命をめぐる思索の旅」が副題。対談が進むにつれ、どんどん思索が深まり、ピュシスという新しい世界観を獲得していく「思索の旅」は感動的だ。
「動的平衡」の福岡伸一氏が、西田幾多郎研究の第一人者・池田善昭氏と「生命とは何か」について対談。「ロゴス」の西洋科学・哲学思想に、「ピュシス」の実在把握によって対峙し、乗り越えることを示す。実在の全的把握で根底から包み込むといえようか。「生命をめぐる思索の旅」が副題。対談が進むにつれ、どんどん思索が深まり、ピュシスという新しい世界観を獲得していく「思索の旅」は感動的だ。
福岡氏は、「生命とは要素が集合しできた構成物ではなく、要素の流れがもたらすところの効果なのである」「生命とは動的平衡にある流れである」と言う。仏法哲学における「法」概念、鴨長明の方丈記に描かれる無常と、常住の十字路に瞬間を位置づけるということに通じる。福岡氏は、「西洋の科学や哲学においては、これまで、時間は点(の集まり)でしかなかった。・・・・・・まさに『不連続の連続』であり、ここにおいて初めて連続した時間が満たされることになる」「池田先生のご教示により、①ピュシス②包みつつ包まれる(逆限定) ③ 一と多(時間と空間)④先回り⑤時間ーーという五つのステップを乗り越えることができ、対話を通して西田哲学の重要性を改めて認識することができた」と言う。なお「ピュシスとは、切り分け、分節化し、分類される以前の、ありのままの、不合理で、重畳で、無駄が多く、混沌に満ち溢れ、危ういバランスの上にかろうじて成り立つ動的なものとしての自然である。自然とはロゴスではなく、結局はピュシスである」と言っている。
池田氏は、「彼は、生命のダイナミズムとしての全体性、すなわち『絶対的状態』を彼の内面に把握することとなり、世界で初めて生命の新たな定義をなし得ることに成功したのであった。福岡氏自身、彼の生命体の内面に『感得』するという全体的直観によって把握されていたがゆえにである」「生命における『実在』とは、存在と言う単にあるなしではなく、常にエントロピーに抗うがゆえに、『現在』がまさに『過去未来』に対して逆限定的に成立するからでこそあった。ここでこそ、有無の同時性が成立しているのである」「先回りという生命上の働きは・・・・・・福岡伸一氏は、西田の言うそうした『逆限定』を、特に、『動』と『静』との絶対矛盾的自己同一に習いつつ『動的平衡』として把握したのであった」と言っている。
量子力学において、ナーガールジュナの「空」の仏法哲学に論が及ぶことがあるが、私にとって「宇宙の法」「空」「諸法実相」「因果倶時」「依正不ニ」「無常と常住」の仏法哲学を思考する旅でもあった。
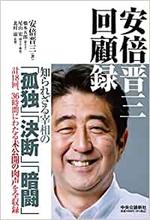 首相辞任直後の2020年10月から、1日2時間のインタビューが始まり、21年10月まで18回、計36時間の肉声を収録したもの。今もふっと安倍元総理が出てくる。表紙にあるあの笑顔が・・・・・・。優しい気配りの人、リアリストの政治家、話が行き交うとグッと身を乗り出してくる姿、外国首脳との会談でも戦略的に主張し当意即妙の鮮やかな切り返しをする姿・・・・・・。公明党のことも大変大事に思ってくれ、「全世代型社会保障」「教育」「中小企業支援」「防災・減災」「観光」など推進できた事はあまりに多い。私が安倍元総理に感じてきたのは、「国を背負う」という気概、戦略的思考だ。
首相辞任直後の2020年10月から、1日2時間のインタビューが始まり、21年10月まで18回、計36時間の肉声を収録したもの。今もふっと安倍元総理が出てくる。表紙にあるあの笑顔が・・・・・・。優しい気配りの人、リアリストの政治家、話が行き交うとグッと身を乗り出してくる姿、外国首脳との会談でも戦略的に主張し当意即妙の鮮やかな切り返しをする姿・・・・・・。公明党のことも大変大事に思ってくれ、「全世代型社会保障」「教育」「中小企業支援」「防災・減災」「観光」など推進できた事はあまりに多い。私が安倍元総理に感じてきたのは、「国を背負う」という気概、戦略的思考だ。
本書で語られることは、1993年当選の同期、2006年第一次安倍政権では私は党代表、2012年第二次安倍政権では国土交通大臣でもあり、くっきりと目に浮かぶ。第一次安倍政権での教育基本法や国民投票法、参院選の敗北・・・・・・。地獄からはい上がった第二次安倍政権――日本再建、経済再生、デフレ脱却、その中での2度にわたる消費税上げ、平和安全法制、70年談話、憲法改正問題、3,000万人を超えたインバウンド観光、そして勝利し続けた国政選挙――。最後に襲いかかったコロナ。その緊迫する毎日の中で安倍元総理は何を考えたか。本書では、「財務省など役所への不信」などを始め、かなり率直に語っている。公にはできない戦略的部分もあろうが、紙面的制約の中でも安倍元総理らしく率直だ。
特に、本書のかなりの部分を占める「地球儀を俯瞰する外交」における世界の指導者とのやりとりは、安倍総理ならではの面目躍如、八面六臂だ。オバマ、トランプ、メルケル、習近平、プーチン、豪州のアボット、フィリピンのドゥテルテなどとの真剣勝負のやりとりは他の誰にもできないことだった。それらが肉声で語られている。面白いし貴重だ。そこには「自由で開かれたアジア太平洋」構想などの戦略性と意志が常にあった。その都度、面白いエピソードを聞かせていただいたが、「1時間にわたるトランプとの電話会談の中身」「大統領は反対党によって倒され、首相は与党から倒される」など本書にはそれが出ている。
1年にわたってよくインタビューをしておいてくれたとの思いを深くする。「回顧録」というにはまだあまりに生々しく、こみ上げてくるものがありすぎる。
 「戦国の怪物から幕末の闇まで」が副題。「とかく、歴史には闇が多い。歴史には裏がある」と言う。歴史は表舞台の歴史であり、勝者の歴史である。民衆の喜怒哀楽の歴史や災害との関係などは、あまり表には出ない。磯田さんは、古文書を徹底して求め、表には出ていない意外な事実を探りだし、解読する。面白い。
「戦国の怪物から幕末の闇まで」が副題。「とかく、歴史には闇が多い。歴史には裏がある」と言う。歴史は表舞台の歴史であり、勝者の歴史である。民衆の喜怒哀楽の歴史や災害との関係などは、あまり表には出ない。磯田さんは、古文書を徹底して求め、表には出ていない意外な事実を探りだし、解読する。面白い。
今回の直木賞「しろがねの葉」では、石見銀山の厳しい現場の実態が胸が苦しくなるほど描かれるが、「日本最古のマスクは1855年頃、石見銀山の鉱山労働者の健康対策に宮太柱が開発した「福面』といわれる」と、本書の「疫病史に照らせば中盤か」「最古のマスク広告か」で書かれている。「江戸マスク開発者ニ人の末路」も面白い。災害について、磯田さんは、いくつもの著作で描いているが、「京都の震災復興、公家の苦闘」「西日本で地震連動の歴史(高槻の1596年の慶長伏見地震)」や、感染症についても、「身代潰した給付なき隔離」「感染症から藩主を守る(登城も出勤も自粛させたのは藩主を守るため)」など興味深い話が出てくる。「歴史は繰り返さないが、よく韻をふむ」という。
「光秀登場の黒幕(細川藤孝)」「比類なき戦国美少年・名古屋山三郎と淀殿」「家康の築城思想(二条城が小さいのは何故)」「三代・徳川家光の『女装』(家光に英才教育を施した三人)」「吉宗が将軍になる直前の尾張藩主の連続死」・・・・・・。「幻の忍術書・間林精要」「赤穂浪士が吉良の首を泉岳寺に運んだ後の「吉良の首切断式」「カブトムシの日本史」「殿様の警護マニュアル(刀を抜かないように刀のグリップにかぶせた柄袋。桜田門外の変で襲撃された時、お供の武士たちはこの柄袋のせいで刀を抜くのが遅れたという説。駕籠の中の井伊直弼はいきなり銃弾で腰を打ち抜かれた)」「鼠小僧は義賊にあらず(もっぱら弱い女子の部屋を覗き、彼女らの金をせしめていた)」「西郷隆盛は闇も抱えた男だった(西郷はもちのような男と言われ、すぐ気持ちが溶け合う男だったが、謀略を始めると暗殺、口封じ、欺瞞、何でもやった恐ろしく闇を抱えた男でもあった)」「コメ日本の圏外が育んだ発想(奄美群島、下北半島には牧畜社会があった)」「松平容保など『高須四兄弟』を生んだ高須藩の謎」「孝明天皇の病床記録の漏洩」「もみじ饅頭と伊藤博文」・・・・・・。
「織田信長の遺体の行方」などについても調べ上げて解説している。


