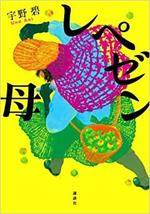 面白い。文章全体がラップのようで心地よい。展開もリズミカルで乗せられる。梅農家を営むおかんと、ダメ息子が、ラップバトルで対決することになる。母親の愛が溢れている。実際、先日、テレビでラップをする高齢女性の話題を見た。
面白い。文章全体がラップのようで心地よい。展開もリズミカルで乗せられる。梅農家を営むおかんと、ダメ息子が、ラップバトルで対決することになる。母親の愛が溢れている。実際、先日、テレビでラップをする高齢女性の話題を見た。
和歌山の田舎で梅農園を営む深見明子、64歳。夫の五郎は膵臓癌でこの世を去った。たった5年8ヶ月の結婚生活、梅農園を切り盛りする忙しい毎日。息子の雄大は、借金はいつものことで結婚・離婚を繰り返すダメ息子で、3年前に失踪して行方知れず。妻の沙羅は大変気の利く女性で明子の手伝いをしている。沙羅は高校を中退した頃からヒップホップミュージシャンになりたいと思っていた。「バトルに出たい」と紗羅が言う。ラッパー同士が、即興のラップで相手を「ディス」りあうラップバトル(MCバトル)。明子にとって全く知らない世界だが、大会に付き添って人生が急カーブ。ひょんなことでラップバトルに出て大ブレイクしてしまった64歳のおかん。なんと行方不明の息子がラップバトルで勝ち抜いてきており、ついに親子対決となる。この展開がなんとも面白いのだ。
そのラップのやり取りで、明子はそれまで行違っていた息子の気持ちを探ろうとする。「格闘技でも将棋でも、名勝負って言われるものには、絶対に相手へのリスペクトがあるし、もっと深いレベルで交差してる感じがある」「本当の勝負は、相手を理解することなんじゃないか」「もしかして自分は、雄大に憎まれていたのかもしれない。果たして自分は、息子を本気で理解しようとしたことが、あったのだろうか」「ずっと面倒かけ続けてきたのは、ひそかな復讐だったのではないだろうか。見落としてきたものとは、一体何なのだろう」「車の中で見つけたときの4歳の雄大の顔。・・・・・・あの時は見ていたのに、見えていなかった」「雄大にしてみたら、彼女の前で面目を潰されて屈辱的だったに違いない。明子の方が無神経だったのだ。見えていなかった。見ていなかった。見ようとしていなかった。――なんでやろ。私は何を見てたんや」・・・・・・。
親の深い愛情、深すぎる愛情、忙しい日常・・・・・・。考えさせられる。
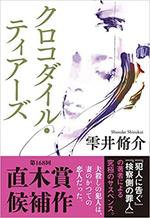 老舗の陶磁器店を営む久野貞彦・暁美夫婦。その後継の息子・康平が刺殺される。犯人は息子の妻・想代子の元恋人・隈本だった。ところが裁判の判決後、隈本は「想代子から『夫殺し』を依頼された」と衝撃的な発言をする。想代子は否定、警察もまったく取り合わないが、暁美は疑う。そういえば夫が死んだというのにのに「嘘泣き(クロコダイル・ティアーズ)」をして、悲しんでいないようにも思えた。暁美の夫の貞彦が、想代子を信頼してるようにも見えて苛立つ。疑念が次々に浮かび膨らんでくる。想代子の冷静な振る舞いが、男に媚びているように感じ怒りすら感じる。
老舗の陶磁器店を営む久野貞彦・暁美夫婦。その後継の息子・康平が刺殺される。犯人は息子の妻・想代子の元恋人・隈本だった。ところが裁判の判決後、隈本は「想代子から『夫殺し』を依頼された」と衝撃的な発言をする。想代子は否定、警察もまったく取り合わないが、暁美は疑う。そういえば夫が死んだというのにのに「嘘泣き(クロコダイル・ティアーズ)」をして、悲しんでいないようにも思えた。暁美の夫の貞彦が、想代子を信頼してるようにも見えて苛立つ。疑念が次々に浮かび膨らんでくる。想代子の冷静な振る舞いが、男に媚びているように感じ怒りすら感じる。
「泥沼に落とした足が.もがくごとに深く嵌まっていく感覚にも似ていた」「一つの疑念に目を向けただけで、そのことに何の確証がないにもかかわらず、那由多に対して今まで通り接することができなくなってしまった」と、暁美に言われて貞彦は、孫の那由多のDNA鑑定までしてしまう。そうしたなか、店の宝ともいうべき「黄瀬戸」が割られたり、駅前再開発の目玉として大型商業ビルの計画が持ち上がり、貞彦が営んでいる陶磁器店「土岐屋吉平」の決断が迫られることになる。
噂の中の社会、ましてや家族の中に起きる違和感、それが増幅して疑念となっていく姿をじわりと描く。ありえることだけに怖さを感じるミステリー。
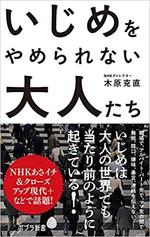 人がつくるこの人間社会は、その人間関係がなかなか難しい。組織と人間の難しさもある。これを「大人のいじめ」という角度でその実態を探っている。
人がつくるこの人間社会は、その人間関係がなかなか難しい。組織と人間の難しさもある。これを「大人のいじめ」という角度でその実態を探っている。
実例が示される。「多忙すぎる教育現場・加速させる親からの要求、全てが生徒・保護者優先の学校現場での教員へのいじめ」「嫉妬がいじめの引き金になった職場、いじめの中心にはボスがいる」「仕事ができる人がいじめられるケースも」「ご近所付き合いは現在の村八分」「高校時代のスクールカーストは50歳を過ぎた同窓会でも」「子供にまで連鎖するママ友いじめの怖さ、いじめは誰もが知る大企業でも」「余裕のない社会、余裕のない職場で生まれるいじめ」などが示される。
目に見える暴力や、ただ働きをさせるというような労働問題等の違法行為とは異なる。法律では裁けない様々な肉体的・精神的な個人の尊厳に対する攻撃のことだ。したがってその解決は法的制裁や金銭の補償だけではだめだ。ハードではなく柔らかな解決の方法が大事となる。子供のいじめは、転校や卒業、クラス替えなので終えられるが、大人へのいじめは職場や地域を変えられないのが苦しい。また男性には自分がいじめられているという事実をなかなか受け入れられない人が多いようだ。いずれにしても、閉鎖的な空間や鬱屈した思いが蓄積し発散する場がないことから大人へのいじめが起きる。社会の歪みが立場の弱い人に集まり、顕在化するのだ。人間社会の嫉妬や社会におけるノルマ等、加害者側の不満が鬱積して、無視、陰口、暴言、連絡を伝えない、陰湿な嫌味が大人へのいじめとして当たり前に起きている。人間社会が続く限り、常にある問題だが、時代とともに深刻になってくる。
11日、12日の両日、奄美大島で「公明党ティダ委員会」「新春政経懇話会」、鹿児島市で「新春政経懇話会」「大光会総会」に出席、地域の発展に向け新年のスタートを切りました。「ティダ」とは太陽。公明党は奄美群島の振興を目指し、「ティダ委員会」を結成、住民の声を聞き実現するために積極的に活動をしてきました。今回も奄美市を始め各市町村長が出席、今年で日本復帰70年を迎える奄美群島の発展に向けて意見交換をしました。2021年、奄美・沖縄が深い世界自然遺産に登録となりましたが、コロナ禍のため観光客が増えない状況でした。しかし、いよいよ今年は飛躍する勝負の年。「観光客を増やしたい」「交通費の関係で物価高が追い打ちをかけている」「人手不足が深刻」「太田国交大臣の時代に創設してもらった振興交付金の拡充と対象拡大を」など切実な要望が相次ぎました。委員長の浜地雅一衆議院議員等は丁寧に答え、要望の実現に向けて頑張ることを誓いました。地域、なかでも離島の諸課題は極めて切迫したものであり、離島振興に懸命に頑張ってきている公明党への期待は極めて大きいものがあります。頑張らなければなりません。
また、奄美でも鹿児島市でも「新春政経懇話会」が、知事、市長、市町村長、自民党の国会・県会等の議員、地域を担う有力者多数の出席を得て、盛大に行われました。4月の統一地方選挙の勝利に向けてのダッシュです。
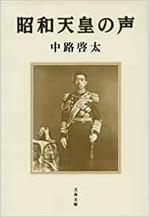 令和となった2019年の著書。昭和50年9月20日、「ニューズウィーク」東京支局長のバーナード・クリッシャーのインタビューに、昭和天皇は自らの役割について、「戦前も、戦後も基本的に変わっていない。自分は常に憲法を厳格に守るよう行動してきた」と言った。統帥権をもち「神聖ニシテ侵スへカラス」の天皇は、西園寺公望によれば、「天皇が自らの一存で一つの内閣を倒し、また、新たな内閣を立てるということになれば、もはや立憲君主ではなく、専制君主である。それでは、大日本帝国憲法を定めた明治天皇の聖旨に背くことにもなるし、失政があった場合、その責任は直接、天皇が負わなければならないことにもなる。天皇や皇室は本来、『悠久の日本』を体現し、時々の権力から超然としていなければならない」ということだ。現実にこの難問は、張作霖爆殺事件をめぐっての田中義一内閣総辞職における西園寺公望と牧野伸顕の見解の相違という形で現れた。本書は「昭和天皇の声」と題するが、「昭和天皇の政治的決定」という大日本帝国憲法下の天皇の難しい位置と決断に真正面から迫っている。
令和となった2019年の著書。昭和50年9月20日、「ニューズウィーク」東京支局長のバーナード・クリッシャーのインタビューに、昭和天皇は自らの役割について、「戦前も、戦後も基本的に変わっていない。自分は常に憲法を厳格に守るよう行動してきた」と言った。統帥権をもち「神聖ニシテ侵スへカラス」の天皇は、西園寺公望によれば、「天皇が自らの一存で一つの内閣を倒し、また、新たな内閣を立てるということになれば、もはや立憲君主ではなく、専制君主である。それでは、大日本帝国憲法を定めた明治天皇の聖旨に背くことにもなるし、失政があった場合、その責任は直接、天皇が負わなければならないことにもなる。天皇や皇室は本来、『悠久の日本』を体現し、時々の権力から超然としていなければならない」ということだ。現実にこの難問は、張作霖爆殺事件をめぐっての田中義一内閣総辞職における西園寺公望と牧野伸顕の見解の相違という形で現れた。本書は「昭和天皇の声」と題するが、「昭和天皇の政治的決定」という大日本帝国憲法下の天皇の難しい位置と決断に真正面から迫っている。
昭和天皇が自ら政治的決定を下したのは三度だという。「天皇はのちに『自分は2.26事件のときと終戦のときの2回だけは、立憲君主としての道を踏みまちがえた』などと回想している」「田中義一内閣の総辞職を加えると、3度だけは天皇は憲法の条規に従わず、余人の輔弼を待たずにみずから決定したと考えられる」と言う。「2.26事件のときには、総理官邸が叛乱軍に襲撃され、岡田啓介総理大臣の生死も不明となって、政府の機能は麻痺した。その中、天皇は断固として叛乱軍討伐の方針を打ち立て、事態を収拾させた」「終戦のときには、首脳たちの意見が対立し、方針を決められなくなったときに、天皇はみずからポツダム宣言受諾を決定した。ことの当否は別にして、立憲君主としての『常道』は踏み外したという思いを天皇は持っていたのだろう」と言う。
本書は5章に分けて、その生々しい現実場面を描く。「感激居士」――。昭和10年(1935)8月12日の陸軍中佐・相沢三郎による永田鉄山殺害事件。激情型の感激居士への北一輝の影響、皇道派と統制派の対立・・・・・・。「相沢さん一人を見殺しにすることはできない」と、相沢事件は2.26事件の導火線となっていく。
「総理の弔い」は、昭和11年(1936)2月26日未明の2.26事件。岡田啓介総理、齋藤実内大臣、高橋是清大蔵大臣、渡辺錠太郎陸軍教育総監が即死、鈴木貫太郎侍従長が瀕死の重体と伝えられた。しかし岡田総理は生きていた。小坂曹長らが救出、天皇は「よかった」と繰り返し言った。「陸軍が躊躇するならば、私がみずから近衛師団を率いて鎮圧にあたる」とまで言った。
「澄みきった瞳」――。2.26事件で瀕死の重傷を負った鈴木貫太郎。妻・たかは、「とどめだけは、やめてください。どうか、やめてください」と叫ぶ。「とどめは残酷だからやめろ」と安藤輝三大尉が言う。その青年の瞳は恐ろしいほど澄み切っていた。「傷つけられた『股肱』として、天皇が真っ先に思い浮かべたのは、鈴木とその妻のたかではなかったか。蹶起軍を叛乱軍とみなし、徹底的に討伐しなければならないとする天皇の方針は、侍従長遭難の報告がもたらされた時点で、ほぼ決まっていたといえそうだ」・・・・・・。
「転向者の昭和20年」――。田中清玄が昭和20年12月21日、天皇に会い、「龍沢寺で山本玄峰老師のもとで修行いたしております。天皇陛下なしに、社会的、政治的融合体としての日本はあり得ません」と述べた話。
「地下鉄の切符」――。昭和20年8月14日、ポツダム宣言受諾の決断。「自分はいかになろうとも、万民の生命を助けたい。・・・・・・少しでも種子が残りさえすれば、さらにまた復興という光明も考えられる」・・・・・・。皇太子時代の渡欧のときの思い出の品「パリで乗った地下鉄の切符」。いずれも日本を背負った天皇の生身の姿が描かれる。




