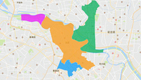政治コラム 太田の政界ぶちかましCOLUMN
NO.2 家康が挑んだ利根川との戦い
文化・芸術の秋、スポーツの秋――。地域行事が活発に行なわれ、参加の途中、北区にある荒川資料館に立ち寄った。赤羽駅からも近いこの水辺空間こそ、荒川をコントロールする大工事、荒川放水路、岩渕水門の位置する歴史的な地だ。
現在の荒川は元々あったものではなく、じつは人がつくり上げた放水路だ。この荒川放水路開削事業は、明治40年、43年の大洪水(下町はほとんど水につかった)を契機として、44年に着手、昭和5年に完成となる。すさまじい大事業だ。そして従来の荒川は隅田川として、放水路は荒川として今日に至ることになる。
この東京は日本一広大で、肥沃で、水もあり温暖な関東平野に位置する。しかし、徳川家康が江戸に転封された1590年、当時の江戸は大湿地帯であった。1457年、太田道灌は、北への陸路の要衝・浅草と、水運における交通の要衝・品川の中間にある千代田に江戸城を築いたが、城下町とまでは到底なり得なかった。当時、利根川は東京湾に注いでおり、雨になれば江戸は一面水浸しになり、人を寄せつけない状況にあったからだ。
家康は決断する。利根川を東遷、水を太平洋に流し、湿原の関東を乾陸化することだ。そのために赤堀川の掘削を開始し、1621年、利根川と西の流域を結ぶ7間(13m)の赤堀川が開通、初めて利根川と太平洋がつながった。そして更なる拡幅工事を続け、1654年、家綱の時代に本格的に利根川は太平洋に注ぐことになったのだ。
あわせて家康は、利根川と結んでいた元荒川の締切りと荒川の西遷までも行っている。関東は湿地から農地へと姿を変えたが、江戸、東京にとって利根川、荒川との戦いはずっと続いた。荒川放水路はその凶暴な水との戦いの結実したものだ。
日本は洪水氾濫区域に50%の人口が住み、75%の資産のある国だ。こんな国は他にはない。治水とは水位を下げることに究極する。それは
(1)川幅を広げる
(2)川底を掘る
(3)放水路等、分流をつくる
(4)堤防を強化する(水位を相対的に下げる)
(5)ダムで貯める
(6)溢れさせるよう遊水池をつくる
――という手法しかない。その組み合わせだ。堤防を30cm上げるといっても何10kmにわたって、しかもノリ面までも拡幅することになる。スーパー堤防の進捗状況をみても不可能に近い話だ。
「八ッ場ダム」について、国交相の突然の中止声明に現地は怒り、利根川、荒川水系関係の各都県は手続きも含めて怒っている。当然のことだ。
多くの人が「八ッ場ダム」の視察に行っているが、本質的にはダム自体の問題ではない。もっと大事なことは、利根川水系全体のコントロールだ。その総合的な治水と利水対策のパーツの1つがダムであり、その沢山あるダムの1つが八ッ場ダムだ。
徳川家康以来400年、人々が苦難とのなかで悪戦苦闘してきた関東の治水・利水の戦い。その歴史と人々の苦闘、そして治水・利水の考えるべき視点をしっかりもつことが大事ではないのか。しかも、この20年、豪雨と旱魃がそれ以前とは大きく異なり、極端に拡大している。この異常気象を直視した治水・利水対策を冷静に考えなくてはならない。