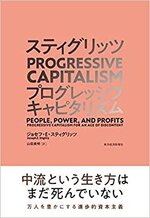 今年1月、コロナ禍の直前に出されたスティグリッツの警世の書。「万人に仕事やチャンスを提供する力強い経済を回復する」「万人にまともな生活、中流階級の生活を提供する進歩的資本主義」を熱く訴える。現在の「一部の勢力の豊かさ」ではない。「万人の豊かさ」であり、「分断なき世界」。そのためには政治を変えなければならない。「政治と経済を再建する」「ますます必要とされる政府」を志向せよ、という。その背景には、スティグリッツの「クリントン政権に参加してから25年がたったいま、私はこんなことを考えている。どうしてこうなってしまったのか? これからどうなるのか? この進路を変えるにはどうすればいいのか?・・・・・・少なくともその原因の一端は経済の失敗にある。製造業中心の経済からサービス業中心の経済への移行がうまくいかなかった。金融産業を制御できなかった。グローバル化やその影響を適切に管理できなかった。そして何よりも、格差の拡大に対応できなかった。その結果アメリカは『1パーセントの、1パーセントによる、1パーセントのための経済や民主主義』へと変わりつつある」という憂いと格闘がある。
今年1月、コロナ禍の直前に出されたスティグリッツの警世の書。「万人に仕事やチャンスを提供する力強い経済を回復する」「万人にまともな生活、中流階級の生活を提供する進歩的資本主義」を熱く訴える。現在の「一部の勢力の豊かさ」ではない。「万人の豊かさ」であり、「分断なき世界」。そのためには政治を変えなければならない。「政治と経済を再建する」「ますます必要とされる政府」を志向せよ、という。その背景には、スティグリッツの「クリントン政権に参加してから25年がたったいま、私はこんなことを考えている。どうしてこうなってしまったのか? これからどうなるのか? この進路を変えるにはどうすればいいのか?・・・・・・少なくともその原因の一端は経済の失敗にある。製造業中心の経済からサービス業中心の経済への移行がうまくいかなかった。金融産業を制御できなかった。グローバル化やその影響を適切に管理できなかった。そして何よりも、格差の拡大に対応できなかった。その結果アメリカは『1パーセントの、1パーセントによる、1パーセントのための経済や民主主義』へと変わりつつある」という憂いと格闘がある。
アメリカを始めとする先進国が陥っている病弊――。成長の鈍化、チャンスの減少、不安の高まり、格差の拡大、社会の分断・・・・・・。その脱出のために必要な肝心の政治が麻痺している。分断と差別、保護主義に走るトランプ政権には、"誤った減税政策""医療の弱体化"を含めてとりわけ厳しく否という。「トランポノミクスでは、富裕層への減税、金融の自由化、環境規制の撤廃が、移民排斥や保護貿易といった厳しく規制されたグローバル体制と、特異な形で結びついている」「格差が拡大した国では、経済が悪化する。成長を鈍化させる」「経済だけではなく、アメリカは人種、民族、性に基づく格差にも引き裂かれている。これらは容赦のない差別から生まれている」・・・・・・。「経済、医療、資産、チャンスの格差を見れば、"市場に任せる"というスローガンはもはや意味を成さない」というのだ。
「市場支配力は価格を上昇させ、賃金を低下させるなど、消費者や労働者を搾取する。イノベーションが市場支配力を生み出し、合併、買収などで支配力を増す。抑制が不可欠だ」「グローバル化によって国家は自らの首を絞めている。保護主義は問題の解決にならない。広い範囲で実り豊かな通商ができるグローバル化に修正する。これまでの強者に有利なものでない労働者や消費者、環境、経済を犠牲にしないルールだ」「市場の力だけでは対処できないことがある。環境保護、教育や研究やインフラへの投資、重大な社会的リスクに対する保険の提供などだ」「イノベーションは適切に管理されなければ、万人を豊かにするどころか、全く逆の効果をもたらす。最も重要なのは完全雇用の維持。金融政策でそれが実現できなければ、財政政策(減税や支出の増加、公共投資を増やす)を利用。どちらの政策も総需要を刺激し、完全雇用に戻る」「財政政策の効果が大きい分野が、インフラである。インフラへの投資はここ数年にわたり不足している」「新たなテクノロジーは、プライバシーやサイバーセキュリティの問題など、新たな課題も生み出す。市場に任せておけないことだけははっきりしている」・・・・・・。まさに一致して行動する共同行動が必要だ。競争が活発で、公正で活力のある経済実現のために、民主主義の再建、政府の役割が重要な手段となるというのだ。
20世紀の工業中心の経済から、21世紀の環境に配慮したサービスやイノベーション中心の経済へどう移行したらいいのか――。環境に優しい経済、高齢者・医療・介護など社会保障の向上、教育、住宅、インフラ、社会的公正を推進していく政策だ。成長と生産性の鈍化に対しては、「労働力の増加(女性・高齢者・移民)」「生産性の向上(市場支配力=独占は経済をゆがめ、インフラへの投資不足がある。学習する社会が大切。科学やテクノロジーに投資)」「社会的公正(機会均等、差別をなくす、世代間平等=政府赤字はまずい)」・・・・・・。そして「私が提案した政策を採用すれば、アメリカ国民全員が、選択、自己責任、自由、平等、道徳的価値観というアメリカの価値観と一致する望ましい生活を実現できる」「ぜひとも成し遂げる必要がある」と強く提言する。
8日、北区立神谷中学校に行き、現在、国で進めている「GIGAスクール構想」の取組み状況を視察しました。これには、浮島とも子衆院議員、岡本三成衆院議員、花川與惣太北区長、文部科学省、北区教育委員会、北区議会議員らが参加しました。
各教室では、学習ソフトを利用した「スタディサプリ」が行われていて、生徒一人一人がタブレットを使って、それぞれが授業のアプリケーションを通して、学習をしており、「わかりやすい」と好評でした。科目や学習内容は、生徒自らが選んで自分のペースで学習していて、ソサエティ5.0時代に相応しい新しい授業の形が始まってきていることを実感しました。
そのあと、意見交換会を行い、北区からは、GIGAスクール構想実現に向けた取り組みについて説明がありました。特に、1人1台端末の対応においては、ランニングコストと教員への技術支援など、地方自治体に直接係る問題についての意見・要望が出されました。
私は、アフター・コロナ社会の劇的に変化する社会環境のもとで、IT教育、GIGAスクール構想等を具体的に進めていくことの大切さについて述べました。
 データの争奪戦、データ・テクノロジーの活用いかんで企業も国も浮沈が決まる。GAFA対BATは今、米国の「FAANG+M(フェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグル、マイクロソフト)」と中国の「BATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)」の戦いとなっている。2020年代のテクノロジーの構図は「データの高速化・大容量を実現する5G、データの保存・処理能力を飛躍的に伸ばすクラウド、それらのデータを使って高度な判断を行うAI。この3つのメガテクノロジーを組み合わせることで形成される三角形=トライアングルの力が、次代の産業・社会・国家を大きく変える原動力となる」ということだ。その中心はAIであり、このトライアングルを基軸に、自動運転やスマートホーム、ヘルスケア、ロボティクスをはじめ全方位で新たな世界が開かれる。加えて4つめの軸としてブロックチェーンが登場し、データや情報がより効率化・民主化されていく。
データの争奪戦、データ・テクノロジーの活用いかんで企業も国も浮沈が決まる。GAFA対BATは今、米国の「FAANG+M(フェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグル、マイクロソフト)」と中国の「BATH(バイドゥ、アリババ、テンセント、ファーウェイ)」の戦いとなっている。2020年代のテクノロジーの構図は「データの高速化・大容量を実現する5G、データの保存・処理能力を飛躍的に伸ばすクラウド、それらのデータを使って高度な判断を行うAI。この3つのメガテクノロジーを組み合わせることで形成される三角形=トライアングルの力が、次代の産業・社会・国家を大きく変える原動力となる」ということだ。その中心はAIであり、このトライアングルを基軸に、自動運転やスマートホーム、ヘルスケア、ロボティクスをはじめ全方位で新たな世界が開かれる。加えて4つめの軸としてブロックチェーンが登場し、データや情報がより効率化・民主化されていく。
「AIのインパクトは、良質のアルゴリズムとデータ量の掛け算で決まる。東京圏のデータ量は世界でも最高水準にある。本気でAIのアルゴリズム開発に取り組めば、世界のAIテクノロジーをリードする存在になり、日本のAIビジネスが再生する可能性は十二分にある」という。AIを中軸とし、5G・クラウド・ブロックチェーンの基礎的考え方と世界の現状、志向している激流の未来を解説する。そして、「貪欲に海外から学び、取り込み、行動しよう」と強く言う。





