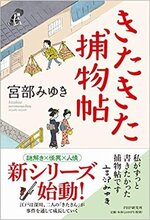 宮部みゆきの新シリーズ始動! 「私がずっと書きたかった捕物帖です」という。主人公・北一(きたいち)は16歳。迷子だった北一を深川元町の岡っ引き、文庫屋の千吉親分が引き取って育ててくれた。ところが突然、千吉親分がふぐに中毒(あた)って死ぬ。時は江戸時代。小説の主役は武士ではない。江戸の町、長屋暮らし、商家の人々の日常に潜む事件や怪談話、呪いや噂、生老病死などが、知恵と情あふれる解決策で結着をみせる。
宮部みゆきの新シリーズ始動! 「私がずっと書きたかった捕物帖です」という。主人公・北一(きたいち)は16歳。迷子だった北一を深川元町の岡っ引き、文庫屋の千吉親分が引き取って育ててくれた。ところが突然、千吉親分がふぐに中毒(あた)って死ぬ。時は江戸時代。小説の主役は武士ではない。江戸の町、長屋暮らし、商家の人々の日常に潜む事件や怪談話、呪いや噂、生老病死などが、知恵と情あふれる解決策で結着をみせる。
「ふぐと福笑い」――。福富屋の遠縁の材木屋に代々伝わっている「呪いの福笑い」。出して遊ぶと必ず祟るというが、知らずに子どもたちが遊んでしまう。どう収めるか。千吉親分に連れ添った「おかみさん(目が見えない)」の凄さ、賢さ、千里眼が発揮される。「双六神隠し」――。裏店暮らしの松吉、魚屋の倅の丸助、商家の跡目の仙太郎の3人は同じ手習所に通っていたが、松吉がある日"神隠し"にあう。3人が打った"閻魔の双六"の一芝居。北一の勘は冴えを見せる。「おかみさん」の鋭さや町の人々の情が滲み出る。
「だんまり用心棒」――。菓子屋「稲田屋」の道楽息子に、富勘が鮮やかな大芝居で鉄槌を下す。しかし、意趣返しなのか、その富勘が攫われた。釜焚きの喜多次の働きによって北一は富勘を助け出す。二人の「きたさん」の誕生、「きたきた捕物帖」が始動する。「冥土の花嫁」――。深川佐賀町の味噌問屋「いわい屋」の跡取り万太郎が嫁を迎えることになった。その祝言を挙げる日、突然、万太郎の先妻・菊と名乗る女が現われる。この大騙りを仕掛けてきた悪人たちをやっつける。
優しさと人情、それに「北一」の成長が加わる物語。
 「人生100年時代の『お金の長寿術』」が副題。「儲け」ようとする資産の運用術ではない。堅実に何が資産かを冷静に考え資産を長寿化させる「診断・把握・処方」の具体的な方法を示す。「健康寿命」と「資産寿命」が人生100年時代では大事なのだという。
「人生100年時代の『お金の長寿術』」が副題。「儲け」ようとする資産の運用術ではない。堅実に何が資産かを冷静に考え資産を長寿化させる「診断・把握・処方」の具体的な方法を示す。「健康寿命」と「資産寿命」が人生100年時代では大事なのだという。
フツーのサラリーマンは「延ばすも何も資産なんて持ってない」と思いがちだがそうではない。「最も大きな金融資産は『公的年金』」「老後生活のお金のやりくりの理想は、①日々の生活は公的年金で②趣味や楽しみのための費用は働いて得る収入やそれを貯めた資金で③退職金や自分の保有する金融資産はできるだけ取り崩さず将来に備える――の3つ」「投資で儲けようとしない。投資の前に①働いて収入を得る②年金の受け取り方を考える③支出をきちんと管理する――の3つが大切」「サラリーマンで資産家になった人に共通するのは、収入以上にお金を使わなかった人(支出の管理)」「過剰な保険とローンは人生の支出で最大のムダ」「支出管理で大事なのはサンカク(義理・見栄・恥の3つを欠くこと)」「年金は貯蓄ではなく保険だ(保険は不測に備えるもの――不測は①長生き②病気、ケガ③自分が死んだ時の家族)」「年金は破綻しない。積立金(H30年3月末、198兆円)やマクロ経済スライド、所得代替率の意味」「投資は楽をして儲かるわけではない」「投資で絶対正しいのは、①先のことは誰もわからない②世の中にうまい話はない――の2つ」「制度を活用した資産運用――iDeCo。つみたてNISA」・・・・・・。
「資産寿命を延ばすことは必ずしも投資することだけではない。投資に頼り過ぎるのは良くない」ということがよくわかる。資産運用ビジネスを仕事にしてきた大江さんのアドバイスは、冷静で常識的で賢くて手堅い。
20日、住宅生産団体連合会との政策懇談会に出席しました。新型コロナウィルスは、住宅業界にも多大な影響を及ぼしています。住団連からは「住宅市場は、消費税率引き上げ後の低迷から回復できないうちに、新型コロナウィルスによる消費マインドが低下し、消費需要は極度に落ち込んでいる。特に、ゴールデンウイーク中に住宅展示場が閉鎖したことによる新規顧客の激減や、中小工務店への影響がある」などと、住宅産業の窮状が述べられました。景気に大きな波及効果のある住宅業界だけに影響は深刻です。
私は「"3LDKT"(TはTelework)と言われたり、オフィスビル需要の変化など、コロナウィルスの影響により、住宅に対する消費者ニーズが大きく変化している。こうした新しい住宅環境の動向、マインドをよくウォッチし、新しい生活様式に対応した施策を考えなくてはならない」と挨拶しました。
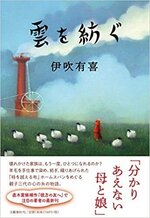 「お父さんは小さい頃、羊毛は雲みたいだと思った。・・・・・・そこに飛び込むと雲のなかにいるようで。うちの仕事は雲を紡ぐことだって思っていた」――。登校できなくなった高校生の山崎美緒。母・真紀も父・広志も悩みをかかえ、家族全体が心が通じ合わず、崩れかけていた。思い余って美緒は盛岡の祖父・紘治郎の所へ駆け込む。大正期の民藝運動の流れを汲み、ホームスパンを織っている山崎工藝社。工房に触れるなかで、美緒は自分を取り戻し、訪ねてきた父と久し振りに父娘の会話ができたのだ。
「お父さんは小さい頃、羊毛は雲みたいだと思った。・・・・・・そこに飛び込むと雲のなかにいるようで。うちの仕事は雲を紡ぐことだって思っていた」――。登校できなくなった高校生の山崎美緒。母・真紀も父・広志も悩みをかかえ、家族全体が心が通じ合わず、崩れかけていた。思い余って美緒は盛岡の祖父・紘治郎の所へ駆け込む。大正期の民藝運動の流れを汲み、ホームスパンを織っている山崎工藝社。工房に触れるなかで、美緒は自分を取り戻し、訪ねてきた父と久し振りに父娘の会話ができたのだ。
しかし、母娘の間はうまくいかない。美緒も自分自身に"信"がたち上がってこない。仕事でも追い詰められた母・真紀は「涙を売りにして。どうしてあなたはいつも女を売りにするの」と罵倒してしまう。分かりあえない母と娘、それぞれの思いが業のようにスレ違う。父・広志も会社が売却されようとし、「俺も本当に疲れた」と家庭崩壊の危機を迎える。
祖父・紘治郎もかつて同じ道に進んだ妻・香代と別れた。その妻が死に、苦悩を心にため込み、乗り越えてきた。この「おじいちゃん」の語る言葉は明らかに"境地"に達した者の言だ。壊れかけた家族が美緒を中心に、ホームスパンの糸が心の糸となって紡がれていく。
 18日、北区志茂にある国土交通省荒川河川下流工事事務所で行われた「第22回日本水大賞」の表彰式に参加し挨拶しました。
18日、北区志茂にある国土交通省荒川河川下流工事事務所で行われた「第22回日本水大賞」の表彰式に参加し挨拶しました。
これは、「北区・子どもの水辺協議会(石渡良憲代表)」や「北区水辺の会(柳澤耕太郎代表、太田桐正吾参与)」が長年取り組んできた荒川下流・岩淵のワンド(本流とつながり池のようになっている地形の場所)の整備・保全・活用の取り組みが高く評価され、日本水大賞の「審査員特別賞」を受賞となったもの。
「日本水大賞」は、日頃から健全な水循環のために活動している団体、学校、企業を表彰するものです。本来は、国全体として盛大に行われる表彰式ですが、新型コロナウイルスの影響の為、規模を縮小して各部門ごとの表彰式となりました。
平成13年に市民による「北区水辺の会」が設立され、 私もワンド(大池・小池)のスタート時から何度も足を運んできました。協議会の底泥改善作業や清掃などの大変な活動が続けられ、近隣の小学校の魚とり総合学習、区民の水辺交流、中央大学の水質調査などのフィールドワーク活動、国・区・市民の協働による水辺の生物などの視察会などが広範に行われています。この日の受賞式で私は、整備活動をしてきた協議会の方々への感謝を述べるとともに、豪雨が多いなか、「防災・減災」「水辺空間の共生」「水との交わり」の大切さを短く話しました。見えない所で黙々と頑張って下さっている協議会等の皆様、本当に有難うございます。




