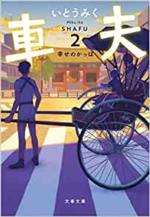 浅草を走る人力車。主人公・吉瀬走は、両親が出奔、家庭が崩壊して高校を中退、陸上部の先輩・前平に誘われて車夫となった。その「力車屋」には、離婚して大手商社まで辞めた山上や羽柴、親方の神谷力、女将の琳子など、不本意な出来事を抱えながらも明るく生きる仲間がいた。たまたまではあっても、客として来る人々の人生模様に触れ、吉瀬走はその思いを乗せて伴走することになる。「車夫ってのはさ、人を笑顔にできる商売なんだよ。それってすげーだろ」・・・・・・。いい話がいくつも続く。温かくさわやかな風を受けて走るような作品。
浅草を走る人力車。主人公・吉瀬走は、両親が出奔、家庭が崩壊して高校を中退、陸上部の先輩・前平に誘われて車夫となった。その「力車屋」には、離婚して大手商社まで辞めた山上や羽柴、親方の神谷力、女将の琳子など、不本意な出来事を抱えながらも明るく生きる仲間がいた。たまたまではあっても、客として来る人々の人生模様に触れ、吉瀬走はその思いを乗せて伴走することになる。「車夫ってのはさ、人を笑顔にできる商売なんだよ。それってすげーだろ」・・・・・・。いい話がいくつも続く。温かくさわやかな風を受けて走るような作品。
「つなぐもの 遠間直也」――陸上部を突然やめて去っていった走に対して、「なぜ」との思いを引き摺る仲間。「ストーカーはお断りします 吉瀬走」――走を指名する一途な女性客・香坂まり子。「幸せのかっぱ 山上洋司」――山上の離婚(あなたは、あたしのことをなにも見ていなかったの。ね、あたしの好きな色知ってる?)。「願いごと 成見信忠」――余命半年といわれた妻が人力車に乗りたいという。信忠は、大事な存在がそばにいたことに初めて気付くのだ。「やっかいな人 悠木乃亜」――父の再婚に複雑な感情を抱く走と同年代の娘・乃亜。「ハッピーバースデー 吉瀬走」――行方不明だった母親が体調を崩したという手紙が突然届く。走は母に会うかどうか迷う。母が「高校をやめたと知って、取り返しのつかないことをした」と思っていることを知る走。「なくしたものはいっぱいある。高校も好きな陸上も、大学も、いるはずだった人がいなくなり自分の夢も未来も。自分のことなのに、自分ではどうにもできなかった。子どもだったから」・・・・・・。だがもう子どもに止(とど)まらない。「本当に叶えたいことは、ほしいものは、自分で、自分の手と足でつかみたい」と走は思うのだ。
解説を書いた中江有里さんは「どれだけ年を重ねても、人は子どもの自分をどこかに持ち続けて、共存しているのだと思う。走の姿を追いながら、自分の中の子どもの部分が何度も疼いた」という。
25日(火)、豊島区上池袋の「上池袋防災備蓄倉庫」と、東池袋の造幣局跡地「としまみどりの防災公園(IKE・SUNPARK)」を視察しました。これには、岡本三成衆院議員、長橋けいいち都議会議員、豊島区公明党区議団が参加しました。
まず、上池袋防災備蓄倉庫を視察。区内にある防災備蓄倉庫では7か所目ですが、最大規模のもので、救援センターと合わせて水と食料が3日分確保されます。災害時に大きな力となることは間違いありません。公明党が設置を強く要望してきたものです。豊島区では、すべての区立小中学校や豊島体育館、南長崎スポーツ公園など35か所が救援センターとなっています。また、2016年熊本地震の「ラストワンマイル」を教訓とし、区内8か所の各地域拠点に2tトラックを配備し、すぐに出動できる体制となっています。
続いて、「としまみどりの防災公園」に行き、公園設備や深井戸(震災対策用水利)を視察しました。災害時にこの地域に来た人を守るために、放水設備は25メートル以上広範囲に届くという力のあるもので、防災拠点を守ります。
首都直下地震をはじめとする災害への備えに万全を期します。
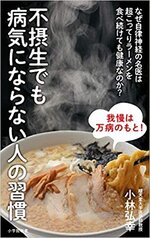 「なぜ自律神経の名医は超こってりラーメンを食べ続けても健康なのか?」という副題が付いているが、それは「正しいリカバリーの方法」を知っているから。自律神経は「交感神経」と「副交感神経」から成るが、両者がバランスの良い状態にあることが大切。「深酒をした翌朝のリカバリー」「怒った後のリカバリー」「余裕をもって何事も生きる」「許す解決法(ゆったりとした気持ち)」「自律神経や腸を整える」などのヘルス・リテラシーを具体的に示す。
「なぜ自律神経の名医は超こってりラーメンを食べ続けても健康なのか?」という副題が付いているが、それは「正しいリカバリーの方法」を知っているから。自律神経は「交感神経」と「副交感神経」から成るが、両者がバランスの良い状態にあることが大切。「深酒をした翌朝のリカバリー」「怒った後のリカバリー」「余裕をもって何事も生きる」「許す解決法(ゆったりとした気持ち)」「自律神経や腸を整える」などのヘルス・リテラシーを具体的に示す。
「朝食は自律神経にとって重要。まず起き抜け一杯の水(胃腸が刺激され、自律神経がオンモード)。バナナ一本(カロリーと食物繊維)。リラックス効果のある副交感神経が高まり、血流も良くなる」「理不尽に叱られるなどの対人ストレス――怒りは自律神経を乱す。反論せず、深呼吸」「精神的ストレス、メンタルヘルスの不調――便秘や下痢の腸内環境を変える。発酵食品と食物繊維(ヨーグルト、納豆、海藻や野菜・果物)」「運動不足は筋肉の硬直・うっ血を起こす。適度なウォーキング。夜ゆっくり歩く」「肉好きな人に長寿が多い。動物性食品の良質なタンパク質が自律神経の働きを高めている。その脂肪対策に野菜・果物・ナッツを」「飲酒・深酒は、肝臓の分解・解毒プロセスで水分が消費されて、脱水が進む。お酒1杯に水も1杯を」「焦りや緊張で自律神経は乱れる。30分前行動、時間的余裕を」「夫婦喧嘩には、沈黙や階段の上り下り、とくに皿洗いを」「休日も平日と同じように起床から1日の基本ペースを崩さない」「運動不足には1分間ストレッチを」「ぬるめのお湯でゆっくりあたたまる」・・・・・・。
 コロナ禍で、企業ではテレワーク、学校はGIGAスクール、日常の買い物等でもオンラインが急速度に進む。一方、若者の「活字離れ」や幼児的・情緒的言葉が蔓延し、中・高校生が教科書等の問いがわからないという「読解力」不足が指摘されている。「デジタル文化は『読む脳(読字脳)』をどう変えるのか」「『深い読み』は絶滅寸前?」「紙の本は『深く読む脳』を育む」「デジタルで読む脳は、連続で飛ばし読みになり、短絡的で真の理解ができない」・・・・・・。著者は読む脳(読字脳)の研究者として国際的に知られ、古今東西の哲学者・教育者・文学者・研究者と交わり行動している神経科学者だ。「紙の本などの印刷媒体からデジタル媒体へ」という劇的変化のなか、「紙とデジタルでは、読む脳の回路にどんな変化を及ぼすか」という根源的かつ重要な問題に真っ向から挑み、提示する。
コロナ禍で、企業ではテレワーク、学校はGIGAスクール、日常の買い物等でもオンラインが急速度に進む。一方、若者の「活字離れ」や幼児的・情緒的言葉が蔓延し、中・高校生が教科書等の問いがわからないという「読解力」不足が指摘されている。「デジタル文化は『読む脳(読字脳)』をどう変えるのか」「『深い読み』は絶滅寸前?」「紙の本は『深く読む脳』を育む」「デジタルで読む脳は、連続で飛ばし読みになり、短絡的で真の理解ができない」・・・・・・。著者は読む脳(読字脳)の研究者として国際的に知られ、古今東西の哲学者・教育者・文学者・研究者と交わり行動している神経科学者だ。「紙の本などの印刷媒体からデジタル媒体へ」という劇的変化のなか、「紙とデジタルでは、読む脳の回路にどんな変化を及ぼすか」という根源的かつ重要な問題に真っ向から挑み、提示する。
人間には、文字を読むための遺伝子が備わっていない。遺伝子でプログラムされている見る・聞く・話す・嗅ぐ等とは全く異なり、年代に合わせた大人・親からの忍耐強い文字教育があって「読む脳」の回路が育っていく。著者は「紙の本を『深く読む』ことの重要性」を指摘する。脳内に、文字・音・意味を結びつける複合的な神経回路を成長させる不断の努力が、とくに初等教育で重要となる。「深い読み」の回路が形成されるのは何年もかかる。しかし、「感じられる思考、イメージをつくる能力(俳句でも)」「共感――他者の視点を得る」「会わなくても他者とコミュニケーションを実らせる」「他人の人生に入り、自分の人生に持ち込む」「孤独を脱する」「他者の生活や気持ちに入り込む認知忍耐力をもつ(今の若者は同類でない人々への共感を失い、攻撃的、不寛容になる――トランプやメディア)」「過去の思い込みを忘れて、別の人、別の地域と文化と時代に対する知的理解を深め、高慢と偏見を消す」「推測、推論、思考と共感の基礎をつくる――フェイクニュースの犠牲を避ける」「文字から情報を取り込み、批判的結論を得て、未知の認識空間へと飛び込み、新しい世界へと開示する」――。熟慮、洞察の世界であり、物事の本質を見ることで、「読字脳」から進んだ到達点が「他者に共感したうえで自分の思想を築く『深く読む脳』」だ。それはゆっくり時間をかけて考える「紙の本を読む」ことで育まれる。他者を知り自己を磨く読書の意義だ。
一方、デジタル媒体は速読になり、「iPadは新手のおしゃぶり」で、どうも「恒常的注意分散」になるという。自ら考えず過多な情報を、最も速く、最も簡単に処理する。「斜め読み」で「目がF字やジグザグに動く」「文章全体ですばやくキーワードを拾い、最後の結論に突進する」「O・ヘンリーの小説の夫婦の"懐中時計と髪"のような情感は画面読みはわからなくなる」ようだ。また「自分が時間と空間のどこにいるかわからず"世界で道に迷う"」「キーワードを拾って斜め読みする21世紀の読み手は、意図的に配列された言葉と考えの美しさを見逃していること自体に気づかない」。そして「言語力と思考力が衰えるとき、複雑な社会を単純に幼稚な自己中心主義で断じてしまうことになる」と危惧する。ツイッターで育った若い世代は、難解な文構造や比喩には苦労し、離れていく。書くことも劣化し、難しい散文にはなじみが薄くなり「認知忍耐力」「認知的持久力」を獲得できないことになる。
しかし、デジタル化は更に進み後戻りはできない。本書では「2歳になる前」「2歳から5歳」「5歳から10歳まで」の段階に、「どう読むか」について詳細に、実践的に述べている。そして「読み書き能力ベースの回路」と「デジタルベースの回路」の両方の限界と可能性を理解し、「バイリテラシー読字脳の育成」を提唱する。バイリンガル学習者の育て方と同じ基盤だ。デジタル力も読み書き力と同様に上手く育てる。「デジタル媒体と紙媒体双方で、"深い読み"のできる"二重に読むバイリテラシー読字脳"を育む」「子供の時に多くの本に親しみ、デジタル媒体は意識的に注意深く読む習慣をつけ、それを続けて文章を分析・批判できる『バイリテラシー脳』を育む」ことを提唱する。「デジタルで読む脳×紙で本を読む脳」の「×」は掛け算。







