2日(水)、公明党の文化芸術振興会議 (議長=浮島智子衆院議員)が行われ参加しました。これには、文化・芸術関係から、日本芸能実演家団体協議会、緊急事態舞台芸術ネットワーク(東宝、劇団四季など)、日本歌手協会、日本バレエ団連盟、演劇緊急支援プロジェクトなど11団体が参加し、党から高木陽介衆院議員(文化芸術振興会議顧問)をはじめ、多くの衆院・参院議員が参加しました。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、現在、多くの文化芸術公演が中止、延期に追い込まれ、文化・芸術関係者は大変厳しい状況にあります。6月の第二次補正予算では文化・芸術関係者と意見交換し、560億円の支援を決めています。今回はその支援の現状、さらに来年度予算への要望を聞きました。
文化・芸術支援に力を注ぎます。
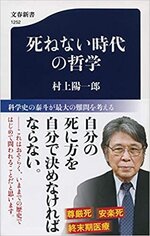 人生100年時代――それは、細菌やウイルスの攻撃によって「理不尽に」命を奪われる時代から脱し、老化によるさまざまな機能の劣化によって「必然的な、あるいは自然な死」を迎えるという流れにたどり着いた今の状況だ。しかし、私たちは「なかなか死ねない」時代に直面しているともいえる訳だ。歴史上はじめて、一人ひとりが自分の人生の終わり方を考えざるを得なくなったことでもある。科学哲学者・村上陽一郎氏が、「死」というものを考える道筋を示してくれている。生老病死、科学・哲学の世界を深く考えさせる必要不可欠、納得の書だ。
人生100年時代――それは、細菌やウイルスの攻撃によって「理不尽に」命を奪われる時代から脱し、老化によるさまざまな機能の劣化によって「必然的な、あるいは自然な死」を迎えるという流れにたどり着いた今の状況だ。しかし、私たちは「なかなか死ねない」時代に直面しているともいえる訳だ。歴史上はじめて、一人ひとりが自分の人生の終わり方を考えざるを得なくなったことでもある。科学哲学者・村上陽一郎氏が、「死」というものを考える道筋を示してくれている。生老病死、科学・哲学の世界を深く考えさせる必要不可欠、納得の書だ。
そこで立ち現れてくるのが永遠の難問である「死」をどう考え、どう迎えるのか。死は自己決定できるか。死生観、安楽死、尊厳死、終末期医療等々の問題だ。21世紀に入り、安楽死をめぐる世界の状況は大きく変わってきた。世界各国で安楽死、もしくは医師による自死支援(PAD)が認められるようになってきているという。安楽死は、医師が直接、死ぬための薬を投与する行為、PADは、死を希望する終末期の患者が、医師から死ぬための薬物、方法を与えられ、それを使って自ら死ぬこと。これを「積極的安楽死」と呼ぶ。一方で、延命治療を患者の意志で中止するのが「消極的安楽死」で、日本ではこれを一般的に「尊厳死」と呼ぶ。オランダ、カナダ、コロンビア等でPADと安楽死がこの20年程で認められ、1975年の「カレン事件」を受けアメリカでは「尊厳死」が容認され、アジアでも韓国と台湾で「尊厳死」(延命治療の中止)を認める法律が近年施行されているという。
しかし、これが"時流"などという軽いものではなく、「死は自己決定できるか」「安楽死の要件」という最大の哲学的・科学的問題に直面していることを語るのが、本書の凄い所。患者自身、医師の覚悟、死の関係者への広がりを含めて哲学、倫理と生死の現実の葛藤が濃密に語られる。思索の深さが心に浸透してくる。「死を避ける方法がなく、死期も間近い。患者に耐え難い、見るに忍びないほどの肉体的苦痛がある」――。医療現場、司法等々、ギリギリの模索がこの50年、世界で続けられている。「米のカレン事件(1975年)」「米の医師キヴォキアンの点滴タナトロン(1987年)」「オランダのポストマ事件(1971年)」「名古屋安楽死事件と司法の安楽死要件(1962年)」「東海大安楽死事件(1991年)」「川崎協同病院事件(1998年)」「7人の終末期患者が生命維持装置を外され死亡した富山県の射水市民病院の事件(2006年)」・・・・・・。法制化はこのデリケートな問題については難しい。「オランダ等のようには法的に安楽死を認める方向には、日本社会は進まないだろう」「私はあくまでも原則としてですが、PADや安楽死は常に否定されるべきものではない、という個人的な意見を持っている」という。なだいなださんは「法律になじまない問題だと考えてきた。安楽死が法的に認められてしまうと、権利や義務の意識でこの問題に対処するようになるのではないか、と危惧する」といっており「私も全く賛成です」と村上さんはいう。自己決定については、「本人の意志は欠かすことのできない必要案件であるが、十分案件とは言えない。本人はそう考えているけど、どうしましょうか、という所から初めて議論が始まる。・・・・・・自己決定の原理そのものが最大限尊重されるべきであることに異論は少ないでしょう。ただしその中に死も含まれるか、ということになると、人それぞれ思いは違ってくるはず」ともいう。「自分の運命は自分のもの」という考え方について、また「自己決定と自己決定権の違い」についても述べる。生命倫理学者の小松美彦氏の著書「『自己決定権』という罠」の「死は関係のなかで成立し、関係のなかでしか成立しない事柄なのだから、人は死を権利として所有も処分もできない」を引きつつ、「自分の人生ですから、それをどうするかについて、刻々自己決定を迫られる。けれどもそれは、権利として、その人の生あるいは死を覆うわけではない、という彼の主張にはうなずかされるところがある」という。さらに「安楽死で逝きたい」「周りの人に迷惑をかけたくない」という思いが、その時の自己決定であっても、「人間の意志は変わりうる」ことも事実だ。この長寿社会、死ねない時代、そして安楽死や尊厳死、終末期鎮静、自己決定、個人主義と民主主義社会の問題は、現前する難問であるが、その問題の提起する深さを剔抉している。
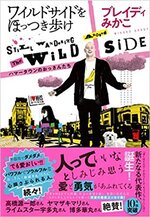 「ハマータウンのおっさんたち」が副題。「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」では息子さんたち、フレッシュな少年たちの生きいきとした日常を描いたブレイディみかこさん。今度は、「人生の苦汁をたっぷり吸い過ぎてメンマのようになったおっさんたち」の日常、喜怒哀楽の日々を描く。英国の国民がいかにEU離脱(ブレグジット)の国民投票で揺れ動いたかが、くっきりと浮かび上がる。とくに「労働者階級のおっさん」の日常は激震に見舞われている。EU離脱派として「EUなんぞの言うなりになってグローバル資本主義を進めた政府がロンドンを外国人に明け渡した。俺らの国の主権はどうなってんだ」「移民が増えすぎて学校や病院がパンクしそうになっている」「英国は移民をコントロールできる主権を取り戻すべきだ」「2010年からの保守党の緊縮財政が、病院、学校、福祉、地域の図書館まで切り捨ててきた。経済成長のよき時代の若者だった"おじさん"たちが追い詰められている」「NHS(国民保険サービス)はもう福祉国家だった頃の英国の医療制度ではない。いまや福祉国家の縮小を体現しているのがNHSだが、英国の人々はNHSに執念にも似たほどの愛着をもっている。俺たちのNHSだ」「ブレグジットすればEUへの拠出金週3.5億万ポンド(約500億円)をNHSの資金として使える、という離脱派の流したデマが離脱派勝利の決定的な要因の一つになった」「俺はサッチャーにもグローバル資本主義にも負けたくねえし、加担したくもねえ」「ハマータウンのおっさん世代は今、社会に対して最後の抵抗をしているのかもしれない」・・・・・・。
「ハマータウンのおっさんたち」が副題。「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」では息子さんたち、フレッシュな少年たちの生きいきとした日常を描いたブレイディみかこさん。今度は、「人生の苦汁をたっぷり吸い過ぎてメンマのようになったおっさんたち」の日常、喜怒哀楽の日々を描く。英国の国民がいかにEU離脱(ブレグジット)の国民投票で揺れ動いたかが、くっきりと浮かび上がる。とくに「労働者階級のおっさん」の日常は激震に見舞われている。EU離脱派として「EUなんぞの言うなりになってグローバル資本主義を進めた政府がロンドンを外国人に明け渡した。俺らの国の主権はどうなってんだ」「移民が増えすぎて学校や病院がパンクしそうになっている」「英国は移民をコントロールできる主権を取り戻すべきだ」「2010年からの保守党の緊縮財政が、病院、学校、福祉、地域の図書館まで切り捨ててきた。経済成長のよき時代の若者だった"おじさん"たちが追い詰められている」「NHS(国民保険サービス)はもう福祉国家だった頃の英国の医療制度ではない。いまや福祉国家の縮小を体現しているのがNHSだが、英国の人々はNHSに執念にも似たほどの愛着をもっている。俺たちのNHSだ」「ブレグジットすればEUへの拠出金週3.5億万ポンド(約500億円)をNHSの資金として使える、という離脱派の流したデマが離脱派勝利の決定的な要因の一つになった」「俺はサッチャーにもグローバル資本主義にも負けたくねえし、加担したくもねえ」「ハマータウンのおっさん世代は今、社会に対して最後の抵抗をしているのかもしれない」・・・・・・。
英国のベビー・ブーマー世代(1946~1964)の"おっさん"は、「ブレグジット」「緊縮財政」「世代、階級の意識の違い」「社会の変容」のなかで、家庭、恋と離婚、仕事、趣味、社会等のあらゆる場面で右往左往させられているが、ブレイディみかこさんの描く"おっさん"は、たくましくて魅力にあふれている。愛すべき"おっさん"たちだ。
27日(木)、豊島区内にある西巣鴨橋の架け替えに伴う工事について進捗状況を視察しました。
私の地元では、山手線、湘南新宿ライン、埼京線、京浜東北線、高崎線、都電荒川線、都営地下鉄三田線、東京メトロ南北線、都営日暮里・舎人ライナーなど多くの鉄道が走っています。とくに北区は"鉄道の町"でもあります。線路に架かる橋梁は、建設から数十年経過しており、老朽化による安全性の低下が懸念され、対策が必要です。
西巣鴨橋もその一つ。国道254号線(春日通り)と都道(宮中公園通り)とを結ぶ西巣鴨橋は、昭和34年に架設され今年で61年。現在、架け替えに伴う工事が始まっており、予定では撤去が2022年3月までかかり、橋の完成は2025年をめざしています。
橋梁の老朽化対策が大事になります。さらに力を注いでいきます。






