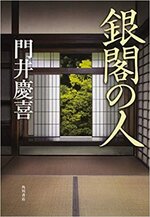 室町幕府第8代将軍の足利義政――。1435年に生まれ、1490年に没す。応仁の乱(1467年~1478年)のさなか、「わび」「さび」の美を体現する建築を構想し、東山殿・慈照寺銀閣を建てた。在職24年、妻は日野富子。息子は第9代将軍・義尚で、富子が溺愛し、なんと将軍就任の9歳から酒におぼれ、義政に先立ち25歳で病死した。後継者争いに執念を燃やした富子にとって、義尚の孤独な死は大きな誤算だった。
室町幕府第8代将軍の足利義政――。1435年に生まれ、1490年に没す。応仁の乱(1467年~1478年)のさなか、「わび」「さび」の美を体現する建築を構想し、東山殿・慈照寺銀閣を建てた。在職24年、妻は日野富子。息子は第9代将軍・義尚で、富子が溺愛し、なんと将軍就任の9歳から酒におぼれ、義政に先立ち25歳で病死した。後継者争いに執念を燃やした富子にとって、義尚の孤独な死は大きな誤算だった。
すでに幕府の力は衰えていた。それを象徴するかのように義政の父・義教は義満の実子だが、なんと"くじ引き"で選ばれ第6代将軍となった。しかし傀儡に徹するどころか逆に「政治への野心は無限」であり、大名討伐を企て行動したが、最終的には赤松満祐によって殺害される。その"血の海"に6歳の三春(義政)は居合わせ恐怖した。乳母"おいま"に抱きしめられる。
"下剋上"の権力闘争が繰り広げられ、幕府の力は更に落ちる。その政治に関与したのは富子であり、義政は政治に背を向け、己の美意識を「わび」「さび」の文化の極致・慈照寺銀閣、その東求堂に今も残る部屋「同仁斎」に凝縮していく。お互い別の者を後継者にしようと応仁の乱まで起こした義政と富子の夫婦――二人の愛憎は激しく、義政は政治とも距離を置いて銭もない。孤独な将軍義政は、「"充足の美"ではなく"不足の美"」「政事より文事」「『わび』(侘び)どころか、その先の『さび』(錆び)へ」「四畳半における世界との交歓、世界と個人の対等な屹立」「孤独の空間における世界との対峙」「金をかけて地味をつくる」「閑静枯淡」への道を突き進んだ。義政の死後、下剋上の暴風は日本を覆い、将軍も"流れ公方"となり、大名同士の戦争に巻き込まれていく。
めまぐるしく動く、室町のど真ん中、義政と富子とその子・義尚の心の底を剔り出し、その後の日本文化に大きな影響を与えた源流「銀閣」をあわせて鮮やかに描いた作品。公明新聞に連載して好評を博した。
免震・制振技術の飛躍的向上のために「実大免震試験機」の導入を――。30日、国会内で「実大免震試験機」導入をめざす会議を開催、出席しました。これには、日本免震構造協会の和田章会長、笠井和彦・東京工業大学特任教授、高橋良和・京都大学教授、日本学術会議会員の米田雅子氏などの有識者が集ったほか、三浦のぶひろ参院議員、国土交通省、文科省も参加しました。
日本には、これほどの地震国でありながら、土木構造物・建築物に対して免震・耐震を測る実物大の試験装置がありません。耐震工学は世界最先端の技術水準ですが、更なる技術水準アップのためには、この実物大の免震試験機は不可欠のものです。実現に向けて良い話し合いができました。
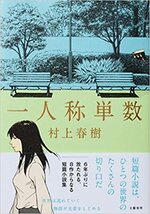 8つの短篇小説集。団塊の世代でもある村上春樹の自伝的な要素を思わせ、同時代を生きた者として感ずるもの大である。たしかに人生を振り返ってみると、不思議な出来事も夢想も虚実一体となって立ち現われてくるものだ。この世界と異界との"あわいの世界"。有と無に偏しない諸法実相の世界。夢と現実との境界での交差。心の深層の無意識層から湧出する意識と感情。8つの短篇に流れるのは仏法でいう末那識・阿頼那識の哲学性と、いかにも団塊の世代らしい芸術・文化との絶妙なコラボレーションだ。
8つの短篇小説集。団塊の世代でもある村上春樹の自伝的な要素を思わせ、同時代を生きた者として感ずるもの大である。たしかに人生を振り返ってみると、不思議な出来事も夢想も虚実一体となって立ち現われてくるものだ。この世界と異界との"あわいの世界"。有と無に偏しない諸法実相の世界。夢と現実との境界での交差。心の深層の無意識層から湧出する意識と感情。8つの短篇に流れるのは仏法でいう末那識・阿頼那識の哲学性と、いかにも団塊の世代らしい芸術・文化との絶妙なコラボレーションだ。
「ネコや犬がしゃべったら面白いだろうな」と思うことは多かったが、本書の「品川猿の告白」では日本語をしゃべる老猿が出て、ドーパミンが出て女性が欲しくなって、「名前を盗む」ことを行ったと聞く。猿に「人間は何をしてるんだ」と揶揄されているようで恐くなる。「一人称単数」で、見知らぬ女性から「3年前に、どこかの水辺で、どんなひどいことを、おぞましいことをなさったかと。恥を知りなさい」とからまれ罵倒される。すると街は三変土田、木という木には蛇が巻きつき蠢いていたと描く。
「石のまくらに」では、ふとした成り行きで一夜を共にした女性。詩を書く女性で詩集を送ってくる。生老病死を感ずる年代になってその詩は心に染み入る言葉となる。次に「クリーム」という小篇。ピアノを同じ先生に習っていた女の子から演奏会の招待状を受け取り、行ってみたがそんな演奏会はないという。出会った老人が口を開く。「中心がいくつもあって、しかも外周を持たない円を、きみは思い浮かべられるか?」「きみの頭はな、むずかしいことを考えるためにある。わからんことをわかるようにするためにある。それが人生のクリームになるんや。それ以外はな、みんなしょうもないつまらんことばっかりや」・・・・・・。結論を出して思考停止するのではなく、考え求める続けることだろう。1955年に死んだはずのチャーリー・パーカーが63年に「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」というアルバムを出したという文章を主人公は大学生の頃に書いていたが、その後ニューヨークのレコード店で同名のアルバムを見つけたという。この「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」や他の小篇「ウィズ・ザ・ビートルズ」「ヤクルト・スワローズ詩集」などは私たちの世代としてはよくわかるものだが、他世代も共有できるのだろうか。
「謝肉祭」――。容貌が著しく醜かった女性は人を引きつける特別な吸引力をもっていた。彼女と究極のピアノ音楽として一致したのがシューマンの「謝肉祭」。襲いかかる梅毒と分裂症によって、シューマンは幻聴と悪霊の「謝肉祭」を書いた。宇宙を感じたのだろうと思う。
「ポストコロナ時代の新たな社会を!」――。27日(日)、第13回公明党全国大会を開き、山口那津男代表、新任の石井啓一幹事長、竹内譲政調会長の新しい体制でスタートを切りました。自民党総裁として菅義偉総理大臣が挨拶。私は引き続き、公明党議長(全国議員団会議議長)として頑張ります。
直面する「コロナ」への対策。経済活動・雇用への支援、デジタル化の推進、大地震への備えや流域治水などの防災・減災対策などを推進。どこまでも立党精神「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」を胸にたたき込み、戦うことを誓いあい、出発しました。菅総理からも「公明党の"大衆とともに"の精神は、市議会議員の時代からの私の姿勢でもある」「自公政権として結束して頑張りたい」との挨拶がありました。
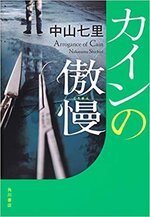 練馬区の公園で少年の死体が発見され、しかも臓器が取り去られていた。捜査に当たった捜査一課の敏腕刑事・犬養隼人と後輩の高千穂明日香、そして地元・石神井署の長束。少年は中国人で、明日香は中国に向かうが、そこには息をのむような貧しさがあった。そして、都内で臓器が取り出された少年の死体が次々と発見される。それら日本の少年も、貧しい家庭で育ったという共通項があった。
練馬区の公園で少年の死体が発見され、しかも臓器が取り去られていた。捜査に当たった捜査一課の敏腕刑事・犬養隼人と後輩の高千穂明日香、そして地元・石神井署の長束。少年は中国人で、明日香は中国に向かうが、そこには息をのむような貧しさがあった。そして、都内で臓器が取り出された少年の死体が次々と発見される。それら日本の少年も、貧しい家庭で育ったという共通項があった。
捜査を進めるなか、この国で静かに潜行している臓器売買ビジネス、暗躍する臓器ブローカーの実態、そして今回は貧困家庭の子どもが狙われ犠牲になるというおぞましい姿が明らかになる。さらに「日本には臓器移植を待ち望んでいる人が多くいる。時間との闘いのなかで」「米中とも臓器移植のハードルが低い。社会的コンセンサスもできている。日本は脳死基準が厳格で、従来からの死生観もあり、ハードルが高い」との実態が明らかになる。生命倫理と現実との苦悩と葛藤のなか、臓器売買の闇、医療と社会の闇に切り込む警察ミステリー。


