2日、リサイクル技術で日本有数の石坂産業株式会社(石坂典子社長、埼玉県三芳町)を視察しました。これには、埼玉県会議員、地元三芳町の町議のほか、環境省等も参加しました。
同社は、建設業廃棄物などのリサイクル技術でトップクラスを誇り、高いリサイクル化率を可能にするため分別分級を徹底的に追求しています。また、地域環境に配慮した投資を行ったり、里山再生、人材教育等にも力を入れています。
現場では、コンクリート、土砂、木材などが独自のノウハウで処理されていて、「分ければ資源、混ぜればゴミ」のモットーのもと、分別分級も徹底的に行われていました。
一方、同社は敷地内に、人と自然が共生できる里山づくりに取り組んでいます。この日も遠足の子供達や多くの見学グループが訪れていて、里山フィールドで食事や散策をして楽しんでいました。
脱炭素化など本格的な循環型社会経済を目指す日本にとって、その模範であり最先端を走るこのような企業の取組みがさらに広がっていくよう、バックアップする必要性を感じました。
11月1日は、豊島区が定めた「としま文化の日」――。全国でコロナ禍の諸行事が軒並み中止となるなか、記念式典を盛大に開催し、「としま文化推進期間」のイベントがスタートしました。高野之夫豊島区長、各種団体のリーダー、国会・都議会・区議会議員らが参加しました。
挨拶に立った私は、豊島区が、①SDGs未来都市に選定されたこと②国際アート・カルチャー都市を目指し力を入れていること――は素晴らしいこととし、「この二つこそ、2030年へ、ポスト・コロナの道しるべだ」「1930年代、アメリカがニューディール政策によって経済を発展させて、世界恐慌を乗り越えたことは有名だが、もう一つの大きな柱が、文化・芸術の振興策に力を入れたことだ。ハリウッド映画はここから一気に広がった」などと述べ、豊島区の文化・芸術を盛り上げる行動に声援を送りました。
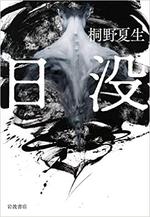 「良い小説と悪い小説を見分けるには」「良い小説の定義は? 自分に正直な小説です。・・・・・・まず自分が書くことに心を打たれないと」・・・・・・。当然、国家が評価するようなものではない。
「良い小説と悪い小説を見分けるには」「良い小説の定義は? 自分に正直な小説です。・・・・・・まず自分が書くことに心を打たれないと」・・・・・・。当然、国家が評価するようなものではない。
小説家・マッツ夢井のもとに一通の手紙が届く。「総務省文化局・文化文芸倫理向上委員会」とある。無視していると「召喚状」が届き、召喚されてC駅まで赴くと、海崖にある「七福神療養所」に連れてこられる。療養所というが、自由を完全に奪われた強制収容所だ。反社会的な作家たちを"更生"させる施設だという。「社会に適応した小説を書け」と命ぜられ、反抗できない者はあの手この手で、狂うのを待たれ、弱い人間は何人も崖から飛び降り死んでいた。社会と隔絶された収容所での悪夢がこれでもかこれでもかとマッツに迫り、精根尽き果てる。
「『表現の不自由』の近未来を描く、戦慄の警世小説」と帯にある。近未来でも、あってはならないことだし、人権感覚の摩耗を防ぎ磨くことだ。
30日、北区王子の飛鳥山公園内にある旧渋沢庭園で行われた「渋沢ガーデンスペシャルホリデー」に参加しました。北区観光協会が、来年のNHK大河ドラマ「青天を衝け」、2024年に新一万円札の顔となる渋沢栄一翁をテーマとした飛鳥山公園の新しい活用やコロナ禍における飲食イベントを考えて開催したものです。
渋沢栄一翁は、1840年に埼玉で生まれましたが、30年以上もっとも長く住んだのがこの飛鳥山公園内で、終の棲家となった場所です。約500もの企業を育て、同時に約600の社会公共事業にも関わり、「日本資本主義の父」と称されます。この旧渋沢庭園には、重要文化財となる洋風茶室「番香廬」、書庫や接客の場「青淵文庫」があり、内外の賓客を招き食事会が行われていました。
飛鳥山公園は「徳川吉宗以来の飛鳥山の桜」「旧渋沢庭園」など観光としても素晴らしいスポット。観光協会が力を入れた今回の企画です。








