 論語に描かれる"神格化"された孔子ではなく、不運や失意、失言や失敗もあった孔丘という人間の波瀾万丈の生涯を書いた大河小説。構想して20年、意を決して70代になった宮城谷さんが力業で書き上げた。「十五歳で学に志した孔丘は、休んだことがない。この死は、孔丘の生涯おける最初の休息であった」と結んでいる。「子曰く、学びて時にこれを習う、亦た説ばしからずや――これが、いつ、どこで、いわれたのか、・・・・・・わからない」と「あとがき」で孔子を小説に書くことの難しさを語るが、私も宮城谷さんも、この言葉からとった時習館高校の同窓生、1学年違いだ。
論語に描かれる"神格化"された孔子ではなく、不運や失意、失言や失敗もあった孔丘という人間の波瀾万丈の生涯を書いた大河小説。構想して20年、意を決して70代になった宮城谷さんが力業で書き上げた。「十五歳で学に志した孔丘は、休んだことがない。この死は、孔丘の生涯おける最初の休息であった」と結んでいる。「子曰く、学びて時にこれを習う、亦た説ばしからずや――これが、いつ、どこで、いわれたのか、・・・・・・わからない」と「あとがき」で孔子を小説に書くことの難しさを語るが、私も宮城谷さんも、この言葉からとった時習館高校の同窓生、1学年違いだ。
「子曰く、吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず」という言葉が、孔丘の人生そのものであることが活写される。父が孔丘三歳で亡くなり、母は孔家を去る。武勇を烈しく憎む母の本心、「十五歳になったとき、自分はけっして武人にはなるまい、学問で身を立てるべく懸命に学ぼう」という立志だ。三十歳を迎える時、「官から辞去し魯の曲阜に教場をひらく」ことを決断をする。妻は離婚を告げ、息子・鯉との対立が始まる。四十の不惑は「周文化がもっともすぐれていると確信したことにほかなるまい」。魯国から斉に亡命していた孔丘に「陽虎が内戦に敗れて、陽関の邑に逃避した」との報せが入る。「このとき五十歳の孔丘は、天に想像を絶する力があることを実感する」「斉を去り、魯に帰るべし。天が孔丘にそう命じている」と天命を知るのだ。「魯を文化国家にする。それを魯だけでなく天下の人々にみせる」――。しかし、理想の国づくりは困難をきわめる。そして再び魯国を去ることになる。五十五歳から十五年近くにわたる亡命生活があり、魯に帰国がかなうのは六十八歳であった。「六十歳の耳順は衛国の実情を観て大いに失望し、天命をより強く意識。どんないやなことでも、天が命ずることであれば順っておこなう」ことだという。七十歳は「自由自在を得たということであろう。・・・・・・七十歳でこういう心境に達した、という精神の推移を述懐したともとれる」という。
弟子との同志的結合には凄味がある。師弟は天の下での縁である。苦難に遭遇した時に発せられた言葉が「論語」となるが、それが苦難に直面する弟子にとって生き生きとした闇を打ち破る「希望」「光」であったことがよくわかる。机上の単なる名言ではないのだ。師弟の一体――仲由(子路)、漆雕啓、閔損、子説、顔回、冉耕、冉求、端木賜(子貢)・・・・・・。「いまだに孔丘の生年が確定しないのはふしぎであるが、非家の私としては、以前は信じなかった司馬遷の説を採って、孔丘が紀元前五五一年に生まれたとした。それが自分なりの割り切りである」(あとがき)を読んでも、いかに春秋時代の魯、斉、衛、宋、曹、鄭、周、晋、呉等々の攻防と人を調べ抜いて書いた小説かと、感動する。孔丘の人生の一本の筋がくっきりと見える。
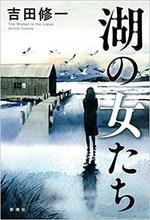 琵琶湖の近くにある介護療養施設「もみじ園」で百歳の男・宮島民男が死ぬ。人工呼吸器の誤作動による"殺人"と睨んだ刑事たちは、かなり強引に施設で働く女たちを取り調べる。過酷な捜査に精神的にまいってしまう女性も現われる。そんななか、捜査する濱中圭介と、施設で働く豊田佳代は異常な愛、離れられなくなり落ちていく。一方、事件を取材する週刊誌記者・池田立哉は、90年代に起きた血液製剤事件を調べるうちに、何年もたって葬られていたこの事件と死んだ宮島民男との結びつき、さらに旧満州・ハルピンでの731部隊との関連にまでたどり着く。静かな琵琶湖、湖畔。そしてハルピンにも美しい湖があり、そこでもある事件が起きていた。昭和から令和へ――時代を超えて湖畔に佇む女たち。その心の底に沈殿した秘密と闇――。人間の自分ではどうにもならない衝動と打ち払うことができない心の傷が描かれる。
琵琶湖の近くにある介護療養施設「もみじ園」で百歳の男・宮島民男が死ぬ。人工呼吸器の誤作動による"殺人"と睨んだ刑事たちは、かなり強引に施設で働く女たちを取り調べる。過酷な捜査に精神的にまいってしまう女性も現われる。そんななか、捜査する濱中圭介と、施設で働く豊田佳代は異常な愛、離れられなくなり落ちていく。一方、事件を取材する週刊誌記者・池田立哉は、90年代に起きた血液製剤事件を調べるうちに、何年もたって葬られていたこの事件と死んだ宮島民男との結びつき、さらに旧満州・ハルピンでの731部隊との関連にまでたどり着く。静かな琵琶湖、湖畔。そしてハルピンにも美しい湖があり、そこでもある事件が起きていた。昭和から令和へ――時代を超えて湖畔に佇む女たち。その心の底に沈殿した秘密と闇――。人間の自分ではどうにもならない衝動と打ち払うことができない心の傷が描かれる。
 「怒りと憎悪の政治」が副題。近代という時代は、人びとが啓蒙され、自由となり、理知的かつ合理的になり、民族やナショナリズム、宗教や人種といった共同体から解放されるはずであった。それが21世紀に入り、グローバル化、移民、社会的な自由主義などに対する憎しみ、怒り、敵意が政治の世界で繰り広げられている。戦後の秩序を形成したリベラリズム。しかし今、リベラルやリベラリズムの退潮、保守対リベラルの日本政治の対立構図は明らかに溶融している。リベラルの理念と構造変化を考え、深淵を探ることによって日本と世界の政治の変化を剔抉するのが本書だ。
「怒りと憎悪の政治」が副題。近代という時代は、人びとが啓蒙され、自由となり、理知的かつ合理的になり、民族やナショナリズム、宗教や人種といった共同体から解放されるはずであった。それが21世紀に入り、グローバル化、移民、社会的な自由主義などに対する憎しみ、怒り、敵意が政治の世界で繰り広げられている。戦後の秩序を形成したリベラリズム。しかし今、リベラルやリベラリズムの退潮、保守対リベラルの日本政治の対立構図は明らかに溶融している。リベラルの理念と構造変化を考え、深淵を探ることによって日本と世界の政治の変化を剔抉するのが本書だ。
リベラルやリベラリズムの定義は画然としない。日本では保守対リベラル、米国では大きな政府の志向、欧州では改革志向。元来は市民としての道徳、義務、寛容、公共善の促進を追求する思想であり、個人の解放や自由、かつ寛容を求める近代の中心軸であったが、最近は劣勢であり、拡散・変容している。
本書は「共同体」「権力」「争点」の三位一体が崩壊しつつあると、根源から指摘する。「国民国家・家族等の境界線が流動化」し、「政党や議会、企業、労働組合などの権力行使が衰退」し、「価値をめぐる分配、移民や歴史認識問題など争点が変化」している。20世紀の後半は、「リベラル・デモクラシー」こそが秩序原理であった。それは「代議制民主主義を基本に、個人の権利や権力分立を保障したうえで、民意を国政に反映させる。リベラリズムは個人の自由を、デモクラシーは個人間の平等を尊重し、両者を合わせた」ものだ。それは大戦後、経済成長によって全体が底上げされて格差が解消、中間層が増大したことに支えられていた。製造業がその中核であった。しかし90年代、グローバル化による産業構造と雇用市場が変化し、製造業に代わってサービス業が中核におどり出る。ここで経済成長が鈍化するなか、雇用が不安定化し、中間層が没落し始め、右派も左派も「リベラル・コンセンサス」へと収斂していく。ここに戦後に安定していた「共同体」は液状化を始め、こぼれ落ちた人々の不満・不安・悲観が蓄積し、権威主義的なニューライトやポピュリズムが台頭する。反リベラルの有権者が増大し、トランプ大統領や英国のEU離脱を生み出すことになる。しかも、「リベラル・コンセンサス」は経済リベラルに反感をもつ労働者と、政治リベラルに対抗するニューライトという"反リベラル連合"を生み、「保守VS左派」の対立軸は変化する。「権威主義VSリベラル」の対立軸だ。加えて、共同体の液状化は、経済成長の背後に隠れていた「歴史認識問題」を表面化していく。国民国家とは「記憶の共同体」であるからだ。さらに剥奪感は旧中間層だけでなく、若者や特に移民第二世代を覆い、ラディカルな暴力行為、テロに進む。宗教の原理主義ではなく、孤立感が原理主義を身にまとうことになるようだ。
吉田さんは5つのリベラリズムを示す。「人権・立憲の政治リベラリズム」「商業取引・貿易等の自由の経済リベラリズム」「個人主義、個人の能力の自由な行使を擁護する個人主義リベラリズム」。そして「社会は人智と人為で良くできるという社会リベラリズム(社会保障、教育、市場の規制、人権擁護)」「民族や宗教、ジェンダーやマイノリティの権利を擁護し、寛容の精神を説く寛容リベラリズム」である。しかし現実はリベラル・デモクラシーは退却し、「リベラル・コンセンサス」に対抗して中間層から転落する労働者の反感と不満と怒りのポピュリズムと、文化・伝統の価値を掲げるニューライトという両面からの反リベラルに挟撃されている。歴史認識問題の世界的波及や移民とテロの問題も顕在化している。それは「5つのリベラリズム相互の不適応と不具合の結果」だという。そして、「個人リベラリズムに対して寛容リアリズムを対置させて均衡を取り戻す」「公的な政治が、再分配や経済的平等性に敏感になるという、経済リアリズムに対する社会リベラリズムの優位性の回復」などの手掛かりを提起する。「共同体・権力・争点とも対応する、アイデンティティ・個人・主体という三角形の均衡と相互の緊張関係が重要」だという。歴史的にも変転してきた「人間性の剥奪に抵抗するリベラリズム」の思想を多様で豊かなダイナミズムに進展させうるかどうか――それがアフター・リベラルに求められているといえようか。
秋晴れとなった21、22、23日の三連休――。地元の北区、足立区、豊島区で、岡本みつなり衆院議員と街頭演説。また「防災訓練」や「親子でチャレンジ飛鳥山」の行事などに出席しました。
街頭演説で岡本みつなり衆院議員は、「鉄道駅のホームドア設置の加速化に取り組む」「生活必需品となった携帯電話料金の値下げは重要だ。電波は国民の共有財産であり、それを使う事業者へ値下げの働きかけを行う」「荒川の洪水防止のため、遊水池の建設に力をいれている」などと述べ、「さらに仕事をさせていただきたい」と決意を語りました。
私は「政治家は仕事ができるかどうかだ。政治は結果だ。岡本さんは結果を出している政治家だ」と訴えました。
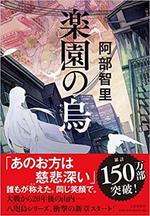 資産家の養父の遺言で山を相続した安原はじめ。その遺言書には「どうしてこの山を売ってはならないのか分からない限り、売ってはいけない」と不思議な一言が書かれていた。今時、山を相続してもと思いがちだが、翌日から「売ってくれませんか」と言う者が続いた。さらに「私と一緒に来てくれませんか」「私は幽霊です」という美女が誘いに来て、「あの山は、ある者にとってはまさしく桃源郷のような場所」という。"幽霊"に誘われ、山に入り、トロッコに乗せられて着いた場所は、山内(やまうち)という異界。
資産家の養父の遺言で山を相続した安原はじめ。その遺言書には「どうしてこの山を売ってはならないのか分からない限り、売ってはいけない」と不思議な一言が書かれていた。今時、山を相続してもと思いがちだが、翌日から「売ってくれませんか」と言う者が続いた。さらに「私と一緒に来てくれませんか」「私は幽霊です」という美女が誘いに来て、「あの山は、ある者にとってはまさしく桃源郷のような場所」という。"幽霊"に誘われ、山に入り、トロッコに乗せられて着いた場所は、山内(やまうち)という異界。
猿と八咫烏の大戦から20年――。山内衆を手足として治めていたのは八咫烏一族の博陸侯であった。"慈悲深い人"で「楽園」を築こうとしているというが、今でも猿の残党に襲われるという。山を相続した安原はじめは、その世界の戦いに巻き込まれ、"楽園"の真実に否応なく迫っていく。
八咫烏シリーズの最新作。作者は松本清張賞を受賞した早大大学院博士課程に在籍する若手小説家。







