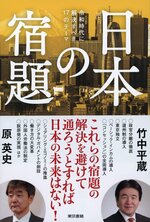 2020年代からの日本は厳しい山に差しかかる。①少子・高齢・人口減少社会②AI・IoT・ロボットの急進展③次元の変わった頻発する大災害――。これがコロナ禍によって更なるデジタル社会と感染症対策が加わる。構造変化が激しい。
2020年代からの日本は厳しい山に差しかかる。①少子・高齢・人口減少社会②AI・IoT・ロボットの急進展③次元の変わった頻発する大災害――。これがコロナ禍によって更なるデジタル社会と感染症対策が加わる。構造変化が激しい。
「令和時代に解決すべき17のテーマ」を副題として、「これらの宿題の解決を避けて通ろうとすれば日本の未来はない!」としたのが本書だ。「政治」においては「真の政・官分離を実現する――官僚主導のゆがみを是正せよ」「地方衰退を解決する――権限・財源を地方に移す、高齢者の地方移住を促進」「道州制を導入する」「東京を独立させる――東京を日本全体の戦略基地として特別行政地区とする」「令和の農地改革を実施する――企業の農地所有を認める」――。
「経済」では「ベーシック・インカムを導入する」「コンセッションを全面導入する――とりわけ当面、水道や林業」「シェアリング・エコノミーを推進する」「経済の新陳代謝を高める――総理主導の規制改革」「デジタル・ガバメントをつくる――マイナンバー制度と歳入庁」――。
「社会」では「働き方をさらに変革する――自由な働き方と自由な雇い方、同一労働同一賃金」「移民法(外国人労働法)をつくる」「脱原発を実現する」「少子高齢社会を克服する――特別養子縁組をしやすくする法改正、フランスの少子化対策」「東大を民営化し、教員資格制度を変える」「真のジャーナリズムを育成する」「政治・メディアの悪循環を糺す」――。
これまで論議してきたこと、私自身がかかわり具体的に進めてきたこと等々があり、問題を常に思考し続けることが大切!
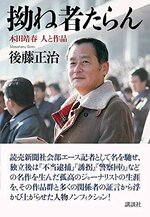 伝説のジャーナリスト、ノンフィクション作家・本田靖春について、その作品と数多くの関係者の証言から語る。「本田靖春 人と作品」だ。際立つ文章のうまさと弱者への情とリズム。人物も「含羞を帯びた男気、あるいは侠気(後藤正治)」「誇り高き"無頼"、精神の貴族(筑紫哲也)」「権力に阿らず、財力にへつらわない"由緒正しい貧乏人"(自称)」「どこからともなく滲み出る情感、背中に漂う含羞、風情ある大人のたたずまい(伊集院静)」「義とユーモアの人」「勉強家、努力家だが、文における素養が飛び切り豊かな人(南晋三・潮出版社社長)」と魅力にあふれていた。
伝説のジャーナリスト、ノンフィクション作家・本田靖春について、その作品と数多くの関係者の証言から語る。「本田靖春 人と作品」だ。際立つ文章のうまさと弱者への情とリズム。人物も「含羞を帯びた男気、あるいは侠気(後藤正治)」「誇り高き"無頼"、精神の貴族(筑紫哲也)」「権力に阿らず、財力にへつらわない"由緒正しい貧乏人"(自称)」「どこからともなく滲み出る情感、背中に漂う含羞、風情ある大人のたたずまい(伊集院静)」「義とユーモアの人」「勉強家、努力家だが、文における素養が飛び切り豊かな人(南晋三・潮出版社社長)」と魅力にあふれていた。
本田は、「戦後という混沌とした時代を生きた人間」を描いた。「私の書くものは社会的弱者に対して甘いんです。強者と弱者がいたら迷わず弱者の側に立つ」と自身が言っているように、「戦後」は皆、生きることに必死だった。人びとは飢え、まともな家もなく、着るものも、履く靴すらなく、差別や暴力も横行していた。しかしその一方で、人びとは桎梏から解放され、自由と希望と熱気をはむ時代の息吹があった。無頼記者の栄光と挫折を活写した「不当逮捕」、闇市時代のアウトローを描いた「疵」、読売新聞社会部時代の若き日を綴った「警察(サツ)回り」、時代の子としての「『戦後』 美空ひばりとその時代」、吉展ちゃん事件の「誘拐」、金嬉老事件の「私戦」、"雑兵の群れ""町の登山家"による「K2に憑かれた男たち」、六ケ所村の部落・上弥栄の「村が消えた」、そして大阪読売新聞社の社会部長だった黒田清の「ちょっとだけ社会面に窓をあけませんか」・・・・・・。全てに「戦後」の一本の強い筋が通り、そして高度成長期の現場に溢れた心の"空洞"を吐き出した。
貧しき昭和20年代を知っている私、黒田清さんと「戦争展」について対談したこともある私、一回り上の本田靖春さんの世代の骨太のジャーナリストと長く接してきた私として、扱われた事件等も生々しく甦る。本書に出てくるジャーナリストや講談社や潮出版社をはじめとして、日本のジャーナリズムが真摯に"いい仕事"をしようと取り組んできたことも改めて感じ、自身を叱咤する。
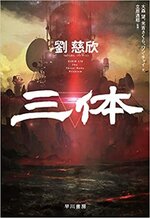 地球文明と異星の三体文明の関わりを描くSF小説。2015年のヒューゴー賞(長編部門)をアジアで初めて受賞した話題作。宇宙との接触、地球文明の現在と未来、文革での知識人の悲惨さ等々を、巨大なスケールで縦横に描く。科学的な力業で押し切った意欲作だ。面白い。
地球文明と異星の三体文明の関わりを描くSF小説。2015年のヒューゴー賞(長編部門)をアジアで初めて受賞した話題作。宇宙との接触、地球文明の現在と未来、文革での知識人の悲惨さ等々を、巨大なスケールで縦横に描く。科学的な力業で押し切った意欲作だ。面白い。
軸となるのは中国人のエリート天体物理学者の葉文潔(文革で惨殺された理論物理学者・葉哲泰の娘)と、その約40年後のナノマテリアル開発者の汪淼(おうびょう)の2人。葉文潔は文革で失意の日々のなか、巨大パラボラアンテナを備える秘密の軍事基地にスカウトされる。そこでは、人類の運命に関わるプロジェクトが極秘で行われていたのだ。そして約40年後、世界的な科学者が次々と自殺していた。汪淼は、ある会議に招かれ、学術団体「科学フロンティア」の潜入を余儀なくされる。そこで三つの太陽を持つ異星を舞台にしたVRゲーム「三体」に入り、異様な感覚に驚く。そして、地球文明と三体文明との異次元と現実が交錯する。
系外惑星の存在と合流は、現実になると、夢ではなく、恐怖なのかも知れない。地球文明が制御のきかない「科学の進展」「欲望の増幅」のなかでどうなっていくのか。そうした根源的問いかけが、このSF小説の背景にある。「人類はいったい何をやっているのだろう。どこに向かっているのだろう」ということの問いかけだ。苦渋の果てに葉文潔らは「文明は、地球上の人類以外の生命を滅ぼし続けるだろう」「人類の文明は、もはや自力では矯正できない。三体文明に人類文明を矯正してもらう」などと問いを発するのだ。そして、地球文明と三体文明との交信が一瞬あるのだが・・・・・・。
8日、公明党岡山県本部の夏季議員研修会に出席し、挨拶をしました。これには、全県から48名の議員が集合、次の戦いへの新たな出発を誓い合う会合になりました。
私は「公明党は太陽の党だ。議員はその地域の太陽として、地域で困っている人のために尽くすこと。誰よりも人と会い、地域を歩き、機敏に動くことだ」「議員は自分がその地域の代表だ、という自覚を持ち、地域行事にマメに食い込んで、地域の問題の解決に知恵を出していくことだ」「議員は誰よりも勉強し力をつけ、人脈をつくり、仕事をして結果を出すことが大切だ」などと挨拶をしました。
研修会に先立ち、岡山経済界の有識者の方々と懇談し、新型コロナウィルス禍において、直面する課題についてうかがい、意見交換をしました。



