GIGAスクール構想が進み、6月の各地方議会では補正予算が組まれています。GIGAスクール構想は、児童生徒1人1台のパソコン端末と高速ネットワーク環境などを整備することで、子どもたち一人一人の個性に合わせた教育の実現を目的としています。特にコロナ禍で休校が続き、各家庭での学びを支援するということが不可欠となっており、教育を充実させる大事な政策です。その体制づくりのためには、端末をもつだけでなく、学校ネットワーク環境の全校整備、GIGAスクールサポーターの配置、各家庭でのオンライン学習環境の整備など、多くの課題があり、現場での推進の力が重要です。
令和元年度の補正予算や、令和二年度の第一次補正予算、さらに今回の第二次補正予算でも、国としてバックアップ体制をとっており、大きく進展することになります。
10日には、文部科学省の丸山洋司初等中等教育局長や、浮島智子衆院議員とともに打ち合わせを行いました。
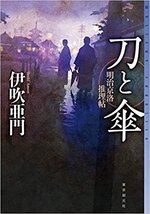 幕末から明治初頭の激動の日本。政治の謀略、激震の京都を背景にして起きる殺害事件の謎に挑む時代本格ミステリー短編集。佐賀、そして近代日本の司法制度の礎を築く江藤新平と尾張藩士であった鹿野師光が、それぞれの個性を生かして事件を解決する。いずれも動乱の時代状況を描くことと、ミステリー事件の謎解きが絶妙に組み合わされ面白い。
幕末から明治初頭の激動の日本。政治の謀略、激震の京都を背景にして起きる殺害事件の謎に挑む時代本格ミステリー短編集。佐賀、そして近代日本の司法制度の礎を築く江藤新平と尾張藩士であった鹿野師光が、それぞれの個性を生かして事件を解決する。いずれも動乱の時代状況を描くことと、ミステリー事件の謎解きが絶妙に組み合わされ面白い。
「佐賀から来た男」――攘夷思想が蔓延する京都で、開国交易論を声高に主張し薩長から睨まれ、越前藩主で賢候として名高い・松平春嶽の相談役を務めた五丁森了介が怪死する。大事な書簡を盗まれた責任を取って、五丁森は腹を切ったのだろうか。「弾正台切腹事件」――弾正台京都支店で大巡察・渋川広元が腹を切り喉を突いて密室で死亡する。自殺か他殺か。明治3年、横井小楠と大村益次郎暗殺に関する資料を探していた江藤新平の打った手は・・・・・・。そして土佐の脱藩浪士・大曽根一衛の心中に渦巻く「攘夷を旗印に維新回天を誓った者が、天下を獲るやその旗印を捨て欧米列強に媚び諂う。それが許されてよいのか」という鬱憤。「監獄舎の殺人」――明治5年、京都の府立監獄舎に収監されていた国家転覆を企てた平針六五が、死刑執行の日に毒殺される。なぜ・・・・・・。
「桜」――明治6年、京都室町下ルの妾宅で、市政局次官・五百木辺典膳と女中が刺殺され、妾がその賊を殺したという事件の真実は・・・・・・。一枚岩だった江藤と師光の間に亀裂が生じていく。「そして、佐賀の乱」――明治6年秋、征韓派と内治派の争いのなか西郷や江藤は政府を去る。佐賀の暴発の恐れがあるなか、江藤を佐賀に行かせず京都に留め置こうと考えた者がいた。明治7年2月、佐賀の乱、3月に土佐で江藤新平は捕縛される。
時代のなかで引き起こされた5つの事件。江藤と師光は真相を究明するが、事件関係者にはいずれも宿業のような物悲しさがある。
 「脱炭素社会」と「脱プラスチック社会」をめざす。「気候変動」という言い方ではなく「気候危機、気象異常事態」と言おう。「産業革命の際に仕込んだ時限爆弾である『温室効果ガスによる温暖化がティッピングポイント(臨界点)に達してしまう』のが早いか、それとも私たち人類が叡智を結集して『ソーシャル・ティッピングポイントと呼ばれる社会の大転換を起こす』のが早いかの競争である」という。副題に「持続可能な地球と世界ビジネスの潮流」とある通り、「脱プラスチック社会」をめざして、各国が各人が各企業やNPOがいかに努力し、挑戦しているかを紹介する。
「脱炭素社会」と「脱プラスチック社会」をめざす。「気候変動」という言い方ではなく「気候危機、気象異常事態」と言おう。「産業革命の際に仕込んだ時限爆弾である『温室効果ガスによる温暖化がティッピングポイント(臨界点)に達してしまう』のが早いか、それとも私たち人類が叡智を結集して『ソーシャル・ティッピングポイントと呼ばれる社会の大転換を起こす』のが早いかの競争である」という。副題に「持続可能な地球と世界ビジネスの潮流」とある通り、「脱プラスチック社会」をめざして、各国が各人が各企業やNPOがいかに努力し、挑戦しているかを紹介する。
まず気候――。産業革命前と比して平均気温は1度上昇し、パリ協定では上昇を2度未満に収め、さらにまずは1.5度未満をめざすとした。「気候変動が社会・経済に深刻な影響を与える」としたが、今は違う。地球が限界となり不可逆の過程に突入するという危機である。ヨハン・ロックストローム博士らは「プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)」を主張する。大きなコストがかかり、人が住みにくくなるというのではなく、ホットハウス・アースに向かう不可逆で破滅的な変化をもたらし、自己強化型のフィードバックメカニズム(熱を海が95%吸収しているが、海の吸収が激減し、氷が融け、それが太陽光を吸収しやすい海へと逆転する)になってしまう。今はこの逆転のスイッチを押してしまう(2度の上昇)ことをさせないギリギリの地点だという。10メートル以上の海面上昇、大洪水と大干ばつで食料生産危機、疫病、最も人が住めるのは南極圏・北極圏。そして循環型の経済にしないともたない。「今後10年間の行動がカギを握る」ということであり、「運命を決める時」だ。これは2015年に定められたSDGsの基礎となる。そのなかに廃棄物問題、プラスチック問題があるというわけだ。
プラスチック――。「世界のプラスチック生産量は年間4億トン。毎年910万トンが海に流出(500ミリリットルのペットボトル5000億本分)」「このまま増え続けると、海洋のプラスチックごみは、2050年には魚や貝の合計より重くなる」「とくに20~30年間に小さく危険なマイクロプラスチックになる。それが食物連鎖で濃縮され、人間の体内まで届けられる」「世界でプラごみ回収の試みが始まっている(ボイヤン・スラットのオーシャン・クリーンアップなど)」「世界各国で使い捨てプラスチック規制が始まっている」「企業も脱プラへの競争が始まり、化石燃料からのダイベスト(投資撤退)だけでなくプラスチックのダイベストも」「日本はプラスチック廃棄物の4分の3が焼却されており、リサイクルではない」「日本環境設計はケミカルリサイクルで世界注目の技術をもっている」などが語られる。また、いわき市の小松事務所の生分解性プラスチック容器技術群も注目されている。
SDGsのウェディングケーキが示すように、自然環境(14番、15番、6番、13番)が17の土台、幹となっている。「環境も経済も大事ですね」という両立ではないフェーズに世界は突き進んでいる。
 「系外惑星が示す生命像の変容と転換」が副題。太陽とは別の恒星をめぐる惑星である「系外惑星」――。初めて発見されたのが1995年、太陽系とは似ても似つかぬ至近距離で恒星を周回する加熱された「ホット・ジュピター」。2010年代初頭には発見数は500個を超え、2019年では4000個近い系外惑星が確認されている。そこで、海を持ち生命を宿す系外惑星は多数存在するのか。適温と水(液体)が存在できる軌道の範囲を「ハビタブル・ゾーン」というが、地球サイズや少し大きい惑星(スーパーアース)で、「ハビタブル・ゾーン」にあるものは何十個と発見されているという。大変な勢いだ。
「系外惑星が示す生命像の変容と転換」が副題。太陽とは別の恒星をめぐる惑星である「系外惑星」――。初めて発見されたのが1995年、太陽系とは似ても似つかぬ至近距離で恒星を周回する加熱された「ホット・ジュピター」。2010年代初頭には発見数は500個を超え、2019年では4000個近い系外惑星が確認されている。そこで、海を持ち生命を宿す系外惑星は多数存在するのか。適温と水(液体)が存在できる軌道の範囲を「ハビタブル・ゾーン」というが、地球サイズや少し大きい惑星(スーパーアース)で、「ハビタブル・ゾーン」にあるものは何十個と発見されているという。大変な勢いだ。
しかし、そこで「地球のような生命、地球のような生物の進化と環境」の呪縛から脱せよ。太陽系の構造が惑星系の標準的姿とする「太陽系中心主義」や、生命を宿す天体に対する考え方も地球のような惑星と考える「地球中心主義」、生命は必然的に人類という到達点に向けて進化する「人間中心主義」から離れよ、という。太陽系の地球しか知らなかった私たちは、「第2の地球」や「地球に似た惑星」を探しがちだが、"異界"の現実・真実を求めるべきだ。そして今がコペルニクスやガリレオの時代のような大転機だという。本書を読んで納得する。それは私たちの存在がノーマルに定置されることになる。
系外惑星研究は、宇宙科学と生命科学を結節する。井田教授のいう宇宙の始まりや天文学・物理学の「天空の科学」と、医学・脳科学・環境科学・地球科学などの「私につながる科学」が交錯する研究分野の進展だ。「天空の科学」では、ブラックホール、ダークマター(実在)、ダークエネルギー(仮説)、ビックバン宇宙、ヒッグス粒子(質量を与える)、超ひも理論等が概説されるが、これがきわめて解り易く面白い。「私につながる科学」では、地球科学における革命・プレートテクトニクス理論、地震、気候変動と地球の温暖化(科学と政治のせめぎ合い)、地球の経験した気温変化と人類自らが原因となった短期の環境変化、遺伝と生命の進化、ゲノム解析、キリスト教とダーウィン進化論の対立、生命の起源・・・・・・。そして「天空と私が交錯する『ハビタブル天体』」では、系外惑星の発見のみちのり、ハビタブル惑星の発見、赤色矮星の惑星、エンケラドス・エウロパ・タイタン等のハビタブル衛星、地球外生命、地球外知的生命と意識の起源等が語られる。
地球も生命の進化も、別様のかたちがいくらでもあり得るという新たな地平が勢いをもって開かれている。



