 「渋沢栄一から下村治まで」が副題。「日本経済学」とも呼ぶべき近代日本の経済・思想を貫く精神とは何か。それを、渋沢栄一、高橋是清、岸信介、下村治の4人を抽出し、その柱がプラグマティズムと(経済)ナショナリズムであることを明らかにする。明治から昭和の終わりまでの日本。激動のなか実際に舵取りをした4人は、現場実践の実感覚と柔軟性を手放すことがなかった。そして、民力、国力、創造力や国民の連帯意識を重視した。当然、積極財政や保護主義を主張し、健全財政や自由貿易のドグマから距離を置く経済ナショナリズムに立った。経済理論や貨幣論が揺れ動くなかで、4人の経済思想が共通することが浮き彫りにされる。その骨太の道を提示する本書の圧倒的な力業、鮮やかさに驚嘆する。
「渋沢栄一から下村治まで」が副題。「日本経済学」とも呼ぶべき近代日本の経済・思想を貫く精神とは何か。それを、渋沢栄一、高橋是清、岸信介、下村治の4人を抽出し、その柱がプラグマティズムと(経済)ナショナリズムであることを明らかにする。明治から昭和の終わりまでの日本。激動のなか実際に舵取りをした4人は、現場実践の実感覚と柔軟性を手放すことがなかった。そして、民力、国力、創造力や国民の連帯意識を重視した。当然、積極財政や保護主義を主張し、健全財政や自由貿易のドグマから距離を置く経済ナショナリズムに立った。経済理論や貨幣論が揺れ動くなかで、4人の経済思想が共通することが浮き彫りにされる。その骨太の道を提示する本書の圧倒的な力業、鮮やかさに驚嘆する。
とくに渋沢栄一の「論語と算盤」。なぜ、論語と算盤か、どういう論語なのか。水戸学のプラグマティズム、朱子学批判。理論は実践のなかにある。萩生徂徠ではなく、伊藤仁斎・会沢正志斎・渋沢栄一と貫かれる「中庸」「常識」の渋沢の論語主義が示される。その理念は、市場の「見えざる手」ではなく、「国家のため」「社会のため」といったナショナリズムや公共精神をもつ渋沢たちの「見える手」によって開拓され、近代日本の資本主義が形成される。渋沢も高橋是清も近代化と戦争のなかで、格闘する。緊縮財政か積極財政か。金本位制等々をめぐる貨幣をめぐる通貨論争は、世界を背景にして揺れ動く。デフレとインフレ、この時代に渋沢をしてもなお超えられなかった商品貨幣論のドグマを超えて次代の扉に手をかけた先駆者・金井延の存在も紹介される。
経済ナショナリスト・高橋是清――。高橋は事象の根本原因を常に問い質す姿勢をとり、経済の「根本」はナショナリズムによって動かされる産業組織であり、それこそが「国力」なのだとした。経済ナショナリズム、国民の生産力を引上げるための産業政策を重視した。井上準之助の緊縮財政の失敗と野心、高橋の積極財政の功は顕著だが、しかし軍国主義化の勢いは止められなかった。この戦時統制経済の責めを受けるのが岸信介だが、「岸が官僚になって以来、一貫して軍国主義者あるいは戦時統制経済論者であったとはいえないのではないか」「岸にとって『統制経済』とは自由主義経済と計画経済の中間形態」と中野さんはいう。そして後の岸政権は、積極財政、インフラ整備を図り、「所得倍増」の池田政権へとつなぐ「協調的経営者資本主義」を進めたのだ。その「所得倍増計画」を理論的に支えたのが、下村治――。渋沢、高橋、岸の経済ナショナリズムの思想を受け継いだ「下村理論」「成長理論」だ。成長の主軸は「国民自身であり、政府ではない」とし、「ケインズの理論に供給側の理論を接続した成長理論」「政府は安易な景気刺激策・需要刺激策ではなく、経済をあるべき姿に向けて誘導するのが役割」だという姿勢を堅持した。さらに低成長時代を経て、「下村は"追い付き追い越せ"型の経済成長が終わったからこそ、民間主導型から政府主導型の経済システムへと転換しなければならないと、新自由主義的な構造改革論者とは正反対の主張を展開した」と指摘する。政府が財政支出を拡大して国内需要の増加を誘発させなくてはならない、ということだ。
最後にこの平成以降、「渋沢が説いた合本主義を時代の遺物として打ち棄て」「高橋の否定した健全財政のドグマに執着し」「岸が嫌悪した弱肉強食を目指して、規制緩和、自由化、民営化を推し進め、日本型の協調的経営者資本主義を葬り去り」「下村が遺した『国民経済を忘れるな』という戒めを忘れ」ていい訳がないと、痛烈に言う。
困窮する大学生に10万円(最大20万円)の給付が決定――。19日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で経済的に困窮する大学生・専門学校生や大学院生、住民票のある留学生、日本語学校などの学生らを対象に1人10万円または20万円(住民税非課税世帯)を給付する「学生支援緊急給付金」の創設が閣議決定されました。
これは公明党が萩生田文科相に新型コロナ感染拡大で、仕送りやアルバイトが無くなり経済的に困窮する学生へ「給付金の創設」を行うよう5月8日の緊急提言をはじめ、3度の申し入れを行い、強く学生支援を求めてきたもの。萩生田文科相からも「早急に対応したい」との返答を得ていました。
支給対象の要件は ①家庭から自立してアルバイト収入で学業を賄っている(原則として自宅外学生) ②アルバイト収入が50%以上減少 ③住民税非課税世帯で高等教育無償化を受給している、もしくは無利子の貸与型奨学金を限度額まで利用しているなど。対象となるのは約43万人。所要額は約531億円。スピードを重視し、今年度の第1次補正予算の予備費を活用します。
大学などを通じて日本学生支援機構から給付を受ける仕組みです。一日でも早く学生の手元に届くように全力を挙げます。
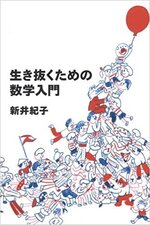 「数学とは何だろう」「微分・積分何になる」「足し算・掛け算・分数がわかれば人生はやっていける」とは、ほとんどの人の思いだろう。しかし、物事を定義づけ、論理的思考をする。思考の幅や自由度を身につける。感情に溺れず、正確に考えることが人生でいかに大切か。新井先生は「日本人は、どうも『とは』と『なぜ』の力を、学校でも社会でもちゃんと鍛えていない」という。そして「他の国の人にも」「宇宙人にも」、しっかりした定義と論理の共通言語で語り合えるように、本書では「かけ算を宇宙人に教えよう」「数学的な構えをチェック」「数直線は変な線」「四角形とは」「ゲームを定義する」「累乗のこわさとおもしろさ」「いろいろなグラフ」「計算できない関数」「三角関数」などの講義を行い、最後はあの小川洋子の「博士の愛した数式(オイラーの等式eiπ + 1 = 0やルート√)」などを語る。あらゆる概念を論理的に考え続け、皆で共有する。「なぜ」と問いかけ、その結論を出す。
「数学とは何だろう」「微分・積分何になる」「足し算・掛け算・分数がわかれば人生はやっていける」とは、ほとんどの人の思いだろう。しかし、物事を定義づけ、論理的思考をする。思考の幅や自由度を身につける。感情に溺れず、正確に考えることが人生でいかに大切か。新井先生は「日本人は、どうも『とは』と『なぜ』の力を、学校でも社会でもちゃんと鍛えていない」という。そして「他の国の人にも」「宇宙人にも」、しっかりした定義と論理の共通言語で語り合えるように、本書では「かけ算を宇宙人に教えよう」「数学的な構えをチェック」「数直線は変な線」「四角形とは」「ゲームを定義する」「累乗のこわさとおもしろさ」「いろいろなグラフ」「計算できない関数」「三角関数」などの講義を行い、最後はあの小川洋子の「博士の愛した数式(オイラーの等式eiπ + 1 = 0やルート√)」などを語る。あらゆる概念を論理的に考え続け、皆で共有する。「なぜ」と問いかけ、その結論を出す。
無限、有限、確率、無限小数、循環小数、数直線、実数、自然数(正の整数)、無理数(分数で表せない)と有理数、円や四角形の定義付け、累乗(ダニやコロナ)、微積分、指数法則、テイラー展開、超越数・・・・・・。
「パワーアップした数学はこれから新たなものを数学に飲み込み、発展するでしょう。そういう数学で育った若い数学者たちは『複雑さ』への耐性を身につけて、前の世紀では想像できなかったような概念への直感を身につけていくにちがいない。それに参加するか、それとも、しないのか、現代の数学というのは、そういうバトルフィールドなんだろうと思う」という。
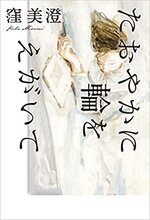 家族というもの、結婚というもの、男という生き物、そして女性の幸せ・・・・・・。静かに、優しく、心の襞、心奥の不安や嵐を濃密に描く。イプセンの「人形の家」を想起させ、現代を浮き上がらせる力作。
家族というもの、結婚というもの、男という生き物、そして女性の幸せ・・・・・・。静かに、優しく、心の襞、心奥の不安や嵐を濃密に描く。イプセンの「人形の家」を想起させ、現代を浮き上がらせる力作。
結婚して約20年、穏やかな暮らしをしていた主婦・酒井絵里子。ある日、離婚した妹の芙美子がいう。「お姉ちゃんみたいに、20何年も結婚生活が続いている人は、やっぱり結婚に向いている人なんだよ。私、結婚しているとき、ほんとうに息苦しかったよ・・・・・・あと、何十年もこんな生活が続くのかって。地獄みたいだった・・・・・・」「お姉ちゃんみたいな人にはわからないって。お父さんが浮気していたことも、お父さんとお母さんが離婚したことも、私が離婚したことも、多分、お姉ちゃんにはわからない。・・・・・・お姉ちゃんが考えているより、人間ってもっと不可解なもんなんだよ」・・・・・・。
そして清廉潔白、大好きだった父の浮気、よりによって夫が風俗に通っていたこと、一人娘の萌がいかがわしい場所で年上の男と遊んでいたという衝撃の事実に絵里子は打ちのめされる。「何も知らないで主婦として過ごす日常とは何であったのか」「家族とは何なのか、結婚とは何なのか、男という生き物っていったい何なのだろう」・・・・・・。しかし、同窓会で再会した整形し店を持って生きる詩織、いっしょに暮らす女性みなも、その友人の風俗嬢、乳癌を患った美しい老婦などと出会って新たな世界に目覚め、自己を変えていく。絵里子は「新しい自分に生まれ変わりたかった」のだ。自分の人生を生きていく。自分の人生でいつも闘っている。自分の人生を歩み出すことの嬉しさが、最後の締めの一行まで息つくことなく描かれていく。とてもいい。
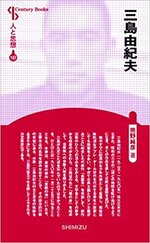 1970年11月25日――。三島由紀夫が自決して今年で50年になる。あまたある三島由紀夫論のなかでも、本書は「戦後民主主義の擬制」「天皇(制)」「日本文化の防衛」や「政治的計画」「私生活」などは除かれ、ひたすら小説等を読み解き、その生と思考の軌跡を明らかにしている。三島由紀夫として、文学者として、小説家として、作家として、芸術家として、キメ細かく書き分けている。眩いほどの"天才"が、何に憧憬し、何に渇え、何に苦悩し、何を究めようとしたかを、作品を関係者の証言も含めて時系列的に読み解いていく。「花ざかりの森」「岬にての物語」「仮面の告白」「潮騒」「金閣寺」「鏡子の家」「憂国」「午後の曳航」「春の雪」「豊饒の海」――。
1970年11月25日――。三島由紀夫が自決して今年で50年になる。あまたある三島由紀夫論のなかでも、本書は「戦後民主主義の擬制」「天皇(制)」「日本文化の防衛」や「政治的計画」「私生活」などは除かれ、ひたすら小説等を読み解き、その生と思考の軌跡を明らかにしている。三島由紀夫として、文学者として、小説家として、作家として、芸術家として、キメ細かく書き分けている。眩いほどの"天才"が、何に憧憬し、何に渇え、何に苦悩し、何を究めようとしたかを、作品を関係者の証言も含めて時系列的に読み解いていく。「花ざかりの森」「岬にての物語」「仮面の告白」「潮騒」「金閣寺」「鏡子の家」「憂国」「午後の曳航」「春の雪」「豊饒の海」――。
はじめに高橋和巳の三島論「仮面の美学――三島由紀夫」が出てくる。「清冽な処女作『花ざかりの森』」「夭折の美学」「硬質の知性」を語っている。私の大学時代、同じキャンパスにいた高橋和巳、そして三島由紀夫は、左右両翼の"教祖"にも似た存在であった。三島の自決が70年、高橋の病死が71年、翌72年は三島を守った川端康成の自殺。私の学生時代は三人の総仕上げの時だったわけだ。そして戦後の思想、論争はこの時一つの区切りとなってることを今、しみじみ思う。
三島の小説に投影される心象は、「美と死」「精神と身体」「絢爛たる才能と危険なまでの激情の純粋昇華(川端康成)」「太陽と海」「有と無」「存在と非存在」「永遠と瞬間」「認識と行動」「破壊と創造」を時を経るごとに掘り詰めている。そして三島は「表現者は死を暗示するだけではなく、じっさいに死んでみなければならない」と主張する。「金閣寺」では、世界からはじき出される「世界との隔絶」「この世への拒絶」「世界を変貌させるのは行為」、認識の境地から行動へと踏み出して世界を破壊するとともに創造し直す。瞬時の三変土田であり、「決定的なものとは時間の流れを堰き止めてなにごとか、瞬間のうちに永遠をやどし、永遠を瞬間のなかに封じ込めるなにものかとなるはずである」というのだ。「豊饒の海」の大尾に「この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまったと本多は思った。庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしてゐる。・・・・・・」とあることを、著者は「三島由紀夫の生涯でおそらく最高の美文である。小説家は、これといって奇巧はない。しかし、このうえなく閑雅な一文を最後の作品として、文学者としての生涯を閉じることを望んだのである」と語っている。この最後の一文の境地に向けて、なるほど三島は走り続けたのだと納得する。すばらしい評伝。

