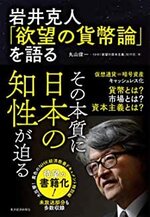 経済学者・思想家の岩井克人氏が資本主義、グローバル経済、貨幣論について語る。NHKはBSスペシャル番組「欲望の資本主義 特別編 欲望の貨幣論2019」を、岩井さんの言語を軸に、スティグリッツ、ティロ―ル、セドラチェフ、ハラリ、ガブリエルらの世界の知性を交えてドキュメントをつくった。その岩井さんの思考を丸山俊一氏がまとめたものだが、なんとも骨太な資本主義と経済・社会の道筋が人類の思想史として明示される。アリストテレス、ジョン・ロー、アダム・スミス、ハイエクやフリードマン等、歴史と思想にふれつつ、「貨幣」と「資本主義」の本質に迫る。ビットコインやMMTにもコメントする。
経済学者・思想家の岩井克人氏が資本主義、グローバル経済、貨幣論について語る。NHKはBSスペシャル番組「欲望の資本主義 特別編 欲望の貨幣論2019」を、岩井さんの言語を軸に、スティグリッツ、ティロ―ル、セドラチェフ、ハラリ、ガブリエルらの世界の知性を交えてドキュメントをつくった。その岩井さんの思考を丸山俊一氏がまとめたものだが、なんとも骨太な資本主義と経済・社会の道筋が人類の思想史として明示される。アリストテレス、ジョン・ロー、アダム・スミス、ハイエクやフリードマン等、歴史と思想にふれつつ、「貨幣」と「資本主義」の本質に迫る。ビットコインやMMTにもコメントする。
「貨幣」をめぐっては「貨幣商品説」や「貨幣法制説」が長い歴史のなかで先行する。しかし「貨幣は他の誰かが交換に応じ受け取ってくれる、ただそれだけのことによって貨幣たりうる」「ゆえに貨幣とは貨幣であるから貨幣である」と岩井さんはいう。貨幣が貨幣として社会に受容されるからこそ貨幣という自己循環論法だ。したがってデジタル通貨の登場は貨幣論からいくと当然の帰結だが、ビットコインは"投機商品"になってしまい、「貨幣になる可能性がほぼゼロ」となったと断じる。またその自己循環論法に行き着いたのは17世紀の"お尋ね者ジョン・ロー"だが、銀行貨幣制度を導入し、貨幣量を増加させるが、ミシシッピー・バブルの"取り付け騒ぎ"で破綻する。シュンペーターはこのジョン・ローの貨幣理論を評価(おそらくケインズも)する。今日の金融システムは「ローのシステム」であり、経済の効率を高める役割を果たすとともに、他方で経済の不安定性を高めるという「効率性と安定性の二律背反」を背負い込むシステムだ。
「資本主義については二つの対立する見方がある」と岩井さんはいう。アダム・スミスを始祖とする「新古典派」は、「見えざる手」に信頼を置き、資本主義を純粋にしていき、地球全体を市場によって覆い尽くせば、効率性も安定性も実現される「理想状態」に近づくという主張だ。ハイエクやフリードマンに受け継がれている。もう一つはケインズを代表する不均衡動学派であり、その先駆者はジョン・ロー。岩井さんもそうだ。資本主義を純粋にしていくと「効率性」は増すが、逆に「安定性」が減る。資本主義が曲がりなりにも「安定性」を保ってきたのは、政府や中央銀行の介入や税制、金融投機の規制があったからだという。
ニューディールのケインズ革命があり、フリードマン等の新古典派の反革命があり、リーマン・ショック後の今日がある。この「二律背反」の鬩ぎあいのなかで、アリストテレスの「貨幣は元々交換のための手段。しかし次第にそれを貯めること自体が目的化する」との言葉が蘇る。貨幣への欲望のパラドックス、さらに「ケインズの美人コンテスト」という、貨幣をめぐる人間の欲望の無限の乱反射(勝ち馬に乗り、稼ぎたい)――まさに、やめられない、止まらない。欲望が欲望を生む"欲望の資本主義"だ。「人間は、貨幣の出現によって、無限の欲望を身につけてしまった」「貨幣があまりにも自由放任されると、資本主義そのものが破壊されてしまう」――そのために、「国家や中央銀行、税制、投機規制等の"外部"の力」そして「貨幣は、本来人間を匿名にする。・・・・・・自分で自分の目的を決定できる存在・・・・・・これが人間の尊厳になる」という。そこで岩井さんはカントの「規範」「道徳律」「相対的な価値である価格ではなく内的な価値である尊厳を持つ」ことを強調するのだ。
「新型コロナによる収入減のうえ、ボーナスが減少すると、住宅ローン返済が大変」――。コロナ禍でこうした不安の声が寄せられています。この問題について国交省(住宅支援機構)、金融庁から返済猶予などの柔軟対応をするという方針が再度徹底されることになりました。岡本みつなり衆院議員が5月29日の衆院国土交通委員会で強く求め、「ボーナス返済や毎月の返済額の変更に、柔軟に対応する」と国交省、金融庁の双方から答弁がありました。
 ノース・カロライナ州の湿地で、チェイスという若者の死体が発見される。疑いの目は、村人から"湿地の少女"と呼ばれるカイアに向けられる。カイアは幼い頃に家族に置き去りにされ、たった一人で未開の湿地で生きてきた。偏見、蔑み、貧困、好奇にさらされるなか、学校に通ったのは1日だけ、語りかける相手はカモメしかいない。手を差し伸べたのは燃料店のジャンピン夫婦と、兄の友人で読み書きを教えてくれたテイトぐらい。圧倒的な孤独。「長い孤独のせいで自分が人とは違う振る舞いをするようになったことに気づいていた。しかし、好んで孤独になったわけではない。カイアは大半のことを自然から学んだ。誰もそばにいないとき、自然がカイアを育て、鍛え、守ってくれたのだ。たとえ自分の異質な振る舞いのせいでいまがあるのだとしても、それは生き物としての本能に従った結果でもあった」・・・・・・。作者はジョージア州出身の野生動物学者。本書は学術論文ではなく、小説としては初めての69歳にしての作品。素晴らしい。
ノース・カロライナ州の湿地で、チェイスという若者の死体が発見される。疑いの目は、村人から"湿地の少女"と呼ばれるカイアに向けられる。カイアは幼い頃に家族に置き去りにされ、たった一人で未開の湿地で生きてきた。偏見、蔑み、貧困、好奇にさらされるなか、学校に通ったのは1日だけ、語りかける相手はカモメしかいない。手を差し伸べたのは燃料店のジャンピン夫婦と、兄の友人で読み書きを教えてくれたテイトぐらい。圧倒的な孤独。「長い孤独のせいで自分が人とは違う振る舞いをするようになったことに気づいていた。しかし、好んで孤独になったわけではない。カイアは大半のことを自然から学んだ。誰もそばにいないとき、自然がカイアを育て、鍛え、守ってくれたのだ。たとえ自分の異質な振る舞いのせいでいまがあるのだとしても、それは生き物としての本能に従った結果でもあった」・・・・・・。作者はジョージア州出身の野生動物学者。本書は学術論文ではなく、小説としては初めての69歳にしての作品。素晴らしい。
文明と自然、野生のもつ生存の優しさと残酷さ、文明のもつ自堕落と軽薄、人間に内在する愛と暴力、偏見と差別等々を問いかけつつ、物語が進む。ミステリー小説を超えたそうした背景の深さと、「むせかえるほどに濃密な緑、広大無辺の闇、そこに息づく無数の命。その脈動と自分の鼓動を重ねるように生きるカイアの姿(友廣純)」は、感動を与える。野生の靭さとしたたかさは、文明の傲慢・暴力性と脆弱さの間隙を衝く。
"ザリガニの鳴くところ"とは「茂みの奥深く、生き物たちが自然のままの姿で生きる場所」ということ。湿地で孤独のなかで懸命に生き続けた美しく聡明な少女から見た現代社会の歪みや汚さが透視される。自然は残酷だが美しい。「本物の男とは、恥ずかしがらずに涙を見せ、詩を心で味わい、オペラを魂で感じ、必要なときには女性を守る行動ができる者のことを言うのだ」・・・・・・。野生動物学者でなければ描けない世界が心に響いてくる。しかもカイアは、1945年10月10日生まれ、私と4日違いという設定。
27日、2020年度第二次補正予算案が決定。このなかで、飲食店の休業や学校給食、各種イベントの中止などで販路が絶たれ、収入が減少した農林漁業者を支援する「持続化補助金」(経営継続補助金)を新しくつくることを決めました。感染防止対策を行いつつ、野菜や花卉などの都市農家をはじめ、農業全般の販路回復や幅広い事業継続等のための助成です。最大150万円の補助で、農林漁業への大きな支援になります。
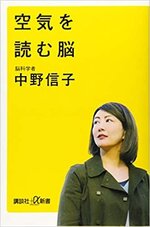 「サイコパス」「脳内麻薬」「シャーデンフロイデ」など、中野信子さんの本を読んできた。「良心というブレーキがない脳」「倫理・道徳というルールを学習できない脳」というサイコパスの脳が「扁桃体と眼窩前頭皮質および内側前頭前皮質とのコネクティビティ」がカギとなっていることを「脳科学」で明らかにした。「快楽とは"頑張っている自分へのご褒美"」として「人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体」を「脳内麻薬」として紹介した。依存と社会的報酬の関わりだ。「シャーデンフロイデ――誰かが失敗した時に、思わず湧き起こってしまう喜びの感情」が、"愛情ホルモン""幸せホルモン"などと呼ばれる「オキシトシン(安らぎと癒し、愛と絆の働き)」と深い関わりのあることを示した。「私から離れないで」「私たちの共同体を壊さないで」「絆を断ち切ろうとすることは許さない」「集団を支配する倫理、正義バブルの正体」を詳述した。本書は日本の心性、日本人の脳の特性について、脳科学を中心にした科学的エビデンスをもとに論じ、その特性を知れば現代社会の息苦しさを突き破れるという。
「サイコパス」「脳内麻薬」「シャーデンフロイデ」など、中野信子さんの本を読んできた。「良心というブレーキがない脳」「倫理・道徳というルールを学習できない脳」というサイコパスの脳が「扁桃体と眼窩前頭皮質および内側前頭前皮質とのコネクティビティ」がカギとなっていることを「脳科学」で明らかにした。「快楽とは"頑張っている自分へのご褒美"」として「人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体」を「脳内麻薬」として紹介した。依存と社会的報酬の関わりだ。「シャーデンフロイデ――誰かが失敗した時に、思わず湧き起こってしまう喜びの感情」が、"愛情ホルモン""幸せホルモン"などと呼ばれる「オキシトシン(安らぎと癒し、愛と絆の働き)」と深い関わりのあることを示した。「私から離れないで」「私たちの共同体を壊さないで」「絆を断ち切ろうとすることは許さない」「集団を支配する倫理、正義バブルの正体」を詳述した。本書は日本の心性、日本人の脳の特性について、脳科学を中心にした科学的エビデンスをもとに論じ、その特性を知れば現代社会の息苦しさを突き破れるという。
まず、「不安が高く、社会的排除を起こしやすく、同調圧力を感じやすいと思われる日本人の脳」だ。神経伝達物質セロトニンは、「精神の安定や安心感の源」「適切に分泌されるとストレスに対する抵抗力が増す(精神安定剤のよう)」「個人より集団をつくろうとする本能に関係する」で、その量の調節を再取り込みという形で担うたんぱく質がセロトニントランスポーターだ。その量が日本人の脳は世界でも最も少ない部類に入るという。それは、「利他的に振る舞おう」「ルールを逸脱した人はバッシングを受ける」「不正をした相手に制裁を加える(不倫も)」「義経、孔明のように悲劇性を持った人物が人気を集める」「醜く勝つより美しく負ける」「賭けでも堅実で慎重な日本人」「新奇探索性が低い日本人」「集団の結束が優先の日本(オキシトシン)」に関係する。
「容姿や性へのペナルティ」「女という『呪われた』性で『婚活』に苦しむ日本人女性」「レールを敷く親――子どもを蝕む『毒親』とは」「愛と憎しみのホルモン・オキシトシン」「同性愛の科学と"生産性"」――。じつは「種の保存のために自然に残した仕組みが同性愛の遺伝子」という驚くべき研究成果が示される。マイノリティを排除する特性のなかで、こうした同性愛の遺伝子が組み込まれているのは興味深い。
「『褒める』は危険」「褒めて育てると"失敗を恐れる脳"が形成され、『挑戦』を避ける」という衝撃的事実が示される。それが進んでしまい「"優秀な人"による"捏造""改竄"まで起きる」「頭がいいねと褒められた子どもは、必要な努力をしなくなる」のだ。「努力のかいがあったね」といえば、難しい問題に挑戦し、面白がるという。また「報酬がいいとやる気や創造力が減退する」「"ごほうび"をいうと"嫌なこと"をさせるときだと脳が反応する」――つまり創造性をあげるには、報酬ではなく、「やりがい」を与えることだという。また「女性は男性に比べて、セロトニンの合成能力が低い」ので、女性の方が不安になりやすい。女性脳は不安になりやすく、楽観的な男性脳は「メールもすぐに返信しない」ことになりがちのようだ。「ステレオタイプ脅威」――人はこうである、男(女)はこうであると決めると、そうなってしまうことに用心。
「幸福度が低い」にはわけがある――。「幸福の感じ方(幸福度)」を調査・研究すると、収入額、配偶者の有無、職業、宗教の影響を受ける等の環境要因の部分は少なく、感じ方や考え方は遺伝的影響が大きいという。「幸福度の高さは、どれくらい陽気で楽観的な性質かと言い換えてもよく、セロトニンの動態と深く関係している」「セロトニントランスポーターが少ないという日本人はやや特異的な性質を持った集団である」「真面目で、慎重、悲観的になりやすく、粘り強い日本人の幸福度の低さは性格遺伝子で特色づけられる」というのだ。その性格は長寿に共通する性格で、「幸福度を高めてやることがその人の寿命を縮めることになりかねない」とのパラドキシカルな考え方に論及する。面白いものだ。「"弱み"は人間の生存戦略上なくてはならない」とし、「"弱み"を生き延びる強さに変える生き方を」という。

