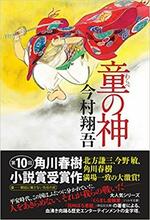 935年平将門の乱から1017年藤原道長が太政大臣になる平安時代後期。京、山城、大和、摂津、丹波の地域――。朝廷を背景にして源頼光、その配下の渡辺綱、卜部季武、碓井貞光、さらには坂田金時らは、京人(みやこびと)として、周辺を「童」と蔑称(童は辛、目、重と分けられ、目の上に墨を入れられ重荷を担ぐ奴婢)し、制圧しようとした。摂津竜王山に移った滝夜叉、北に盤踞する丹波大江山の粛慎(鬼)、南に勢力を拡大する大和葛城山の畝火(土蜘蛛)らは三山同盟して立ち向かう。その中心に押し上げられたのが越後藩原郡の豪族の出の桜暁丸(おうぎまる)。花天狗とも酒呑童子とも呼ばれた桜暁丸は、皆が手をたずさえて生きられる人の世をひたすら求めて戦う。「京人は我らを鬼と呼ぶ。土蜘蛛と呼ぶ。そして童(わらわ)と呼び蔑む。理由などない。己が蔑まれたくないから誰かを貶める」「胸を張ってくれ。我らは何も汚れてなどいない。父母を想い、妻を想い、子を想い、仲間を想う。我らは誰よりも澄んだ心を持って生きたはずだ」「生きるのだ、何があろうと生き抜け。そして愛しき人と子を生し、我らの心を紡いでいこう」――。
935年平将門の乱から1017年藤原道長が太政大臣になる平安時代後期。京、山城、大和、摂津、丹波の地域――。朝廷を背景にして源頼光、その配下の渡辺綱、卜部季武、碓井貞光、さらには坂田金時らは、京人(みやこびと)として、周辺を「童」と蔑称(童は辛、目、重と分けられ、目の上に墨を入れられ重荷を担ぐ奴婢)し、制圧しようとした。摂津竜王山に移った滝夜叉、北に盤踞する丹波大江山の粛慎(鬼)、南に勢力を拡大する大和葛城山の畝火(土蜘蛛)らは三山同盟して立ち向かう。その中心に押し上げられたのが越後藩原郡の豪族の出の桜暁丸(おうぎまる)。花天狗とも酒呑童子とも呼ばれた桜暁丸は、皆が手をたずさえて生きられる人の世をひたすら求めて戦う。「京人は我らを鬼と呼ぶ。土蜘蛛と呼ぶ。そして童(わらわ)と呼び蔑む。理由などない。己が蔑まれたくないから誰かを貶める」「胸を張ってくれ。我らは何も汚れてなどいない。父母を想い、妻を想い、子を想い、仲間を想う。我らは誰よりも澄んだ心を持って生きたはずだ」「生きるのだ、何があろうと生き抜け。そして愛しき人と子を生し、我らの心を紡いでいこう」――。
桜暁丸らの死闘は壮絶なものがあるが、朝廷側にも童(わらべ)と呼んだ渡辺綱、同じ抑圧された側から加わった相模足柄山出身の民・坂田金時らがおり、桜暁丸らとの心の交流が描かれる。大江山の酒呑童子の側から時代を剔抉する力作。
統一地方選挙の後半戦である一般市・東京特別区・町村議選は21日に投票。後半戦で公明党は286市議選に901人、20区議選に150人、142町村議選に171人の計1222人を擁立し、全員当選しました。
女性の当選者は政党最多の439人。市議選は、政党別当選者数で7回連続の「第1党」を達成。区議選も「第2党」の座を死守しました。言葉に尽くせぬ真心からのご支援に心より感謝申し上げます。
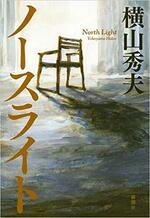 離婚して一人暮らしの一級建築士の青瀬稔。吉野陶太夫妻から「信濃追分に80坪の土地がある。あなた自身が住みたい家を建てて下さい」というたっての希望を受け、浅間山を望み北からの光を思う存分取り込んだ(ノースライト)斬新な木の家を建てる。建築士としても静かな評価が広がっていく。しかし、そのY邸を訪れると、家族が住んだ気配もなく、ただ一脚の古い椅子だけが残されていた。その椅子はなんと「ブルーノ・タウトの椅子」であり、そして肝心の家族はどこに消えてしまったのかわからない。ミステリーとはいっても、建築の美しさ、人の心の美しさが浸み込んでくる長編だ。
離婚して一人暮らしの一級建築士の青瀬稔。吉野陶太夫妻から「信濃追分に80坪の土地がある。あなた自身が住みたい家を建てて下さい」というたっての希望を受け、浅間山を望み北からの光を思う存分取り込んだ(ノースライト)斬新な木の家を建てる。建築士としても静かな評価が広がっていく。しかし、そのY邸を訪れると、家族が住んだ気配もなく、ただ一脚の古い椅子だけが残されていた。その椅子はなんと「ブルーノ・タウトの椅子」であり、そして肝心の家族はどこに消えてしまったのかわからない。ミステリーとはいっても、建築の美しさ、人の心の美しさが浸み込んでくる長編だ。
ナチス・ドイツから逃れた建築家ブルーノ・タウトは白川郷の合掌造りや桂離宮の建築美を褒め称えた。「日本の美」は、自然と人間との調和、物と心のバランスの中にある。タウトは言う。「桂離宮を見て、泣きたくなるほど美しい」――。建築家の求める「唯一絶対の美」「絶対美と呼べるものの在り処を知っていて、美しいものを創造しようと、自分の心を埋める作業。終わりなき作業」と、人間の求める「恩」「心の通い合いの世界」が交差していく。











