 「共生社会」が叫ばれるが、背景には中間層の凋落、分断社会の進行、コミュニティの崩れ、支え合いが難しくなっているからだ。「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、地域住民が支え合いながら自分らしく活躍できるコミュニティ形成は重要だが、難題だ。
「共生社会」が叫ばれるが、背景には中間層の凋落、分断社会の進行、コミュニティの崩れ、支え合いが難しくなっているからだ。「支える側」と「支えられる側」に分かれるのではなく、地域住民が支え合いながら自分らしく活躍できるコミュニティ形成は重要だが、難題だ。
今、「現役世代の低所得化と未婚化」「困窮の連鎖と子どもの貧困」「高齢世代の"再困窮化"」等が進行して、しかもこれらが複合して貧困と孤立が顕在化している。深刻な、かなり本質的事態だ。宮本さんのいう「生活保障」は「雇用と社会保障」を合わせて考える提言だが、従来の「支える側」と「支えられる側」を峻別してきた2分法的な日本の社会保障を、複合的に解決への道をつけるということだ。「強い個人」でいる間に「弱い個人」に転ずるリスクに備えるという20世紀型、2分法的な社会保障制度を変える試みだ。雇用と社会保障・福祉の連携は必須であるが、雇用の劣化、非正規問題、未婚化、孤立化の連鎖と困窮の三世代化に具体的に対応しなければならない。支える側の「強い個人」が標準となりえない時代、身体的には高齢者イコール「弱い個人」ではないといえる時代を迎えたのだ。
そこで提起される共生保障とは、「支える側」を支え直す。職業訓練や子育て支援、就学前教育等だ。「支えられる側」も社会参加、就労支援を促し、より多くの人が「支え合いの場」に参入できるようにする。まさに共生保障は、多様な困難を抱える多数の人々を、社会につなぎ能力を発揮することを可能にする仕組みである。
社会保障の普遍主義的改革が重要だが、現実には「財政的困難」「自治体の制度構造」「中間層の解体」の構造的ジレンマに制約されており、これを突破する具体的対策を進める必要がある。「強い個人」が中間層の縮小とともに減少し、「弱い個人」が増大する今日、中間層の不安や怒りをポピュリズムで対処するのではなく、断層をふさぐ共生保障の政治が期待されている。
30日(日)は強い日差しの大晴天。最近、人気が高まっている北区・赤羽では「第62回赤羽馬鹿祭り」が商店街等各種団体主催で盛大に行われました。ものすごい人出で、パレードにも踊り隊や音楽隊など、盛り上がりました。江戸城を築き、歌道にも精通した武将・太田道灌(関東各地に銅像や地名があり、赤羽にもゆかり)を偲んでの行事でもあります。開会式で挨拶、多くの方々と懇談しました。
また、29日(土)も多くの行事が行われましたが、国立代々木競技場では「POINT&K.O.第32回空手道選手権大会」が開催され、全国各地や世界からも選手が集結。日頃からの錬磨を発揮し、白熱の試合が繰り広げられました。2020年東京五輪で正式種目となった空手道。挨拶・激励をしました。
 保育所を公園に設置――。28日、参院本会議で都市緑化法改正が可決•成立。国や自治体の都市公園内に保育所など社会福祉施設が設置できるようになりました。子育てなどの具体的前進です。
保育所を公園に設置――。28日、参院本会議で都市緑化法改正が可決•成立。国や自治体の都市公園内に保育所など社会福祉施設が設置できるようになりました。子育てなどの具体的前進です。
きっかけになったのは、安倍自公政権になって規制緩和を推進、国家戦略特区を創設しました。そのなかで、「公園内に保育所を」と真っ先に手を上げてきたのが荒川区•西川太一郎区長。公園は国交省の管轄で、私が国交大臣としてこれを推進、強力に進めました。西川区長、地元の公明都議•区議と連携し、この4月1日に、荒川区の都立汐入公園内に「にじの森保育園」がついに開園しました。
今回の改正法は、この流れを特区だけでなく全国に展開。まさに国•都•区のネットワークで不足が問題となっている社会福祉施設が広がることになりました。
 また、今回の改正法では都市農業も大きく前進――。市街化区域内の都市農地で税制上のメリットが受けられる生産緑地の面積要件も500平米から300平米に緩和。小規模な都市農地の保全や都市農家の税負担軽減を促します。画期的な法改正です。
また、今回の改正法では都市農業も大きく前進――。市街化区域内の都市農地で税制上のメリットが受けられる生産緑地の面積要件も500平米から300平米に緩和。小規模な都市農地の保全や都市農家の税負担軽減を促します。画期的な法改正です。
※太田の政界ぶちかましNO,105でも「都市緑化法改正」について書いています。ご覧ください。
https://www.akihiro-ohta.com/vision/2017/04/no105.html
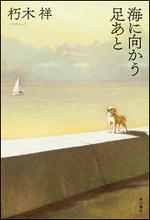 大学でヨット部だった6人。照明デザイナーの村雲佑をキャプテンとするクルーたちは、資金を工面してエオリアン・ハープ号を買い、翌年のゴールデンウィークに開催される外洋レースの参加を決める。小笠原諸島の近くの三日月島をスタートして江ノ島でフィニッシュするレースだ。ヨットに魅せられた6人とその家族や恋人等の日常生活はそれぞれ異なる。家や職場を離れることも多く特異でもある。
大学でヨット部だった6人。照明デザイナーの村雲佑をキャプテンとするクルーたちは、資金を工面してエオリアン・ハープ号を買い、翌年のゴールデンウィークに開催される外洋レースの参加を決める。小笠原諸島の近くの三日月島をスタートして江ノ島でフィニッシュするレースだ。ヨットに魅せられた6人とその家族や恋人等の日常生活はそれぞれ異なる。家や職場を離れることも多く特異でもある。
「幸せとは何だろう」――。風、波、太陽、星など大自然を呼吸するクルーたちの至福が伝わってくる。「本当に好きなことを見つけて夢中な人は幸せだからあんなに楽しそうだし、幸せだから他人に寛容なのだと思った」「命のある誰かを生きがいにしてはいけない・・・・・・」「これまで旅立てなかったのは、心に刻んだ情景を一緒に見たい人がいなかったからだと気づいた」・・・・・・。
しかし、レース直前、突然の破局が訪れる。核攻撃によって東京壊滅。自然のなかでの人間の日常生活の安寧の対極の事態。「我々がやってきたことの報いだな・・・・・・歴史にも学ばず、警告にも耳を貸さず、現実に起きていることに目を閉ざしてきた、その結末ということか」「結局、我々は『よりよいこと』を選択せずに、可能性を遮断し、ここまで来てしまったのだ」との警告が響く。
 「日本の取り組みのフロンティアは世界の取り組みのフロンティアでもある」――日本再建イニシアティブの「日本再発見」プロジェクトを更に進め、21世紀日本の可能性と跳躍を追求する。世には学者・評論家の本は多いが、本書は激烈な社会の各界で活躍している現場のフロントランナーが11のプログラムを率直に語り、きわめて刺激的で面白い。
「日本の取り組みのフロンティアは世界の取り組みのフロンティアでもある」――日本再建イニシアティブの「日本再発見」プロジェクトを更に進め、21世紀日本の可能性と跳躍を追求する。世には学者・評論家の本は多いが、本書は激烈な社会の各界で活躍している現場のフロントランナーが11のプログラムを率直に語り、きわめて刺激的で面白い。
「日本のフロンティアは日本の中にある。しかし世界のフロンティアもまた日本の中にある」「ガラパゴス化をグローバル化し、また、世界の需要や文化をインバウンド化、つまり日本社会に内実化させてこそ、ガラパゴス化から普遍的な価値を引き出すこともできる。それによって、日本の個性と多様性を世界とともに発見し、その過程で日本が自ら再発見するガラパゴス・クールのダイナミックスも生まれるだろう」「これは(グローバル・シビリアンパワー2.0)は、従来の"グローバル・シビリアン・パワー"を下敷きにしつつ、国際社会の"自由で開かれた国際協調秩序"を維持、強化するため、より課題先取り型で、より積極的(プロアクティブ)で、かつより筋肉質の外交姿勢を志向し、世界の平和と安定のための国際的役割を探究し、国際的アイデンティティーを追求する戦略である」「そこでの日本の取り組みの特徴は、シビリアンパワー、開かれた海洋、自由主義、市民社会の独自性と活力、個々人の創意工夫と遊び心、スモール・イズ・ビューティフル、"自然体のまこと(真・誠)"、そして何よりも個性と多様性といった特質によって陣取られることになるだろう」などという。
芸術・文化、デザイン、ライフスタイル、医療、科学、イノベーション、外交など各界のフロントランナーの発言・提言は、激しい競争の中にいるだけに鋭く、現実の行動を促している。






