 9つの短編集。1つ1つが全く角度・色合いも違う。ミステリーもあれば、温かなもの、ジーンとくるものもあるし、コミカルなものもある。短編の面白さを味わう。
9つの短編集。1つ1つが全く角度・色合いも違う。ミステリーもあれば、温かなもの、ジーンとくるものもあるし、コミカルなものもある。短編の面白さを味わう。
最初「正月の決意」――。町長が神社の賽銭箱の前で倒れており、教育長が行方不明。発見者は死を決意していた夫婦。そして・・・・・・。「どうして私たちのような真面目な人間が死ななきゃいけないの?そんなの、絶対に変・・・・・・。私たちも、これからは負けないでもっといい加減に、気楽に、厚かましく生きていきましょう」。
最後は「水晶の数珠」――。父親が息子にかける厳父の愛。こんな形で表現されるのか・・・・・・。
「レンタルベビー」や「サファイヤの奇跡」では、脳や次代の生命科学と人間が愛情をもって提起され、「壊れた時計」「クリスマスミステリ」はまさに謎解きの本格的ミステリー。
「素敵な日本人」という表題とは? 騙し方、騙され方、人生への甘さと、バタくささ、無言の抵抗や愛情、季節や自然との一体感・・・・・・。9編全てを読み終わってみると、たしかに、そんな「素敵な日本人」が浮かび上がってくる。
 「文明史が語るエネルギーの未来」が副題だ。19世紀の頃は日本でも西欧でも木材が利用され国土は荒れ地となっていた。今、再生エネルギーが注目されているが、太陽光も風力もエネルギー効率は低く、生態系をかつてとは別の形で破壊するリスクもある。「各エネルギー源は、全てそれぞれ独自の大きな欠点・問題を抱えており、魔法の杖、救世主のスーパースターはどこにもない」「将来のエネルギーはベストミックスしかないが、それはベストというより、より最悪でない組み合わせでしかない」「進むべき案内板はエネルギー源の動的な多様化と省エネだ」という。
「文明史が語るエネルギーの未来」が副題だ。19世紀の頃は日本でも西欧でも木材が利用され国土は荒れ地となっていた。今、再生エネルギーが注目されているが、太陽光も風力もエネルギー効率は低く、生態系をかつてとは別の形で破壊するリスクもある。「各エネルギー源は、全てそれぞれ独自の大きな欠点・問題を抱えており、魔法の杖、救世主のスーパースターはどこにもない」「将来のエネルギーはベストミックスしかないが、それはベストというより、より最悪でない組み合わせでしかない」「進むべき案内板はエネルギー源の動的な多様化と省エネだ」という。
「再生可能エネルギーの世界史」を語ったあと、「第一の反革命――再生エネルギーは環境に悪い」「第二の反革命――シェールガス革命」「第三の反革命――"石油の世紀"の終焉」を指摘する。CO2削減効果の高い化石燃料利用技術、石炭火力の発電効率向上技術、コージェネレーションなどの技術革新の現状等にも言及する。さらに、「デンマークを見習え」「ドイツは時代を先取りしている」「グリーン・ニューディール政策」などの言説の"言い過ぎ""誤り"をも指摘する。あわせて、「日本の天然ガス輸入価格は世界一高い」とし、経済への影響の深刻さ等々を述べる。
エネルギーと環境に関しての「思い込み」「認知バイアス」を歴史と原理に基づいて剔抉している。
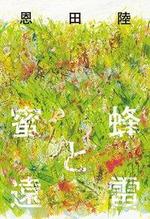 「こんなにも世界は音楽に満ちている」――。宇宙の深遠、自然のなかでの息づかい、生命の鼓動が伝わってくる。光と音と静寂。自然との対話。心通う人間の覚醒と蘇生。心の中の大きな景色を弾き出すピアノ・・・・・・。ピアノコンクールを舞台にして、若者の伸びやかな感受性と未来性が輝きわたる広がりある傑作。
「こんなにも世界は音楽に満ちている」――。宇宙の深遠、自然のなかでの息づかい、生命の鼓動が伝わってくる。光と音と静寂。自然との対話。心通う人間の覚醒と蘇生。心の中の大きな景色を弾き出すピアノ・・・・・・。ピアノコンクールを舞台にして、若者の伸びやかな感受性と未来性が輝きわたる広がりある傑作。
養蜂家の父とともに各地を転々、ピアノも持たず、常識を覆す破天荒な演奏で衝撃を与える破壊力抜群の天才少年・風間塵16歳。天才少女としてデビューしながら、母の死とともにピアノが弾けなくなってしまった栄伝亜夜20歳。名門ジュリアード音楽院の俊英・マサル・C・レヴィ・アナトール19歳。そして音大出身で妻子持ちのサラリーマン高島明石28歳。芳ケ江国際ピアノコンクールに集った若者が才能をぶつけ合い競い合う。互いが刺激を与え合い、化学変化を起こして高めていく臨場感と緊迫感はすさまじい。すがすがしい人間讃歌が響く。



