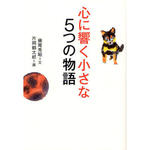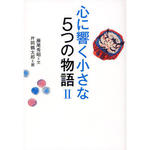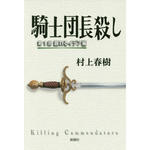
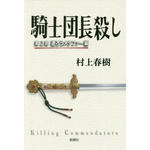 妻から別れ話を切り出された36歳の肖像画家の「私」が、東北・北海道をさ迷った後、友人の父親である著名な画家のもつ小田原郊外のアトリエで一人で暮らすことになる。そしてその屋根裏に隠されていた絵画「騎士団長殺し」を発見する。また谷を隔てた向かい側の山の豪邸に住む免色という男や、尾根続きの山にある家に住む中学生(秋川まりえ)とその叔母(笙子)との交流が始まるが、不可思議な出来事が次々起き始め巻き込まれていく。
妻から別れ話を切り出された36歳の肖像画家の「私」が、東北・北海道をさ迷った後、友人の父親である著名な画家のもつ小田原郊外のアトリエで一人で暮らすことになる。そしてその屋根裏に隠されていた絵画「騎士団長殺し」を発見する。また谷を隔てた向かい側の山の豪邸に住む免色という男や、尾根続きの山にある家に住む中学生(秋川まりえ)とその叔母(笙子)との交流が始まるが、不可思議な出来事が次々起き始め巻き込まれていく。
「眼前に広がる現実と人間の意識が、深層から湧出した一部の表層であること」「人であることの中核を成すものは何か」を、肖像画をモチーフにイデアと称する騎士団長等や、アトリエ裏の雑木林で発見される不思議な穴(石室)などによってきわめて精妙に語っていく。この世界と異界、有無を越え有無に偏する生命実相、主体と客体とその依正不二の相、夢と現実との境界と交流・交差、意識とその深層の未那識・阿頼耶識・九識からの湧出、イデアと心中の善悪、人間変革の機縁等々を、切れ目なく描く。サスペンスと人間存在の哲学性と芸術・文化の絶妙なコラボレーションと洗練された緻密かつ甘美な描写に引き込まれる。難題への挑戦と深さにおいてドストエフスキーの世界を想起したが、重苦しくないのは善人たちの登場と、穏やかな結び、柔らかな曲線的表現であるがゆえか。
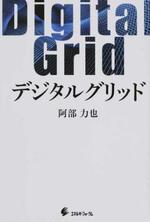 社会も技術も大変革の時代、変化激しき時代だ。IoT時代、AIの進展、パリ協定の発効。世界は再生可能エネルギーを急速度に導入しなければ、2050年を迎えられない。再生エネルギーが急増した場合、現在の電力系統は十分ではない。エネルギーの地産地消、住宅でも太陽光発電、外断熱などゼロエネ住宅、スマート住宅、ひいてはスマートウェルネスシティが目前の課題となる。スマートグリッドは重要だが、デジタルグリッドは電気系統の周波数や電圧をはじめとする電気的な制約を取り払って、しがらみなしに電気を自由に取引する仕組みで、東大技術経営戦略学専攻特任教授の阿部力也氏が研究、実証試験がスタートしている。
社会も技術も大変革の時代、変化激しき時代だ。IoT時代、AIの進展、パリ協定の発効。世界は再生可能エネルギーを急速度に導入しなければ、2050年を迎えられない。再生エネルギーが急増した場合、現在の電力系統は十分ではない。エネルギーの地産地消、住宅でも太陽光発電、外断熱などゼロエネ住宅、スマート住宅、ひいてはスマートウェルネスシティが目前の課題となる。スマートグリッドは重要だが、デジタルグリッドは電気系統の周波数や電圧をはじめとする電気的な制約を取り払って、しがらみなしに電気を自由に取引する仕組みで、東大技術経営戦略学専攻特任教授の阿部力也氏が研究、実証試験がスタートしている。
「従来の電力系統に加え、自営線による多重受電網をもつセルグリッドを無数に構築する。セルの中では多種多様な再エネ技術が開発され、太陽由来のエネルギーをふんだんに取り込み、さまざまな電力パケットとその派生物が取引される。既存の電力系統は、自立するセルと協調して、ベストエフォートなシステムとなり、総合的には高い信頼性をもたらす。メッシュ構造の電力ネットワークで膨大な電力取引を実現しつつ、最終的には日本の電力系統の再エネ比率を80%まで高めることを実現する」と数十年後の実現めざし、結んでいる。
第1話「夢を実現する」はイチローの話から始まる。「人の心に光を灯す。それは自分の心に光を灯すことでもあるのだ」「人は誰でも無数の縁に育まれ、人はその人生を開花させていく。大事なのは、与えられた縁をどう生かすかである」「自分を育てるのは自分。・・・・・・自分は自分の主人公。世界でただひとりの自分を創っていく責任者」「感動は人を変える。笑いは人を潤す。夢は人を豊かにする。感動し、笑い、夢を抱くことができるのは、人間だけである」「難病に次々襲われた作家・三浦綾子さんの幸福論」「新しい時代に適った夢と志を実現する。"歴史創新"とはこのことである。そして夢と志を実現しようとする者に、天は課題として困難を与え、試すのではないか。"歴史創新"の人に共通する条件を1つだけ挙げれば、それは困難から逃げなかった人たち、困難を潜り抜けてきた人たちだ」・・・・・・。
片岡鶴太郎さんの挿絵がまた素晴らしい。
桜の花が咲き始めた25日、地元東京北区では、東京北医療センターの新棟竣工式典が行われ、私も参加し挨拶しました。
この東京北医療センターは、2004年4月に東京北社会保険病院としてスタート。城北地域では初の産婦人科、小児科の24時間救急医療体制を導入した中核拠点病院。途中、旧社会保険庁改革で閉鎖の危機がありましたが、私も存続に動き、現在、東京北医療センターとして地域の重要な病院となっています。この日、63床を持つ新しい棟が完成し、新たに血液の病気に対応できる血液内科が加わり、区民の健康を守る地域医療の要として、さらにいい役割りを果たしていけると思います。
また、26日は一転して花冷えのする雨となりましたが、地元では、「餅つき」や「桜まつり」が行われました。浮間舟渡駅前の「舟渡さくらまつり」では多くの人々が集まり、吹奏楽や踊りなど、活気のあるイベントが行われました。温かい"舟渡ラーメン"をいただきながら多くの方々と懇談しました。
首都直下地震が首都圏を襲った場合、どう首都圏を守り抜くか――3月24日、首都直下地震の最大の防災拠点であり、政府の現地対策本部となる東京臨海広域防災公園(お台場、有明の丘地区)を視察しました。これには公明党の三浦のぶひろ参院議員、こいそ善彦都議、のがみ純子都議、加藤まさゆき都議、まつば多美子都議、細田いさむ区議(都議選予定候補)が参加、国と都が連携をとって動けることを考えてのものとなりました。
首都直下地震が起きた場合、中心の対策本部は首相官邸。そしてこの有明の広域防災拠点が現地対策本部となり、政府や警察、消防、自衛隊、東京都など首都圏の各県・市の行政が一体となって対策を行います。広さは13.2ヘクタール、大型ヘリが7機駐機できるヘリポートを備え、応援部隊、医療、物資の3部門のコントロールセンターとして機能します。オペレーションルームは約960㎡の大部屋で、各機関の職員約200名が一つの部屋で画面を見ながら情報共有して指揮をとります。まさに官邸の指令と災害現場をつなぐ現場の大拠点で、頻繁に防災訓練が行われています。
この日は、この状況を視察するとともに、平時に防災の体験や学習・訓練できるように造られた防災体験ゾーンや学習ゾーンも回りました。
国と東京都、首都圏各県が連携をとり、防災・災害対策の先頭に公明党が立って頑張ります。