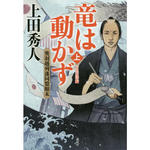
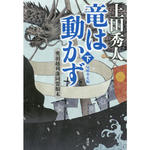 英米仏蘭が日本を狙い、黒船来航以来、騒然たる幕末――。出色の才とうたわれた仙台藩士・玉虫左太夫は逐電し、江戸に向かう。儒学者・林復斎、目付・岩瀬肥後守、外国奉行・新見豊前守等との出会いに恵まれ、幸運にも日米修好通商条約の批准に渡米する外国奉行の従者の座を掴む。太平洋を渡る。そして日本初の世界一周を果たす左太夫の若き進取の眼は、鎖国で閉ざされた日本とは全く違う進んだ文明、恐るべき国力、誰もが同じ扱いを受ける共和の世界をとらえ、驚愕する。
英米仏蘭が日本を狙い、黒船来航以来、騒然たる幕末――。出色の才とうたわれた仙台藩士・玉虫左太夫は逐電し、江戸に向かう。儒学者・林復斎、目付・岩瀬肥後守、外国奉行・新見豊前守等との出会いに恵まれ、幸運にも日米修好通商条約の批准に渡米する外国奉行の従者の座を掴む。太平洋を渡る。そして日本初の世界一周を果たす左太夫の若き進取の眼は、鎖国で閉ざされた日本とは全く違う進んだ文明、恐るべき国力、誰もが同じ扱いを受ける共和の世界をとらえ、驚愕する。
将軍の後継問題に端を発する安政の大獄、桜田門外の変・・・・・・。帰国した左太夫は、藩主・伊達慶邦から、京洛の動静を探ることを命じられる。尊王攘夷、朝廷と幕府、長州・薩摩・会津、勝海舟・西郷隆盛・坂本龍馬・新選組。将軍家茂・孝明天皇の死、まさか薩摩と会津が手を組むとは・・・そして、終にはまさか薩摩と長州が組むとは。大政奉還と慶喜・・・・・・。歴史回転の濁流は、江戸を飲み込み、奥州は奥羽越列藩同盟をもって新政府軍を迎え撃つ。しかし、次々に破られ、列藩同盟の結束はもろくも破れ、同盟に奔走した左太夫の夢は潰える。幕末の各藩・武士の道と恩義と信念と気負い、なかでも怨念、「土佐は安政の大獄、長州は関ケ原、薩摩は木曽三川治水のお伝い。どれも恨みで動いている」・・・・・・。
左太夫が世界や京洛情勢を一定の距離感をもって見る立場にあるだけに、時流がよくわかる。(上)は「万里波涛編」、(下)は「帰郷奔走編」、副題は「奥羽越列藩同盟顛末」。力作だ。
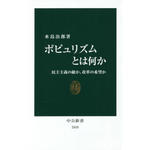 英国のEU離脱、トランプ米大統領誕生・・・・・・。その激震の背景に世界に広がるポピュリズムの台頭がある。その定義は「政党や議会を迂回して有権者に直接訴えかける政治手法」と「人民の立場から既成政治やエリートを批判する政治運動」の二つがあるとする。
英国のEU離脱、トランプ米大統領誕生・・・・・・。その激震の背景に世界に広がるポピュリズムの台頭がある。その定義は「政党や議会を迂回して有権者に直接訴えかける政治手法」と「人民の立場から既成政治やエリートを批判する政治運動」の二つがあるとする。
反エリート、エスタブリッシュメント・既得権益への反発と断罪、代議制民主主義の機能不全と草の根の人々の意思の実現、権力分立・抑制・均衡の立憲主義原則の軽視・・・・・・。そして外国人流入への強い警戒感、反移民・反難民、反イスラム、排外主義、置き去りにされた人々への共感、標的への攻撃、メディアの活用と人民への直接の訴え手法・・・・・・。世界に広がっている姿だが、反エリートということに加えて、富裕層というだけでなく、既存の制度による再分配によって保護された層を"特権層"と見なし、その"特権層"を引きずり下ろすことを訴えかけることから反移民・反イスラムが生まれてくる。
「21世紀の世界はあたかもポピュリズムの時代を迎えたかのようである・・・・・・。ポピュリズムとはデモクラシーに内在する矛盾を端的に示すものではないか。現代のデモクラシーは、自ら作り上げた袋小路に迷い込んでいるのではないか」という。たしかに「ポピュリズムは、デモクラシーの後を影のようについてくる」(マーガレット・カノヴァン)だ。「既成政党の求心力の弱まりと政党間政策距離の狭まり」「組織の時代の終焉と無党派層の増大」「エリート層と大衆の断絶」「グローバル化と格差の拡充、二極分化」など、ポピュリズム躍進の舞台は今、揃い始めているようだ。
 春らしい暖かさとなった4日。地域では、党青年委員会の「東京ボイス・アクション」が行われました。東京・北区の十条駅と赤羽駅周辺で実施された政策アンケートに、私も地元の大松あきら都議(都議選予定候補=北区)や区議らと参加しました。
春らしい暖かさとなった4日。地域では、党青年委員会の「東京ボイス・アクション」が行われました。東京・北区の十条駅と赤羽駅周辺で実施された政策アンケートに、私も地元の大松あきら都議(都議選予定候補=北区)や区議らと参加しました。
一方、北区立赤羽会館では、公明党北総支部女性部による「災害に備えて命をつなぐお片付け&備蓄」と題した女性の視点を生かした防災対策のセミナーが行われました。若いお母さん方がたくさん参加されており、防災対策の大切 さについて意見交換ができました。
さについて意見交換ができました。
また、北区の滝野川第6小学校と紅葉小学校が統合するにあたり、先週と今週で両校の閉校式が行われ、私も参加。多くの方々と懇談しました。
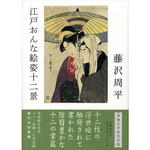 藤沢周平没後20年の記念出版。歌麿や豊国、国貞などの1枚の浮世絵から主題を得て、ごく短い一話をつくり上げた掌篇小説。1月から12月までの江戸の季節感ただよう12話。
藤沢周平没後20年の記念出版。歌麿や豊国、国貞などの1枚の浮世絵から主題を得て、ごく短い一話をつくり上げた掌篇小説。1月から12月までの江戸の季節感ただよう12話。
「あっ」とか「はっ」とか、刹那の女の心の動き、しみ通るような悲しみや小さな安堵、江戸の女の息づかいが伝わってくる。江戸庶民の情感と粋、そして景観と色彩に柔らかに包まれる。
たとえば「馬場通りに出ると、道の正面に沈む日が見えた。その光に照らされながら、おせいは人混みの中を追われるような足どりで歩いた。後悔しちゃいけないよ、これがあたりまえさ、とおせいは胸の中でつぶやく。唇を噛んで、町にただよう晩夏の赤い光を見た。ひとつの季節の終りが見えた」(「晩夏の光」の結びの文章)(絵は「江戸自慢 五百羅漢施餓鬼(歌川国貞)」)など、鮮やかな文章に思わずうなずく。仏典の「心如工画師」(まさに心は工(たくみ)なる画師の種々の五陰を描くごとし)を思う。
 「『神聖』か、『象徴』か」と副題にあるように、天皇は神の子孫たる「神聖」な権威なのか、戦後民主主義の理念を徹底し神秘の片鱗を排除した崇敬される国民統合の象徴なのかを問いかけている。そして、神聖国家への回帰を批判する。
「『神聖』か、『象徴』か」と副題にあるように、天皇は神の子孫たる「神聖」な権威なのか、戦後民主主義の理念を徹底し神秘の片鱗を排除した崇敬される国民統合の象徴なのかを問いかけている。そして、神聖国家への回帰を批判する。
「ジレンマは明治維新に始まった――天皇と臣民のナショナリズム」「神としての天皇と臣民のナショナリズム」「明治維新の二枚看板の矛盾――王政復古と文明開化」「なぜ尊王思想は水戸藩で生まれたのか」「天皇の軍隊と明治天皇の神格化」「明治国家を神聖化した乃木将軍の殉死」「天皇の"仁政"による"慈恵"と福祉国家」「大正デモクラシーの陰で進んだ精神教育」「戦後も生きている国家神道」・・・・・・。
権威と権力、そして権威の源泉――。権力側に使われず、"神"でもなく、しかも、"人間"として議会制民主主義のなか国民から尊崇され、権威を保持する。200年、500年、それ以上も。日本の悠久の歴史のなかで象徴天皇制を考えるには、縦に横に、より重厚な思索が不可欠だ。

